生成AIで磨くエンジニアリングマネジメントスキル:自己成長の新たな形
 うっしー
うっしー 概要
エンジニアリングマネージャー (EM) には多岐にわたる責務があり、様々な知識や技術を柔軟に適用する能力が求められます。しかし、多くの組織では経験豊富なEMが不足しており、若手EMが適切な相談相手やロールモデルを見つけにくい状況にあります。
この課題に対し、生成AIをCopilotとして活用することで、EMとしてのスキルの効果的な向上が期待できます。
具体的には以下の活用方針があります
- シナリオシミュレーション:仮想的な状況でAIと対話し、最適な対応を検討
- 知識拡張:AIに質問を重ね、最新のマネジメント理論や事例の理解を深める
- 自己振り返り:AIとの対話を通じて自身のマネジメントスタイルを客観的に評価
- スキルギャップ分析:現在の能力と目標のギャップをAIと分析し、学習計画を立てる
活用する際は生成AIの特性や限界を理解することが重要です。AIの出力には誤りや偏りが含まれる可能性があり、ハルシネーション (事実と異なる情報の生成) にも注意が必要です。また、コンプライアンスやセキュリティリスクにも配慮が必要です。
そのため、AIの出力を批判的に評価し改善する能力が求められます。この過程で、EMは自身の思考力や創造性を磨き、効率的に知識を吸収することができます。具体的には、AIの回答に対して「なぜそう考えるのか」「別の視点はないか」といった問いかけを重ねることで、より深い洞察を得ることができます。さらに、AIとの対話を通じて培った問いかけ力は、実際のチームマネジメントにも直接活かすことができると思います。
本セッションでは、生成AIを活用したEMスキル向上の具体的な方法論と、AIとの効果的な対話技術と、それをチームマネジメントに応用するテクニックを話します。AIとの対話を通じて自己能力を触媒にしてさらに自己能力を増強し、磨かれた問いかけ力を実際のマネジメント現場で活用することができるヒントになれば幸いです。
Learning Outcome
対象聴衆:
・新任または経験の浅いEM
・適切な相談相手がいないEM
・EMを目指すエンジニア
得られる学び:
・生成AIを活用したEMスキル獲得の具体的テクニックとその実践方法
・生成AI活用時の注意点
・AIとの効果的な対話方法と、マネジメントに活かせる問いかけ力の向上
人と組織の“エン”を結ぶ - 受託開発EMの価値創出と潜在力の引き出し
 口玉
口玉 概要
受託開発ビジネスにおけるエンジニアリングマネージャー(EM)としての1年間の実績と経験を通じ、どのようにメンバーの潜在力を引き出し、組織全体で価値を創出してきたかをお話しします。EMとして「人と人の間」「組織の間」に立つ役割を担い、encourage, empower, engagementといった“エン”の要素を意識し、メンバーが最大限の成果を出せるようサポートしてきました。
単に案件のアサイン率を上げるだけでなく、潜在顧客への広報活動や開発生産性の改善にも取り組みました。その成果として、メンバーの潜在力を引き出し、広報活動として会社からプレスリリースを発信したり、開発生産性の改善にも取り組んで、Findy Team Award を受賞したりといった成果に繋げました。これらの活動を通じ、エンジニアリングの力で受託開発における新たな価値創出の基盤を築く方法を探ってきた中で、考えてきたことを共有します。
Learning Outcome
EMとしての役割の理解:EMが「人と組織の間に立つ」ことで、チームと会社の成長に貢献するアプローチを学ぶ。
Encourage:新たな挑戦に挑むメンバーを勇気づけ、成功に向かわせる具体的な支援方法を理解する。
Empowerment:スキルの高いメンバーが持つ潜在力を最大限に引き出し、組織や顧客に対して価値を創出した方法。
Engagement:eNPS(社員満足度)向上のための施策とその重要性を学び、メンバーとの信頼関係を深める。
専門外のチームを率いてチームの成長をリードする“ゼロからのEM”実践
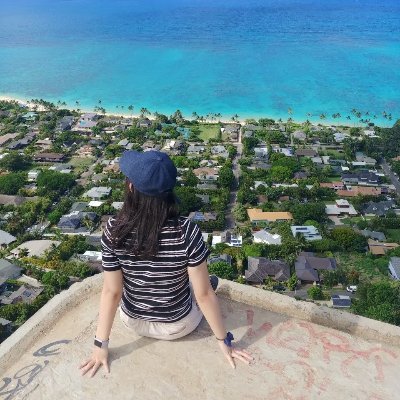 miisan
miisan 概要
スタートアップの初期フェーズは、特に仲間探しの途中で、チームに必要な専門性を持つメンバーが必ずしも揃っていない状況もあると思います。 同様に、各領域のマネージャーが不在であることも珍しくありません。
私はこれまで、QAエンジニアとしてキャリアを積んできましたが、スタートアップ初期フェーズに専門領域外のチームをマネジメントすることになりました。
この初めての経験を通して、「チーム成果を最大化する」というEMとしてのミッションと向き合った経験を振り返り、手探りの中から見えたチームマネジメントの実践方法についてお話ししたいと思います。
自分に専門性が足りない中でもチームとして成果を出すために何が必要かを考え試行錯誤を繰り返し、時には失敗する中から生まれた工夫や重要だと感じた気づきなど、特定の領域に限定しないマネジメントスキルについて考えてみます。
チームの作り方や役割分担、メンバーのアウトカムやコミットメントを引き出す方法など、EMとしてより幅広いマネジメントに挑戦する際の具体的なヒントを共有していきます。
Learning Outcome
スタートアップ初期や専門外の領域をマネジメントすることに戸惑いがある参加者と一緒に、幅広い視点でマネジメントに臨む方法を考えてみます。
- 特定の領域に限定しないマネジメントスキルや考え方について
- 特定の領域に縛られず、EMとしてチーム全体を俯瞰し、適切なタイミングで必要な役割やスキルを補完するマネジメント方法について考察する
- マネジメントスキルを分解し、EMに求められるスキルを抽象化して考える機会にできる
Engineering Management Patterns
 ntk1000
ntk1000 概要
チームの状態や規模は常に変化しており、エンジニアリングマネージャー(EM)はその変化に適応し続ける必要があります。
このセッションでは、私の経験を通じて得たさまざまな状態にあるチームを理解し、効果的にリード・サポートするための「パターン」を紹介します。
具体的な事例や実際に試みた手法を基に、どのようにしてチームを分析し、効果的な戦略を構築できるのかを探ります。
また、成功事例だけでなく、失敗から学んだ教訓についても率直にお話しすることで、参加者が同様の状況に直面した際に参考となる情報を提供します。
目次
- 安定・不安定なチームとは
- チームの特徴を見極める
- 複数チームを同時に見る
- 効果的なリソース配分と優先順位設定
- チーム間のシナジーを引き出す
- 大規模チーム
- コミュニケーションスタイル
- リーダーシップ戦略
- 多言語・多文化チーム
- 多文化チームでの成功事例・失敗事例
- 言語バリアを超えるための工夫
- 崩壊しかけたチームを立て直す
- 危機管理と再建へのステップ
- モチベーションを再燃させる技術
Learning Outcome
このセッションを通じて、さまざまなチームマネジメントのシナリオにおいて即戦力となる知識と技術を提供します。
- 状態判別のスキル: チームが現在どのような状況にあるのかを迅速に見極めるためのフレームワークを習得し、最初の段階で適切なアプローチを取るための基盤を築きます。
- 多様な戦略の理解: 異なるチームの状態や構造(安定・不安定、多文化、大規模)に応じた具体的なマネジメント手法を理解し、実行できる能力を強化します。
- 対処法の引き出しを増やす: 自らが直面した問題や危機を解決するための新しい視点を獲得し、過去の他者の失敗から学ぶことで、自分のマネジメント手法を柔軟かつ適応可能にします。
- コミュニケーション技術: 効果的なコミュニケーションを通じて、チーム内外の関係性を深化させるためのスキルを磨き、特に言語や文化的な障壁を乗り越えるための実践的なテクニックを学びます。
マネージャーが向き合う自己の感情:負の感情を超えて成長するためのアプローチ
 イシイモトヒロ
イシイモトヒロ 概要
マネージャーとして他者と向き合うためには、マネージャー自身が自分自身の感情、とりわけ怒りや焦り、悲しみといった負の感情を理解し、コントロールする力が不可欠です。このトークでは、こうした感情に対処するための実践的アプローチを紹介し、どのように自己理解を深め、日々のマネジメントに生かしていくかを探ります。負の感情を建設的な方向に導くための手法について学びます。
Learning Outcome
対象者:エンジニアリングマネージャーやリーダーシップをとる方
得られるもの:自己の負の感情をコントロールするための具体的なアプローチ、感情との向き合い方、感情管理が他者との関係に与える影響、チームへのリーダーシップに活かす方法
受け身体質なマインドセットを変える!エンジニア1人1人を主役にさせるための試行錯誤
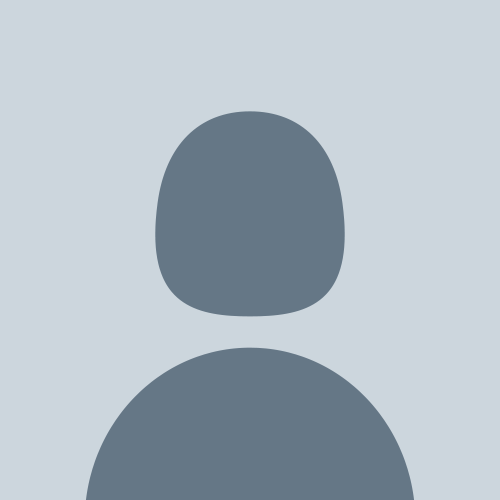 Koji Matsuda
Koji Matsuda 概要
私が現在所属している会社に入社して一番驚いたこと、それが”自社サービスを開発している小さなベンチャー企業なのに受け身なエンジニアが多く、自分の意見を述べたり新しいアイデアを提案する人が少ない”ことでした。
PMから振られたタスクを淡々とこなす日々。
自社サービスを持っているのに、社内のエンジニア組織が”受け身”な状態では、採用がうまくできない起業時にしょうがなく外注の開発会社にお願いするときとなんら変わりません!
8月にEMとなった私がまず着手したことは、そのマインドセットを変えること。
自社内に開発チームを持っていることの優位性を活かすためにも、エンジニアのモチベーションを上げるためにも、1人1人のエンジニアを主人公にする必要がありました。
まだまだその道は半ばですが、これまでに実施してきた施策とその効果を共有し、今後の展望もあわせて紹介します。
Learning Outcome
- 対象の聴衆
- エンジニアのモチベーションを高めたいとお考えの方
- ”考える”エンジニア、”組織に貢献する”エンジニアを育てたい方
- ”受け身”なエンジニアに課題を感じている方
- 得られるもの
- エンジニアのモチベーションを上げるための施策とその結果(失敗談も含む)
- (試行錯誤の先に)1人1人の表情がいきいきと輝くエンジニア組織
FourKeysにピンとこなかった私が考える真の「開発生産性」
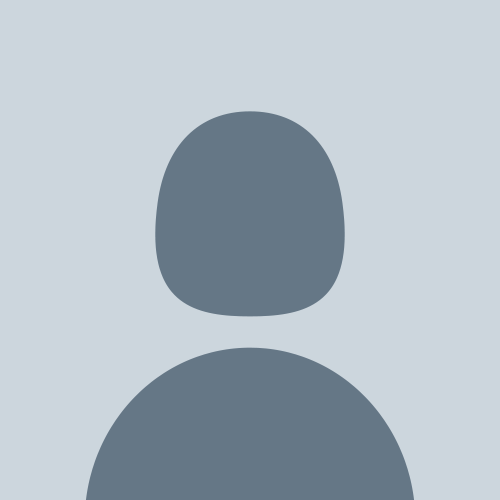 Koji Matsuda
Koji Matsuda 概要
開発生産性を測る指標として使われる「FourKeys」。
社内でもたびたび取り入れてみようという話は出るものの、EMである私はどうしてもピンとこず、未だ導入には至っていません。
ただ、何らかの形で開発生産性が向上しているかどうかは測りたいし、自分がマネジメントしているエンジニア組織が成長していることを証明したい。
そこで、「開発生産性」という普段なんとなく使っている言葉を、改めて自分なりに再定義してみたところ、
これなら非エンジニアな経営層や他部署も納得、といういくつかの指標が見えてきました。
その思考過程と、たどり着いた結果をご紹介します。
Learning Outcome
- 対象の聴衆
- 「開発生産性」とは何なのか、本当にFourKeysでいいのかモヤモヤしている方
- 自社のエンジニア組織の生産性向上に課題を感じている方
- 得られるもの
- 「開発生産性」という言葉の再定義への思考過程とその結果
- 「開発生産性」という言葉を再考するきっかけ
エンジニアをマネジメントするな、エンジニアを取り巻く環境をマネジメントせよ!
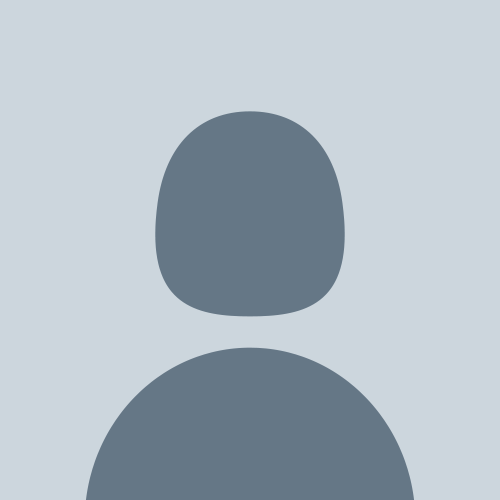 Koji Matsuda
Koji Matsuda 概要
経営層や社内外のステークホルダーがエンジニアに対して理解が不足している場合、または一種の偏見を持っている場合、いくらエンジニアだけをマネジメントしていても十分に生産性が上げられない場合があります。
今年4月に私が入社した会社もまさにそんな状況でした。
「エンジニアは少し負荷をかけるとすぐに辞めてしまう」、「エンジニアにはプロダクトに対するアイデアが出せない」、「エンジニアはコストセンターである」・・・これらはほんの一例です。
社内初のEMとなった私が、エンジニアの生産性を高めるために実施したエンジニア”以外”の人々への働きかけを紹介し、どのように改善を図ったかの事例を共有します。
すべてがうまくいったわけではなく、うまくいかなかったもの、現在進行系で戦っているものも含みます。
同じ課題を持っている方々に、一緒に考えていただくきっかけになれば幸いです。
Learning Outcome
- 対象の聴衆
- エンジニアへの働きかけだけでは十分に生産性を向上できていないとお悩みのEMの方
- 経験の浅いEMの方
- 得られるもの
- 経営層やエンジニア以外の部署への働きかけ事例とその効果
「絶対こうだ」だけではなく「相対こうだ」!EM1年生が学んだ、スタートアップ組織を成長させるコミュニケーションの学びと実体験
 佐藤樹
佐藤樹 概要
明日のコミュニケーションから「絶対こうだ」ではなく「相対こうだ」も意識して話してみませんか?
エンジニアリングマネージャーの重要な役割には、チームの意思決定やディスカッションの場でのナッジングやファシリテーションが含まれます。その際に求められるスキルが、他者への最大限の配慮を持ち、議論や組織全体を前進させるコミュニケーションスキルです。
私は、2024年3月にフルスタックエンジニアからエンジニアリングマネージャーに就任しました。現在、私たちの組織はエンジニアが10名以下の小規模なチームであり、私はプレイヤーとしての役割も担いながら、組織の成長を支えるスクラムマスターの役割も果たしています。この立場で1年間にわたり得た最大の学びは「自分が発信する際の立場を明確にすること」です。
例えば、自分がプレイヤーとして話すべきなのか、マネージャーとしてなのか、あるいは組織の一員として話すべきなのかを意識することが挙げれます。また、発信する内容についても「絶対的な意見」と「相対的な意見」を区別し、それぞれを適切に伝えることも非常に重要と考えております。このようなコミュニケーションを意識することで、私たちの組織は高い生産性を維持し、Findy team + awardやShopify Partner of the Year 2024 - Japanの受賞など、この1年間でプロダクト・組織ともに少しづつ対外的に認められるようになりました。
本セッションでは、私が学んだ組織成長のためのコミュニケーションに対する学びを、私たちのプロダクト開発や組織の成長の経緯も含めてお話しいたします。
Learning Outcome
対象となる方:
・小規模組織のエンジニアリングマネージャーや近しい役割の方
・スクラムマスターなど、多くの場面でファシリテーションを行う方
・将来的にエンジニアリングマネージャーやスクラムマスターを目指す方
このセッションを通じて得られるもの:
・私たちの失敗から得たエンジニア組織の成長やマネジメントの学び
・明日からのコミュニケーションに変化をもたらす新しい意識や視点
Engineering Manager を経験した後、プレイヤーとして実践する事業への関わり方
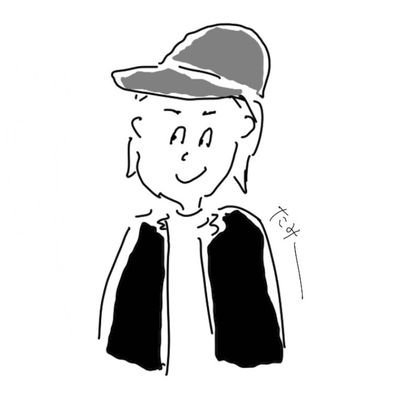 tammy
tammy 概要
私は 2023 年に約 1 年間、Android アプリエンジニアと iOS アプリエンジニアが所属するアプリチームの EM を担当しました。しかし、さまざまな事情により現在はプレイヤーに戻り、Android アプリエンジニアとして業務をしています。
EM としての経験は短い期間でしたが、非常に濃密で学びの多い時間でした。その中で行ったことは以下のようなものです:
- 施策優先になりがちな業務の中で、技術的なチャレンジを「20% ルール」のような形で取り入れること
- メンバーとの 1 on 1 など、不満・疑問点をできるだけ迅速に解消するためのコミュニケーション
- 目標設定と振り返りの方法の見直し
- 中途エンジニアの採用活動
これらはどれも私にとって貴重な経験であり、プレイヤーに戻った今でも活かせるものばかりです。現在はEMで得た経験を活かして事業への貢献方法を模索していますが、その中で「EM 視点を持ったプレイヤーとしての事業の関わり方」という 1 つの具体例をお伝えできればと思っています。
Learning Outcome
- 事業に貢献したいと考えているエンジニアの方が、このトークを通じて EM を事業貢献の挑戦の場として捉えられるようになること
- EM を今後のキャリアの選択肢として考えている方が、このトークを通じてキャリアのイメージを少しでも明確にできること
EMとして走り抜けた1年半の苦悩と葛藤、少しの学び
 倉澤 直弘
倉澤 直弘 概要
ICからアソシエイトマネージャーを経てマネージャーになり、育休に入るタイミングで一区切りつけるまでの約1年間半を振り返り、悩みやつらみ、学びを共有したいと思います。
EMに関する書籍や情報は増えてきて、EM未経験でも「EMって何となくこんな感じかな」というのはイメージすることは可能だと思います。
自分はそうでした。
でも振り返ってみると思ってた通りには全然いかなかったなと。
そういった部分を、恥ずかしい内容ではありますが私が所属する「カミナシ」のバリューの一つである「全開オープン」の精神で語っていきたいと思います。
Learning Outcome
対象者
- EMに興味がある方、なりたての方
- EMベテランだけど、新米EMの話を聞いてみたい方
得られるもの
- 駆け出しEMの失敗事例
- 駆け出しEMの学び
扱うトピック (仮)
- コード書くのを一切やめて、ピープルマネジメントだけで頑張ろうとした話
- 上司、チームメンバー、他職種それぞれが持っている期待値のずれ
- スクラムチームにいるマネージャーって何するの? の悩み
- 今までいたPMがいなくなって、腹を括ったら色々回り始めた話
ハイスピードデリバリー体質を作る「デリバリー目標」の考え方
 松山勇輝
松山勇輝 概要
組織をマネジメントするうえで「目標管理」は非常に悩ましいテーマの一つ。
その中でも、エンジニア組織やチームが「デリバリー目標」を持つかどうかは色々賛否があり、特にハードな納期コミットメントは組織をより防御的にさせ、結果的にデリバリー効率を下げるとされている。
しかし、私はよりハイスピードデリバリーが求められるスタートアップにおいて逆に「デリバリー目標」を用いてデリバリー効率を上げるTRYをしてきた。
このセッションでは私がCTOとして実践してきた目標管理や、エンジニア組織における、デリバリーを加速させる「デリバリー目標」とは何かを話します。
Learning Outcome
- 目標設定が必要なタイミングで、どんな目標をどのレベルで置くべきか、その一つの考え方を知れる
- メンバーに目標を伝える時の伝え方、目標のセットアップ方法、の考え方を知れる
急成長スタートアップの事業フェーズにあわせた組織開発とマネジメントスタイルの変遷
 yoshikei
yoshikei 概要
令和トラベルは、2021年4月にスタートし、2022年に海外旅行予約アプリ「NEWT (ニュート) 」をローンチしました。
その後、プロダクトは順調にグロースを重ね、YoYで予約流通総額が約357%と大幅に成長を遂げてきました。
一方で急成長する事業フェーズに合わせて、組織の形を柔軟に変更していくことが求められてきました。
そして、その過程でエンジニアリングマネージャーとしての自分自身の役割も変化してきました。
本セッションでは、事業や組織のフェーズに合わせてマネジメントスタイルを変化させ、自身がエンジニアリングマネージャーとして組織貢献を最大化させるために取り組んできたことについて振り返ります。
以下のテーマをメインに発表します。
- 急成長スタートアップの事業フェーズの変化とそれに伴う組織体制の変遷
- 組織スケールとマネジメントスタイルの変化
- プレイングとマネジメントのバランス
- 自身の組織貢献を最大化するためには?
Learning Outcome
急成長スタートアップにおいて、自身の組織貢献を最大化したいと考えているエンジニアリングマネージャーの方の学びになるセッションできればと思っています。
- 事業フェーズによって求められる組織のあり方
- 組織スケールにあわせたエンジニアリングマネージャーの立ち回り
- エンジニアリングマネージャーとして組織貢献を最大化するためのポイント
開発組織全員が自ら学んで成長していく組織づくり
 上原 友和
上原 友和 概要
株式会社ネクストビートに入社し、エンジニアリングマネジメントを約5年間やってきました。
お陰様で、この期間で開発組織人数は約2倍、約50名規模と成長してきています。
その過程で、我々も試行錯誤しながら、組織づくりを進めておりますが、取り組んできたことを「開発組織全員が自ら学んで成長していく組織づくり」というテーマとして纏めて、発表させて頂ければと思います。
Learning Outcome
エンジニアリングマネジメントのピープルマネジメントに興味がある方を対象とし、 人・組織が成長していく仕組み作りについての実例集を持ち帰って頂くことを目指します。
EMとして提唱したい「キャリア的ランチェスター戦略」
 わだけん
わだけん 概要
「市場価値の高いエンジニアになりたい」
「時間をかけずに成果を出せるようになりたい」などなど、
多くの新人エンジニアが抱く願望です。
新卒2年目よりマネジメントにチャレンジし約10年、
現在は約100名にも及ぶエンジニア組織の執行役員を務めさせていただいております。
何十人もの新人エンジニア達と1on1をする中で、
「なぜこの仕事をすることがあなたの将来につながるのか」
を一緒に考え、たくさんのキャリアの歩みを覗いてきました。
その試行錯誤してきた末に、自分なりに言語化したのが「キャリア的ランチェスター戦略」です。
経験を手にするための3つの戦略
- 小さなプロダクトを成長させる
- 大きなプロダクトを端から塗りつぶす
- プロジェクトのわらしべ長者
戦略の実現可能性を高める環境の条件
- 拡大する市場
- 組織文化とビジネスモデル
- 投資体力を持っている
上記について述べながら「新人とキャリアを模索するための指針」を提示できればと考えています。
また、本内容は自身で作成したnote記事の内容がたたき台になっています。
https://note.com/wdknwdkn/n/n2efc0893a204
https://note.com/wdknwdkn/n/n20172c032a84
Learning Outcome
- エンジニアにとって市場価値とは何かを定義づけて伝えられるようになる
- エンジニアとしてキャリアを積んでいく手段を言語化できるようになる
- 手段を実現する可能性の高い環境の軸を述べられるようになる
1年目EMの学び:チームビルディングと成果を引き出す実践方法
 Sugar Sato
Sugar Sato 概要
エンジニアリングマネージャーとしての初年度は、想像以上に多くの課題や新しい責任があり、日々奮闘の連続でした。このセッションでは、私が実際に経験したチーム内での課題解決のプロセスや、信頼関係をどう築き、成果を引き出すためにどんな実践をしてきたかをご紹介します。新任のEMとして直面した問題と、その解決策について具体例を交えながらお話しするので、特に新任のEMやこれからEMを目指す方にとって、明日から役立つ内容になればと思っています。
Learning Outcome
- 対象者: 新米EM
概要
新任EMの悩みや課題とその対策を理解する
初年度に直面しがちな悩みやよくある失敗について、具体的な事例を通して紹介します。「同じことで悩んでいる」「そんな対策があるのか」と感じていただけるよう、私の実体験に基づいた解決策もお話しするので、新任の方に役立つ学びを持ち帰ってもらえたら嬉しいです。
信頼関係を築き、メンバーが働きやすい環境を作る方法を知る
チームビルディングには、メンバー同士の信頼が欠かせません。どうやって信頼を築き、安心して働ける雰囲気を作ったかについて、明日から実践できるヒントも交えてお話しします。すぐに活かせる具体的なアイディアを持ち帰ってもらえるようにします。
成果を引き出すための目標設定やフィードバックの具体的なアプローチ
チーム全体で目指す目標の立て方や、メンバーの力を引き出すフィードバックの仕方など、成果を生むための具体的な工夫を共有します。新任EMとしてどうすればメンバーの力を引き出せるかを知っていただくきっかけになればと思います。
他のEMと共有したい「気づき」や「実践してみて良かったこと」
私が経験して得られた気づきや「こうすればよかった」と思う工夫をお伝えしつつ、参加者同士でも共感や新たな発見が生まれる場にできたら嬉しいです。異なる視点を知ることで、日々のマネージャー業務に役立てていただければと思います。
「チームからの期待と理想役割のギャップを埋める挑戦:権限委譲と組織課題へのアプローチ」
 daitasu
daitasu 概要
いままで、エンジニアリングマネージャー(EM)とチームリードの役割を行き来してきました。今年入社した職場では、新チームの立ち上げのチームリードを担うことになりました。初期は、チーム基盤やプロダクト基盤を構築し、技術方針やアーキテクチャの意思決定に従事しながら、プロダクトとチームの成長を支えました。しかし、立ち上げ段階からの継続的な「自転車操業」により、組織全体の中長期的な課題に割く時間が不足していることに気付きました。
エンジニアリングマネージャーとして、組織課題に取り組むにはチームの技術リードをメンバーに委譲し、チームが自律的に動ける体制を整えることが重要です。そのため、チーム内での期待役割の明確化と、適切な権限委譲のプロセスが不可欠です。
しかし、チーム内でワークショップを実施した際、多くのメンバーからは技術的なリーダーシップを期待されていることが判明し、自分が組織課題に注力したいという方向性とのギャップに悩みました。
このセッションでは、EM、リーダー職が組織課題に越境して関わるための権限委譲の重要性、期待役割の可視化とギャップ解消に向けて模索した具体例ををお話しします。
- 対象者:
- 役割を越境し、組織課題の解決に挑むエンジニアリングマネージャーやリーダー職の方
- 組織全体の課題に取り組む必要を感じており、チームへの権限委譲に悩まれている方
- チーム全員のオーナーシップを引き上げるための試行錯誤や事例に関心がある方
Learning Outcome
- チームの期待と自身の役割のズレを認識し、解消するための実践的な方法
- EMとして権限委譲を円滑に進め、組織課題に注力するためのプロセス
- 組織全体の成長に貢献するための具体的なアプローチとその成果
横断組織マネジメントのリアル:組織の壁を越えた協力と課題解決の道筋
概要
複数の部署と協力して活動する横断組織には、一般的な縦割り組織とは異なるマネジメントの難しさがあります。
私も半年前に横断組織のEMとして着任し、日々その課題に直面しています。
横断部門の組織と特定事業を担当する専門組織とでは、同じ開発組織であっても会社から求められる役割に微妙な違いがあります。
そのため、優先順位の付け方や価値観の違いから衝突が起こりやすく、各チーム間でのリソース調整や目標の共有が必要です。
本発表では私の体験談を交えながら、横断組織のマネジメントで直面した課題と、その解決に向けた具体的な対策をご紹介します。
本発表では、以下の3つの観点から、体験した困難とその解決策を共有します。
- 利害関係の調整:異なるチーム間での目標や価値観の違いから生じた対立やギャップに対して、どのように試行錯誤を重ねて対応したか。
- リソース管理:限られたリソースを各チームに公平に配分し、全体の効率を上げるために工夫した方法。
- 情報共有と透明性の確保:組織全体での情報伝達を円滑に進めるために行った取り組みとその成果。
これらの課題に対して、どのようにアプローチし、コミュニケーションの頻度や方法を調整したか、また、各部門のキーパーソンを巻き込み意思決定を促進した方法について、具体的な経験をもとにお話しします。
Learning Outcome
- 横断組織のEMが抱える独特の課題とその解決策
- 他部署との摩擦や調整方法
- リソース管理の工夫に関する実践的なアイデア
- 透明性を重視した情報共有の重要性に関する理解
- 組織横断でのリーダーシップに関心のある方や複数チームと関わる方に向けた共感と実践的な内容
エンジニア採用を成功に導くための戦術と実践
 清水 勲
清水 勲 概要
エンジニアリングマネージャーが事業の成長に寄与するための一つの要素としてエンジニアの採用があります。本セッションでは「家族アルバム みてね」の事業の成長を加速させるために、必要なエンジニアをどのようにして採用したかの具体的な取り組みを紹介します。
勉強会やカンファレンスへの登壇、ブログ記事の執筆など、企業やプロダクトの露出を増やすことで、エンジニアの採用に一定の効果があるのは言うまでもありません。実際に多くの企業が採用強化の施策の1つとして取り組んでいると思います。しかし、それだけで採用は成功しづらいのが現実です。採用に必要な要素は他にも多くあります。例えば、求職者が採用プロセスの中で募集企業に求めているものは一体何なのかを知り、情報をわかりやすく提供することや、組織一体で採用活動に取り組むために必要なことな何なのかを考え、実践することが大事です。
本セッションでは、具体的にエンジニア採用においてどのような取り組みをおこなったかを、20分のセッションの中でできる限りわかりやすくシンプルに共有します。エンジニア採用に関わり始めたばかりの方にもお役に立てたらと思っています。
セッションの主なトピックは以下を予定しています(発表時には追加・修正される可能性があります)。
- 求職者にとって有益な情報とは何か
- 採用プロセスでの工夫点
- 実際に効果があった施策の紹介
- 採用は採用決定で終わりではない
Learning Outcome
- 自社の採用プロセス改善のための具体的なヒントを得ること
- 求職者に対してどのような情報が有益かを理解する
- 他社の事例からエンジニア採用のベストプラクティスを学ぶ
- エンジニアリングマネージャーが採用プロセスに効果的に関わる方法を知る
明日からはじめられるEMの効果的な採用のアクション
 daiksy
daiksy 概要
採用はEMの重要な仕事のひとつです。
組織をつくるための基盤となる業務であり、成果がわかりやすい仕事でもあります。
EMの仕事の多くは、エンジニアがコードを書くことと違って自分の活動の成果が見えづらいことが多いです。一方、採用の仕事は実際に成功した採用人数に現れますから、成果がわかりやすい仕事です。
わたしは、現在EMとして採用業務に多くコミットメントしており、一般的に採用難易度が高いと言われているポジションでの採用に貢献することができました。わたしがここ数年で採用に関わり、うまくいったポジションは以下です。
- EM
- アジャイルコーチ
- SRE部門のマネージャー
- モバイルエンジニア
もちろん採用業務は自分ひとりでできる仕事ではありません。人事部を中心に、関係者の多大な尽力があって成せる仕事ではありますが、EMは採用プロセスの中でも最初の方に関わるケースが多く、やれることがたくさんあります。
採用の成否は行動量に比例します。EMが採用業務で行う仕事は多岐にわたりますが、このセッションでは、EMとして採用にコミットするためにできる「直接的な行動」にスポットをあてて掘り下げてみます
このセッションで扱うトピック
- 採用は自分の主業務であると覚悟を決める
- ジョブディスクリプションの作成
- どういう人を採用したいのかを言語化する
- JDを失敗すると候補者は離れていく
- ex: スクラムマスターの採用なのにPjMのようなJDを書く
- スカウト
- 読んでもらえるスカウト文
- スカウト文はできるだけ自分で書く
- ガツガツしないSNSとの良い付き合い方 (DMでスカウトって送っていいの問題)
-
カジュアル面談
- EMが自分の裁量で好きに活動できる最後がここ
- カジュアル面談はアトラクトに全振りする
- 言いづらいことほどちゃんと言う
EMの業務範囲ではあるがこのセッションで扱わないこと
- 採用プロセスの設計や改善
- 1次面接~オファー面談までの採用活動の後半戦
-
エージェントとの関係構築
Learning Outcome
- 採用の仕事の一部を具体例を伴って知れる

