AI時代におけるアジャイル文化の再構築:XP x AIのコラボレーションで生産性を2.5倍を目指す
概要
背景
レガシー改善(クラウド移行、リアーキテクチャ)を実施する上で、スクラムからよりソフトウェア開発に特化したXPに開発手法を変更、定着しつつあった矢先に、AIの進化が急加速して瞬く間に普及しました。
業界的にもAI活用が急務になっており、自社でも生産性の向上のため、XPとAIの共存ではなく共創が必要になりました。
※ スクラムからXPへの移行背景
2024年初めに、レガシー改善(クラウド移行、リアーキテクチャ)をメインで動く組織を編成。
システム改善は事業的な不確実性が少ないため、スクラムよりソフトウェア開発に特化したXPに移行した。
内容
本セッションでは、XPを実施している開発チームにどうやってAIを普及・定着させ、目標として掲げている開発生産性2.5倍の実現に向けて動いたかをみなさんに共有します。
XPの有名なプラクティスであるペアプロやTDDにおいて、AIの恩恵を受けやすい部分と受けにくい部分に対して、それぞれにどう向き合って、どう改善していったか、
やめる or 続けるの意思決定をしていったのか、を赤裸々に紹介していきます。
Learning Outcome(対象の聴衆と、その人たちが得られるもの)
対象の聴衆
- 既存の開発スタンスを、AI活用でさらに最適化したいと悩んでいる人
- 組織のAI向き合いについて悩んでいる方
- 導入検証
- 文化定着
- AIが組織に与える影響について知見や事例の情報がほしい人
得られるもの(持ち帰ってほしいもの)
- アジャイル(XP) x AIで生産性を向上させるヒント
- AIの普及などの組織の変化点にどう対応していったかという知見や学び
- 組織へのAI導入で困ったことやつまづいた失敗事例
型から文化へ──チームが自走しはじめる瞬間をつくるマネジメント
異なるバックグラウンドを持つメンバーが集まるチームを、どうすれば一つの方向に進ませられるのか。
本セッションでは、“仕組みづくり”と“対話の設計”によって、チームが自走し始めるまでのプロセスを、EMとしての意思決定を軸に紹介します。
最初の一歩は、「まずは型を守る」こと。一定のリズムでミーティングを重ね、チームの状態を定点観測しました。
その結果、課題が可視化され、メンバー自身が改善を提案するように変化します。
やがて“ルールを守る”段階から、“自分たちで仕組みを育てる”段階へと進化。
このセッションでは、成長実感を持てるチームを育てるためのアプローチ──定例の運用、アンケートの活用、文化を継続させる工夫──を共有します。
テクニックではなく、マネージャーとして「どう関わるか」に焦点を当てたリアルな実践知をお届けします。
●アウトライン(発表の流れ)
① 文化の異なる組織がひとつになる──混沌のスタートライン
異なる価値観・ルールを持つメンバーが合流し、開発の足並みが揃わない混沌を前に「秩序づくり」が必要だと判断した状況。
② “型”が生む秩序──スクラム導入で整う共通リズム
共通言語と対話の機会を作るために“型”としてスクラムを導入し、異文化の融合とコミュニケーション活性を実現した判断。
③ 自律を生む目標設定──組織課題を個の挑戦に翻訳する
組織課題を分解し、メンバー個人の目標に紐づけることで、各自が主体的に課題解決へ動き始める仕組みを整えたプロセス。
④ 定点観測で状態をつかむ──アンケートと対話の循環
アンケートで心理状態と課題を可視化し、EM主導の対話を通じて改善サイクルを回し続け、文化が更新される状態をつくった継続運用。
⑤ 文化をつなぐオンボーディング──回り続ける組織へのアップデート
価値観・型・改善のリズムをオンボーディングとして仕組化し、新メンバーが文化の担い手となる“続く組織”を実現した最終段階。
肩書きではなく構造。「全員プロダクトエンジニア」への道
 梶川 琢馬
梶川 琢馬 概要
私たちは、プロダクト開発をより一貫した形で進めたいという課題から「全員がプロダクトエンジニアとして動ける状態をつくる」という方針を掲げました。
技術領域ではなく、価値に向き合う単位で動けるチームを目指した形です。
ただし、役割をそろえるだけではチームは変わりません。
肩書きや担当範囲を動かしても、日々の流れや連携の仕組みがそのままなら行動はほとんど変化しません。
私たちは、人ではなく構造を変える必要があると判断しました。
コードの設計を見直すように、チームの境界や依存関係を整理し、情報の流れを整えました。
意思決定の範囲を明確にし、プロダクト単位で完結できる形へ移行しています。
フロントエンドとバックエンドの分断をなくし、企画と開発が同じループで動ける土台も用意しました。
小さな改善を続けられる構造へ組み替えた形です。
取り組みを進める中で、マネジメントの役割も変わりました。
「どう動かすか」を決めるのではなく、「どういう構造なら自然に動けるか」を設計する側へと比重が移っていきました。
このセッションでは、全員プロダクトエンジニア化を支えた構造設計の実践と、そこから得た視点を共有します。
Learning Outcome
対象:
- エンジニアリングマネージャーとして、組織の成果を技術と結びつけたい方
- チームの動きが事業の動きと噛み合っていないと感じている方
- 「マネジメント=人の管理」から抜け出し、構造的にチームを設計したい方
得られること:
- マネジメントを構造設計として捉え直し、事業と技術のつながりを強化するためのヒント
- 役割変更で組織が動かない理由を理解し、構造的な課題を見抜く視点
- チームの境界や依存関係を整理し、自律的に動ける環境をつくるための方法
マトリクス組織でのEMの苦悩
 a1yama
a1yama トーク概要
マトリクス組織では、サーバーサイドのEMとして横断的な技術課題や基盤整備を担っていても、メンバーは日々の事業部プロジェクトを中心に動いています。
1on1を通して事業部側の状況は把握できているし、メンバーとの関係も良好で、みんな前向きに仕事をしている。
それでも、サーバーサイドとして取り組みたい改善や、横断的に解くべき技術課題が思うように進まない──そんな状況が静かに積み重なっていく。
事業部の優先度も正しいし、現場のプロジェクトが重たいのも理解している。
ただ同時に、サーバーサイドとして未来を守るために取り組むべき課題は明確に存在している。
両方の“正しさ”の間で、どのように改善を進めていけば良いのか。そこにマトリクスならではの難しさがある。
このトークでは、
- メンバーは動いているのに、サーバーサイドの横断課題だけが後回しになる構造
- 事業部中心の動きの中で、技術的な改善が進みにくい背景
- EMとして軸をどう持ち、どうすればサーバーサイドの基盤整備を前に進められるのか
といった点について、実際の現場で起きている状況をベースにお話しします。
マトリクス組織では、縦の動き(事業部)と横の動き(サーバーサイド)が必ず揺れます。
その“揺れ”をどのように扱い、改善を継続できる体制をどう設計するか。
その考え方と実践を共有します。
対象となる聴衆
- メンバーが事業部プロジェクトに多くの時間を使う環境で、サーバーサイドの改善が進まず悩んでいるEM
- 日々の1on1で状況を把握できているのに、横断課題へのアクションにつなげづらいと感じている方
- プロダクト側のスピードと、サーバーサイドとしての中長期的改善のバランスに悩むマネージャー
- マトリクス組織で“縦と横”の動きがぶつかる構造に関心があるエンジニアリングリーダー
このトークから得られる学び
- サーバーサイドの横断課題が進みにくくなる、マトリクス構造ならではの理由を理解できる
- メンバーの負荷を増やさずに横断的な改善を進めるためのアプローチ
- 事業部の動きを尊重しながら、サーバーサイドとして必要な改善をどう組み込むか
- EM自身が判断軸を整え、改善を継続的に前に進めるための具体的な視点
- マトリクス構造を前提にサーバーサイドの基盤を育て続けるための考え方
EMを機能させる仕組みを探して ─ マトリクス組織で見えた変化と現実
 Genki Sano
Genki Sano 概要
私たちの開発組織では、目的別チーム構造のもとでEM(エンジニアリングマネージャー)を独自ロールとして運用していました。
EMは複数チームを束ねる立場として、もともと組織変更や配置計画にも深く関与していましたが、会社制度上の正式な「マネージャー」ではなかったため、評価や人事決定といった権限を十分に持てませんでした。
そのため、EMが責任を果たすには、制度上のマネージャーを兼任する必要があり、兼任による追加業務が負荷となって EMを増やしにくい構造 になっていました。
この問題を解消するために導入したのが、 職能別マトリクス組織 です。
職能軸を明確に持たせることで、EMを会社制度上のマネージャー枠組みに接続し、形式的な兼任を不要にしました。
現在は、四半期ほど運用を経て、 新たにEMを追加任命しやすい体制 が動き始めています。
本セッションでは、
- 制度の外にあったEMロールを、制度の内側へ位置づけ直すまでのプロセス
- その中で整理した権限設計・責任範囲・評価体制の具体例
- 制度変更後の運用で見えてきた変化と、新たに発生した課題
を具体的に共有します。
EMが現場と制度のあいだで、どのように動けば組織を前に進められるのか、今も模索を続けている実践をお話しします。
Learning Outcome
対象:
- 複数チームを見ているEM、または制度設計・組織設計にも関わる立場のマネージャー
得られるもの:
- EMの役割を制度上の位置づけに接続するための現実的ステップを学べる
- EMを拡張可能にする構造設計と運用上の工夫を理解できる
- マトリクス化による権限整理と現場運用のリアルな課題を学べる
EMの透明性をどう作るか ─ 社内ラジオを始めて見えてきたこと
 Genki Sano
Genki Sano 概要
「EMって何してるのか、よく分からない」
そんな声をきっかけに、私たちは “EM同士の雑談を垂れ流す社内ラジオ” を始めてみました。
隔週の社内勉強会のあとに15分だけ実施。スケジュールを先に決めて締切駆動にして、事前準備はトークテーマを考えるだけ。録画や集客は既存の勉強会の仕組みに乗せる。など、 運用負荷を極力増やさない設計 にしました。
アンケートや特別な編集もせず、 「続けることを最優先」 に継続しています。
まだ始めて3ヶ月ほどで、明確な効果は見えていません。
それでも、EMが何を考えているのか、どう意思決定しているのかを少しでも伝えられる手段として、価値を感じ始めています。
このセッションでは、 “透明性を仕組みではなく、日々の発信の積み重ねで育てる” という視点のもと、社内ラジオを通じて見えてきた運営の工夫・違和感・気づきを率直に共有します。
「成果が出る前の試行錯誤」を通じて、 EMの透明性をどう増幅していけるか を皆さんと考えたいです。
Learning Outcome
対象:
- チームやメンバーとの情報共有・信頼形成に悩むマネージャー
得られるもの:
- EMが透明性を高めるための“無理なく続ける”仕組み設計を学べる
- 成果が見えない段階でも実践を続けるための考え方を得られる
- 透明性は、仕組みよりも“日々の発信”の積み重ねで育つという視点を持ち帰れる
中途入社EMが社内問い合わせの窓口対応で築く信頼と組織価値
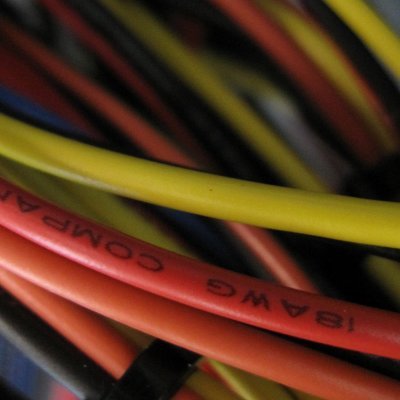 とりい
とりい いわゆるパラシュート人事のような形で既存組織にジョインしたEMが直面する代表的な課題として「コードベースの理解不足」「事業ドメイン理解不足」「既存メンバーとの信頼関係不足」が挙げられます。
私はEM候補として中途入社した自社Webプロダクト開発企業で、上記課題を解消する一環として社内問い合わせ窓口対応を継続してきました。
問い合わせ調査と対応を重ねる中で個人レベルでの上記課題の解消だけでなく、開発組織やプロダクトレベルへEMとしての貢献領域を広げられることが実感としてわかってきました。
これまで累計数百件の問い合わせに対応してきた約2年間の経験から、本セッションでは以下気づきを共有することで、参加者の学びや行動のきっかけにつなげられたらと考えています。
- チームへと広げる。信頼を築く窓口対応の実践
- 初動返信を徹底する
- 緊急度と重要度を判断する軸を磨く
- プロダクトへと広げる。統計データからの改善プロセス構築
- 問い合わせの傾向と頻度を把握する
- 優先度に応じた改修プロセス構築とタスクの見える化
- 組織へと広げる。顧客志向醸成に向けての展望
- 社内業務と問い合わせ先に存在するユーザーを理解する
- EMの隣接領域としてCRE業務を捉える挑戦
対象の聴衆
- 専任CRE組織がない環境で自社プロダクトを開発するEM
- 中途入社・異動でEMポジションに就いた方
- プレイング要素を委譲する中で、新たな選択肢を模索するEM
Learning Outcome
- 社内問い合わせ窓口対応からチーム内外との信頼関係を構築する具体的手法
- 問い合わせ調査を介して、プロダクトの安定運用に貢献する方法
- 問い合わせ対応の構造化を通して、顧客志向を組織へ広げるためのヒント
開発組織における合理的な意思決定 〜感情や曖昧さにどう立ち向かうか〜
 めもり〜
めもり〜 概要
メンバーとコミュニケーションをするたびに「バランスが大事」「上が言っているから」と曖昧なことを言っていませんか。
また,相手の発言を "自分の感覚や感情で" 否定したりしていませんか。
「言語化」は開発組織で合理的な意思決定をする上で最も重要です。私たちは普段,ロジックを積み上げてプロダクトを作っています。
しかし,マネージャーというロールを担った途端にロジックがうまく形成できないといった悩みを持っている方も多いのではないでしょうか。
マネージャーを長期間担っている方でも,曖昧な表現であったり,それこそ感情的なコミュニケーションの取り方になってしまっている方も見受けられます。
マネジメントは色が出やすいロールでもありますが,一貫して言えるのは,マネジメントの役割はスループットの最大化だと私は考えています。
スループットを最大化するためには,会社・事業の仕組みを理解し,言語化してメンバーに伝えていく必要があります。
本セッションでは,開発組織において合理的な意思決定をするための考え方から言語化まで解説します。
Learning Outcome
対象の聴衆
- エンジニアリングマネージャー,VPoE,CTOなどマネジメント職を担っている方
- 言語化に悩みを持たれている方
得られるもの
- 明日から実践で使える合理的な意思決定の方法
- 対メンバーに対して納得度合いを上げるコミュニケーション・言語化の方法
PdM不在のチームのEMが挑んだ、事業価値を生み出すための組織づくり
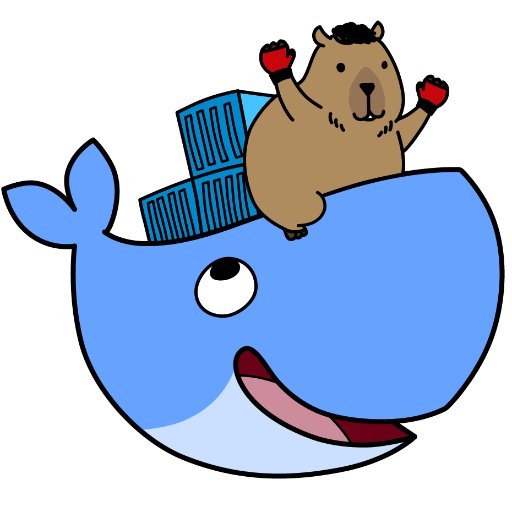 HonMarkHunt
HonMarkHunt 概要
一言でEMといっても、そのあり方や求められることは組織によって大きく異なります。
私は2025年1月からSREチームのEMを務めています。
SREチームは直接的なプロダクト開発から距離があり、チーム内に中長期の開発方針を決めるPdM(プロダクトマネージャー)が存在しません。
PdMがいないチームでは、「何を優先すべきか」「自分たちは何のために存在しているのか」を自分たちで定義する必要があります。
こうしたチームはSREに限らず、QA・データ基盤・Platform Engineering・セキュリティ・MLなど、プロダクトを支える領域に広く存在します。
私たちのチームもまさにその状況でした。日々の改善や運用タスクをこなしながら、「意味がないわけではないが、事業にどう貢献できているのか実感できない」という課題を抱えていました。
こうしたチームでは、EM自身が“プロダクトマネジメント的な役割”を担う必要があると気づきました。
チームのMissionを再定義し、業務をカテゴリごとに整理し、バックログを事業価値の視点で見直す、などの試行錯誤を通じて、少しずつ「自分たちの仕事の意味」をチーム全員で再定義していきました。
本セッションでは、PdM不在のチームのEMが事業価値と向き合うために行った具体的な工夫と、その中での失敗・気づきをお話しさせていただきます。
Learning Outcomes(聴衆が得られること)
- PdM不在のチームが自律的に事業価値とつながるアプローチの実例を知る
- プロダクトマネジメントの思考をチーム内に育てた実例
- 事業貢献、広くいうと「自分たちの仕事の意味」を再発見するまでのリアルなプロセスと苦労を知ることで、自分のチームでの変化のヒントを得られる
サーバントリーダーシップに「何を足すか」 〜事業価値を最大化するために”何でもやった”1年間〜
 ShinoP/しのぴー
ShinoP/しのぴー 概要
スクラムマスター(SM)/アジャイルコーチ(AC)からエンジニアリングマネージャー(EM)へのキャリアパスは、まだ少数派だと感じます。
本セッションでは、登壇者がSM/ACからEMへとキャリアを移行した実体験をお話しします。
企業の急成長期において、SMとして一つのチームにコミットするだけでは事業全体に大きな影響を与えられないと感じ、より大きな影響力を持って事業に貢献するためEMになることを決意しました。
EMとしての1年間の経験を通じて、EMには「確固たる定義がない」という現実でした。SM時代に培ったサーバントリーダーシップが、必ずしもEMとして全ての状況で最適解とは限らないこと 、そしてチームの状況に応じて事業価値や顧客価値に貢献するために不足している部分を補う「何でもやる」姿勢の必要性を痛感しました。
本セッションでは、従来のプロセス改善といった得意分野が活かせない状況下で、事業価値や顧客価値に貢献するための別の「武器」を持つ必要性を感じた経緯や、チームの状況に応じて自らが適応し、足りない部分を補う「チームにとって必要なこと、事業にとって必要なことは何でもやる」という、より広範囲な「何でもやる」姿勢こそが、真のエンジニアリングマネージャーに求められる立ち振る舞いであると結論付けます。
Learning Outcome
対象の聴衆
- これからエンジニアリングマネージャー(EM)を目指そうとしている方
- スクラムマスターやアジャイルコーチからEMへのキャリアチェンジを検討している方
- エンジニアなど、他のロールからEMへのキャリアチェンジを検討している方
- 現役のEMで、自身の役割や立ち振る舞いについて他の事例を知りたい方
その人たちが得られるもの
- SM/ACからEMという、まだ一般的ではないキャリアパスの実例
- EMの役割に「確固たる定義がない」中で、事業やチームの状況に応じてどう価値貢献していくかの視点
- サーバントリーダーシップがEMの現場でどのように機能し、またどのような限界があったかという実例
- EMとして事業価値に貢献するため、自身の得意分野(プロセスマネジメントなど)以外で「何でもやる」必要性に直面した際の具体的な行動例
「お手並み拝見」を「協奏」に変える。 新任EMと受入れ側の90日オンボーディング戦略
 げん
げん 「概要」
「EMポジションでの転職が初めて」— 私が身構えていたのは、「お手並み拝見」という見えない壁でした。
しかし、その不安は杞憂に終わります。
なぜか? 分析して見えたのは、単なる運ではなく、新任の私と「受け入れ側」の行動が噛み合った「協奏」でした。
私(新任EM)が意識したことは 「リスペクト」と「アクセル調整」です。
まず、転職者が陥りがちな「前の職場との違いを、今の職場の課題としてしまう」ことを避けるため、徹底的に「過去の意思決定へのリスペクト」に注力し、信頼の土台を築きました。
同時に、自身の理想とのGAPに対しては「踏みすぎか?もっと踏むべきか?」と、自らアクセルの踏み具合をチューニング。周囲にフィードバックを求め、最適な速度を探り続けました。
受入れ側が意識していた(であろう)ことは絶妙な「期待値調整」と「戦略的チャレンジマネジメント」です。
「期待はしているが焦らなくて良い」と伝えつつ、"期待していない"と誤解される難易度の低すぎるタスクも、"パニックになる"緊急度の高すぎるタスクも避ける。
私を信頼し、「重要だが緊急ではない」絶妙なアサインメントを任せることで、早期に「アウトプット」を出す機会を創出してくれました。
本セッションは、この体験を再現性ある仕組みとして棚卸ししたものです。「自分が受け入れる側になった時に活かしたい」、このオンボーディングの協奏モデルを20分に凝縮してお話しします。
「Learning Outcome」
対象の聴衆
- (特に重要) 新しいEMをチームに受け入れ、その立ち上がりを支援したいマネージャーやメンバー
- EMポジションで初めて転職し、どう価値発揮すべきか悩んでいる方
- エンジニアからEMへのキャリアチェンジを目指す方
その人たちが得られるもの
- 新任EMが「お手並み拝見」の壁を越えるために、「受入れ側」が仕掛けるべき「絶妙な期待値調整」と、"簡単すぎず・緊急すぎない"「戦略的チャレンジマネジメント」の手法
- 新任EMが信頼を獲得するために、「本人が」実践すべき「過去へのリスペクト」と「フィードバックを活用したアクセル調整」という具体的な行動
- 新任EMと受入れ側の「すれ違い」を防ぎ、「協奏」を生み出すための、最初の90日間のオンボーディング設計図
EMからVPoEを経てCTOへ:マネジメントキャリアパスにおける葛藤と成長
 yunon_phys
yunon_phys 本セッションでは、EMからVPoEを経てCTOへと役割を広げていったキャリアパスを歩んできた実体験を通じて、
各役割における視点の違いを理解し、自らの意識や行動を変えながら成長してきたプロセスを共有します。
各役割では、異なる視点とアプローチが求められました。
EMではPeople/Project/Product/Techのマネジメントをフル活用して、チームの成果をいかに最大化することにフォーカスしました。
VPoEではエンジニアリング組織全体の戦略と実行を担い、開発組織視点での人・組織の仕組みづくりや人の配置の最適化により、短期的な成果の最大化をはかりました。
CTOでは技術戦略とビジネス戦略の接続を担い、経営リソースをフルに活用した意思決定を行い、短期〜中長期的な組織的な成果の最大化をはかっています。
役割の変化に応じて、求められる知識やスキルの領域も広がっていくことを実感してきました。
特定領域における深い専門性はコスト効率の高い意思決定を可能にする強力な武器である一方で、
対応領域の広さは経営に近づけば近づくほど重要になってきます。
特に、組織開発・ファイナンス・アカウンティングといった経営の知識を身につけることは、より戦略的な意思決定が可能になる糧となりました。
この広さと深さのバランスをどう取るかは、マネジメントキャリアパスを歩む上で重要な課題だと理解しました。
役割の広がりの過程には、避けて通れない葛藤や悩みも伴いました。
エンジニアとして良しとされているスペシャリスト思考のキャリア観から外れているという感覚に、悩まされる日々。
専門外のスキルが要求されるようになってくることによる無能感、コストに見合わない人材になっていく不安感なども、マネジメントキャリア特有の悩みでした。
自分が一人で抱えることの限界を迎えたときに誰かに業務を渡すことの、その球の重さへの申し訳なさは現在でも良く起こる葛藤です。
本セッションでは、これらの困難や葛藤を乗り越えるために、どのように視点や意識や行動を変えて成長してきたかを、マネジメントキャリアパスの実体験を通じて共有します。
Learning Outcome
- EM/VPoE/CTOの視点の違いと必要とされるスキルセット
- マネジメントキャリアパスを歩んでいく際の心構えとスタンス、考え・行動の変え方
リリース効率を犠牲にしないチーム設計 ― 理解とデリバリーをつなぐ仕組みづくり
 shunsuke
shunsuke 概要
複数ドメインの並行開発が進む中で、チームの認識齟齬とリリース効率の低下に直面しました。 EMとして、私は「Project / People / Technical」を横断しながら、チームの理解と実装をつなぐ構造の再設計に取り組みました。
当時のチームは、各人が別タスクを進める“リソース効率”型の進め方に陥り、さらに新規ドメインのキャッチアップとリリースが並走していました。 認識ズレや手戻りが増え、チーム全体の学習速度とアジリティが低下していました。 この混乱を抑えるため、PdM・QA・実装担当・レビュアー全員で行うタスク分解セッションを導入。 FigJam上で受け入れ条件・要件・実装方針・テスト観点を整理し、1つのPBIを全員で分解して理解を揃えました。
当初は不確実性を最速で減らすための対応でしたが、振り返るとこれは、チームが課題を認識し、理解し、判断できる構造をつくる試行でもありました。
PdMは実装難易度を肌感で掴み、エンジニアはWHYを踏まえた実装を行い、QAは仕様不足に気づけるようになりました。 短期的にはスプリントが安定し、レビューや再実装に伴う手戻りが減少しました。
一方で知識や判断軸の非対称性は依然として残り、「どこまで同期し、どこから任せるのか」という構造設計の境界に今も模索が続いています。
本セッションでは、リソース効率の罠を超え、チーム状態に合わせてフロー効率と学習構造を再設計する実践を紹介します。
以下のブログに記載した実践の振り返りを踏まえ、そこからさらに見えてきた課題と仮説を共有します。
https://tech.up-sider.com/entry/20251003_card-division
Learning Outcome
対象:
- 複数ドメイン・複数案件を同時に抱える EM / PdM / Tech Lead
- スプリント内で認識ズレ・手戻り・リリース遅延に悩むチームを率いる方
得られること:
- 複雑なドメインでも、チーム全体で理解と判断を同期させる構造設計の具体的アプローチを学べる。
- タスク分解や意思決定の可視化を通じて、理解と速度を両立させるファシリテーション設計の実例を得られる。
- EMがチームを“動かす”のではなく、“自ら動き出す構造”を設計するための思考の枠組みを持ち帰れる。
行政と共に歩む開発組織 ーデジタル庁の立ち上げからの4年間を振り返る
 松館 大輝
松館 大輝 デジタル庁は設立から5年目を迎えました。
中央省庁にありながら官民融合のチームとして、デジタル政策を推進し、数々のサービスや仕組みを生み出してきました。
私もその一員としてデジタル庁の立ち上げから携わり、これまでの専門性に固執せずにさまざまな領域の担務に関わりながらデジタル庁のエンジニアとしてのあるべき姿を模索してきました。
私が現在ユニット長を務めるエンジニアユニットには、民間から参画したソフトウェアエンジニアが所属しており、デザイナー、プロダクトマネージャーたちと調達では実現できないスピードと専門性で社会的インパクトのある課題に挑戦しています。
このトークでは、行政組織という特殊な環境で立ち上げからエンジニアが活躍できるようになるまでを振り返り、内製開発への取り掛かりと実践を紹介します。
「iPhoneのマイナンバーカード」や「マイナンバーカード対面確認アプリ」などの内製開発の事例における振る舞いや開発におけるアプローチも紹介しながら4年間の試行錯誤を共有します。
組織の成長とともにこの4年間で私自身の振る舞いや態度がどのように変わっていったのかも見どころのひとつです。
民間組織のEMと呼ばれるポジションとの違いから、行政組織におけるEMの役割を定義してみたいと思います。
Learning Outcomes
対象: 特に行政・公共領域に興味がある現在EM/VPoE、TL、エンジニア、デザイナー、プロダクトマネージャーの方、その他将来EMと呼ばれるロールになってみたい全ての方々
• 新しい行政組織における内製開発の最初の一歩
• 官民融合組織における民間専門人材の振る舞いから、専門領域の違う方々との協業の仕方
• 既存の調達中心の開発にどのように内製開発を両立させていくか進め方やアプローチ
• エンジニア上がりのEMがマネジメントを進めるうえでのコツ
• 行政と民間組織のEM目線での違いと振る舞い方
“Next EM”仲間を知るワークショップ?
 高原 宏(piro)
高原 宏(piro) EMConf JP 2025 で『マネージャー全員でマネジメントポリシーを作った』話をさせていただいた際は、EM 同志での経験知と探究テーマの共有を試みました。
ところが協賛案内資料で前回参加者の「職種」分布をみると、もちろん EM が最多でしたが、その半数以上も「エンジニア」の方々が参加されていたと分かりました!そしてそれ以外の様々な役割で開発組織に関わっている方々も大勢!!
つまり、前回の EMConf JP に集まった 1/3 以上が、『自分は今 EM じゃないけど EM 向けの話を聞きに来た』方々だったのです(そんな志の高い皆さんを “Next EM” と呼んでみます)。
ならば、これだけ多くの “Next EM” が集う機会を生かすことができないか?
→“Next EM”な皆さんの関心事を知る場にしたい
→“Next EM”な皆さん同志がお互いを認識し合い、繫がれる場にしたい
さらに、“現役EM” を含む “先輩EM” の皆さんもこの場に集まってくださるならば・・
→“Next EM”な皆さんに“先輩EM”からヒントを贈れる場にしたい
→“Next EM”な皆さんそれぞれの関心事に寄り添えるメンター的な“先輩EM”と出逢える場になると最高じゃないか?
・・などとイメージが膨らんじゃいました。
そのような場を、いろいろな角度から問いかけをさせていただいたり、燃料になる情報を示させていただいたりして実現したいと思います。
そして参加者の皆さんにも能動的に場づくりに加わっていただける、創発的なワークショップやタウンミーティングのような場づくりを試みたいと思います。
Learning Outcome:
for “Next EM”
・エンジニアリングマネジメントに関心のある仲間の存在を知れる
・エンジニアリングマネジメントについて他者の関心事を知れる
・EM を目指す/担うにあたってのヒントを得られる
(→次に探究するテーマが見つかって新しい扉が開くようだと最高です)
for “先輩EM”
・“Next EM” が考えていることを知れる
・自身のエンジニアリングマネジメントを客観的に見直す気付きを得られる
・(マネージャーのなり手が少ない組織も多いなか)未来の EM の成長を支援する材料を得られる
※他社の仲間と共同登壇を検討しています
創業取締役元CTOからの継承 - 外部参画ディレクター『最初の1年』で築いた信頼の3階層
 向田英雄
向田英雄 ▼概要
2025年3月、私は上場スタートアップ株式会社Rebaseに初の外部ディレクターとして参画しました。前任者は共同創業者で元CTO。技術力が高く組織から信頼される10歳年下のリーダーです。30名で上場を成し遂げ、入社時には45名に成長した組織。この継承に臨むにあたり、私は3つのミッションを定義しました。
・創業取締役元CTOからのスムーズな引き継ぎを実現すること
・外部ディレクター初事例として会社に成功体験をもたらすこと
・自部門だけでなく全社視点で価値を創造すること
エンジニア出身でEM・VPoE、事業責任者、プロダクトマネジメントなど約20年のキャリアを持っていますが、外部参画の壁は高かったです。
第1階層:組織の歴史を最大限尊重する(最初の3ヶ月)
最初の3ヶ月は変革を起こさないと決め、社員の80%と1on1を実施。前任者との週次1on1も提案し、「まず理解する」ことで課題の質を高めることを重視しました。
第2階層:見えない課題を発見し先手を打つ(4〜6ヶ月)
事業責任者経験を活かし、事業計画から未来の課題を予測。PMやCXチームとの連携を少しずつ深め、水面下で自部門メンバーのキャリアなどもヒアリング。未来の体制変更に向け準備を進めました。
第3階層:信頼を基盤に変革を実行する(7〜12ヶ月)
下期開始時には、エンジニアリング部門12名の大幅な体制変更を実施。幸いにもメンバーからの大きな抵抗はなく、「なぜこの変更が必要か」を理解してもらえたように感じます。
このトークでは、外部参画の最初の1年で私が直面した課題、試行錯誤、失敗と小さな前進を率直にお話しします。
▼対象の聴衆
・外部から参画したが組織に溶け込めず苦戦しているエンジニアリングマネージャー
・組織変更や体制変更に抵抗を感じ、実行できずにいるリーダー
・上場後の成長ステージで組織課題に直面しているリーダー
▼その人たちが得られるもの
・「ヒトに興味を持つ」ことから始まる信頼構築の実践手法 - 社員の80%と1on1を実施した具体的アプローチと傾聴
・外部参画者が最初の1年で成果を出すための取り組み - 信頼ゼロから体制変更実施までの具体的ロードマップ
・エンジニア×事業責任者×PMの3視点を統合した連携術 - 技術・事業・プロダクトを繋ぐ具体的な取り組み
1人目EMとして入社した私がプロダクト組織のボトルネックになり、2人目EM採用を通じて乗り越えた話
 naopr
naopr 現職に1人目のEMとして入社してから2年が経ちました。
当時、エンジニアは10名ほどで、CTOと私の2人でEMの役割を分担していました。
しかし、エンジニアが20名を超え私のレポートラインが15名ほどになった頃から、
採用・育成・組織運営のすべてが中途半端になり、私自身がボトルネックとなってしまいました。
そこで2人目EMの採用を検討し始めたものの、いくつもの壁に直面しました。
たとえば次のような論点です。
- 「内部登用にするか、外部採用にするか」
- 「候補者が少ない中、どんな期待値で募集すべきか」
- 「経営陣にどう必要性を説明すべきか」
加えて、私自身が1人目EMとして多岐にわたる業務を担っていたため、
どの業務を2人目EMに委譲し、どのように責任を分担すべきかという点にも大きく悩みました。
本セッションでは、
「1人目EMしかいない組織が、どうやって次のEMを迎え入れ、活躍できる体制を作るか」
をテーマに、実際に私が経験した検討・採用・業務設計・立ち上げまでの具体的なプロセスをお話しします。
アジェンダ(予定)
- 1人目EMとして取り組んできたことと、見えてきた限界
- 2人目EM採用の検討(内部登用/TL兼務/外部採用)
- 経営とのすり合わせと期待値の明確化
- 2人目EM候補者への魅力づけと採用プロセス設計
- 入社後の業務分担・権限移譲の進め方
- 2人目EMの参画による変化と学び
想定リスナー
- 組織拡大に伴い、2人目以降のEM採用を検討しているCTO/VPoE/EM
- 小規模プロダクト組織でEMとして入社・活躍を目指す方
- 小規模プロダクト組織に属しており、将来的にEMを目指しているエンジニア
得られる学び
- 2人目EMを採用する際に直面する典型的な課題と、その乗り越え方
- EM人数の少ない組織における期待値設定とオンボーディング設計の実践例
- マネジメントを特定個人に依存させず、権限を分散・委譲するための実践的アプローチ
QA組織の変化を支える仕組みと基盤づくり 〜自律的に動ける組織を目指して〜
 tarappo
tarappo 概要
本セッションでは、組織拡大に伴い生じたQA課題に対し、QA組織が体制と運営を見直し、変化を進めた実践を紹介します。
開発やプロダクトの組織が成長に合わせて仕組みを変える一方、QA組織は従来のやり方を続け、変化に追いつけていませんでした。
当初、QAEは開発チームに入り、QAの実践をリードする立場として活動していました。
しかしチームが増えるにつれ、横断的なイネイブリング活動を強化し、レビューや壁打ちなどの支援を通じての関わり方も進めました。
一見うまく機能しているように見えましたが、少しずつQA組織としておこなえていることの幅が狭くなっていきました。
そこで「ボトムアップ」と「トップダウン」の両輪を活かすことができるQA組織にする必要があると考えました。
まず、QA組織のメンバーがより自律的に動けるように「成果を出せる環境作り」「成果が評価される仕組みづくり」「成果を知ってもらう仕組みづくり」を整えるために、次のようなことを進めていきました。
- 進む方向性の提示として目指す姿の共有
- 進む方向の後押しをするためのスキルの現状把握とスキルアップ支援
- 評価の軸の明確化と方向性がよりわかる等級制度の見直し
さらに、QA組織が他組織と動けるようにマネジメント層との連携強化や、そのための品質保証部から本部への拡大など、より横断的に動けるような組織へと整備をしていきました。
この両輪によって、QA組織が他組織と連携しながらQA面でリードできる基盤が整いつつあります。
結果として「QAEをどこにアサインするか」ではなく「どんなスキルが必要か」という視点でQA体制を検討できるようになり、組織全体で考える第一歩が進み出しています。
組織の変化に合わせてQA組織が適切にコミットメントできるようにするための実践と、その過程で得た知見を共有します。
Learning Outcome
対象:QAに関わるメンバー、EM、プロダクトマネージャー、開発チームのメンバーやEMなど
得られること
- 組織の成長に合わせてQAの役割や体制を再設計するための視点
- QA組織が他組織と連携しやすい仕組みを整えるアプローチ
- メンバーが自律的に動けるようにする制度・支援設計の具体例
- 変化を続ける組織でQAが持続的に機能するための実践知
属人化から組織化へ、他責から自責へ。 〜2つのチームで学んだ組織スケールの処方箋〜
本セッションでは、生成AI機能を開発するチームとタブレットアプリを開発するチームで直面した課題について、我々が試行錯誤したアプローチや学びについて紹介します。
生成AI機能開発チーム
生成AIを活用した新機能開発プロジェクトが発足し、社内でメンバーを集めて生成AIチームを立ち上げました。
チームとして活動を進める中で、いくつか課題がありました:
-
社内に生成AIを専門とするエンジニアが不在で、一からキャッチアップする必要があった
最初はkintoneをデータソースとしたRAGの機能を提供するために、自分が主導してPoCを作ったり設計をしてチームに展開しました。
それと並行してLLMに関する知識のキャッチアップをチーム皆で進めつつ、機能開発を進めていきました。 -
属人化していて、自分含む特定のメンバーが抜けると業務が回らなくなるリスクがあった
OJT方式で併走することで、後任を育成するところを進めました。
こうしたことで移譲が上手くいったのもあり、組織化して堅牢な体制を作ることができました。
モバイルチーム
kintoneと連携できるタブレットアプリ開発のプロジェクトが発足しました。
モバイルチームの課題として、
開発速度が遅い→Webチームの方が価値提供が早い→機能開発の経験が積めない→開発速度が遅い...の負のスパイラルに陥っていて、周囲からも信頼が得られていない状況が続いていました。
チームとしても、利用できるAPIが整備されていないことや、UI/UXデザイナーが不在なことが要因で遅くなっていると他責なマインドになっていました。
開発速度が遅くなっている要因を特定するため、メンバーへのヒアリングや実際の開発現場の観察を通じて情報収集を行いました。
その結果、メンバー間のスキル差とAPI整備の不足という2つの課題が浮かび上がったため、まずはこれらの改善に着手しました。
特にモバイル開発において、APIが十分に整備されていないという問題がありました。そこで、共通インターフェースの設計方針やチーム内のコミュニケーション方法を決定し、開発環境を整えていきました。
こうした施策を実施した結果、徐々にメンバーの意識が他責から自責へと変わっていく変化が見られました。
現場を離れたCTOが手を動かし再発見した「マネジメントの原点」〜ハンズオンと組織視点を行き来した1年の物語〜
 赤沼 寛明
赤沼 寛明 現在私は、UPSIDERの「支払い.com」事業部で、事業とプロダクト開発・運用の両面に関わりながら、CTO/EMとして活動しています。
マネジメントを担う立場でありながら実際に手を動かす“ハンズオンCTO”として過ごしたこの1年は、「マネジメントの原点とは何か」を改めて考える期間でした。
以前は10年間、取締役CTOとして組織・人・事業のマネジメントに注力していました。
経営判断や採用・評価に時間を割く一方で、現場感覚が薄れ、“自分がバリューを出せていないのでは”という違和感を抱えていました。
再び現場に戻ったことで、マネジメントの視点は大きく変化しました。
少人数でも高速に動くチーム体制、プロダクトマネジメント・技術・経営の橋渡し、そして「手を動かすこと」が意思決定やチームの信頼に与える影響を実感しています。
本セッションでは、
- 経営と現場を行き来して見つけた“マネジメントの原点”
- 少人数・高速開発を支える組織構造と意思決定の工夫
- 現場に関わることがチーム関係性を変えた実例
これらの実体験と学びを通して、マネジメントの役割を改めて問い直します。
スピーカー略歴
エムスリー、Nubee Tokyoを経て2015年ユニファに参画。取締役CTOとしてチームを率い複数プロダクトを立ち上げ。2025年4月よりUPSIDER「支払い.com」事業部CTO。
Learning Outcome(対象の聴衆と得られるもの)
- 対象の聴衆:
- CTO/VPoE/EMとして、組織拡大期・変革期にある技術部門を率いている方
- 少人数体制・スタートアップフェーズにおいて、マネジメント/開発/運用を兼務している方
- 現場から離れたマネジメント経験者で、再び開発・プロダクトに関わる意義を探している方
- 得られるもの:
- 経営マネジメントに専念していたCTOが再び現場に戻った際に直面した“ギャップ”とそれを乗り越えるステップのリアルな知見
- 手を動かしながらマネジメントを行うことで生まれた「チームの信頼」「技術/開発速度」「意思決定の質」の変化と、その実践から得た仕組み
- ハンズオンと組織視点の間を行き来できるマネジメント体制の設計ヒント(特に少人数・高速開発を前提とした体制)

