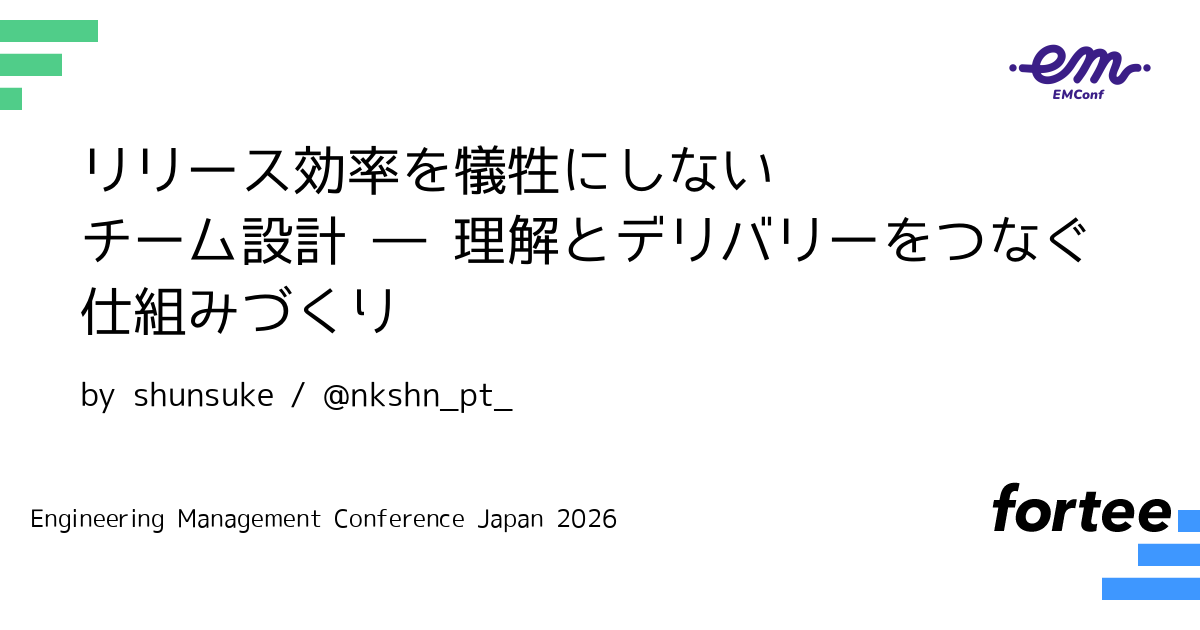
Engineering Management Conference Japan 2026
セッション(20分)
リリース効率を犠牲にしないチーム設計 ― 理解とデリバリーをつなぐ仕組みづくり
 shunsuke
nkshn_pt_
shunsuke
nkshn_pt_
概要
複数ドメインの並行開発が進む中で、チームの認識齟齬とリリース効率の低下に直面しました。 EMとして、私は「Project / People / Technical」を横断しながら、チームの理解と実装をつなぐ構造の再設計に取り組みました。
当時のチームは、各人が別タスクを進める“リソース効率”型の進め方に陥り、さらに新規ドメインのキャッチアップとリリースが並走していました。 認識ズレや手戻りが増え、チーム全体の学習速度とアジリティが低下していました。 この混乱を抑えるため、PdM・QA・実装担当・レビュアー全員で行うタスク分解セッションを導入。 FigJam上で受け入れ条件・要件・実装方針・テスト観点を整理し、1つのPBIを全員で分解して理解を揃えました。
当初は不確実性を最速で減らすための対応でしたが、振り返るとこれは、チームが課題を認識し、理解し、判断できる構造をつくる試行でもありました。
PdMは実装難易度を肌感で掴み、エンジニアはWHYを踏まえた実装を行い、QAは仕様不足に気づけるようになりました。 短期的にはスプリントが安定し、レビューや再実装に伴う手戻りが減少しました。
一方で知識や判断軸の非対称性は依然として残り、「どこまで同期し、どこから任せるのか」という構造設計の境界に今も模索が続いています。
本セッションでは、リソース効率の罠を超え、チーム状態に合わせてフロー効率と学習構造を再設計する実践を紹介します。
以下のブログに記載した実践の振り返りを踏まえ、そこからさらに見えてきた課題と仮説を共有します。
https://tech.up-sider.com/entry/20251003_card-division
Learning Outcome
対象:
- 複数ドメイン・複数案件を同時に抱える EM / PdM / Tech Lead
- スプリント内で認識ズレ・手戻り・リリース遅延に悩むチームを率いる方
得られること:
- 複雑なドメインでも、チーム全体で理解と判断を同期させる構造設計の具体的アプローチを学べる。
- タスク分解や意思決定の可視化を通じて、理解と速度を両立させるファシリテーション設計の実例を得られる。
- EMがチームを“動かす”のではなく、“自ら動き出す構造”を設計するための思考の枠組みを持ち帰れる。

