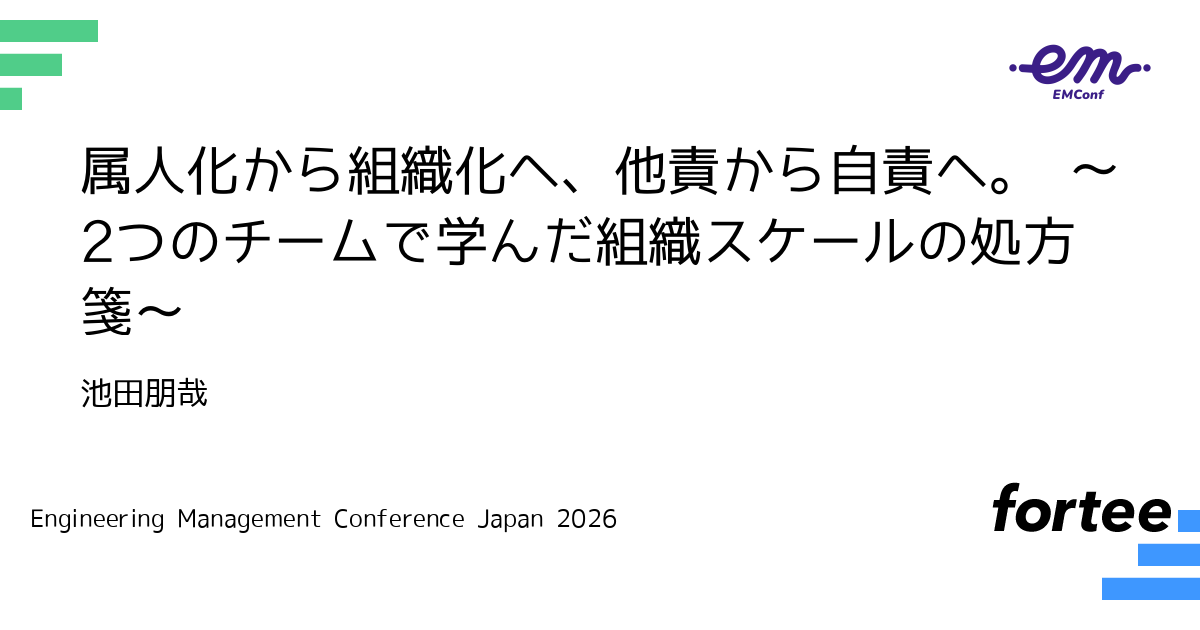
Engineering Management Conference Japan 2026
属人化から組織化へ、他責から自責へ。 〜2つのチームで学んだ組織スケールの処方箋〜
本セッションでは、生成AI機能を開発するチームとタブレットアプリを開発するチームで直面した課題について、我々が試行錯誤したアプローチや学びについて紹介します。
生成AI機能開発チーム
生成AIを活用した新機能開発プロジェクトが発足し、社内でメンバーを集めて生成AIチームを立ち上げました。
チームとして活動を進める中で、いくつか課題がありました:
-
社内に生成AIを専門とするエンジニアが不在で、一からキャッチアップする必要があった
最初はkintoneをデータソースとしたRAGの機能を提供するために、自分が主導してPoCを作ったり設計をしてチームに展開しました。
それと並行してLLMに関する知識のキャッチアップをチーム皆で進めつつ、機能開発を進めていきました。 -
属人化していて、自分含む特定のメンバーが抜けると業務が回らなくなるリスクがあった
OJT方式で併走することで、後任を育成するところを進めました。
こうしたことで移譲が上手くいったのもあり、組織化して堅牢な体制を作ることができました。
モバイルチーム
kintoneと連携できるタブレットアプリ開発のプロジェクトが発足しました。
モバイルチームの課題として、
開発速度が遅い→Webチームの方が価値提供が早い→機能開発の経験が積めない→開発速度が遅い...の負のスパイラルに陥っていて、周囲からも信頼が得られていない状況が続いていました。
チームとしても、利用できるAPIが整備されていないことや、UI/UXデザイナーが不在なことが要因で遅くなっていると他責なマインドになっていました。
開発速度が遅くなっている要因を特定するため、メンバーへのヒアリングや実際の開発現場の観察を通じて情報収集を行いました。
その結果、メンバー間のスキル差とAPI整備の不足という2つの課題が浮かび上がったため、まずはこれらの改善に着手しました。
特にモバイル開発において、APIが十分に整備されていないという問題がありました。そこで、共通インターフェースの設計方針やチーム内のコミュニケーション方法を決定し、開発環境を整えていきました。
こうした施策を実施した結果、徐々にメンバーの意識が他責から自責へと変わっていく変化が見られました。

