SIerの開発者組織で横串活動を推進していたら組織のリーダーになったので最初の2ヶ月間の試行錯誤をシェアしたい
当社にはエンジニアの中でも特にシステム開発に強みを持つ人を100名ほど集めた仮想組織があり、私は2025年6月からそこの長をやることになりました。
社内に無数に存在する大小様々なシステム開発プロジェクトに対し、設計や実装だけでなく開発プロセスマネジメントや品質保証なども含む、広い意味での技術力をもって貢献することが主なミッションで、加えて新技術検証や技術者育成も行っています。
私は新卒から勤めて11年目にあたり、昨年からはこの組織内で開発プロセス関連施策のチーム(6,7名程度)をリードする立場にいたものの、組織全体をリードするのは初めての経験であり、ワクワクと不安を同時に抱えています。
大吉祥寺.pmで話す頃には就任して2ヶ月ほど経過しているはずなので、開発者組織で横串活動をしている方やこれからやっていきたい方向けの参考として、本トークでは私の試行錯誤の過程をシェアできればと思います。
WezTerm運用におけるプラクティスと、Terminal & CodingAgentの相互運用性
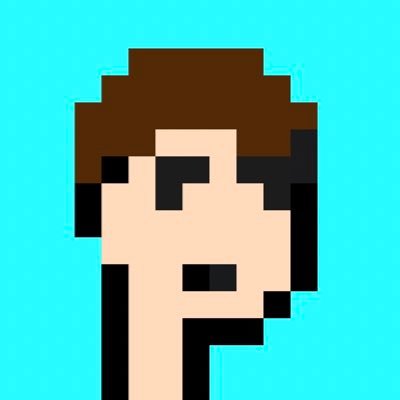 fujitani sora
fujitani sora WezTermのConfiguration as Codeによるカスタマイズ性と、Workspaces機能によるシンプルなセッション管理は取り回しが良く、いくつかのTerminalEmulatorを触ってきた自分の現状ベストな開発環境であると言えます。
また、エディタと一体化したCodingAgentの利用が開発者の生産性を向上させ、議論に上がることが多いここ最近です。
Terminalから起動するNeoVim等でも同等の目的を果たすためのプラグインが出ていますが、それでもベンダー提供のIDEに移行する開発者も多いように感じています。
この課題を解決しようとしている手段に、今年の技術トレンドの一つであろうCodingAgentのCLI実行環境の提供があると考えています。
本発表では、WezTerm運用の個人的プラクティスと、CodingAgentツールとの相互運用性についてまとめます。
開発を加速するための開発
 karupanerura
karupanerura 生成AIによるコーディング支援などによって、ソフトウェアエンジニアとしては「どう作るか」について考える機会が多くなってきた昨今でしょう。
しかし、アイディアを形にする方法が多様化し効率化してきた一方で、それ以外の部分について考えることがより重要性を増してきているとも感じます。
そのなかでも開発を加速するための開発は、場合によってはその要求すらも明確ではないものの、もしそれが存在すれば明らかに便利なものが実はたくさんあるのではないかと思います。
たとえば、それは動作確認を便利に行うためのツールであったり、単にアプリのなかのデバッグメニューであるかもしれません。あるいは、クラウドソリューションに足りない機能を補完するものかもしれません。
このセッションでは筆者が実務を通じて実際にそういったものを作ってきた経験から、チームにとって本当に必要なものの形を見極めるエッセンスをご紹介します。
「狭間人間」だった私が、みんなが「狭間人間」となれることに期待している
 大山奥人
大山奥人 昔、とある界隈のジャーゴンとして「狭間人間」という言葉がありました。
2019年前後から、デザインエンジニアのようなデザインとエンジニアリングの両輪を担う存在として称されていました。それぞれの職域が交わるベン図のような「狭間」の部分が存在し、その部分が狭間人間としてバリューを提供できていました。
2025年現在、生成AIが世の中に徐々に浸透しだし、かつて1人ではなかなかできなかったことが、できるようになってきました。つまり、プログラミングをしたことがなかった人が自身のバリューを活かしながら他の領域に染み出せるようになっています。
私はこの状況を見て、いろんな人たちが「狭間人間」となれるのではないか、と考えています。
このトークでは、2019年のころに生まれた狭間人間を振り返りつつ、2025年現在の私が考える狭間人間についてをお伝えしたいと思っております。
noteを100日間書き続けて気づいた「言語化と承認」の力
2025年春、毎日noteを100日間連続で書いてみました。
目的は「アウトプットの習慣化」でしたが、やってみると気づきがたくさんありました。
・承認欲求との向き合い方
・書き続ける中で見えてきた自分の「軸」
・誰かのために書くことの意味と限界
・noteという“半分パブリック”な場所が持つ絶妙な距離感
「100日書く」という行為そのものよりも、その過程でどう気持ちが揺れ動き、何が残ったのかを中心に話します。
今まさに情報発信やアウトプットに迷っている人、自分の声の届け方を模索している人に、ちょっとしたヒントになる話ができればと思っています。
言っておきたいことを言う技術
 Masaki ASANO
Masaki ASANO 日常でコミュニケーションを取らない日はない、と言っても過言ではありません。
一方、コミュニケーションで「言っておきたいこと」を適切に伝えるのは難しいと感じることはありませんか?
例えば、ミーティングで「コレ、聞いてええんかな?」と躊躇したり、ふりかえりの場で「アレを言いたかったのに…」と後悔したり、あるいは、ネガティブなことを伝えるにはどうすればいいんだろうか?と悩むこともあるのではないでしょうか。
このトークでは、そうした「言っておきたいこと」を、どのように考え、どうすれば伝えられるようになるのか、そのための「技術」についてお話しします。
アジェンダのイメージ
- 「言っておきたいこと」は何のため?
- 自分が言うべきなのか?
- 自分が言わなきゃ誰が言う?
- 代打依頼、悪魔の代弁者
- 何をどのくらい伝えるのか?
- どうやって伝えるのか?
独立系中堅SIerのリードエンジニアから事業会社のテクニカルPdMになった話
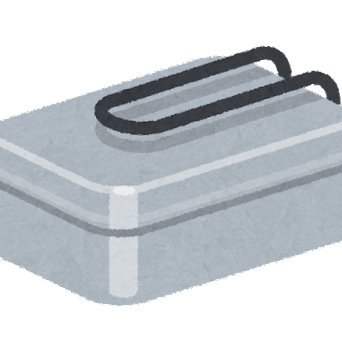 kazu_kichi_67
kazu_kichi_67 昨今、「テクニカルPdM(プロダクトマネージャー)」というロールが注目を集めています。
私自身、新卒から10年以上にわたり独立系中堅SIerのリードエンジニアとしてキャリアを重ねてきましたが、2025年4月に突如として事業会社のテクニカルPdMへと転身しました。
この「大吉祥寺.pm 2025」が開催される頃には、転職から約5ヶ月が経過したところ。
まだまだ駆け出しPdMではありますが、エンジニアからテクニカルPdMへロールチェンジしたリアルを、等身大でお伝えできればと思っています。
想定しているアジェンダ
- 簡単に自己紹介
- SIerと事業会社の働き方の違い
- PdM / テクニカルPdMってどんな仕事?
- 転職活動について
- エンジニアバックグラウンドだからこそ活かせる強み
- 逆に弱み、苦労していること
- まとめ(これからPdMを目指す人に伝えたいこと)
~キャラ付け考えていますか?~ AI時代だからこそ技術者に求められるセルフブランディングのすゝめ
 モブエンジニア
モブエンジニア 初めまして。モブエンジニアと申します。
ChatGPT、Claude含む生成AIサービスを通じて、コーディング・設計含むさまざまな業務が効率化していっています。
そのうえで、「技術者として生き残っていくために何を行わなくてはいけないのか」といった課題に直面していると思います。その断面から、「セルフブランディングの視点」から技術者の生き残り戦略について、15分のトーク内でお話ししていきたいと思います。
【ターゲット層】
1.SNSでのセルフブランディングに悩んでいる方
2.AI時代に技術者として生き残る方法を模索している方
(3.私の句を聞きたい方)
【持ち帰ってもらいたいこと】
1.セルフブランディングはツールであり目的でない
2.キャラ付けは日々ブラッシュアップさせていく
3.X・勉強会をうまく活用していく
AI Agentで下駄を履け!エンジニアの世界から事業推進の世界に飛び込んだ話
 daitasu
daitasu 今年、今までの畑であるエンジニアの世界から距離を置き、営業組織やCSなど、様々な組織と連動して事業を推進する「事業推進」といった役割に転生しました。
日常的な会話が横文字中心の世界から一転、「事業数値」や「原価」、「販管費」など、数字と漢字だらけの日常へと変化しました。
昨今、AI が世間を賑わせ、より職能越境のニーズが高まっています。
今回はその一例として、私が全く畑違いの業務で途方に暮れた数ヶ月と、そこから Cursor を相棒に構築した下駄履き戦略をお話します。
2025年の今、AI Agentは開発だけでなく、職種転換の強力な補助輪にもなります。
「技術は好きだが事業数字はさっぱり」という方、「AI活用で新しい領域に挑戦したい」という方に、具体的な手法と勇気をお届けします。
この技術変遷の激しい時代、借りれる下駄はどんどん履いて、新しい挑戦への切符を手にしましょう!
もう井崎脩五郎しか勝たん〜時間を費やすことでは価値は産まない世界でどう生き残る?
 フクイ@供養
フクイ@供養 某エンタープライズ子会社で情シスをしているフクイです。
クラウドからアジャイル、SaaSからプロジェクトマネジメントといろいろなコミュニティに顔を出しているおじさん(もうすぐじいさん)です。
2022年の登場以来、生成AIの進化は凄まじい限りです。
最近ではエージェントとかリサーチなどの新しい機能がいろいろなところで人々の仕事を変えていっています。
先日DeepResearch機能を使用して競馬の宝塚記念を予想してもらったら、ものすごく緻密に情報を集め、集めた結果の情報から緻密な予想を立ててくれました。しかも穴馬のメイショウタバルが来て見事的中!
ここで考えてみたら、競馬の予想をする人の仕事の「価値」の大きなひとつである「一般の人よりも時間を掛ける事によって産んだ価値」が生成AIによって失われてしまったことを意味していることに気が付きました。そこからの考察です。
責任とプレッシャーを愉しむ法
 松下正嗣
松下正嗣 納期や品質のプレッシャー、大きな責任、はじめての挑戦。
こういったものは、人によっては辛くて、楽しくないかもしれないです。
一方で、諸条件さえ整えれば、結構楽しめるものです。成長すればするほど、そうしたプレッシャーのかかる場面が増えます。
自分自身のメンタルを健全に保ち、継続して仕事を楽しむために、責任とプレッシャーとどう向き合うといいか、を語ります。
ロールチェンジで失ってしまった視点・こだわり・喜び
 三谷昌平
三谷昌平 私は去年の4月にプレイングマネージャーとしてEMになり、今年の4月からはEM of EMsとして専任EMになりました。この1年間で経験したロールチェンジは、思っていた以上に「持つべき視点」や「こだわりポイント」、「得られる喜び」を大きく変えるものでした。例えば、かつては「一つ一つの機能を作ってリリースする楽しさ」を感じていた自分も、今では「半年や一年などの期間を通じてどれだけアウトカムを作り出せたか」ばかりを気にして、個々の開発へのこだわりやそこから得られる喜びが薄れてしまい、少し寂しく感じています。
この考えも揺れ戻しで1年後には違うことを考えているかもしれませんし、今の考え方に染まってしまい寂しさすら感じなくなるのかもしれません。このトークではロールチェンジの真っ只中な今だからこそ感じる変化を、リアルなエピソードを交えてお話しします。キャリアに悩んでいる人への参考になれば嬉しいです。
人間だけが出来る、激変のデジタル世界を軽やかに生き抜く道
 わいとん
わいとん 本トークでは「技術を磨きつつ、長く豊かなキャリアを築く」ための指針を提示します。
特定の技術習得だけでなく、「心のあり方」と「学びの姿勢」に焦点を当て、「足るを知り、流れに身を任せ、循環を意識し、自分軸を持つ」という考え方を軸に、持続可能で充実した働き方を提案します。
おもな内容
- 「満ち足りる心」でコードと向き合う
- 完璧主義を手放し、「ちょうどいい」価値を届け、心の豊かさを感じる開発姿勢。
- 「流れに身を任せる」学びと成長
- 情報過多に疲弊せず、自身の興味やプロジェクトに合わせた「自然な学び」を追求。
- 「恵みへの感謝」と「循環」の精神
- チームやコミュニティへの貢献を通じ、知識や助け合いの「良い流れ」を生み出す。
- 「比較を手放し」、自分だけの価値を見出す
- 他者との比較から解放され、あなた自身の「情熱」を原動力とするキャリア形成。
あなたのコード、誰のですか? 〜 停滞していた開発チームがオーナーシップを取り戻し、爆速で価値提供を実現するまでの軌跡 〜
開発が思うように進まず、チームに閉塞感が漂う。そんな経験はありませんか?
「誰かがやってくれるだろう」と感じてしまう時、その根底にはチームから「自分ならできる」という自己効力感が失われているのかもしれません。
本セッションでは、かつて停滞していた私たちのチームが、小手先のプロセス改善では越えられなかった壁をいかにして乗り越えたか、その「軌跡」をお話しします。
転換点は、技術的な特効薬ではなく、チームの「オーナーシップ」を再構築することでした。
一度立ち止まってUI/UXから要件を再定義し、「動くもの」を囲んで対話する。
そのプロセスを通じて、メンバー一人ひとりの「自分がやる」という思いがチームの推進力に変わっていきました。
この「軌跡」の共有が、皆さんのチーム、そしてあなた自身の「次の一歩」を踏み出すための具体的なヒントと勇気になれば幸いです。
「みんなを頼らせてください」と言うこと
 しまぶ
しまぶ 心のどこかで最後は自分が何とかすると抱え込み、気づけばプロジェクトのボトルネックになっていた私。メンバーからも頼りにされていないと感じられてしまうこともありました。
そこで、私はチームメンバーへ「みんなを頼らせてください」と宣言しました。
ここに至るまで非常に葛藤がありました。リーダーが頼ることは、弱さをさらけ出すことだと思っていたからです。
しかし、頼ることは決して弱さではなく、むしろ強さであると気づきました。
当セッションでは、この決断に至るまでの経緯、その結果どのような変化が自分やチームにあったのかをお話しします。
「自分が頑張ればなんとかなる」と思いがちな方、リーダーとしての重圧に悩んでいる方などに、抱え込みを減らすヒントとなれば幸いです。
話すこと
- なぜ抱え込むリーダーになるのか
- 決断までの葛藤
- 決断後に起きた変化
- 頼ったうえでリーダーとしてやるべきこと
サイロを壊す~極私的DevOps体験
 幡ヶ谷亭直吉
幡ヶ谷亭直吉 私は18年のエンジニア歴の大半を与えられた環境で最善を尽くしてきました。
ただ、それだけでは自分の思考の枠を越えられず、枠の外にある課題は解消できないことに気付きました。
そうして昨年から勉強会やカンファレンスに参加し始め、外部の知見を取り入れることの重要性を実感しました。
また、ただ学ぶだけではなく、対話を通じて認知を揃えることの大切さを感じるようになりました。
今年は一歩踏み出し、実践したことを発信することで双方向の関係を築こうとしています。
まだ手探りの状態ではありますが、
こうした営みこそが、私の置かれた環境の「サイロ」を壊し、
より開かれた活性化された環境の土壌を育てると考えています。
本セッションでは、私自身の試行錯誤やその中で得た気づきをもとに、
サイロを壊す実践について共有させていただきます。
テストカバレッジ100%を10年続けて得られた学びと品質
 もっち
もっち テストカバレッジ100%はアンチパターンと言われていること、みなさん知ってますよね。
しかし実際に10年間やり続けた話は、あまり聞いたことがないんじゃないでしょうか。
エンジニアとして働き始めてから複数のプロジェクトで単体テストのC0/C1カバレッジを100%をテストの完了条件として実施し続けてきた時期がありました。
世の中では「テストカバレッジ100%は意味がない」「コストパフォーマンスが悪い」と言われていますし、どちらかというと自分自身も勧めるものではありません。
ただ、得られたものもたくさんあったなあと、今では感じています。
実際にやってみて何が得られたのか、どんな結果になったのか、リアルな経験から感じたことをお話します。
生成AIが大半のコーディングをすることになるだろう近い未来。
ガードレールとしても重要になるテスト、そしてテストカバレッジ、今だからこそ再考してみませんか?
やる気のない自分との向き合い方
 Genki Sano
Genki Sano 「やる気が出ない。でも何かしなきゃ。」
そんな焦りに飲み込まれていた自分が、少しだけラクになれた経験をお話しします。
仕事での責務が増えてアウトプットが止まり、アウトプットするネタも浮かばず、周りがどんどんアウトプットしているのに自分だけが取り残されているように感じて、焦っていた時期がありました。
そこで私は、無理に動かず“できる範囲だけ続ける”ことを選びました。
このセッションでは、私が試してきた工夫や気づき、そして“やる気がない前提でどう設計するか”についてお話します。
やる気が出ないことにモヤモヤしている方、立ち止まっている自分に不安を感じている方へ、少しでもヒントになれば嬉しいです。
今叫びたい!「自分の言葉で!ダサいスライドで!熱意を持って伝えろ!」と!俺は!今!叫びたい!
 ナカミチ
ナカミチ ジョン・ウィリアムスというクラシックギター奏者について昔先生が話したことを最近よく思い出す。
「ジョンの演奏の唯一の欠点はミスをしないことです」
彼の技術は非常に高く、クセがなく実に模範的な演奏をする。でもそれが欠点だと先生は言った。
最近不格好なものに触れる機会が減った気がする。登壇も同様だ。
AIのおかげなのか、はたまた大量に溢れる整ったテンプレートのおかげなのか、見栄えよく話も整っておりなんともストレスのない話が多くなった。
それでいいのか、と問いたい。速度や楽さに流されて一点ものであろうとする毒を抜かれてないだろうか?
批判を恐れ教科書的で隙のない言葉ばかり選んでいないだろうか?
気をてらうことは推奨しないが、本心が見えないほどにラッピングされたものはどこか悲しい。
だから今、過度に整ったものが与える心理と、不格好でいいから自分の言葉で伝える術について皆に話したい。
セカンドペンギンの重要さ
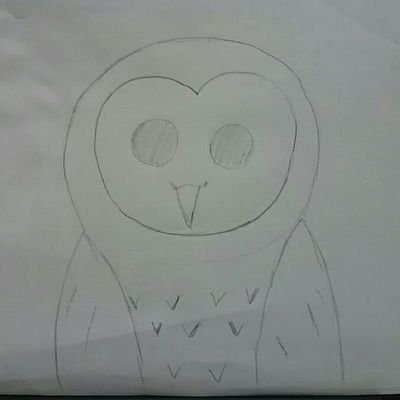 Rinchoku
Rinchoku 最近はプロダクト開発に必要なツールが多く開発されています。
最近ではObsidianやAI Agentなど、少し前だとFigmaやnotionがあったと思います。
これらを会社ないし、チーム内で活用を進めていくためには、ファーストペンギンが必要でもありますが、セカンドペンギンもいないとまったく普及しません。
本トークは一番最初に挑戦する人に追随してくれる「セカンドペンギン」の重要性について解説し、「セカンドペンギンになろう」と思ってくれる人が増えればと思います。


 おぎ
おぎ