提案レベルを上げてみたら、私の『提案』が『進捗』になっていた件
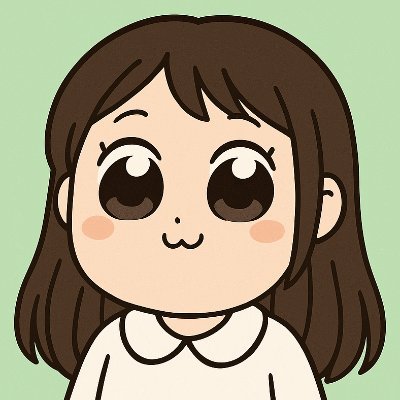 なってぃ
なってぃ こにふぁーさんのLTで紹介されていた「提案レベルを上げる」という話。
https://speakerdeck.com/konifar/ti-an-noreberuwoshang-geru-number-qiitaconference
それを実際にやってみたら──気づけば私の『提案』が、そのまま『進捗』として通るようになっていました。
提案内容を構造化し、先回りしてリスクや背景も整理。やることが明確だから、上司は「いいね」と言うだけ。業務の会話は最小限、仕事は爆速。
2025年の今、そんな“提案=実行”な世界を生きています。
このトークでは、「提案レベルをどう上げたか」「何が変わったか」「気をつけた落とし穴」など、実践して得たリアルな変化と気づきをシェアします。
提案がうまく通らない、仕事が前に進まない──そんな悩みを抱える誰かのヒントになればうれしいです。
ChatGPT、Gemini、Claude は、なぜ似たようなUIを採用しているのか
 ふわり
ふわり 2022年の末にChatGPTが現れて、はや2年余り。今日では一般の人にも広く普及し、我々の日常に欠かせないツールになりました。Gemini、Claudeなどの類似サービスも登場し、様々な用途に利用されています。
日々これらを使用する中でふと疑問に思ったことがあります。
「なぜ似たような画面なんだろう」
最初は先駆者であるChatGPTを真似しただけと考えていましたが、実は既存のUIを心理学的な根拠に基づいて応用したUIであり、理由があって選択されたものでした。
本トークでは、AIチャットボットのUIにどんな既存のUIが応用されているのか、なぜそれが選ばれたのかを解説します。
❚ ターゲット
UI/UXに興味があるエンジニア
❚ 話す内容
共通のUIパターン(2分)
- チャット形式(4分)
- ストリーミング表示(4分)
- 推論過程の表示(3分)
まとめ(2分)
コミュニティはいつまでも続くわけではない - PostgreSQLコミュニティの危機
 曽根 壮大
曽根 壮大 データベースはいつの時代もビジネス、ソフトウェア共に中心に存在し、大きな貢献を続けています。
その裏にはコミュニティがあり、様々な支援活動を行っています。
PostgreSQLユーザ会(以下 : JPUG)もその一つ。
そんなPostgreSQLコミュニティですが、運営メンバーが入れ替わらずに平均年齢は毎年カウントアップされています。
このセッションでは直接的な解決策まで提示できません。なぜなら 今、PostgreSQLコミュニティが無くなるかもしれない危機 だからです。
そんなPostgreSQLコミュニティの理事の一人である私がどうやってコミュニティに向き合って、そしてどんな未来を目指していくのか。
10年後に「あのときは結構苦労したんだよな」とみんなと酒を飲みながらふりかえられるようなことをお話します。
地方でエンジニアコミュニティを成功させる秘訣:”身内ノリ”を避け、”熱狂”を生み出すための挑戦
 こうの
こうの コロナ禍を経て、エンジニアの働き方やコミュニティのあり方は大きく変わりました。「東京は(心理的に)遠い」と感じるようになった私は、地元に根差したエンジニアコミュニティを立ち上げました。しかし、地域コミュニティにありがちな「身内ノリ」は避けたい。オープンな場で「熱狂」を生み出すには何が必要か?
たった1年で参加枠が9時間で埋まるほどの盛況ぶりを達成した裏側には、緻密な戦略がありました。本セッションでは、「やらないことを明確にする」、「対話をオープンにする」といった具体的な工夫を惜しみなく共有します。
地域コミュニティのパイオニアである大吉祥寺.pmの精神にも通じる、参加者が「また来たい」と心から思えるコミュニティ運営の秘訣。この1年の東葛.devを振り返り、本気の“今”をお届けします。
エンジニア採用を引き継いだあなたへ 〜EMが採用に向き合うとき、まず知っておきたいこと〜
 長江佳亮
長江佳亮 概要
「気付いたら、エンジニア採用の主担当になっていた」
そんなあなたに届けたい内容です。
本トークでは、私がEMとして採用を引き継いだ際に直面した課題や、初動の取り方、そして採用を成功に導くために意識していることについてお話しします。
「採用はEMの“主戦場”である」という想いについても、熱く語らせてください!
アジェンダ
- 直面した課題
- 初動でやるべきこと、大切にしてほしいこと
- 採用にどこまで関わり、どのような数値責任を持つべきか
- 採用を推進するための実践的なアプローチ(Scrum@Scale、ステークホルダーマップ など)
- 採用はEMの“主戦場”である
対象
- エンジニア採用の主担当になったばかりの方
- EMを目指している方、または新任EMの方
- 今後採用に関わるかもしれないエンジニアの方
大「個人開発サービス」時代に僕たちはどう生きるか
 sotarok
sotarok 時は大AI開発時代。
Copilotすげえ、と言われていた時代から、たった数年で、ChatGPT、Cline、Cursor、Devinなどと変化し、
応募時点では、Claude Codeがあらゆるものをなぎ倒しています。
これから来るのは大「個人開発サービス」時代なのではないか!?と私は思っています。
そう、2000〜2010年代初頭、個人がWebサービスを量産していたあの時代から、たった10数年で開発現場は大きく変わりました。
ゲームにせよ、アプリにせよ、当たり前の品質がたかくなったことにより、資本力こそが開発競争力になりつつあった、と思いきや、AIがそれを変えるのではないか、と思っています。
それで、なんというか、開発するのが毎日めちゃくちゃ楽しい!!
(今の所。開催時点まであと3ヶ月。この間に仕事なくなってるかもしれないけど)
という話をしたいです。

