プログラミングに出会って20年、「今」が1番楽しい
 クドウマサヤ
クドウマサヤ みなさんの「Hello, World」はいつ、どこでしたか。
私は20年前、とある工業高校の教室でした。
2025年の今、あの頃と同じようにワクワクしながらプログラミングを楽しんでいます。いえ、あの頃以上なのかもしれません。
「楽しい」という感情を構成している要素はなんなのか。
それは、この20年の中で変わっているものもあれば、変わらないものもあると気づきました。
生成AIの進化によって、職業プログラマとしての働き方は既に大きく変わりつつあります。
それでもプログラミングの楽しさが終わることは無いと信じています。
これはひとりのプログラマの、ただの自分語りです。
でも、ベテランの方にとっては深く共感してもらえる、若手の方にとっては明日からの希望になれる。
プログラミングが好きなみなさんの活力になる話を今、届けたいと思っています。
クラウドのセキュリティインシデントスレポンスの現場から
当社はプロダクトやパブリッククラウドのセキュリティを高める業務を提供しています。
業務の一環でクラウド環境のセキュリティインシデントレスポンスの支援をすることがありますが、
"事前の備え"が準備か否かでインシデント対応の予後が大きく変わってしまいます。
誰もが体験したくないセキュリティインシデント。
インシデントレスポンスの現場で困ったことから、苦しみを小さくするための準備をお伝えします。
転職したら周りがつよつよエンジニアばかりだった件
 時田円象
時田円象 皆さんは転職した時に今までの職場と比較してどんな違いを感じるでしょうか?
開発環境や文化、制度等あると思いますが、一番は人ではないでしょうか。 私はそうでした。
今までの会社では見る事も無かったような人たちがそこにはいました。
ただ、単純に「つよつよ」と言っても実際に何を見て強いと感じるのでしょうか?コードの速さ?設計力?問題解決能力?
このLTでは、マルイユナイトのつよつよエンジニアたちと働く中で気づいた「この人強いな」と感じる瞬間と明日から出来ることを中心にお話しします。
これで明日から、強いエンジニアに一歩近づけるかも!?
2011年 「ぼっちが懇親会でするべき97のこと」 #97bocchi から積み重ねた【令和7年最新】技術コミュニティ交流戦略2025
 bash
bash 10年代初頭より「プログラマが知るべき97のこと」をはじめ"97"をキーワードとする名著が出版されてきました。
2011年頃「IT勉強会」の人たちが「ぼっちが懇親会でするべき97のこと」 大喜利を当時Twitter #97bocchi ハッシュタグで行っていました。 https://togetter.com/li/140804 としてまとめを読むことができます。
それから10数年...令和に入り、エンジニアたちもその取り巻く環境も変化したものの、未だ交流の場における"ぼっち"不安は人々の間にあり続けています。例えば「登壇すればぼっち回避」などのハックが人口に膾炙していますが、実感として確実ではありません。
わたしは当時の大喜利参加者として、また登壇・運営・主催・スポンサーなどのロールを持ってきた経験から、懇親会や交流の場で得るものを最大化するためのカンファレンス参加戦略をお話します。
2025年になってもまだMySQLが好き
 yoku0825
yoku0825 - 2012年からMySQLほぼ一筋13年です
- キャリアの9割以上はMySQLユーザー企業のDBAでした
- 2025年5月にDBAではないポジションで転職しました
- 故あって多少MariaDBの面倒を見たりして感じたMySQLとの違いとか
- オンコール対応から離れて感じた「DBAとしては昔からあったタイプの監視の過不足」とか「こういうの無いと結構不便なツール, 仕組み」についてと
- 離れてわかったMySQLへの愛を語ります
【実演版】カンファレンス登壇者・スタッフにこそ知ってほしいマイクの使い方
 Arthur
Arthur https://blog.arthur1.dev/entry/2024/03/01/210535 に書いた、マイクの正しい使い方、あるいはやってはいけないことについて、実演を交えて簡潔にお伝えします。
みなさまのスピーチがもっと聴衆に伝わる、そんなTipsをぜひ!
提案レベルを上げてみたら、私の『提案』が『進捗』になっていた件
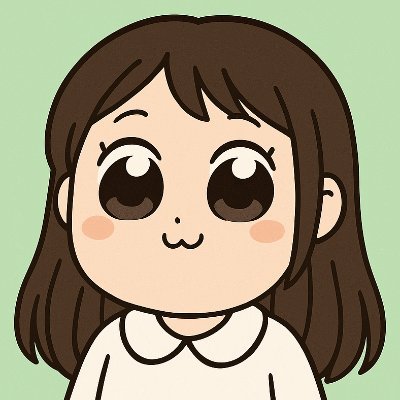 なってぃ
なってぃ こにふぁーさんのLTで紹介されていた「提案レベルを上げる」という話。
https://speakerdeck.com/konifar/ti-an-noreberuwoshang-geru-number-qiitaconference
それを実際にやってみたら──気づけば私の『提案』が、そのまま『進捗』として通るようになっていました。
提案内容を構造化し、先回りしてリスクや背景も整理。やることが明確だから、上司は「いいね」と言うだけ。業務の会話は最小限、仕事は爆速。
2025年の今、そんな“提案=実行”な世界を生きています。
このトークでは、「提案レベルをどう上げたか」「何が変わったか」「気をつけた落とし穴」など、実践して得たリアルな変化と気づきをシェアします。
提案がうまく通らない、仕事が前に進まない──そんな悩みを抱える誰かのヒントになればうれしいです。
今!ソフトウェアエンジニアがハードウェアに手を出すには
 macopy
macopy AIによる開発の発達によりソフトウェアの分野では比較的短時間で物が作れる領域が増えつつあります。
一方で我々ソフトウェアエンジニアの中には自らの手で物作りすることこそ喜びであると感じている方もいるでしょう。これは趣味のエンジニアリングでは重要なことに思えます。
ハードウェアの分野では、人が手を動かさないと実現できないことがたくさんあります。
このセッションでは自分で手を動かしてものを作りたい!と考える方に向けての最初の地図を提示します。
- 今!LEDを光らせるなら
- M5Stack
- Raspberry Pi Pico
- Addressable LED
- 今!ハードウェアのガワや基板やメカを設計・制作するなら
- 3Dプリンタ
- 基板を中国へ発注
もしこのトークを聞いていただいて、あなたの手であなたしか作れないハードウェアを作りたいと思えてもらえれば幸いです
機能追加とリーダー業務との類似性
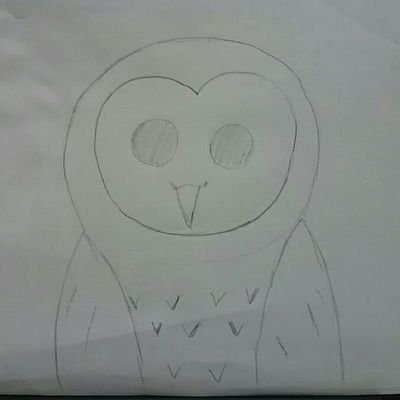 Rinchoku
Rinchoku 会社に入社後数年経つとやってくる上長から「リーダーやってみない?」と言われた(言われたい)人は多くいると思います。
メンバーからリーダーになると、責任範囲の拡大、実業務の様変わり、場合によってはピープルマネジメントと、メンバー時の業務から大きく変わる印象がある人も多いと思います。
そうすると「リーダーをやっていけるのか」「リーダーになるために色々な情報をインプットしないと」と心配事などが出てきます。
本トークでは、「機能開発」と「リーダー業務」の流れにある類似性を解説し、リーダーになる際の不安を少しでも和らげたり、より信頼のおけるリーダーへの一助になればと思います。
対象聴講者
- 将来リーダーになりたい人
- いきなりリーダーになり、どういう心構えをすればいいか心配の人
- リーダー業務がうまくいっていないと感じる人
ChatGPT、Gemini、Claude は、なぜ似たようなUIを採用しているのか
 ふわり
ふわり 2022年の末にChatGPTが現れて、はや2年余り。今日では一般の人にも広く普及し、我々の日常に欠かせないツールになりました。Gemini、Claudeなどの類似サービスも登場し、様々な用途に利用されています。
日々これらを使用する中でふと疑問に思ったことがあります。
「なぜ似たような画面なんだろう」
最初は先駆者であるChatGPTを真似しただけと考えていましたが、実は既存のUIを心理学的な根拠に基づいて応用したUIであり、理由があって選択されたものでした。
本トークでは、AIチャットボットのUIにどんな既存のUIが応用されているのか、なぜそれが選ばれたのかを解説します。
❚ ターゲット
UI/UXに興味があるエンジニア
❚ 話す内容
共通のUIパターン(2分)
- チャット形式(4分)
- ストリーミング表示(4分)
- 推論過程の表示(3分)
まとめ(2分)
コミュニティはいつまでも続くわけではない - PostgreSQLコミュニティの危機
 曽根 壮大
曽根 壮大 データベースはいつの時代もビジネス、ソフトウェア共に中心に存在し、大きな貢献を続けています。
その裏にはコミュニティがあり、様々な支援活動を行っています。
PostgreSQLユーザ会(以下 : JPUG)もその一つ。
そんなPostgreSQLコミュニティですが、運営メンバーが入れ替わらずに平均年齢は毎年カウントアップされています。
このセッションでは直接的な解決策まで提示できません。なぜなら 今、PostgreSQLコミュニティが無くなるかもしれない危機 だからです。
そんなPostgreSQLコミュニティの理事の一人である私がどうやってコミュニティに向き合って、そしてどんな未来を目指していくのか。
10年後に「あのときは結構苦労したんだよな」とみんなと酒を飲みながらふりかえられるようなことをお話します。
地方でエンジニアコミュニティを成功させる秘訣:”身内ノリ”を避け、”熱狂”を生み出すための挑戦
 こうの
こうの コロナ禍を経て、エンジニアの働き方やコミュニティのあり方は大きく変わりました。「東京は(心理的に)遠い」と感じるようになった私は、地元に根差したエンジニアコミュニティを立ち上げました。しかし、地域コミュニティにありがちな「身内ノリ」は避けたい。オープンな場で「熱狂」を生み出すには何が必要か?
たった1年で参加枠が9時間で埋まるほどの盛況ぶりを達成した裏側には、緻密な戦略がありました。本セッションでは、「やらないことを明確にする」、「対話をオープンにする」といった具体的な工夫を惜しみなく共有します。
地域コミュニティのパイオニアである大吉祥寺.pmの精神にも通じる、参加者が「また来たい」と心から思えるコミュニティ運営の秘訣。この1年の東葛.devを振り返り、本気の“今”をお届けします。
エンジニア採用を引き継いだあなたへ 〜EMが採用に向き合うとき、まず知っておきたいこと〜
 長江佳亮
長江佳亮 概要
「気付いたら、エンジニア採用の主担当になっていた」
そんなあなたに届けたい内容です。
本トークでは、私がEMとして採用を引き継いだ際に直面した課題や、初動の取り方、そして採用を成功に導くために意識していることについてお話しします。
「採用はEMの“主戦場”である」という想いについても、熱く語らせてください!
アジェンダ
- 直面した課題
- 初動でやるべきこと、大切にしてほしいこと
- 採用にどこまで関わり、どのような数値責任を持つべきか
- 採用を推進するための実践的なアプローチ(Scrum@Scale、ステークホルダーマップ など)
- 採用はEMの“主戦場”である
対象
- エンジニア採用の主担当になったばかりの方
- EMを目指している方、または新任EMの方
- 今後採用に関わるかもしれないエンジニアの方
2025 年のコーディングエージェントの現在地とエンジニアの仕事の変化について
 azukiazusa
azukiazusa 2025年現在、開発現場では「コードを書く」から「AIと協働する」への大転換が起きています。GitHub Copilotのような補完型から始まったAI支援は、今や自律的にタスクを遂行するエージェントへと進化しました。
2025 年時点ではどのような類型のコーディングエージェントが存在しているか、コーディングエージェントの登場により私達エンジニアの仕事がどのように変化しているのか、急速な変化に伴いどのような課題が発生しているのかについて話します。
そして数年後に、「2025年は確かに時代の転換点だったね」と振り返ってその瞬間に立ち会えたことを楽しめるようにしましょう。
参考: https://azukiazusa.dev/blog/coding-agents-and-developers-work/
大「個人開発サービス」時代に僕たちはどう生きるか
 sotarok
sotarok 時は大AI開発時代。
Copilotすげえ、と言われていた時代から、たった数年で、ChatGPT、Cline、Cursor、Devinなどと変化し、
応募時点では、Claude Codeがあらゆるものをなぎ倒しています。
これから来るのは大「個人開発サービス」時代なのではないか!?と私は思っています。
そう、2000〜2010年代初頭、個人がWebサービスを量産していたあの時代から、たった10数年で開発現場は大きく変わりました。
ゲームにせよ、アプリにせよ、当たり前の品質がたかくなったことにより、資本力こそが開発競争力になりつつあった、と思いきや、AIがそれを変えるのではないか、と思っています。
それで、なんというか、開発するのが毎日めちゃくちゃ楽しい!!
(今の所。開催時点まであと3ヶ月。この間に仕事なくなってるかもしれないけど)
という話をしたいです。
定義のない仕事ーー2025年の今CTOになった私から伝えたい[CTOになった人/CTOを目指す人/CTOを迎え入れる人]たちに必要なナレッジ
 nrs
nrs CTOの仕事に定義はありません
定義のない仕事にまつわるナレッジをお話します
多くの職種では「何をどのようにするか」といった業務内容はある程度決まっています
だからこそ組織は具体的な業務を指示できます
しかし、組織のトップに立つと状況は一変します
私は今年4月にCTOに就任しました
組織の規模は300人を超え、一般的には推奨されない着任の仕方です
着任当初は苦労の連続です
右も左もわからない中、どんどん埋まるスケジュール
バリューを発揮できない自分への葛藤
何を誰に聞けば答えが見つかるかはわからない模索
「自分が何をすべきか」を誰も知らないという現実
CTOに求められる役割は組織によって大きく異なります
そして、求められるバリュー(未定義)の発揮には組織の仲間のサポートが必要です
本トークではCTOに限らない定義のない仕事を進めるノウハウや考え方、必要な組織の支援をお話しします
明日から役にたつLTをダメにする技術をあなたに
 ナカミチ
ナカミチ 「明日から役にたつLTをダメにする方法をあなたに」
5分間で想いを伝えるのは難しいぞ!
良かれと思ってやったことが命取りになる!挽回の時間も残されていない!それがLT!
私の経験から導き出した個人的見解に基づく、やめておけってLTを解説を交えながら実践します🕺
これであなたも最悪なLTが実践できるね!ヤッター!!!
- 笑いを取るのはやめておけ
- 奇抜なキャラ付けは逆効果
- 自己紹介はいらない
- 伝えたいことは最初と最後に
- もうスライドはダサいくらいでいい
- 情報量が多いスライドを作っちゃった時に発するべき言葉
- 登壇の方向性が定まっていないとみんなが混乱する
組織が大きく変わろうとするとき、自分はどうありたいかを考えている
 うーたん
うーたん 私の勤める会社では、外部の事情によって、これから組織の体制や文化が大きく変わっていくことが予想されています。
実際に何がどうなるかはまだ分かりませんが、周囲の雰囲気や人間関係に、少しずつ変化の兆しが見え始めています。
このままここに残って働き続けるのがいいのか。もっと自分に合った環境があるのか。
そんなことを考えるようになってから、私はこれまでのキャリアを振り返ったり、身近な人に相談したりしながら、少しずつ動き出しました。
まだ決断を下したわけではありません。でも、悩みを抱えたまま止まっているよりも、何かしら行動をすることで気持ちが少し落ち着いてきました。
このセッションでは、組織が大きく変わろうとしている中で、私がどんなふうに考え、どう動いてきたのかをお話しします。
同じように環境の変化に向き合っている方の、ヒントや安心につながればうれしいです。

