プロポーザル駆動学習:暗黙知を形式知へ変える実践的学習法
 Masaki ASANO
Masaki ASANO 皆さん、技術カンファレンスへのプロポーザル、書いていますか?
中には、「登壇するほどのネタもないし…」「わざわざ書くほどのこともないよな…」そう思っている方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、プロポーザルを考えて出すことがエンジニアとしての成長を加速させる、様々なメリットが秘められているのです。
この「プロポーザル駆動学習」という考え方を通じて、プロポーザルが登壇するための単なる「提出書類・前提条件」ではなく、皆さんにとっての「学習の機会」であるということをお伝えします。
アジェンダのイメージ
- プロポーザルで暗黙知の言語化をする
- 自分の中の想いや経験を見つめ直す時間にする
- 登壇への思いの発露・自己開示
- 採択された後の話
- 採択されなかった後の話
カオスエンジニアリングを5分でわかった気になろう
 工藤ユミ
工藤ユミ ソフトウェアはハードウェアと違って、制約があいまいになりやすく、
それによって意図しない挙動をすることが多々あります。
もはや異なる文脈のソフトウェアとの接続、分散システムが当然のように使われる世の中。
人同士の連携で言っても、異なる文脈で育ってきた人々が連携し、多様性を重んじながら全体の系を実現する世の中。
こういった世界観では、もはやアジャイルだけでなく、カオスエンジニアリングの思想がマストになってきます。
今回は、カオスエンジニアリングの勉強会と、過去にセキュリティカオスエンジニアリングの案件に入って、
薄くなりにも経験を重ねてきて、カオスエンジニアリングを分かった気になったわたし目線で、
5分でコンパクトにカオスエンジニアリングの世界観をお届けします。
2025年のPython環境はここまで簡単になりました! 環境構築ツールパビリオン クイックツアー
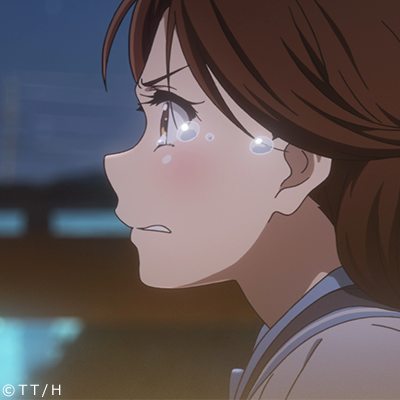 nikkie
nikkie PythonはWebアプリからデータ分析、自動化などなど幅広い用途で利用されており、多くのユーザがいる言語です。
そんなPythonですが、一番難しいのは環境構築になってしまっているように思われます。
30年の歴史の中で「環境管理といえばこのツール」がなかった言語ゆえ、Webに情報が入り乱れている印象です
このLTでは2024年から注目されているuvを取り上げ、2025年時点のPython環境が著しく簡単になっていることを全力で伝えます。
私が7-8年前に入門したときの苦労は、もはや全人類経験しなくていいんです!!
- パラダイムシフト:"仮想環境"を人間が作る時代は、もう終わりました。ツールに任せて楽してこーぜ!
- 楽々 uv sync
- uv run script.py (inline script metadataなるもの)
- uvx (手札は、全PyPI!)
令和でもブログを自宅サーバで
 うすゆき
うすゆき AIで猫も杓子も生成できる時代にブログ https://blog.usuyuki.net を書き続けています。
学生→社会人と続け5年目となったブログ執筆を踏まえて、今伝えたいことを5分に凝縮します。
話す内容
- 新卒2年目世代(24卒)の一人としてのブログの捉え方
- YouTubeやPodcastsでなくブログ
- テキストの強さ(Unix哲学を添えて)
- Google検索を無料全文検索に使う「うすゆきブログ 大吉祥寺.pm」
- 生成AI時代のブログ
- 結果よりアウトプット行為が強い
- アウトプットはキャッシュされる
- 自宅サーバでコスパ良く所有欲も満たす
- 1万円台で始めるミニPC。Proxmox仮想化してコンテナ管理
- Cloudflare TunnelでV6プラス環境でも外に公開
なぜスクラムはこうなったのか?歴史が教えてくれたこと
 Genki Sano
Genki Sano RSGT(Regional Scrum Gathering Tokyo)2025のClosing Keynoteで、ホンダのシティ開発に関わった本間日義さんの講演を聞きました。
それをきっかけに歴史を遡ったことで、スクラムの源流には日本の製造業──ホンダやトヨタ──の実践があることを知り、スクラムの“考え方”が一気に立体的に見えてきたんです。
それまでの私は、スクラムを「こうやるもの」として捉えていましたが、背景を知ったことで、運用の一つひとつに込められた意図がより分かるようになりました。
スクラムに対する理解が深まったことで、これまで以上に納得感を持って向き合えるようになったのです。
このセッションでは、私の追体験をもとに、そんなスクラムのルーツを5分で紹介します。
スクラムの形骸化に悩んでいる方や、なんとなくモヤモヤを抱えている方こそ、原点に立ち返ってみませんか?

