MustをWillに変える技術 〜アイドル・郁田はるきが"すべき"の壁を超えるまで〜
 Subroh Nishikori
Subroh Nishikori 「昔は楽しかった仕事が、今は楽しいと思えない」
ふとこんなことを感じる瞬間、みなさんにはあるでしょうか?
仕事に対して、自らを内面から突き動かす内発的動機を見つけた時、人は高いパフォーマンスを発揮し、大きな成果を生み出すことができます。
ですが、そんな内発的動機を長く保ち続けることは、簡単なことではありません。過去どんなに楽しかった仕事であっても、環境や役割の変化によっていつの間にかその動機を見失ってしまうことは、誰の身にも起こり得ることです。
283プロダクションに所属するアイドル・郁田はるきも、そんな壁にぶつかった1人です。アイドルになる前から「絵を描く」ことをはじめとした様々な表現に挑戦し続けてきたはるきは、アイドルとなることで「表現」を仕事としてこなす初めての機会を得ます。
仕事をこなすなかで、「表現」に対する動機を一度見失い、そして再発見したはるきのストーリーから、周囲の要求に内発的な動機を見出す「MustをWillに変える技術」をTipsとして共有します。
※当日は愛知ではるきのパフォーマンスを見届けるため、採択された際にはリモートまたは録画での登壇とさせていただきたいです。
「ハウルの動く城」 - あなたの呪いを解き明かす物語
 あずま
あずま 「ハウルの動く城」 というアニメにはさまざまな「呪い」が登場します。
主人公の少女ソフィーを老婆の姿に変えてしまう魔法は、物語に登場する呪いの代表格です。
ですが、いかにもおとぎ話の「魔法」のような呪いだけが、呪いなのでしょうか?
このアニメの登場人物たちは、様々な呪い=自己の檻に囚われながら生きています。
それらは実は、私たちが生きる現実でもすぐ身近にある呪いなのです。
呪いは解除することも重要ですが、その正体を探求することこそ、呪いから受けるネガティブな効果から逃れるための第一歩となります。
さあ、「ハウルの動く城」から、身の周りの呪いをさがしにいきましょう!
メイドインアビスから学ぶ、リーダーに必要な要素
 しゅういちろ
しゅういちろ 突然リーダーを任された!でも、チームメンバーは自分より能力の高いエンジニアばかり。一体何をどうやってリードすればいいのか!?悩みますよね。
そんな新米リーダーの悩みを解決するために、メイドインアビスの主人公であり、強い人に囲まれて冒険を続けるリコの行動をふりかえりましょう。そして、行動と仲間の状態からどのようにリーダーシップを発揮しているかを知ることで、リーダーシップの取り方を学んでいきましょう。
チームリーダーを目指す方や、チームリーダーを任されている人、憧れは止められない人に刺さるトークです。
アウトライン
- メイドインアビスの世界観解説
- リコの冒険ふりかえり
- オースの街〜深界二層
- リコの活躍、メンバーの活躍
- ドメイン知識を活用したリーダーシップ
- 深界三層〜深界四層
- ナナチの参加、メンバーの活躍
- 対話と共感によるリーダーシップ
- 深界五層
- プルシュカの参加、メンバーの活躍
- ビジョンを語るリーダーシップ
- オースの街〜深界二層
- リーダーシップの変遷
- メンバーの変遷とリコのリーダーシップがどう変わったか
- リーダーシップに必要なもの
- 冒険を続けるのに必要なマインド
友達ではなく仲間とはなにか 映像研には手を出すな!から学ぶ仕事の取り組み方
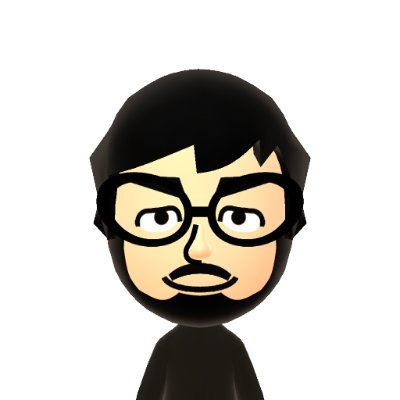 infixer
infixer 「映像研には手を出すな!」の中で、主人公である浅草みどり、同じ映像研のメンバーの金森さやか、水崎ツバメと作った自主アニメ作品を、文化祭で上映したあとの反省会をしている所に、水崎ツバメの両親が現れるワンシーンがあります。
ツバメ母「あ!!ツバメのお友達?」
浅草氏「い、いえ。」
浅草氏「仲間です。」
このシーンを観たとき私は、友達と仲間って何が違うのだろうか?という問いが出てきました。
普段業務をしている中で、チームメンバーと楽しく開発したいという気持ちがあります。
本トークでは、自分なりに友達と仲間を定義して、チームで仕事に取り組むために必要なことを「映像研には手を出すな!」を辿りながら考察していきます。
『境界の彼方』に学ぶ、境界防御の限界とゼロトラスト 〜メガネで見抜け、見えない脅威〜
 キタジー(kitaji0306)
キタジー(kitaji0306) 概要:
『境界の彼方』に登場する異界士たちは、妖夢という未知の脅威と戦いながら、目に見える「境界線」の存在を頼りに、そこから先の危険に備えています。
しかし現実のサイバーセキュリティの世界では、境界だけでは守りきれない時代が来ています。ゼロトラスト――つまり“誰も信じず、すべてを検証する”という考え方が求められているのです。
本セッションでは、境界防御という発想の限界と、ゼロトラストの必要性を、栗山未来のメガネ視点で楽しく紐解きます。見える境界の外にも、見えない脅威は潜んでいる――その現実を、メガネ越しに見つめてみませんか?
アジェンダ:
・『境界の彼方』とサイバー空間の共通点
・境界防御の考え方とその限界
・ゼロトラストとは何か?誰も信じず、常に検証する世界
・メガネと見える化の大切さ
・セキュリティ担当者は異界士である
薬屋のひとりごとにみるトラブルシューティング
 草場友光
草場友光 薬屋のひとりごとでは時折驚くような推理でトラブルを解決していきます。
これは、ITの世界においても応用できる要素です。
いつも完全な情報があるとは限らず断片的な情報をもとにより確率の高い事象を探り当て真実に迫っていく
それでも、断定はしない。
そんな姿はとても参考になることがおおいです。
「魔法少女リリカルなのは」から学ぶ他者理解
 Eli
Eli 私は未経験からエンジニア転職に向け、半年間学習を進めてきました。
学習をする中で、最初は「何を言ってるのかわからない!」「怖い!」という気持ちに襲われました。
技術書を読む際も、宇宙語に感じて、読み終わるのが果てしなく遠く感じることもありました。
そんな中、子供の頃から大好きな「魔法少女リリカルなのは」という作品に支えられました。
主人公・なのはは常に真っ直ぐで、何度も「お話を聞かせてほしい」と向かい合うのです。
はじめましての難しい技術も、私を批判したいのではなく、世の中を便利にするとても優しい技術なのだと、私は信じています。
なのはのように立ち上がって向かい続けることを、皆さんにお伝えできたらと考えています。
悩む君へ:「自分を信じるな。俺を信じろ。お前を信じる俺を信じろ。」
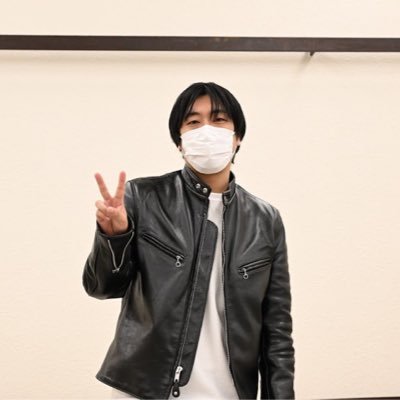 hehehenohe
hehehenohe 私の仕事は転職エージェントをしておりますが、毎年キャリアパスに悩む方と多くお話させて頂いております。
その際、ジョブホッパーになりたくないけどなってしまった方や、色々と選択肢で悩み過ぎてモヤモヤしている方とお話する事が多々ございます。
この様な方々は下記の様な考えを持ってしまう時があります。
「自分の選択は合ってるのだろうか・・・?」
前述通り私の仕事は転職エージェントです。最終的な転職の判断は候補者様に委ねられますが、そこに違和感を感じる時があります。
提案しておきながら、転職エージェントは最後に責任を持たないことに対して、嫌だなと思っていた時、久しぶりに見た大好きなアニメ「天元突破グレンラガン」を観た際、主要キャラのカミナが同じく主要キャラのシモンに言ったセリフが私の核心を突きました。
「自分を信じるな。俺を信じろ。お前を信じる俺を信じろ。」
これだ・・・!
判断に迷う方に対して転職エージェントとしての専門性を持ったコンサルティングをする事=自分の言葉、提案に責任を持つ事=候補者様の人生に責任を持つ事。
迷うなら専門性を持って、あなたの人生にも責任を持ってお話します、自分を信じられないなら私を信じてくれ。
これは私が自信と責任を持って提案出来る様になった物語です。
本トークでは過去事例を交えて、なぜそういう提案をしたかなど考えを可視化したお話が出来ればと思います。
「きらら枠」インターフェイスで見る抽象化
 こうの
こうの 「きらら枠」を通してインターフェイスや抽象化の概念をざっくり話します!
「きらら枠」とは『まんがタイムきらら』系雑誌連載作品に多い、かわいい女の子たちの日常と共通した雰囲気・特徴を持つアニメのことを指します。
「きらら枠」作品群に共通する要素を「インターフェイス」に見立て、その特徴を持つ作品が「きらら枠」と呼ばれる現象を分析します。
これは技術における「抽象化」と等しい思考プロセスです。
身近なアニメの例を通じて、「抽象化とは何か?」を分かりやすく解説し、新たな学びを提供します。
【アジェンダ】
- 「きらら枠」とは何か?
- 「きらら枠」の共通項を抽出する
- 「きらら枠ではないきらら枠」に見る抽象化
アニメ「ラーメン赤猫」からの学びクイズ! プロが出す力は、何%?
皆さま、アニメ「ラーメン赤猫」はご存知ですか?
私はエンジニアニメで熱い布教を受け、先日完食しました!🍜
「ラーメン赤猫」からの学びはいくつかあるのですが、今回は一番印象的な学びをクイズ形式でお伝えします。
私はエンジニアリングで対価をいただいたらエンジニアの"プロ"だと思っているのですが、
ではプロは何%の力で物事に当たるとよいのでしょうか?常に全力でしょうか?
ラーメン赤猫のハナさま🐈はここに明確な回答をしており、そこからの学びを共有します。
ラブリーイェイイェーイ!!
高校生ロックバンドアニメの究極「音楽」から見る漢の後ろ姿
 フクイ
フクイ 数あるハイスクール世代のロックバンドアニメは数多くありますが、その中で異彩を放つ「音楽」というアニメについて話します。
このアニメの寡黙な主人公の姿から、なぜ音楽をするのか?という問いから、なぜその行動を取るのか?そこを掘り下げて観たいと思います。
このLTにより
・理屈よりも湧き上がる想いが大事
・言葉はなくても、伝わる人にはつながる
早朝の渋谷の青さ、あるいは溺れた人を助ける為に飛び込んだ海の向こう側に見る、自己覚知と自己開示の尊さ
 0yu
0yu アニメ『ブルーピリオド』の主人公・矢口八虎は、早朝の渋谷の青さを描き、それが他者に理解されたことで「絵を描く悦び」に目覚めます。また、鮎川龍二と“同じ海に飛び込んで対話する”ために、芸大二次試験直前という大事な時期に、冬の小田原の海へと向かいます。そこで二人はセルフヌードを通して、それぞれの本音をさらけ出しました。
人間とは、多面的であり、多層的な個性を持った存在です。常に周囲に合わせて要領よく立ち回ってきた矢口八虎という青年が、「あなたが青く見えるなら、りんごもうさぎの体も青くていいんだよ」という作中のセリフに象徴されるように、自分自身の「青」を肯定し、それを描き出したとき、初めて本当の意味で自己を他者に開示します。
「青い渋谷」を描くことは、彼自身のその後の生き方を決定づけた行為でした。そして、鮎川龍二をはじめとする他者という「世界」との接触に正面から身を投じることで、自己を覚知していきます。
矢口八虎の生き方から得た学びとして、他者と真摯な対話をするための自己開示、その対話によって得られる自己覚知の尊さについてお話しします。
『氷菓』の心理的安全性と多重解決ミステリからチームでの課題解決を学ぶ!
 こうの
こうの チームで開発するとき、うまく意見が出てこないことや出せないことはありませんか?
心理的安全性の高くない状態だと発言が難しいケースがあります。
本セッションでは『氷菓』というミステリアニメを題材に、心理的安全性の高いチームをいかにして実現していくかを洞察します。
このセッションで学べることは次の通りです。
- 心理的安全性とはそもそも何か
- なぜ心理的安全性を重視するのか
- 『氷菓』から学ぶ心理的安全性を高めるためのアクション
『氷菓』は多重解決というジャンルのミステリです。
多重解決とは、1つの事件に対して複数の解決が示されるミステリのことで、システムのチーム開発の状況にとても良く似ていると考えています。
メンバーは自分の思う、考えうる限りのベストな設計や実装(=解決)を示します。ただ、各メンバーはそれぞれの視点を持っていて、見えていない仕様や背景(=証拠)があるかもしれません。
私たち開発者は見えていないものがあるかもしれない、最良な選択肢ではないかもしれないことを発言する勇気を持つ必要があります。
少ない勇気で発言できる環境を得るヒントを『氷菓』から学んでいきましょう!!
- エンジニアの世界にKOはない - 久瀬大作から学ぶエンジニアとしての生き方
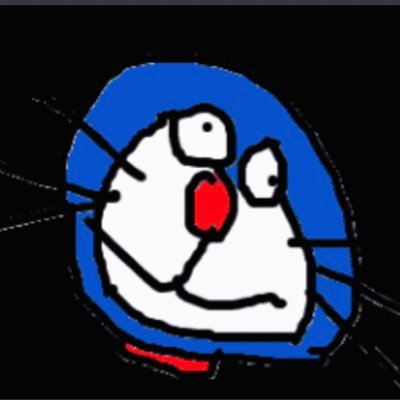 マグロ
マグロ 「自分はエンジニアとして生きていけるのだろうか」
誰しもが思うことだと思います。僕は常日毎思っています。
周りが優秀で、自分が置いて行かれている様に感じる。もう努力しても追いつけないのではないか。
そう思っていた矢先、私は龍が如くに出会いました。
日本の裏社会を重厚なストーリーで描くゲーム、「龍が如く」。
ただ裏社会を描いているのではなく、キャラクターがそこを生きる人間として魅力的に描写されています。
義理と人情。裏切りと愛憎。
現代社会を生き抜く我々にも学ぶべき生き様があります。
今回お話しするのはシリーズの原点「龍が如く0 誓いの場所」。
舞台は1988年、バブル景気により活気のある日本。
極道の最盛期として、様々な男の生き様が描かれています。
この中で私が影響を受けたのは「久瀬大作」という男。
自分のエンジニアとしての能力に限界を感じていた私に、彼の生き様が非常に刺さりました。
エンジニアとして、そして一人の人間として、どう生きるべきか。
久瀬を通じて気づいたその答えを、お伝えしたいと思います。

