あなた...『覚悟して(IT業界に)来てる人』.........ですよね 【ジョジョの奇妙な冒険シリーズより】
 ひもの
ひもの あなた...『覚悟して来てる人』.........ですよね
人に「マサカリ」を投げつけようとするって事は
逆に「マサカリ」を投げつけられるかもしれないという危険を 常に「覚悟して来ている人」ってわけですよね...
といいつつも、コンテキストを無視された強い正論をぶつけられると人間辛くなる人が多いのではないかと思います。少なくとも私はそうです。
ジョジョの奇妙な冒険は根本的なテーマに「人間賛歌」があると私は思います。自分も、相手も、等しく尊ぶためにはどんな語り掛け方をするのがよいのでしょうか?
また、どうしようもなく決裂したと判断せざるを得なかったときどう相対すべきなのか。流石に現実ではオラオララッシュはかませません。
そういった瞬間で必要な「覚悟」、暗闇の荒野に進むべき道を切り開くために、具体的にどうすべきなのか
自分がジョジョを読んで学んだことをお話し、また一緒に考えることが出来たらと思います。
UDDのススメ - 拡張版 -
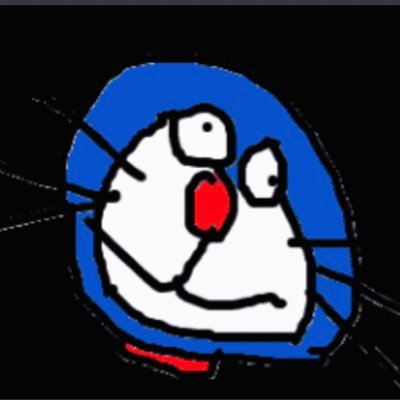 マグロ
マグロ 皆さん、テストコードを書いていますか?
僕は書くのが辛いです。
テストケースが多いと書く量が増えて大変だったり、テストが落ちると辛かったり…
そんな中、僕は「機動戦士ガンダムユニコーン」を視聴しました。
主人公のバナージ・リンクスは、非常に純粋でかつ真っ直ぐな人間で、どれだけ過酷な現実を突きつけられても「それでも」と言い続け、折れません。
始めは世間知らずな少年という側面が強かったのですが、戦いを続けていく中で成長していき、戦場の構図を変えていきました。
僕もそれに倣い、テストを書くのが辛くとも「それでも」言い続けるようになりました。
仕事で実践していく内に、「それでも」を通して社内の雰囲気も徐々に変わっていきました。
バナージ・リンクスが僕と社内に与えてくれた影響をお話ししたいと思います。
冴えない彼女の育て方から学ぶ情熱と合理性の使い分け
 オオハシ
オオハシ 「冴えない彼女の育て方」
2015年から放送が始まり、2019年の映画で最終となったアニメ。
アニメ、ゲーム好きのオタクが界隈で有名な天才クリエイターの少女たちと共にゲームを作り、コミケを目指す。
クリエイター要素あり、王道の学園ラブコメ要素ありのアニメです。
このアニメの中でエンジニアとしても参考になる言葉がたくさん詰まっています。
そんな中で劇場版「冴えない彼女の育てかた Fine」から抜粋した情熱と合理性の使い分けというところを話したいと思います。
組織とは?人とは?意思決定者に対して本当に必要なものは何なのか、
その本質をつくアニメ「冴えない彼女の育てかた Fine」について話したいと思います。
烈海王に学ぶ、敗北から築くキャリア論〜私は一向に構わんッッ〜
 ニシ サダオミ
ニシ サダオミ 本プレゼンの目的:「失敗を恐れず、敗北を糧にキャリアを築く」ヒントを得る
目次(と概要)
・『バキ』シリーズ紹介 & 烈海王のキャラ紹介
・烈海王の敗北分析とビジネスへの置き換え
①ピクル戦での完敗→自分のやり方の限界痛感
②宮本武蔵戦での死亡→最期まで学びを追求するストイックさ
③異世界転生後の活躍→言葉も常識も違う中で大活躍
・烈海王が教えてくれるキャリア論
①敗北は学びを教えてくれるプロセスッッ
②適応する力こそがカギッッ
③「変わること」と「変えないこと」の両立ッッ
・まとめ
敗北を恐れるな。誇りを持って挑み、何度でも立ち上がれ。
キャリアとは、「勝つこと」よりも「立ち直ること」でできている。
それでも、なお私は一向に構わんッッ!!
アイカツから学ぶビジネスパーソンとしての姿勢
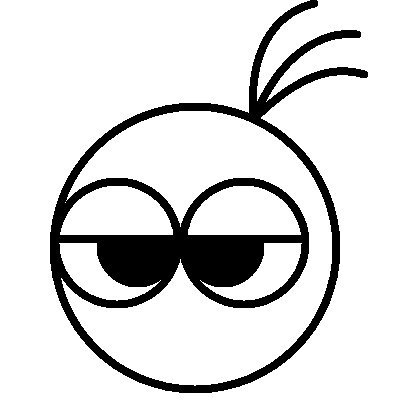 kazto
kazto 「うんうん、それもまたアイカツだねっ☆」
アイカツは人それぞれですが、根底には共通する愛があります。
名場面を振り返りつつ紐解いていきます。
「16ビットセンセーション」のディストピアは現実になってしまうのだろうか
 たまい
たまい ※※※概要の時点で作品の盛大なネタバレを含んでいます※※※
昨今、生成AIの活用が群雄割拠し、ありとあらゆるモノづくりの主役となりつつあります。
最近では製造工程での活用だけではなく、企画・創作段階でも活用されています。
「16ビットセンセーション」では、「売れるゲーム」の要素が集約された似たようなゲームが大量生産され、本来生まれるはずだった名作が存在しないディストピアが訪れました。
現在の生成AIを中心としたモノづくり活動はそんなディストピアの入口な気がしています。
エンジニアとしての生成AIとの付き合い方に関してお話ししたいと思います。
後付け改修の限界と専用設計の重要性
 ヨウ
ヨウ アニメ「マジンガーZ」に登場するアフロダイAは、もともと採掘用に設計されたロボットでしたが、戦闘用に改造されて戦場に投入されました。
しかし、本来の用途が異なるため、戦闘力や耐久性に限界があり、何度もやられてしまいます。
最終的には専用設計の戦闘ロボット「ダイアナンA」が新たに建造されました。
このエピソードは、現場で別用途のシステムに手を加え、転用した結果、結局作り直しになる「あるある」な状況と重なります。
アフロダイAの物語から、後付け改修の限界や専用設計の重要性について考察します。
「壊れるほど愛しても1/3も伝わらない」ので、伝わらない前提でコミュニケーションを取ろう!
 こうの
こうの エンジニアリングは他者とのコミュニケーションの連続です。
「なんで言ってることが伝わらないんだろう?」なんて思ったことは1度や2度ではないはずです。
また最近ではAIに対してのコミュニケーションも増えています。
アニメ「るろうに剣心」の曲にもあるように、想いは伝わらないものなのです。
その前提に立って次のアニソン2曲からコミュニケーションについての私の考えを展開します。
- 1/3の純情な感情 SIAM SHADE
- 片道きゃっちぼーる MOSAIC.WAV
このトークを通して伝わらない気持ちをいかに伝えていくかと、伝わらないときの割り切り方をお伝えします。
友達ではなく仲間とはなにか 映像研には手を出すな!から学ぶ仕事の取り組み方
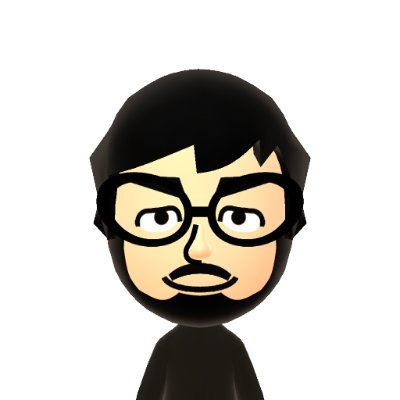 infixer
infixer 「映像研には手を出すな!」の中で、主人公である浅草みどり、同じ映像研のメンバーの金森さやか、水崎ツバメと作った自主アニメ作品を、文化祭で上映したあとの反省会をしている所に、水崎ツバメの両親が現れるワンシーンがあります。
ツバメ母「あ!!ツバメのお友達?」
浅草氏「い、いえ。」
浅草氏「仲間です。」
このシーンを観たとき私は、友達と仲間って何が違うのだろうか?という問いが出てきました。
普段業務をしている中で、チームメンバーと楽しく開発したいという気持ちがあります。
本トークでは、自分なりに友達と仲間を定義して、チームで仕事に取り組むために必要なことを「映像研には手を出すな!」を辿りながら考察していきます。
薬屋のひとりごとにみるトラブルシューティング
 草場友光
草場友光 薬屋のひとりごとでは時折驚くような推理でトラブルを解決していきます。
これは、ITの世界においても応用できる要素です。
いつも完全な情報があるとは限らず断片的な情報をもとにより確率の高い事象を探り当て真実に迫っていく
それでも、断定はしない。
そんな姿はとても参考になることがおおいです。
「魔法少女リリカルなのは」から学ぶ他者理解
 Eli
Eli 私は未経験からエンジニア転職に向け、半年間学習を進めてきました。
学習をする中で、最初は「何を言ってるのかわからない!」「怖い!」という気持ちに襲われました。
技術書を読む際も、宇宙語に感じて、読み終わるのが果てしなく遠く感じることもありました。
そんな中、子供の頃から大好きな「魔法少女リリカルなのは」という作品に支えられました。
主人公・なのはは常に真っ直ぐで、何度も「お話を聞かせてほしい」と向かい合うのです。
はじめましての難しい技術も、私を批判したいのではなく、世の中を便利にするとても優しい技術なのだと、私は信じています。
なのはのように立ち上がって向かい続けることを、皆さんにお伝えできたらと考えています。
「きらら枠」インターフェイスで見る抽象化
 こうの
こうの 「きらら枠」を通してインターフェイスや抽象化の概念をざっくり話します!
「きらら枠」とは『まんがタイムきらら』系雑誌連載作品に多い、かわいい女の子たちの日常と共通した雰囲気・特徴を持つアニメのことを指します。
「きらら枠」作品群に共通する要素を「インターフェイス」に見立て、その特徴を持つ作品が「きらら枠」と呼ばれる現象を分析します。
これは技術における「抽象化」と等しい思考プロセスです。
身近なアニメの例を通じて、「抽象化とは何か?」を分かりやすく解説し、新たな学びを提供します。
【アジェンダ】
- 「きらら枠」とは何か?
- 「きらら枠」の共通項を抽出する
- 「きらら枠ではないきらら枠」に見る抽象化
アニメ「ラーメン赤猫」からの学びクイズ! プロが出す力は、何%?
皆さま、アニメ「ラーメン赤猫」はご存知ですか?
私はエンジニアニメで熱い布教を受け、先日完食しました!🍜
「ラーメン赤猫」からの学びはいくつかあるのですが、今回は一番印象的な学びをクイズ形式でお伝えします。
私はエンジニアリングで対価をいただいたらエンジニアの"プロ"だと思っているのですが、
ではプロは何%の力で物事に当たるとよいのでしょうか?常に全力でしょうか?
ラーメン赤猫のハナさま🐈はここに明確な回答をしており、そこからの学びを共有します。
ラブリーイェイイェーイ!!
高校生ロックバンドアニメの究極「音楽」から見る漢の後ろ姿
 フクイ
フクイ 数あるハイスクール世代のロックバンドアニメは数多くありますが、その中で異彩を放つ「音楽」というアニメについて話します。
このアニメの寡黙な主人公の姿から、なぜ音楽をするのか?という問いから、なぜその行動を取るのか?そこを掘り下げて観たいと思います。
このLTにより
・理屈よりも湧き上がる想いが大事
・言葉はなくても、伝わる人にはつながる


 hato_code
hato_code