WebKit のバグ修正に挑戦してみた
 Megabits
Megabits 去年 WKWebView 関連の開発をするとき、どうしても解決できない問題を発見しました。
当時作った issue: https://bugs.webkit.org/show_bug.cgi?id=274818 (クリックがランダムで反応しなくなる問題。)
それを頑張って調べて、WebKit のバグだと確認し、WebKit の Bugzilla に提出しました。
WebKit の開発者から、それはすでに別の PR で解決されていると言われ、でも再現できませんでした。
色々試した結果、それは WebKit のテスト用スクリプトに問題があると判明しました。
このスクリプトは、ローカルでコンパイルした WebKit を既存のアプリに取り込んで実行するスクリプトです。
実行する際、必要な環境変数の設定に失敗して、アプリは古い WebKit のままで実行されます。
このバグは将来 WebKit の修正に取り組む皆に影響するので、私は新しい Issue を作って、PR を出して、マージされました。
https://bugs.webkit.org/show_bug.cgi?id=275207
(SIP環境でDYLD_FRAMEWORK_PATHが設定できない問題)
https://github.com/WebKit/WebKit/pull/29578
この LT は、この問題発見から PR を出した流れとその中の面白いところを話します。
Embedded Swift & Matterでスマートホーム対応デバイスを操作してみよう!
 Atsushi Miyaji
Atsushi Miyaji WWDC24で登場したEmbedded Swiftによって、ついにSwiftでも組み込み開発ができる時代がやってきました!これによりSwiftらしい書きやすさ・安全性をそのまま活かして、直感的にデバイス制御できるのが大きな魅力です。
このLTでは、Embedded Swiftを使ってLEDやセンサを動かしてみた実例を紹介します。さらに、Appleが推進しているスマートホーム規格「Matter」と組み合わせて、iPhoneのホームアプリから操作するデモも行います。
具体的には、以下のような操作を紹介します
● ホームアプリからLEDライトの明るさを調整する
● 温度センサの値をリアルタイムに取得し、ホームアプリから確認する
普段アプリ開発をしている方の中には、「組み込みって難しそう…」と思っている方も多いかもしれません。しかしEmbedded Swiftを使えば、Swift開発の延長でハードウェアの世界にぐっと近づけます。このトークを通じて、ハードウェアの世界に一歩踏み出してみませんか?
iPhoneを光学式マウスにする試み
 aohara
aohara 光学式マウスの仕組みを知っていますか?
マウスの底にあるLEDで机の表面を照らし、その模様の変化を毎秒数百〜数千回のスピードで撮影。
画像同士を比較して「どっちに動いたか」を計算し、カーソルを動かしているんです。
カメラと画像処理で動きを検出する、まさに小さな画像認識システム。
これってiPhoneでもできそうですよね?
そう思い、意気揚々と始めた「iPhoneを光学式マウスにするアプリ」の開発。
このトークではその過程で得た様々な知見を皆さんに共有します。
このトークを通じて、iPhoneの新たな可能性を探る楽しさを一緒に感じていただければ幸いです。
気づいて!アプリからのSOS 〜App Store ConnectAPIで始めるパフォーマンス健康診断〜
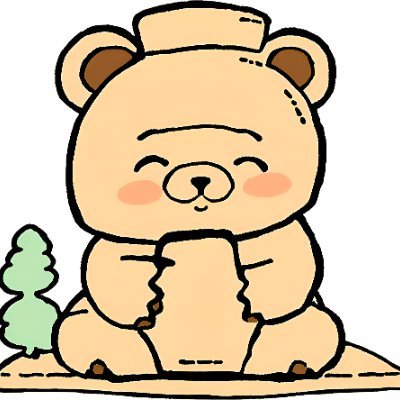 Rikkuma
Rikkuma 皆さん、最近健康診断は受けましたか?
実はアプリでも健康診断は行われているんです。
起動時間やHang率など、パフォーマンスデータは自動で記録されています。
ただし、それを確認するにはXcode Organizerを開いて自分で見に行く必要があります。
でも、わざわざ開くのは面倒だし、忙しいとつい忘れてしまいます。
そのまま見逃してしまえば、アプリからのSOSに気づけないままに…。
・バッテリー消費が激しい
・スクロールがカクつく
・画面がフリーズする
こうした不調が続けば、ユーザーのiPhoneからあなたのアプリが静かに削除されてしまうかもしれません。
本トークでは、App Store ConnectAPI × GitHub Actions で構築する自動パフォーマンス監視体制について、5分で解説します。
Next Talk's HINT:
・App Store ConnectAPI(perfPowerMetrics)
・GitHub Actions
・Xcode Organizer
ジムはOK、代々木公園はNG。位置判定アプリの奇妙な現象
「目的地に行ったらスマホ制限解除」というアプリを作っていた時の話です。
開発は順調でした。近所のジムで何度テストしても完璧に動作。「位置判定範囲200mで実装完了!」そう思っていました。
ところが、友人からの一通のメッセージで事態は急変します。
「代々木公園の中にいるのに判定されない!バグってない?」
まさか、そんなはずは...。慌てて現地に向かい検証すると、確かに公園内部で全く反応しません。一方で、同じコードを使ったジムでは相変わらず正常動作。
いったい何が違うのか?
・GPS精度の問題?→同じ精度設定
・デバイスの問題?→同じiPhone
・通信環境?→どちらも良好
・コードの問題?→全く同じ実装
同じ位置判定機能なのに、なぜ場所によって動いたり動かなかったりするのか?
調査を進めるうち、ある重要な事実に気づきました。そして最終的に辿り着いた解決策は、なんとAIに「ある質問」を投げかけることでした。
この奇妙な現象の正体とは?
そして「ある質問」とは一体何だったのか?
同じような位置判定機能を実装している方、実は知らずに同じ罠にハマっているかもしれません。実際コードとデバッグの軌跡をお見せしながら、この謎解きの全貌をお話しします!
MIDIコントローラーを用いたイコライザーアプリの拡張方法
 masacom
masacom Swift初学者でAVFoundationを使用したイコライザーアプリ開発に挑戦をしていたところ
MIDIコントローラの接続を実装してみたくなりました!
本トークでは、CoreMIDIフレームワークを使用し、アプリに接続されたMIDIデバイスからコントロールチェンジ(CC)メッセージを受信し
それをアプリ内の任意の処理に割り当てる実装の流れと、SwiftUI・音声処理・ハードウェアをつなぐ設計上のポイントなどを共有します。
音声・音響・映像を扱うアプリのMIDIコントローラー拡張が必要な時、プロジェクトへ応用していくための小さなヒントになれたら幸いです。
話す内容:
・CoreMIDIにおけるMIDIClientRefとMIDIInputPortRefの基本構成
・MIDIPacketListからのCCメッセージの解析と値の取得方法
・各CC番号とEQスライダーの動的なマッピング設計
・SwiftUIと組み合わせたリアルタイムなUI同期
・自分専用の機器を想定したプリセット対応
「iPhoneのマイナンバーカード」のすべて
 Daiki Matsudate
Daiki Matsudate 身分証をApple Walletをはじめとしたデジタルウォレットに搭載する動きが、近年世界的に広がっています。アメリカでは一部の州において、州発行の運転免許証の搭載が進んでいます。各国での実証実験が進行しており、これらはISO/IEC 18013-5や-7、23220といった国際標準で定められ、セキュリティやユーザープライバシーに配慮しながら世界中で互換性を持たせる動きが進んでいます。
こうした流れの中で、2025年6月24日から、日本でもiPhoneへのマイナンバーカードの搭載が始まりました。Apple WalletにNational IDを搭載するのは、日本が世界で初めての事例であり、デジタル庁とAppleとの協業によって実現されました。
マイナンバーカードを持っていれば、誰でもApple Walletにmdoc(Mobile Document)として搭載することができ、iPhoneだけでさまざまな行政サービスを利用できるようになります。
これに限らず、開発者もAppleが提供するID Verifier APIを使えば、自分のアプリに年齢確認や本人確認といった機能を国際標準に準拠した形で実装することが可能です。たとえば、酒類購入時の年齢確認や、オンライン口座開設時の本人確認など、民間サービスへの応用が期待されています。
このトークでは、「iPhoneのマイナンバーカード」を活用し、アプリ内、対面、ブラウザの3種類のVerifier APIの使い方とユースケースを紹介します。
また、mdocとはそもそも何であるか、そのデータ構造と検証手法など実装詳細にも触れていきます。
さらに、電子証明書をiPhoneから取り出して利用できる日本のために作られたAPIについても紹介しながらBehind the Sceneにも少し触れてみたいと思います。
5000万ダウンロードを超える漫画サービスを支えるログ基盤の設計開発の全て
 デスクス
デスクス 旧ログシステムから新しいシステムへ移行する際、新システムにはiOS SDKが提供されておらず、なんとログ基盤を自作することに!
そんな大規模なサービスの基盤を構築することは、実際にはそれほど怖くありません!
このセッションでは、5000万ダウンロード規模のiOSアプリにおけるログ基盤移行の実践事例を紹介します。
このセッションでは以下の内容について詳しく説明します。
- 行動ログを取るために必要な知識、仕様、注意点
- 完全なテストカバレッジを前提としたインターフェース設計
- 移行に向けた既存実装の整理と置き換え戦略
- Firebase Remote Configを用いたリスクを抑えた段階的リリースプラン
- 完全Swift 6の実装
このセッションを通じて、中〜大規模サービス基盤刷新の具体的な手順と注意点を理解し、実践に役立てていただければ幸いです。
ゼロタップの世界へ - UWB × Nearby Interaction 実装ガイド
 岡 優志
岡 優志 アプリ開発において、ユーザーの操作を極力減らし、よりスムーズで摩擦の少ない体験を提供したいと考えたことはありませんか?
UWB(Ultra-Wide Band)は、ナノ秒単位で到達時間を計測することにより、高精度で距離と方向を取得することが可能です。
iOSでは、Nearby Interactionフレームワークを利用してこれらのデータにアクセスできます。この技術により、以下のようなタップレス操作が可能になります。
- デバイスが近づいただけでチェックインを開始
- 画面に触れずにデバイスを操作
など、まるで魔法のようなタップレス操作が実現可能です。
しかし、DiscoveryTokenの共有方法やセッションの開始・維持など、通常のアプリ開発ではあまり馴染みのない実装が多く、これがハードルと感じるかもしれません。
本セッションでは、UWBの基本的な知識から、Nearby Interactionを用いた具体的な実装方法をデモを交えて紹介します。
さらに、実装時のハードルを下げるためのTipsもご紹介いたします。
このセッションを通じて、“タップレスなアプリ開発” の第一歩としてNearby Interactionフレームワークの可能性を探ってみませんか?
4100万ユーザーを支えるTVer iOSアプリ開発 〜0人から始まったチームのAI活用による挑戦〜
 福島 友稀
福島 友稀 月間4100万ユーザー、4.5億回再生を誇る民放公式動画配信サービス「TVer」。
そのiOSアプリ開発チームは、2023年のiOSDC登壇時はプロパーiOSエンジニア0人という状況からスタートし、2024年は1人、そして2025年現在は3人体制へと成長しました。
直近は体制を強化していくだけでなく、AI技術を使った業務効率化にもチャレンジしています。
本セッションでは、以下の実践的な事例をご紹介します。
実装・ソースレビューでのAI活用
実際のプロジェクトにおける仕様調整プロセスでのAI活用
Markdownベースの図表作成による劇的な時短効果
「実装でのAI活用は試しているけど、プロジェクト推進や仕様調整など、実装面以外での活用方法がわからない」という方に特におすすめです。明日から使える具体的なノウハウをお持ち帰りください!
ネイティブ製ガントチャートUIを作って学ぶUICollectionViewLayoutの威力
 西 悠作
西 悠作 「こんな複雑なUIどうやって実装してるんだろう」と思ったことはありませんか?
UICollectionViewLayoutはその疑問に対する1つの答えとなるかもしれません。
私たち株式会社アンドパッドが提供している施工アプリには「工程表」と呼ばれるガントチャート機能が存在します。ガントチャートとは縦軸に作業項目、横軸に時間をとる棒グラフです。
この機能は従来WebViewで提供してきましたが、いくつかの理由からネイティブUIで作り直すことに決めました。
iOSのデザインにフィットしてスムーズに動作する、複雑なガントチャートUIを作るには…… たどり着いた答えがUICollectionViewLayoutのサブクラス実装による独自レイアウトでした。
本セッションでは以下の内容をお届けします。
- UICollectionView × UICollectionViewLayoutを採用した理由
- 簡単なガントチャートUIを実装しながらUICollectionViewLayoutの設計思想と実装方法を学ぶ
- 自由自在なレイアウト
- UI要素のピン留め
- セクションの開閉
- ピンチジェスチャによるズーム
- その他UICollectionViewLayoutの応用例
UIKitはまだまだ現役のフレームワークです。
UICollectionViewLayoutの圧倒的な応用力を知り、「どんなUIでも作れそう」という万能感をぜひ味わってみてください。
止められない医療アプリ、そっと Swift 6 へ
 Shogo Yoshida
Shogo Yoshida 2024年にリリースされた Swift 6 は、iOS アプリ開発者に数多くの恩恵 (と少しの混乱) をもたらしました。
まだ Xcode のデフォルト言語バージョンではないものの、すでに対応済みのチーム、鋭意対応中のチーム、様子見をしているチームなど、取り組みはさまざまです。
2016年にリリースした総合医療アプリ「CLINICS」は、病院・薬局の予約からオンライン診療・服薬指導、お薬手帳までをカバーし、9年間にわたり多くの患者様の医療体験を支えてきました。
その裏側では、SwiftUI への置き換え、複雑化する依存関係の解決、メンテナンスが止まったライブラリの移行など、長期運用ならではの技術的負債と向き合い続けています。
本セッションでは、今秋予定の大規模ブランドリニューアルを見据えて実施した、Swift 6 移行プロジェクトの取り組みを紹介します。
- SPM マルチモジュール構成を活かした段階的移行戦略
- AI を取り入れた効率的なコード変換とリファクタリング
- 医療アプリ特有の高い品質要求に応えるテストの刷新
- Xcode 26 での Swift 6 運用 Tips
「止められないシステム」を支える医療現場のアプリの、既存資産を活かしながら最新技術スタックへ移行した知見をお伝えできれば幸いです。
CI/CD「健康診断」のススメ。現場でのボトルネック特定から、健康診断を通じた組織的な改善手法
 鵜沼 慶伍
鵜沼 慶伍 私たちが日々開発をするなかで、CI/CDはプロダクトの品質を担保し、開発を効率化する上で不可欠な存在です。特に自動テストはバグを早期発見し品質向上に貢献しますが、その一方で、私たちはCI/CDを信頼しすぎていないでしょうか?
「CIが成功しているからOK」と、ビルドやテストにかかる"時間"やテスト成功率といった「不健康なサイン」から無意識に目をそらしていませんか?
実際私の担当するプロジェクトでは導入した自動配布で40分ほどかかっている現状があり、その無視できないサインから、「CIが遅い」という課題に正面から向き合ってみることにしました。
このセッションでは、その小さな気づきから始まったCI/CDが「健康」になっていくまでの改善の過程を、個人と組織、両方の視点からお話しします。
まず、改善の第一歩として「どこに注目すべきか」という観点を整理します。実行時間や安定性といった指標に対して、CircleCIやGitHub Actionsなど各サービスごとの機能を活かしながら、どうボトルネックを特定していくのか。各サービスごとに比較しながら、その分析手法からお話しします。
その上で、ビルドツールのキャッシュ見直しやマルチモジュールによる高速化、そして見落としがちなテストコード自体のアンチパターンやリファクタリングといった具体的な改善アクションをお伝えします。
しかし、個人の改善活動だけでは、プロジェクトやチームを横断した品質の維持には限界があります。より大きな視点で、全社的にCI/CDの健全性を保つためにはどうすればよいでしょうか? 本セッションの後半では、その問いに対する弊社なりの答えとして、組織的な仕組みである「健康診断」や月次レポートについても詳しく解説します。
時刻と位置特定の秘密を解き明かす 〜 大航海時代から未来の測位技術へ〜
 綾木 良太
綾木 良太 本セッションでは、位置情報アプリを開発しているアプリエンジニア、または位置情報技術に興味を持つ方を対象とし、位置情報の「精度」や「時刻の取り扱い」について解説します。
スマートフォンで取得できる位置情報は、地図アプリ、交通サービス、IoT、防災など、日常生活を支える多くのアプリで活用されています。しかし、その位置情報がどのような仕組みで得られているのか、特に時刻情報がどのように関わっているのかについては、普段意識することが少ないかもしれません。
本セッションではまず、古代より人類がどのように時刻を求めてきたかを述べ、位置と時刻を求める人類の挑戦として、18世紀イギリスで制定された「経度法」と、それにより始まった経度問題の解決に向けた競争、そしてジョン・ハリソンによる海洋クロノメーターの開発を振り返ります。次に、電波を使った測位方法の歴史と、GPSをはじめとするGNSS(全地球測位システム)の基本原理を解説し、衛星信号を用いて端末の位置を特定する仕組みを解説します。
さらに、GNSSの生データを取得・解析するための専用ツール「GNSS Logger」と「GNSS Analysis」を活用し、端末が捕捉している衛星の数や種類、方向、信号強度といったデータを可視化します。これにより、都市環境でのマルチパス反射、大気遅延(電離層・対流圏)、衛星の配置や補足数不足といった精度劣化要因が、どのようにデータに現れるのかを具体的に解説します。
最後に、センチメートル級の高精度測位の仕組みと、それがもたらす未来の可能性についての展望を語ります。
聴講後には、位置情報と時刻情報の本質的な関係を理解し、位置特定にまつわる歴史と技術の知識が身につきます。
逆向きUIの世界〜iOSアプリのRTL言語対応〜
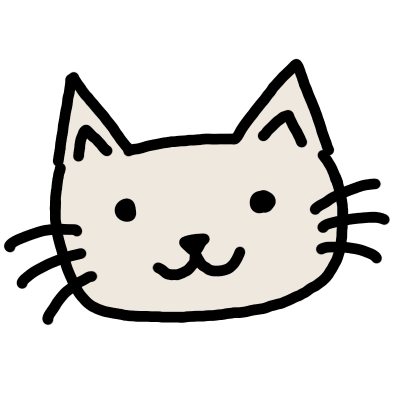 akatsuki174
akatsuki174 多言語対応をしていると、いつかはRTL(Right To Left)言語、つまり右から左に書く言語への対応が必要になる場面に出会います。私が担当しているiOSアプリでもその対応が求められました。
ではRTL言語対応って具体的に何をすべきかご存知でしょうか?iOSでは、OSやフレームワークによってある程度「自動対応」がされます。しかし、UIの崩れ、画像の反転、レイアウトの意図しない挙動など、エンジニアが「手動対応」しなければいけない場面も存在します。
このトークでは次のような観点から、私が調査、実装をしたRTL言語対応の知見を共有します。
- そもそもRTL言語対応とはどんなものか
- RTL言語対応に関するAppleの公式情報をおさらいしてみる
- OS、フレームワーク側が「自動で」してくれるRTL言語対応
- エンジニアが「手動で」頑張るRTL言語対応
- レイアウト修正
- 画像修正
- その他思わぬ落とし穴
- 対応状況をどのように確認するか
このトークを聞けば、初めてRTL言語対応に取り組む方でも迷わず対応できるでしょう。逆向きUIの世界、覗いてみませんか?
Apple Vision Proでの立体動画アプリの実装と40の工夫
 服部 智
服部 智 Apple Vision Pro上で180°立体動画を体験できるViewerをSwiftネイティブで実装し、100名以上に実際に体験いただきました。
その事例をベースに、Apple Vision Proを初めて体験する方でも楽しめるアプリを作るための数多くの工夫を解説します。
40を超える具体的改善ポイントがありました。
そこから、操作ミスや混乱を生まないための徹底したUIのシンプル化、カルーセル形式のコンテンツ選択UI、空間上で押しやすくしたカスタムボタンの設計などをソースコードとデモを交えて紹介。
Vision Pro上での空間コンピューティングUIを実装する上で得た知見と、ブラッシュアップを余すことなくお伝えします。
このViewer実装では、体験者のフィードバックから得た改善点の反映を数ヶ月に渡って行いました。
多くの時間を使って得た知見を皆に共有することがこのセッションの目的です。
このセッションを見ることで、visionOSでカスタムUIコンポーネントを作る際の要素が整理でき、Apple Vision Pro未体験者でも使えるアプリを作成する知見が得られます。
Vision Proアプリ開発の実例に興味がある方、立体動画や空間UIの最適化に取り組んでいる方に特におすすめのセッションです。
スマートフォン 来し方行く末 〜どこから来てどこへ往くのか〜
 @hak & @tomzoh
@hak & @tomzoh みなさんが日々使い、そして飯の種でもあるスマートフォン、その便利デバイスがどのように生まれ、発展し、そしてどこへ向かうのか…
スマートフォン15年史を振り返りつつエナジードリンクを嗜む、ちょっと長めですが俯瞰的情報をご提供するセッションです(途中休憩はいります)
プログラマのための作曲入門
 CHEEBOW
CHEEBOW 音楽とプログラミングはまったく違うもの。芸術と情報工学の間に、共通点などない。
……と思われている方も多いようです。
しかしながら、それは大きな誤解なのです。
なぜなら、音楽は数学だから!
「ド ド# レ レ# ミ ファ ファ# ソ ソ# ラ ラ# シ」、誰もが知っているこの音の並びを生み出したのは、古代ギリシャの数学者ピタゴラス、と言われています。
プログラマと音楽は相性が良いのです。
私自身も、平日はプログラマ、週末はアイドルなどへの楽曲提供をする作曲家です。
プログラミングはコード(code)を書き、作曲はコード(chord)を使います。
この「コード」を中心にプログラマなりの作曲を考えてみましょう。
コードネームから構成音を求めるプログラムを作ることができます。
コード進行にはパターンがあり、デザインパターンやライブラリのように利用することができます。
コード進行からメロディを導き出して作曲していくことができます。
本トークでは
- 作曲とはなんなのか
- コードの仕組み
- コード進行はパターンである
- コード進行を演奏するiOSアプリを作る
- コード進行から曲を作る
についてお話しします。
『ホットペッパービューティー』のiOSアプリをUIKitからSwiftUIへ段階的に移行するためにやったこと
 Akihiro Kokubo
Akihiro Kokubo 『ホットペッパービューティー』のiOSアプリは、UIKitからSwiftUIへの移行を進めており、UIコンポーネントの実装と、単一画面ごとの実装とリリースにフェーズを分け、段階的に移行しています。このアプリは、9年前にObjective-CからSwiftへのリプレイス時にUIKitで実装され、現在では年間2億件近いサロン予約を支えるアプリです。
UIKitからSwiftUIへの移行と聞くと、単にプレゼンテーション層を書き換えて完了と思いきや、そう簡単な話ではありませんでした。
システムがモノリシックな構成であったため、Xcode Previewsの動作は重くSwiftUIの良さが活かせず、マルチモジュール化を進めました。
Figmaで定義されたUIコンポーネントとコードベースとの間には構造上の乖離があり課題でした。そこで、改めてデザイナーの意図が実装に反映され、再利用性が向上する形で各UIコンポーネントをSwiftUIで実装しました。合わせて、命名規則の統一、コンポーネント間の一貫性の担保、不足パターンの追加などデザインガイドラインの整備を行いました。
また、テストやデザインの受け入れなど、周辺の開発プロセスも軽視できません。Xcode Previewsを活用して、自動でスナップショットテストを作成し、UIカタログアプリを配布する仕組みを整えました。
さらに、既存仕様が必ずしも単純とは限りません。多面的なプロダクト仕様をいかに品質を落とさず置き換えるかという観点で、LLM(大規模言語モデル)を活用しました。
本セッションでは、UIKitからSwiftUIへの段階的な移行に関して、背景や目的、直面した課題と方針、コンポーネント実装と画面実装のフェーズ、デザインガイドラインの整備、Previewsを活用したテストやUIカタログの準備、さらにLLMの活用についてお話しします。
少人数体制を実現するモバイルアプリ開発のDevEx改善
 417.72KI
417.72KI ウェルスナビでは「ものづくりする金融機関」というビジョンのもと、金融機関でありながら自社サービスのモバイルアプリを内製で開発しています。
しかし在籍するモバイルアプリエンジニアの人数は少ないため、どうしても一人ひとりの負荷が高くなりがちです。
そこで、ウェルスナビのモバイルアプリ開発では開発生産性を高めるために、プロセスの自動化を初めとする様々な取り組みを実施してきました。
本セッションでは、その中でもiOSアプリ開発における以下の取り組みについて紹介します。
- 開発環境構築の自動化
- テストコードの拡充
- CI/CDの改善
- リリースフローの部分自動化
本セッションを通じて、モバイルアプリエンジニアのDevEx(Developer Experience)を向上させる参考になれば幸いです。

