俺と地方勉強会 -KomeKaigi・地方勉強会への期待-
 ふぁらお加藤
ふぁらお加藤 KomeKaigi キックオフおめでとうございます。
北陸で生まれ育ってきた地方勉強会の事例をもとに、エンジニアがつながる理由、そしてつながることで得られる価値についてお話しします。
富山で10年続く「BuriKaigi」、北陸を超えて各地を新幹線で結ぶ「JAWS-UG 北陸新幹線」、そして全国規模のイベントを地方で実現した「JAWS FESTA 2025 in 金沢」などの運営経験を通じて、地域のエンジニアがどのように出会い、協力し、互いの活動を支え合ってきたのかを具体的に紹介します。
地方では、同じ技術や課題を語れる仲間と出会うこと自体が貴重であり、その「つながり」こそが学びの継続や挑戦の原動力になります。本セッションでは、勉強会運営の裏側やコミュニティ形成の工夫を交えながら、なぜエンジニアがつながることが大切なのか、そしてその輪をどう広げてゆけるかをともにに考えましょう。
新潟のエンジニアコミュニティを盛り上げたい!
 akshimo
akshimo 「東京では毎日のように勉強会が開催される一方、新潟は勉強会が多くない」ーー4年前に東京から新潟へ移住しそう感じました。
では、実際の新潟の勉強会事情はどんなものでしょうか?どうすればより新潟を盛り上げられるのでしょうか?
本トークでは新潟でエンジニアコミュニティ運営に関わってきた実体験と具体的なデータの分析から、「新潟のエンジニアコミュニティを盛り上げるには?」を考えます。
トーク内容
- 新潟の勉強会事情
- 勉強会数や人口などのデータ紹介
- 新潟のエンジニアコミュニティを紹介
- 新潟を分析してみる!
- データの統計的な分析を行う
- 新潟特有の文化や背景を考える
- 新潟のエンジニアコミュニティを盛り上げたい!
- 2.の分析結果とコミュニティ運営の実体験をもとに、新潟に適した活性化策を探る
本トークが新潟のエンジニアコミュニティを盛り上げる一助となれば幸いです!
地方学生の成長を加速させる支援とは〜新雪プログラムでの開発経験と修了後の展望〜
 Akiba
Akiba 新雪プログラムは,北海道在住の25歳未満クリエーターを対象とする人材育成・発掘プロジェクトで,2023年度に開始されました.
私は「電子ペーパーサイネージの省電力化」のプロジェクトで採択され,開発を進めてきました.
地方で活動する学生は交流の機会が限られるという課題がありますが,本プログラムの伴走支援と横断的な交流により,他分野の視点を取り入れ,互いに刺激を与え合う環境で開発を進めることができました.
修了後は,成果を研究論文として発表し,新雪コミュニティでのハッカソンの企画・運営にも継続的に関わっています.
本トークでは,私が,育成支援プログラムを通じて得た学びと,修了後に広がった活躍の場について自身の経験をもとにお話しします.
このトークを通じて,地方に住む学生が技術を楽しみながら成長していくための環境や支援のあり方について,皆さんのご意見をいただけると幸いです.
地域で挑戦するPdM兼エンジニアのプロダクト開発
 八子 勇一郎
八子 勇一郎 新潟でPdM兼エンジニアとしてWebアプリ「Groov Hub」を開発しています。小規模チーム・複業体制ならではの制約がありつつも、生成AIやFlutter、Firebaseといった技術の進化により、地方からでもスタートアップ的な開発が可能になっています。本トークでは、PdM兼エンジニアとして取り組んだ「暗黙知を残さない徹底したドキュメント化」や「AI Agentsが参照しやすい環境整備」等の工夫を紹介します。AI時代における小規模チーム開発のヒントを共有します。
AIエージェントを作ろう!
 みのるん
みのるん 2025年はAIエージェント元年。エンジニアを中心に、コーディングエージェントなどを「使う」のは当たり前になりつつありますが、自分の業務に合わせて「作れる」人はまだまだ少数です。最近はPythonやTypeScriptで簡単にAIエージェントを書けるフレームワークが豊富で、ローコードと同じぐらい簡単に自分専用のエージェントを作れます。王道Webアプリとして構築できるため、内製開発の入門にもピッタリ!そもそもAIエージェントとは何か、どこから始めればいいのか。最新トレンドや活用事例とともにやさしく解説します。
設計に疎いエンジニアでも始めやすいアーキテクチャドキュメント
 林 知範 / ぴーはや
林 知範 / ぴーはや GKE で運用している Web アプリケーションを Cloud Run に移行する上でのモチベーション/検証過程/得られた学びについてお話しします。
移行における新しい技術として、今年 4 月の Google Cloud Next '25 にて発表された Cloud Run worker pools という出来立てほやほやのサービスを中心に取り組んでいます。
Cloud Run worker pools とはどんなサービスなのか?なぜ移行を検討するモチベーションになったのか?検証過程での気づき・学びにはどんなことがあったのか?
初めて挑むインフラリビルドに取り組む中で Google Cloud に特化した話から技術に携わる方にぜひ伝えておきたい話まで幅広い品種のネタを詰め込んだ 15 分間をお届けします!
HTTPじゃ遅すぎる! SwitchBotを自作ハブで動かして学ぶBLE通信
 越智 翔一
越智 翔一 最近、スマートホーム分野で話題になっている SwitchBot というものがあります。
私はドア開閉を楽にするために自作の顔認証プログラムと組み合わせて使っています。
SwitchBot製品は、SwitchBotハブを使うことによってHTTP通信で操作できます。SwitchBotハブを購入せずに操作したい場合には、BLE(Bluetooth Low Energy)通信を用いることで操作できます。
このトークでは、BLE通信の概要とその通信の流れや仕様の詳細について、
"自作SwitchBotハブによる顔認証ロック"を題材にお伝えします。
以下の流れでお話しする予定です。
- 今回作成した顔認証ロックのシステム構成の概要説明
- BLEの仕様の詳細解説
- 自作してどれくらいのコスト(お金)削減になったのか?
- BLEとHTTP 経由で通信した場合のレイテンシー比較
「惰性で生きる」はずだったプログラマが、セキュリティ企業を経営することになるまで
 つめたいうどん
つめたいうどん かつての私は、プログラマとして定年までコードを書き続ける、そんな安定した未来を思い描いていました。
セキュリティ企業を経営し事業拡大を目指す現在の姿は、当時は想像もしていませんでした。
転機となったのは、昔から持っていたセキュリティの興味とふとしたきっかけ、少しの勇気がセキュリティの世界へと自身を誘います。
このセッションでは、私のキャリアや考え方を大きく変えた経験をお話しすると共に、それぞれの立場から見えてきたセキュリティの課題、そしてコクチョウが今、どのようなセキュリティ課題を解決していこうとしているのかをお話します。
新米エンジニアが放置PRという小さな種と戦うアプリを開発して見えた、横断的開発で大きな収穫を得るまでのレバレッジ戦略
 はるおつ
はるおつ 概要
「このPRだれかレビューして〜!」という日常的な課題を開発ボトルネックとして捉え、レビュワーをランダムにアサインして定期リマインドするツールharuotsu/slack-review-notifyを開発・運用しました。
開発速度の向上に伴い、ボトルネックが日々移り変わる現代の開発現場。
このOSS開発を通じて2年目の新米エンジニアとして見えてきた、小さな種から横断的な価値創出へと展開し、小さな投資で大きなリターンを得るレバレッジの効く開発の実践例をお話しします。
技術実装の詳細に加え、個別問題解決から構造的解決への転換とチーム内の当たり前を加速する知見を掘り下げます。
発表内容
- 新米視点での課題発見
- レバレッジの効く横断的開発に伴うDB再設計までの道のり
- 開発効率を最大化する通知システムの設計
- 個人プロジェクトからチーム全体への新米エンジニアの成長戦略
新米エンジニアがJapan AWS Jr.Championsになるまで〜ゼロから始めたAWSとの歩み〜
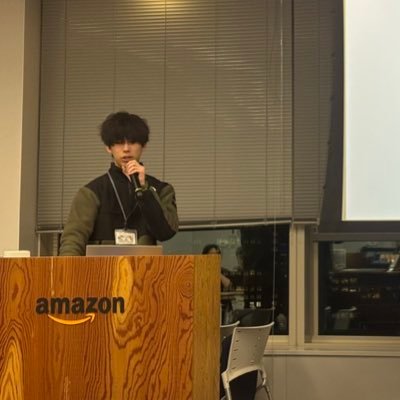 八雲慎之助
八雲慎之助 私は2024年IT企業へ新卒入社しました。
そして2025年、AWSに対して情熱を持って活動を続けてきたことが評価され、AWS Jr. Champions に選出されました。
この発表では、クラウドやAWSにほとんど触れたことがなかった私が、どのように興味を持ち、どのような活動を続けてきたのか、Jr.Champonsの表彰制度の概要から、具体的な取り組み、意識していたことまでお話します。
また、なぜ今まで情熱を持って活動をしてこれたのか、何が大切だったのか。身近なロールモデルの一例として、ヒントや勇気をお届けできればと思います。
同じ「新米」として、これからの一歩を踏み出そうとする皆さんに向けて、あるいは将来のチャンピオンに向けて、私自身の等身大の体験談をお届けします。
異業種転職×新米広報担当が挑む!IT企業のインナーブランディング
 えみがわ
えみがわ 私は印刷会社からIT企業へ転職した新米広報担当者です。
IT業界の風習も広報業務も初めてで右往左往する中、会社では「社員同士のつながり」をどう生み、広めるかが課題になっていました。
部署を越えた交流や会社への帰属意識を育てるために行っているインナーブランディングの取り組みを、異業種出身だからこそ気付いたエンジニアの凄さや「IT企業あるある」などを交えながらご紹介します。
社内のコミュニケーションや組織づくりのヒントになれば嬉しいです!
新米エンジニアをTech Leadに任命する ― 成長を支える挑戦的な人と組織のマネジメント
 naopr
naopr 多くの新米エンジニアにとってTech Lead(以下TL)は憧れであり身近な目標の1つです。
しかしTLには技術的な意思決定、プロジェクト推進、チームマネジメントなど幅広いスキルが求められるため、経験豊富なエンジニアが長く務めるケースも少なくありません。
一方で、あえてジュニアなメンバーにTLを任せることで本人に非連続な成長機会を与えると同時に、チームとしても属人性を排除し学習する組織へと進化できる可能性があります。
私はこれまで、新卒2年目で自身がTLを務めた経験、前職での「短期間交代制TL」、現職での「新卒1年目のTL任命」など、挑戦的なアサインを実践してきました。
本トークでは、これらの事例をもとに以下3点をご紹介します。
- TLを任せるポテンシャルを持つ新米エンジニアの特徴
- 任命にあたり必要となるマネジメントの工夫
- 本人・チーム双方の成長を支える仕組みづくり
AIがコードを書いてくれるなら、新米エンジニアは何をする?
 なかざん
なかざん エンジニアのAI活用が一般的になってきたことで、細かい実装についてはAIエージェントに任せられる場面が増えてきました。
さて、自身の開発作業を「AIエージェントが開発を担う小さな開発チーム」と見做す場合、開発者はAIエージェントに対して「良き共同開発者」「良きアーキテクト」として振る舞うべきです。
従来のITエンジニアキャリアでIndividual Contributorを目指す場合、ジュニア時代にコーディング中心の下積みを経て、試行錯誤の中でアーキテクト能力を少しづつ身につけていました。しかしながら、今後はジュニアエンジニアも早い段階からアーキテクト的な視座を持ってAIエージェントというプログラマーに向き合う必要が出てくるかもしれません。
本発表では、AI時代の新米エンジニアが求められるかもしれない、アーキテクトという分野について、どのような切り口で親しんで行けばよいのかを考えてみます。
“新米”エンジニア組織、“新潟”で自社サービスの内製化
2024年10月、同年2月に万代島に開設した弊社BPOセンター内に自社サービスの内製開発※を行うシステム開発エンジニアのチームを新設いたしました。
今回のセッションでは、弊社を知っていただくとともに
自社サービス開発の内製への取り組み、開発事例とAIの導入、弊社システム基盤のコア技術を『技術的な挑戦と内製化』としてご紹介させて頂きます。
以下内容を補足)
・<事例> MEGAサービス(ユーザ数1000万超)のクラウドネイティブ化、リアーキテクト【クラウド移行のリアル】
・<取組> AIによるエンジニア支援/AI駆動のドキュメンテーション【AIによるドキュメント自動化】
・<技術> MEGAサービスを支える認証技術(OAuth2.0/OpenID Connect)とセキュリティ向上策【内製化の推進 ~技術選定から】
※2020年より自社サービス開発を業務委託から内製へ方針転換
積雪地域の路面状態識別技術について
新潟のような積雪地域では、道路の維持管理が課題になっているのはご存じでしょうか?
雪が降ると道路が埋もれないための除雪作業や、凍結防止剤の散布などが必要となります。しかし大量の降雪に加え広域にわたる道路網を持つ新潟や北海道では、維持管理にかかるリソースが膨大(新潟県の24年度道路除排雪費は過去最高の153億円以上)であり、発生するロスも問題になっています。
そこで近年検討されているのが、走行中の車両に搭載されたカメラやセンサからリアルタイムに路面情報を識別し、必要なリソースを的確に投入するというアプローチです。
本LTでは、その実現に必要な「冬季の路面状態の自動識別」に焦点を当て、現在の技術的課題と検討されている手法について近年の論文を交えてご紹介します。積雪地域における道路維持管理のための技術に少しでも興味を持っていただければ幸いです。
「まずは一つの専門性を」と言われて困る新米に伝えたい、マルチポテンシャライトの可能性
 hkws
hkws よくあるキャリアのアドバイスとして、「まずは一つの専門性を得ましょう」と言われます。しかし、新米の皆さんの中には、興味の対象が広くて一つに定められない!と言いたい方もいませんか?私もその一人で、尖った武器を持てず、周囲から求められるエンジニアになれないのではと怯えていました。
本トークでは、そんな広く興味を持って探求する人々「マルチポテンシャライト」について、以下の内容を紹介します。
- マルチポテンシャライトとはどんな人たちか
- 広い興味で得たキャリアの選択肢:JTC社員兼スタートアップの一人エンジニア
- LLMが加速させる興味の探求:仏教学から着想を得た、犯罪者の説得についての事例
確かに私たちは、一つの分野の専門家にはなれないのかもしれません。でもそれでもなんとかなりそうじゃん、それにすごい楽しそうじゃん!そう思っていただけるトークを目指します。
深く知りたいなら、内側に行け!〜非エンジニアがエンジニアコミュニティに潜り込む技術〜
 ずんだまる
ずんだまる (新米…?)DevHRとして非エンジニアの私が、なぜ技術コミュニティに積極的に参加するのか?その答えは「エンジニアのリアルな声や文化を理解し、より良い関係を築きたいから」です。
本発表では、私が実践してきた非エンジニアがコミュニティに溶け込むための考え方と具体的なノウハウを共有します。
技術トレンドのキャッチアップ方法から、コミュニティで信頼を築くコミュニケーション方法まで、明日から使える実践的なヒントをお話しする予定です。
新米エンジニアの皆さんには、非エンジニアとの連携を円滑にするヒントを、
そして非エンジニアの皆さんには、エンジニアの世界への一歩を踏み出す勇気をお届けします!
新米DPEが取り組む開発者体験の向上
 alpaca-tc
alpaca-tc DPE(Developer Productivity Engineering)は自動化等の手法を用いて開発者体験・開発生産性を向上する職種です。
日本でメジャーとまでは言えないDPEの職種は、新しい取り組みだと思います。
また、自社においては、1人でDPEユニットを立ち上げて活動しており、DPEとしては新米です。
似たような課題を持つ方に、DPEとしてのアプローチをお伝えすることが刺激になるかもしれません。
トーク内容
- DPEとは何をする職種か 1min
- 自己紹介 30sec
- DPEとして取り組んだこと、その成果 2.5min
- CI/CDの改善
- Rubyの高速化
- Railsのモジュラモノリス化
- 失敗・難しいこと 1min
- 開発者と共に改善する体制の構築。例えばflaky testを開発者が改善する体制にイネイブリングすること
アンラーニングの大切さ: 新しい領域に取り組んだ新米の学び
エンジニアとして働き始めて9年、7月から新米データエンジニアとして歩み始めました。初めは「身に着けた経験や知識」に頼り失敗を繰り返したものの、周囲の方々のサポートを受けてゼロからやりなおし、今では能動的にアクションを起こせるようになりました。
本トークでは、これから様々なキャリアを歩んでいく方々や新たな挑戦をしようとしている方々に向けて、「これまでの慣れや考え方」に頼って起きた失敗と学びについて共有します。 新米エンジニアやこれから挑戦を考えている方々に対して、既存の知識にとらわれず柔軟に学びなおすことの大切さをお伝えできれば幸いです。

