資格を「お守り」から「武器」にする戦略
 アキキー
アキキー 「資格を取得しても意味がない」こんな言葉を誰かから聞いたことはありませんか?
取得した資格が履歴書を飾るだけの「お守り」になっているなら確かに「意味がない」かもしれません。
しかし、資格を戦略的に取得すれば、キャリアを指し示す強力な「武器」になります。
私自身、AWS認定15冠を含む24個の資格を取得する中で、「武器」にするための戦略を導き出しました。
このLTでは、その戦略を次の3つのステップで解説します。
- 資格を取得する目的
- 資格の選び方
- 取得後のアクション
せっかく資格を取得するなら「武器」にしましょう!
令和でもブログを自宅サーバで
 うすゆき
うすゆき AIで猫も杓子も生成できる時代にブログ https://blog.usuyuki.net を書き続けています。
学生→社会人と続け5年目となったブログ執筆を踏まえて、今伝えたいことを5分に凝縮します。
話す内容
- 新卒2年目世代(24卒)の一人としてのブログの捉え方
- YouTubeやPodcastsでなくブログ
- テキストの強さ(Unix哲学を添えて)
- Google検索を無料全文検索に使う「うすゆきブログ 大吉祥寺.pm」
- 生成AI時代のブログ
- 結果よりアウトプット行為が強い
- アウトプットはキャッシュされる
- 自宅サーバでコスパ良く所有欲も満たす
- 1万円台で始めるミニPC。Proxmox仮想化してコンテナ管理
- Cloudflare TunnelでV6プラス環境でも外に公開
50代からのイベント・カンファレンス当日スタッフ参加のすすめ
 hmatsu47(まつ)
hmatsu47(まつ) 50代、そろそろエンジニア人生も後半から終盤へ…というところでコロナ禍が終わり、イベント・カンファレンス当日スタッフ参加を少しずつ始めた私から、(だいたい)同世代の皆さんに向けて、あえて主催者でも登壇者でもなく当日スタッフという「裏方」という立場でイベント・カンファレンスに参加してみませんか?という話です。
会社ではキャリアの終盤が近づいてくる中、一回りや二回りも若い主催者・コアメンバーの下で、様々な年代・性別のスタッフ仲間と一緒に働く経験が、今後の人生にプラスの影響を与えるかもしれません(?)
プロポーザル駆動学習:暗黙知を形式知へ変える実践的学習法
 Masaki ASANO
Masaki ASANO 皆さん、技術カンファレンスへのプロポーザル、書いていますか?
中には、「登壇するほどのネタもないし…」「わざわざ書くほどのこともないよな…」そう思っている方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、プロポーザルを考えて出すことがエンジニアとしての成長を加速させる、様々なメリットが秘められているのです。
この「プロポーザル駆動学習」という考え方を通じて、プロポーザルが登壇するための単なる「提出書類・前提条件」ではなく、皆さんにとっての「学習の機会」であるということをお伝えします。
アジェンダのイメージ
- プロポーザルで暗黙知の言語化をする
- 自分の中の想いや経験を見つめ直す時間にする
- 登壇への思いの発露・自己開示
- 採択された後の話
- 採択されなかった後の話
巻き込みに一番必要なのは巻き込む力ではなかった
 ponyoxa
ponyoxa ちょうど1年ほど前にあった上司との面談で、「もっと周りを巻き込んでほしい」と伝えられました。そこで、「自分ひとりの問題ではないのか。巻き込むと言っても何をすればいいのか」と悩みました。
悩んだ末、自分が続けられそうなこととして、自分が好きなことややりたいと思っていること、感じていることをシンプルに素直に周りに伝えるということを実践しました。
行動した結果、社内Slackで「巻き込みがすごい(意訳)」と言われるまでになりましたが、振り返ってみると自分の行動は小さな波を与えたかもしれませんが、それを大きくしたのは自分の力ではない、と思いました。
このトークでは、自分が周りを巻き込むにあたって考えていたことやマインドセット、結果としてみんなでやっていくには何が必要だったのかを話します。
周りを巻き込むのって難しい!と感じてらっしゃる方にひとりの事例として参考にしていただきたいです。
AI時代のチームビルディング〜共有知の作り方〜
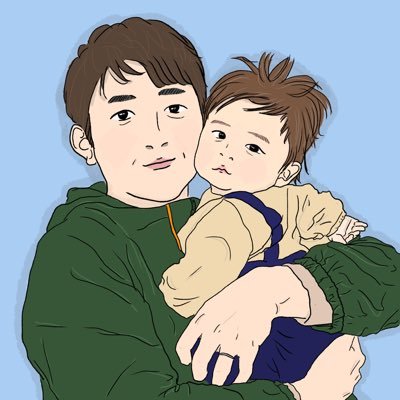 ふくすけ
ふくすけ AIが身近な存在となった今、先輩や上司に頼らずとも知りたい情報を得られるようになりました。各人の生産性は確実に上がっている一方で、チーム内の会話が減って知識やノウハウがサイロ化し、蓄積されてきた暗黙知や文化の継承が困難になっていませんか?
AIは使う人の知識レベルで引き出せる答えの質が大きく変わるため、経験豊富なメンバーと新卒・若手メンバーとの間の知識差をさらに広げてしまう懸念があります。
また、これまで「ちょっといいですか?」と交わされていた相談がAIへの質問に置き換わることで、チーム内では「誰が何に困っているか」が見えにくくなり、偶発的な学びの機会も失われがちです。
本LTでは、これらの課題に対して試行錯誤した結果得られた、AI時代の「共有知」を育むための実践的な知見をお話しします。
AI時代のチームビルディングに悩んでいる方のヒントになればうれしいです。
周り、強すぎない?
 じゅんじゅん
じゅんじゅん 「周り、強すぎない?」そう思ったこと、ありませんか?
技術スキルに自信がない私が選んだ、生き延びるための戦略。
弱くても価値を出す方法、2025年の今だからこそ話します。
カオスエンジニアリングを5分でわかった気になろう
 工藤ユミ
工藤ユミ ソフトウェアはハードウェアと違って、制約があいまいになりやすく、
それによって意図しない挙動をすることが多々あります。
もはや異なる文脈のソフトウェアとの接続、分散システムが当然のように使われる世の中。
人同士の連携で言っても、異なる文脈で育ってきた人々が連携し、多様性を重んじながら全体の系を実現する世の中。
こういった世界観では、もはやアジャイルだけでなく、カオスエンジニアリングの思想がマストになってきます。
今回は、カオスエンジニアリングの勉強会と、過去にセキュリティカオスエンジニアリングの案件に入って、
薄くなりにも経験を重ねてきて、カオスエンジニアリングを分かった気になったわたし目線で、
5分でコンパクトにカオスエンジニアリングの世界観をお届けします。
仮説: 全部AIに任せるならコードファーストで書かせるといいのでは
 macopy
macopy 私は https://github.com/mackee/tanukirpc というGoのWebフレームワークを作って仕事でも使用しています。このフレームワークは1人でバックエンドとフロントエンド両方を作成することを目的としていて、コードファーストでAPIスキーマを作成し、APIクライアントを出力します。
ところでこのtanukirpcをAIに使わせてみたらどうでしょう、なんかうまいこと使えてる気がする! というのもAIというのは実装については人間によるコーディングをなくして自分で全部やらした方が上手くいくことが多いように思ってます。APIスキーマを書くのもAIにやらせるならスキーマファーストのメリットが無くなるのでは? という仮説のもと色々やっていったのを話します
生成 AI 時代に技術ブログを書く理由
 azukiazusa
azukiazusa 生成 AI が台頭しているこの時代、知りたい情報はチャットで体系的にわかりやすく教えてくれます。技術的な情報ブログに手間ひまかけて書かずとも、 AI に任せれば一瞬で生成してくれる可能性は高いでしょう。実際にコードの生成の多くは AI に任せている人も少なくないでしょう。
AIの方が正確で網羅的な情報を提供できる」「AIに聞けば済むことをわざわざ書く意味がない」といったブログを書くことが躊躇われるような感覚を抱くなかで、なぜ私が技術ブログを書くのかについて話します。
- 導入: なぜブログを書くのをためらうのか?(1分)
- AI時代だからこそのブログの価値(3分)
- ブログを書くことによる知識の内在化
- 人間の体験談
- ブログの執筆に AI を活用する(1分)
期待の新人 Coding Agent くんと上手に付き合う方法 〜暴走を防いで良き相棒にするコツ〜
 ふわり
ふわり 2025年、 Coding Agent が身近な存在になりました。 Claude Code や Cursor 、 GitHub Copilot など様々なツールが登場し、コーディング作業を大幅に効率化してくれます。
私は様々な Coding Agent を半年程度、直近1ヶ月は Claude Code を使用し、人間が到底追いつくことができない開発速度に驚く一方、明後日の方向への暴走でクレジットをドカ食いするおちゃめな一面も目撃しました。
本LTでは、暴走しがちな Coding Agent を適切にコントロールし、良き相棒として活用するための具体的な手法をお伝えします。
❚ ターゲット
Coding Agent を使い始めた、またはこれから使おうと思っているエンジニア
❚ 話す内容
典型的な暴走パターン(1分)
どうやって暴走を防ぐのか(3分)
良き相棒にするための心構え(1分)
懇親会に日本酒🍶を持ち込み理由
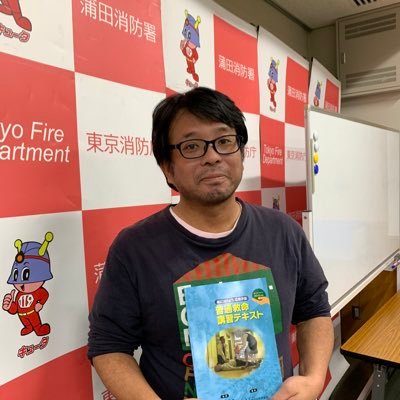 カワハラ
カワハラ 私は、勉強会から、そのまま懇親会をする場所では、日本酒🍶を持ち込むことがあります。
建前としては、主催者の金銭的負担の軽減や、懇親会の時に振る舞えるといのもあります。
しかし、別に壮大な理由があります。
それを話します。
ChatGPTは小説を書けない
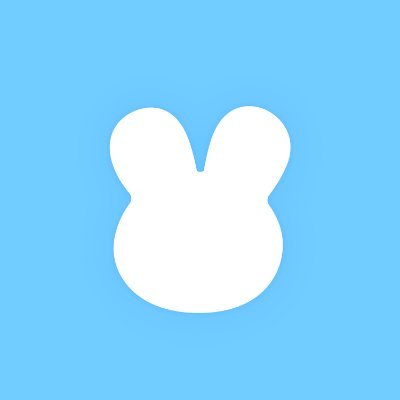 匿名希望Y
匿名希望Y 「ChatGPTに小説を書かせてみたけど、思ったより浅かった」──そんな経験はありませんか?
このLTでは、ChatGPTがどこまで物語を創作できるのかについて、実体験に基づいた分析を通して、生成AIの限界と可能性を探ります。
・なぜChatGPTはドラマ性やどんでん返しを自然に生成しないか
・ChatGPT、AIのべりすと、NovelAIの比較
・エラーの傾向(不自然な行動、キャラ崩壊、規約違反)とその対策
AR グラス + ミニ PC で実現する新しいモバイル環境
 gara
gara 昨年の大吉祥寺.pmで愛用の Linux ラップトップ PC について LT しましたが、ついにその PC も壊れてしまいました。
買い替えのタイミングで、私は大胆な挑戦をしてみることにしたのです。
2025 年の今だからこそ現実的になった AR グラス + ミニ PC という組み合わせで、従来のラップトップに代わるモバイル環境を構築しました。
本 LT では、物理ディスプレイを手放して AR グラスに移行する際に考えたことと、新しいモバイル環境の体験について共有します。
Outline
- ラップトップに感じていたつらさ
- 使用している AR グラスとミニ PC
- 現時点での感想
Learning Outcome
- AR グラスを使いたくなる。
- AR グラス + ミニ PC という構成の可能性を感じてもらう。
【実演版】カンファレンス登壇者・スタッフにこそ知ってほしいマイクの使い方
 Arthur
Arthur https://blog.arthur1.dev/entry/2024/03/01/210535 に書いた、マイクの正しい使い方、あるいはやってはいけないことについて、実演を交えて簡潔にお伝えします。
みなさまのスピーチがもっと聴衆に伝わる、そんなTipsをぜひ!
2025年のPython環境はここまで簡単になりました! 環境構築ツールパビリオン クイックツアー
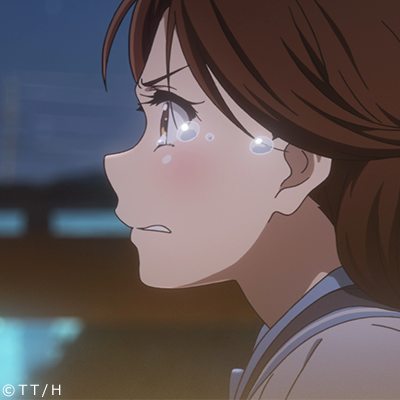 nikkie
nikkie PythonはWebアプリからデータ分析、自動化などなど幅広い用途で利用されており、多くのユーザがいる言語です。
そんなPythonですが、一番難しいのは環境構築になってしまっているように思われます。
30年の歴史の中で「環境管理といえばこのツール」がなかった言語ゆえ、Webに情報が入り乱れている印象です
このLTでは2024年から注目されているuvを取り上げ、2025年時点のPython環境が著しく簡単になっていることを全力で伝えます。
私が7-8年前に入門したときの苦労は、もはや全人類経験しなくていいんです!!
- パラダイムシフト:"仮想環境"を人間が作る時代は、もう終わりました。ツールに任せて楽してこーぜ!
- 楽々 uv sync
- uv run script.py (inline script metadataなるもの)
- uvx (手札は、全PyPI!)
夏だ!祭りだ!浴衣で歩こう!!~浴衣の歩き方のコツ~
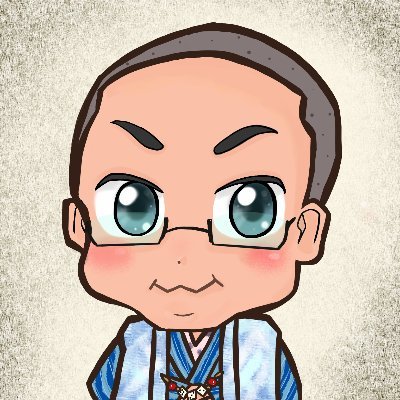 白栁隆司
白栁隆司 大吉祥寺.pmの開催は9月6日です。言うまでもなく、まだ夏ですよね。
今年も夏祭りや花火大会に浴衣で出かけた方も多いことでしょう。
ですが、浴衣で歩く歩きにくかったり、気崩れしたりしませんか?
実は、洋服のときと浴衣のときでは、適した歩き方が違うんです。
サンダル、靴、下駄(草履)の3種類、男女に分けて浴衣での歩き方のコツを、普段着が着物な白栁が紹介します。
キレイに見えて楽に歩ける、そんな歩き方を身に着けて、残りの夏を浴衣で祭りを楽しみませんか?
そして、次の夏への準備もぜひ……。
わりとなんでもできちゃう Fargate SPOT bastion (with ecsta とか)
 sogaoh
sogaoh 本トークでは、Terragruntとecspressoを利用してIaCで構築したFargate bastion('踏み台')を、
多少の手を加えることでプロダクト運用に役立てようとしている事例を紹介します。
Fargate SPOT採用によるコスト最小化や、ecsta等のツール連携による柔軟なタスク実行、CI/CDとの統合など、
「なんでもできる」bastionを実現するための工夫と、実際に直面した課題を具体的に共有します。
5分で駆け抜けるモダンJavaの「今」
 こうの
こうの 「JavaはSIer言語」なんて言わせない!2025年の今、Javaは驚くべき進化を遂げています。まだJava 8で止まっていませんか?
本LTでは、5分という限られた時間で、Java 8以降の主要な進化(var、Records、Sealed Classesなど)を「勢い」と「熱量」でお届けします。関数型プログラミングの強化、モダンなAPIの追加まで、開発体験が劇的に変わるポイントを駆け足でご紹介。
これは単なる機能紹介ではありません。今のJavaがどれだけモダンで、パワフルで、そして楽しいかを感じてほしい!「5分でJavaのイメージが変わった!」「もっと深く知りたい!」と思ってもらえるよう、最新Javaの「今」を凝縮してお伝えします。Javaの進化の勢いを、ぜひ体感してください。
組織が大きく変わろうとするとき、自分はどうありたいかを考えている
 うーたん
うーたん 私の勤める会社では、外部の事情によって、これから組織の体制や文化が大きく変わっていくことが予想されています。
実際に何がどうなるかはまだ分かりませんが、周囲の雰囲気や人間関係に、少しずつ変化の兆しが見え始めています。
このままここに残って働き続けるのがいいのか。もっと自分に合った環境があるのか。
そんなことを考えるようになってから、私はこれまでのキャリアを振り返ったり、身近な人に相談したりしながら、少しずつ動き出しました。
まだ決断を下したわけではありません。でも、悩みを抱えたまま止まっているよりも、何かしら行動をすることで気持ちが少し落ち着いてきました。
このセッションでは、組織が大きく変わろうとしている中で、私がどんなふうに考え、どう動いてきたのかをお話しします。
同じように環境の変化に向き合っている方の、ヒントや安心につながればうれしいです。

