Introducing RFC9111
 小山健一郎
小山健一郎 現在HTTP Cacheに関するRFCは7234...ではありません。2022年に改訂され、RFC9111 HTTP CachingとしてInternet Standardになっています。
本発表ではRFC9111、特に共有キャッシュについて見ていきます。
プロキシサーバのアップストリームに位置するWebアプリケーションとしてどうすればキャッシュをしてくれるのか、もしくは拒否できるのか。理解すれば、実装にはよりますが少なくともRFCに沿った議論ができるようになります。
発表者はRFC9111に沿ったキャッシュミドルウェアを実装しています。
https://github.com/2manymws/rc
この実装経験に基づいた紹介をします。
(なお、2025年8月現在rfc9111で検索して出てくるのは我々のリポジトリを含めて5つ)
この機会に「RFC9111完全に理解した」になりましょう!
カンファレンスのこちら側とあちら側2025
 長谷川智希
長谷川智希 「いつかはカンファレンスで発表したい」そんな風に思っている方も多いのではないでしょうか。
私は今でこそ年に何度も発表をしていますが、勉強会デビューは30代後半のことでした。そして、初めてカンファレンスで発表したのは10年前、第1回のPHPカンファレンス福岡 2015でのことでした。
このトークでは2013年の勉強会デビューからどの様にしてカンファレンスで発表する様になったのか、勉強会やカンファレンスの楽しみ方、そしてそれから10年、カンファレンスでの発表が人生に与えた最高の影響についてお話します。
このトークを聞いた方がカンファレンスを一緒に楽しめる「仲間」になることを祈っています。
カンファレンスのつくりかた
 長谷川智希
長谷川智希 近年、PHP系カンファレンスが大流行していて、今後もその流れは続きそうです。
このトークでは過去に16回のカンファレンス主催をしてきた私が、これからカンファレンス主催したい方の最初の一歩に役立つであろう内容をお話します。
- カンファレンスをつくるのに必要な4種類の参加者
- 会場の探し方と選び方
- カンファレンス開催にかかるお金
- 管理する必要があるものとそのためのツール
- ノベルティや会場装飾の作り方
- カンファレンス準備カレンダー - いつ頃、何をするか
カンファレンス主催したい方だけでなく、スタッフとしてカンファレンスを作ってみたい方、カンファレンスがどうやって作られているかが気になる方にもお楽しみ頂けると思います。
このトークがカンファレンス主催したい方の助けになり、PHPカンファレンス福岡の復活や、福岡での新たなカンファレンス誕生の助けになることを祈っています。
E2Eテストで開発を止めないためのPlaywright高速化
 ゆずねり
ゆずねり E2Eテストの重要性は理解していても、実行時間の長さがボトルネックになっていませんか?
Playwrightはユーザー体験をテストするE2Eテストツールです。
PHPのテストでよく使われるバックエンド検証のユニットテストツールPHPUnitでは検証が困難な領域をカバーできます。
Playwrightは実際のブラウザを動かすため、ユーザーがWebサイトを操作するのと近い状況でテストを実行できます。
しかし、ユニットテストと比較すると実行時間が長くなる傾向があります。
テストケース数が増加すると、CI/CDのボトルネックとなり、開発者のテスト実行頻度低下の要因となります。
本セッションでは、Playwrightのテスト実行時間を大幅に短縮するための実践的なテクニックをご紹介します。
PHPからはじめるコンピュータアーキテクチャ
 長谷川智希
長谷川智希 現代のコンピュータはハードウェアから私たちプログラマが書くプログラムの動作までの間が多くのレイヤーに分けられて動作しています。
レイヤーは自分より下を抽象化し、下のレイヤーを詳しく理解しなくても多くの場合プログラマはプログラムを書けます。
一方、プログラムが期待した様に動作しない時には下のレイヤーの動作の理解が問題の解決の助けになることもあります。
このトークでは私たちが愛するPHPをスタート地点にして、「VMって何?」「 PHPやJavaとC言語の根本的な違い」など、コンピュータプログラムがどの様に動作するのかを解説します。
コンピュータのレイヤー構造を理解すると、いままでは見えていなかった角度からプログラミングを楽しめるようになります。
このトークを通じて、低レイヤーが好きになったり、いろいろなレイヤーで面白いことをしたりする方が増えることを期待しています!
ありがとう、そしてその先へ
 長谷川智希
長谷川智希 私が初めて参加した技術カンファレンス、それが2015年、第1回PHPカンファレンス福岡でした。
初めて体験した技術カンファレンスはとても刺激的で楽しく、すっかり虜になってしまいました。
当時iOS関連開発にも関わっていた私はiOS関連開発にもこうしたイベントが欲しくなり、無いなら作るとiOSDC Japan を立ち上げました。
あれから10年、私の人生は大きく変わりました。ここ数年はカンファレンスを2つ主催し、各地のPHPカンファレンスへの遠征参加を楽しんでいます。
そのきっかけをくれたPHPカンファレンス福岡への感謝の気持ちを伝えるとともに、PHPカンファレンス福岡が今回いったんの最終回を迎えることでカンファレンスロスになりそうなみなさんに、各地で開催されているPHPカンファレンスの楽しみ方をお伝えします!
弱小エンジニアだった自分がカンファレンスに行って変わった話
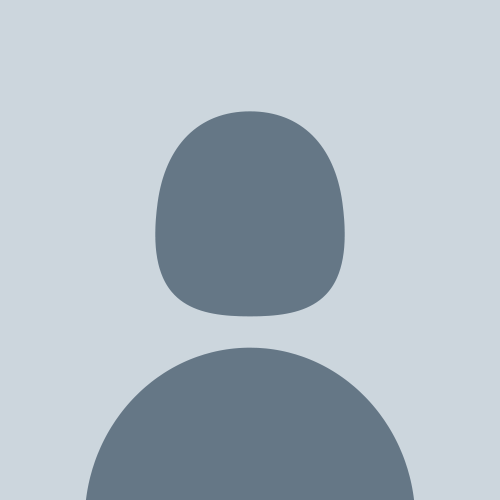 Psyduck
Psyduck 社会人1年目の自分は弱小エンジニアだったので、色々な勉強会に参加して、そこで会った人に誘われてカンファレンスに行ったのが全ての始まりでした。登壇者や他社の取り組みに触れることで、「自分もこうなりたい」と思う反面、一般的な潮流とのギャップを痛感する機会になりました。その後、カンファレンススタッフにも挑戦して、視野が大きく広がりました。結果的に、転職や技術的成長にもつながり、社内イベント登壇などの機会を得るようになりました。本セッションでは、私がどのように技術コミュニティと関わり、そこから得た経験が自分自身にどのような変化をもたらしたかを共有します。まだ経験の浅い方や、エンジニアとしての視野を広げたい方の参考になれば幸いです。
新卒でもできた!Laravel×AIエージェントフレームワーク「LarAgent」
OJTプロジェクトでOpenAI APIをcurlで呼び出していたのですが、プロンプトやAPIクライアントの管理が煩雑になりました。
そんな時社内にてAWS Strands Agentsの話を聞き、LaravelにもAIを効率的に実装する方法があるはずだと調査したところ、LarAgentというフレームワークを見つけました。
LarAgentを使うことで、AIエージェントの定義と呼び出し部分を簡単に分離でき、実装ロジックが単純になりました。
また、artisanコマンドでエージェント生成ができ、#[Tool]属性を活用することで、エージェントのFunction Tools定義が簡単になり、従来のJSONによるAPI呼び出しから解放され、認知負荷を大幅削減できました。
LarAgentを使うことで、新卒の私でも簡単にAIエージェントをつくことができました!その体験を皆さんに共有します!
AIを活用する事で バックエンドエンジニアが フロントエンドの領域に挑戦できた話
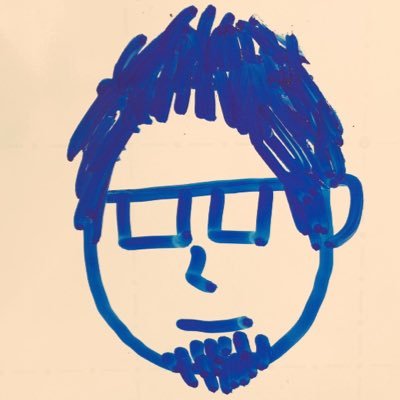 Endo Futoshi
Endo Futoshi 生成AIの登場で、エンジニアの学び方と働き方は大きく変わりました。
私は普段バックエンドを担当していますが、とあるプロジェクトでフロントエンド領域への挑戦が必要になりました
最初は「何がわからないのかすらわからない」状態でしたが、PRレビュー補助やコード理解のガイドとして生成AIを活用することで、実装と学習のサイクルを加速させられました。
その結果、当初目標の倍以上のフロントエンドに関わる改善を出せるまでに成長ができました。
この発表では実際に、バックエンドエンジニアが生成AIを活用して、フロントエンド領域へ挑戦した実体験を発表します。
俺たちの「経験主義」は間違っている - 経験から学びを得る本当の意義
 プログラミングをするパンダ
プログラミングをするパンダ 「愚者は経験に学び、賢者は歴史に学ぶ」はドイツ帝国宰相ビスマルクの言葉として有名です。しかし、ソフトウェア界隈では、「とりあえずやってみよう」を標語に経験から学ぶことが奨励されています。 またスクラムもその理念の一つとして、経験主義を掲げています。 経験から学ぶことは本当に悪いことなのでしょうか。
本セッションではネットの記事や書籍、スライドや発表から学ぶことと、自分で経験することから学んだことを区別する考え方を紹介します。 そして経験主義の語源や哲学史上の意義を紹介し、誤解されがちな経験主義の本当の位置づけを見直します。
AI時代におけるドメイン駆動設計入門
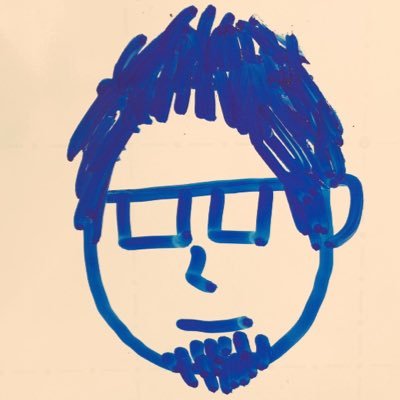 Endo Futoshi
Endo Futoshi ChatGPTやClaude Codeなどの生成AIツールの登場によりコードの自動生成や設計補助を一瞬でこなせるようになり、開発のスピードはかつてないほど上がりました。
しかし、システムの価値を決める設計の心臓部である中核の業務領域のモデリングや設計判断は、いまだ人間の理解と経験が不可欠と考えています。
本セッションでは、『はじめてのドメイン駆動設計』で紹介されている「中核の業務領域」に焦点をあてドメインモデリングを行う方法、それ以外の領域で生成AIを活用する事例を発表します。
- 設計を取り組むべき「中核の業務領域」について
- ドメインモデリングを活かした具体的な実装例
- 「中核の業務領域以外」でAIツールを効果的に使うポイントについて
このセッションを通じて、AI時代でも揺るがない設計の軸と、生成AIを使った開発を上手く共存する方法を持ち帰っていただければ幸いです。
ソフトウェアエンジニアなら知っておきたいシステム思考入門
 プログラミングをするパンダ
プログラミングをするパンダ 我々はソフトウェアエンジニアです。 ソフトウェアは時にシステムと呼ばれます。 しかし、そもそもシステムとは何でしょうか。
このセッションではシステムというものの定義をした上で、問題解決をする際に世界をその構造と振る舞いに着目してモデル化するシステム思考の考え方を紹介します。
システム思考は組織改善にも役立ちます。溜まってしまったエラーをどう解消していくのか、なぜフィードバックが重要なのか、部分ではなく全体に着目するためにはどうすればいいか。 システム思考を身に付けると自然と解決策が見えてきます。
キーワード
・システムの構成要素: ストックとインフロー・アウトフロー
・フィードバックの種類: 自己強化型フィードバック、バランス型フィードバック
元祖オブジェクト指向言語のSmalltalkを触り、オブジェクト指向とMVCを完全に理解する
 プログラミングをするパンダ
プログラミングをするパンダ アラン・ケイ博士が考案した最初のオブジェクト指向言語Smalltalkは、トリグヴェ・リーンスカウク氏が論文でMVCを提唱するきっかけとなり、あのKent BeckもTDDやXPの考案者として有名になる前はSmalltalkの開発者、SUnitの作者として名を馳せました。
Smalltalkを学んでみたいと思っても、学習環境はあまり整っていないように思います。 しかし我々の手元にはAIがあります。 私はAIの力を借りて、Smalltalk を(少し)学んだ結果、オブジェクト指向とWebのなかった時代のMVCの真髄に触れた気がしました。
このセッションでは、Smalltalkを通してメッセージ指向のオブジェクト言語、またMVCフレームワークではない真のMVCとは何かを紹介することで、現代に生きる我々が過去を学び、日々の開発に対して新しく視野が開かれていくという温故知新を目指します。
決済システムの信頼性を支える技術と運用の実践
 かがの
かがの 決済システムを長年運用してきた経験から得たTipsを語ります。
最大で1日約300億円の決済があるシステムを運用していました。
その決済負荷に対してどのような対応をしてきたかをお話しします。
ECのトレンドとして、以前はアリババのように1日単位でGMVを最大化していましたが、最近はユーザーの購買行動を分散させるために数日続けるキャンペーンが増えてきています。
システムを安定化させるためにはこのようにビジネス側の設計も必要になると思います。
現場で実際に効果があった施策を中心に以下についてお伝えします。
・データベース設計
・負荷テスト
・バッチ設計
教科書では学べない現場のTipsを決済・金融系のエンジニア向けにお届けします。
20代エンジニアが実践する「どうせ無理」に抗う方法
 Yuya
Yuya 何かを志そうと思った時
「どうせ無理」
「そんなのできる訳がない」
と言われたり
「私にはどうせ無理か…」
と諦めてしまったりすることがあるかと思います。
システムエンジニアとして働く中でそんな”どうせ無理”に抗い、今では好きなことを仕事にすることができています。
どう抗い、どう好きなことを仕事にしてきたのかをご紹介します。
誰かが少しでも自分らしく生きるためのヒントになれば幸いです。
PHPで"本気"でWebAssemblyを動かす方法
 近藤うちお
近藤うちお WebAssembly(Wasm)はブラウザ上で動かすだけでなく、複数の言語環境で動くユニバーサルバイナリとしても流行しつつあります。
もちろんPHPの中でもWasmを動かしたいところですが、PHPでWasmを動かすことはまだ敷居が高いようです。Wasmを動かす場合、基本的にはC製のWasmランタイムをPHP拡張としてネイティブコンパイルする必要があり、動かそうとして失敗した報告も多いです。
果たして、一体どうすればもっと簡単にPHPでWasmを動かせるのか…。
今回、筆者は考えました。自分にはWasmのVM自作経験がある。では、PHPでWasmのVMを自作し、その上で動かしてみるのはどうか?そうすれば、C言語不要でWasmの力を享受できるはず!
ということでこの発表は、PHPでWasmのVM(のPoC)を作り、動かしてみる…その無謀な挑戦の記録です。
PHPにもVMはある!
 近藤うちお
近藤うちお 皆さん、バイナリやバイトコードはお好きですか?
さて、Java、Python、Lua、Ruby他、モダンな言語は言語VMという機構を備えています。さらに、WebAssemblyのような、特定の言語に依存しないVMもあります。
そしてご多分に洩れずPHPにもVMがあります。とはいえ、PHPプログラマが直接VMのバイトコードを書くわけもなく、「OPcacheが使うなんか高速にするやつ」というふんわりした理解の方も多いのではないかと思います。
このトークではPHPのZend VMを通して、VMとはそもそも何か、なぜ必要か、VM実装の基本についてお話しします。以下のトピックの予定です。
・VMに関する基礎知識
・レジスタマシンとスタックマシン
・バイトコードの基本
・言語におけるVMの意義とメリット
・PHPのZend VMに触れてみよう
・Zend VM互換のVMを自作してみた(?)
「10分以内に機能を消せる状態」の実現のためにやっていること
皆さんのコードは捨てやすい設計になっていますでしょうか?
現在私がリードを勤めているチームでは派生元となったチームの思想を引き継ぎ、「捨てやすい設計」を意識して開発を行なっています
でも捨てやすいって一体どういうことなんでしょうか?
このトークでは実際の開発現場で我々が日々取り組んでいることをお話しするとともに、
失敗したことによって再認識した「捨てやすさ」について実例やコード例を元に紹介します
このトークを聞いて「10分以内に機能を消せる状態」を一緒に目指していきましょう!
PHP-Parserでコードの整頓を加速させる
みなさんはnikic/PHP-Parserをご存知でしょうか?
様々なライブラリの裏側で使われているPHP-Parserですが、実は皆さんにとっても身近な存在かもしれません
このトークではPHP-ParserやASTの概要について軽くお話しするとともに、
PHP-Parserを利用してASTの差分を取り、同じプログラムであることを保証することで軽微なリファクタリングを気軽に行う方法を紹介します
「レガシーな環境だし、テストもないからLinterをかけたいけどかけられない」
そんなお悩みを持っている方の一助になれば幸いです
存在論的プログラミング
 郡山昭仁
郡山昭仁 ソフトウェア工学の70年の歴史において、我々は三つの主要なパラダイムを経験してきました。命令型(How)は実行の手順を、オブジェクト指向(Who)は実行の主体を、関数型(What)は計算の内容を問いました。本講演では、第四のパラダイムとして「存在論的プログラミング(Whether)」を提唱します。それは「存在するか否か」を問う、プログラミングの本質的な変革です。
時間と存在は分割できない – 存在論的プログラミングは「時間と存在の不可分性」を基礎とします。OOPが永遠の現在に囚われ真の自律性が保てなかった一方、このパラダイムにおいてはオブジェクトは時間の中で変態(メタモルフォーシス)し、その各瞬間において完全な自立存在として現れます。
70年間、我々は「より良い命令」を追求してきました。しかし、複雑性の増大、AIとの共生という時代の要請が、新しいパラダイムを必要としています。


 おぎ
おぎ