初心者へ!コミュニティ参加のすゝめ
 須藤真由
須藤真由 学生としてJavaDo、JJUG CCC、PyLadies、Agile Japanなど、さまざまなIT系コミュニティに参加してきました。その中で強く感じたのは「初心者こそ、実は一番コミュニティに飛び込みやすい!」ということ。参加するだけでも得られるものはたくさんありますし、登壇やスタッフなど一歩踏み出すことで楽しさも大きく広がります。この発表では、初心者の私がなぜコミュニティに参加してきたのか、そしてどう楽しんできたのかを、実体験をもとにお話しします。
安全な開発を目指して、ESLint & TypeScriptで自作ルールをつくろう
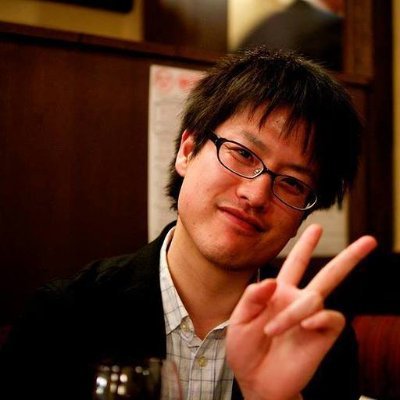 榊原昌彦
榊原昌彦 vibeコーディングに規律を、チーム開発に共通ルールを。ESLintとTypeScriptを使って、自分たちの開発スタイルに合った静的解析ルールを実装する方法を学びます。ASTの基本から型情報を使った制約の書き方、既存ルールの拡張、自作ルールの配布方法まで、実践を通して体系的に理解。プロジェクトの基盤づくりに向き合いながら、「こう書いてほしい」をコードで伝える力を身につけましょう。
生成AIに都度ルールを説明して、それでもルールが守られていない。チームに新しい人が入ってくる度にレビューコストがかかる、そういった非効率なタスクをなくしましょう!
ワークショップでは、 rdlabo/typescript-template-eslint-plugin を使って、ルールとテストの開発を行います。
AI大活用時代を生きのこる半歩ずらしのリーン開発の取り組み方
 照沼 頌
照沼 頌 リーン開発は2008年頃から注目され、高い失敗率に悩むスタートアップ界に科学的アプローチによる解決策を提示し、現在でも非常に有効な手法です。しかし、AI普及によりプロダクトへ求める需要が変化し、開発スピードへの期待が急激に高まる中、この優れた基盤にプラス要素を加えた「半歩ずらし」のアプローチが求められています。
本セッションでは、リーン開発の本質的価値である「無駄の排除」と「科学的な仮説検証」を活かしつつ、AI時代にフィットする実践法を紹介します。大企業やスタートアップが基本的なAIサービスを日々提供する中で、PMFを確認するために何をプロダクトで作るべきか、作らないべきか。変化に対応するためにプロダクトをどう構築すべきか。
優れた従来手法をベースとした進化版リーン開発戦略を一緒に考えてみませんか。
遠距離家族の2か月を支えた、自作のステータス通知デバイスとその結果
 鈴木孝宏
鈴木孝宏 10年ぶりに北海道へUターンした私。しかし、Uターン直後に待っていたのは、2か月にわたる家族との別居生活でした。
この発表では、そんな状況の中、家族と私をつなぎ続けた自作のステータス通知デバイスについて紹介し、2か月間の運用結果を報告します。
具体的には、
・ESP-WROOM-02は現役? 2か月連続稼働で問題は?
・あらかじめ用意していたOTAアップデート、実際に活用できたのか?
・想定とは異なる、思いがけない使い方になった機能
といったトピックを中心にお話しします。
小さな自作デバイスでも、遠く離れた家族の安心や日常を支えることができる。
そんな可能性を感じた体験を、共有できればと思っています。
「マジで何もわからん」な言語をAI Agentと歩く —— 僕らはどうプログラミング言語を学べばいいのだろうか? ——
 Yourein
Yourein 「〇〇をあの言語でチャチャっと作ってよ!」、そう短くないプログラマ人生、誰しも一度はそう言われたことがあるのではないでしょうか?私たちはそうして幾度も見ず知らずの言語に立ち向かってきました。時は流れ、2025年。生成AIやその技術を利用したコーディング支援ソフトウェアの台頭によりプログラマの知識習得のステップは様変わりしたように見えます。このトークでは偶然にも「マジで何もわからん」言語での開発機会を得た私の経験やAIについて一般に言われているプラクティス、そして、我々がずっともっと初学者だった頃の思い出から、初学者から入門者までのステップアップをメインの部分として、令和最新版の知の高速道路を駆け抜ける方法について考えます。
"GoogleAIEdge"によるオンデバイスAIの今
 Atria
Atria 昨今AI技術が生活に浸透し、Webやスマートフォンなどのアプリに組み込まれているケースが散見されます。
現状クラウド上のAIが強力でよく利用されますが、リソース管理問題やセキュリティ上の課題があります。オンデバイスで動作するAIであれば、これらの課題は回避できます。
このセッションでは、Android、iOS、ウェブ、組み込みデバイスなど、クロスプラットフォームに対応したオンデバイスAI技術であるGoogleAIEdgeをユースケースとともに解説します。
セッション内では、今年5月にGoogleが発表した小規模モデルGemma 3nの動作デモをAndroidデバイス上で行います。
こんな方におすすめ
- GoogleのオンデバイスAI周辺の取り組みを知りたい方
- オンデバイスでAIを動かしたい方
- クラウド上のAIモデルを使いまくった結果、従量課金で痛い目を見たことがある方
インフラ初心者がつくってみた Ansible × Packer × Pythonで始めるAMI自動化入門
 satak
satak 本セッションでは、私自身がインフラ初心者としてゼロから学び、Ansible・Packer・Pythonを組み合わせて、EC2用のAMI(サーバーイメージ)を自動で作れる仕組みを構築した体験を紹介します。難しいことはしていません。1つのリポジトリでコードを管理し、開発・ステージングなど環境ごとに切り替えてAMIをビルドしたり、エラーもログで追えるようにデバッグしやすいような工夫もしてみました。
インフラは難しそう・・・と感じていた私でも手を動かしながら少しずつ仕組みを理解し、自動化までたどり着けました。
この発表では、その試行錯誤のプロセスごとお話しします。今まさに同じことで悩んでいる人に、「こんなやり方もあるんだ」と感じてもらえるきっかけになればと思います。
部活で使えるツールが増えてきた? のでSSO(シングルサインオン)を実装してみた話
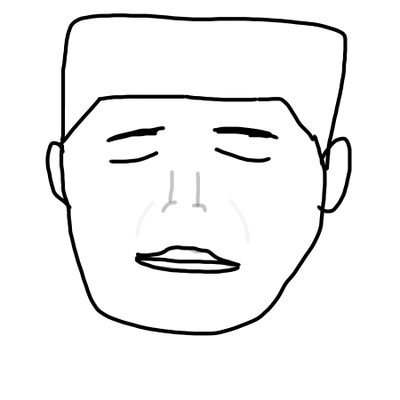 しのひろ
しのひろ 部室の鍵が空いているか確認できる「syorikey」システムを更新するにあたり、これまでの“basic認証”というレトロ感あふれる方法に別れを告げ、ちゃんとした認証を導入しようと決意。
そもそもVPN、クラウドサーバ、Wi-Fiなど部内には認証が必要なサービスが多く、「これもうSSO(シングルサインオン)しかないじゃん?」という声がずっとありました。
そこでついに、学祭準備しながら、バイトしながら、研究もしつつ、部活で後輩にネットワークとサーバ構築を教えつつ、なぜか睡眠不足になりながら、意地で実装してみたという話を、サクッと軽めにお届けします。
MDN Web Docs に日本語翻訳でコントリビュート
 うーたん
うーたん Webアプリ開発者なら一度はお世話になった「MDN Web Docs」の日本語訳ドキュメントにコントリビュート(貢献)する方法を体験できます。
Node.js と Git 環境さえあれば、誰でも今日から翻訳に参加可能です。翻訳ガイドに沿って実際に翻訳・プルリクエストを作成することで、「自分が翻訳したドキュメントが MDN に反映される」体験をしていただきます。
想定対象者
- 技術ドキュメントの翻訳に興味のある方
- 初めてドキュメント翻訳にコントリビュートしたい方
- Git/GitHub の基本操作(pull, commit, push)を知っている方
- Node.js の実行環境とGitの環境が整ったPCをお持ちの方
ぜひこの機会に、普段使っているMDNドキュメントの翻訳に実際に手を動かして参加してみませんか?
ブラウザ上でコード実行!Python×Dockerで作るオンライン実行環境の裏側
 うーたん
うーたん 「コードをブラウザに入力して、すぐに実行結果が見られる」 そんなプログラミング学習サイトのような仕組み、自分で作れたら面白そうだと思いませんか?
本セッションでは、PythonとDocker(Docker outside of Docker)を活用して、複数の言語をブラウザから実行できるアプリを自作について、デモを交えながら紹介します。
この内容は、月刊I/O 2024年3月号・4月号にも掲載されました。
こんな方におすすめ
- PythonからDockerコンテナを扱う方法に興味がある方
- Docker outside of Docker の実践例を知りたい方
プログラミング学習サイトのような仕組みを自作してみたい方、仕組みに興味のある方はぜひご参加ください。
アイデア次第で、あなたのプロジェクトにも応用できるかもしれません。
毎月のように社会課題解決の素振りをする者達 ~「ヒューリスティック」な競技プログラミングへの招待~
 allegrogiken
allegrogiken 競技プログラミングの中でも「ヒューリスティック」「マラソン」などと呼ばれるジャンルがあることをご存じでしょうか!
競技プログラミングといえば、アルゴリズムを使ってなるべく多くの問題を早く解く・・・ という形式のものが広く認知されていると思いますが、
「ヒューリスティック」では1つの複雑なお題に対して「正解」ではなく「なるべく良い解」を出力できるプログラムを作って競い合います。
例えば「膨大な都市での配送計画」「逃げる動物を柵で囲うパズル」「プロジェクトマネジメント」といったようなお題に取り組みます。
真面目に取り組むほど「これって労働では・・・?」という気持ちになるのですが、 ISUCON のような楽しさがあると感じています。
このジャンルがもっと流行って欲しい、そんな願いを込めてヒューリスティック沼に浸ってしまったプレイヤーからのご招待をお届けします。
スマホでPCを支配しよう
 こた
こた 「キーボードとマウスが突然壊れてしまった!」や、「steamdeckで快適なショートカットがしたいがお金が...」などといったお悩み、誰しも一度は抱いたことがあると思います。
本セッションでは、そんな時に手元のモバイル端末をキーボード、マウス化させてしまうアプリケーションの開発で得た知見をお話します。
主にこのようなことをお話します。
・何故このプロダクトが必要だったのか
・最初のアプローチの結果と欠点
・Bluetoothを使用したアプローチの結果と仕組み
対象聴講者
・モバイル(特にAndroid)アプリ開発に興味がある方
・Bluetoothキーボード、マウスの仕組みに興味がある方
プログラムを1行、いや1文字も書けない僕がITコミュニティーを運営したらどうなるか?
 Hazime
Hazime 北海道のへその街 富良野で活動するFuraIT(ふらいと)。
2014年に設立されてから10年が経過。
途中からこのコミュ二ティーを引き継いだのはいいけど、どうしたものか。
ただ継続することを自身の目標に掲げていたら今は何が起きているのか。
そんな話をします。
今日はラッキーなのか、どうなのか?!毎日違う旭川〜美瑛〜富良野の風景
 Hazime
Hazime TechRAMEN 2025 Conference の写真撮影担当が趣味で撮影した風景写真をただただ流す時間。
ちょっとした息抜きに。
写真を見るとまた違う時期に来てみたくなるはず!
四季を通して美しいこのエリアのファンになって欲しい!
そんなLTもアリですか?
ウェブセキュリティ脆弱性体験~CSRF、XSS、セッションハイジャックについて学ぼう
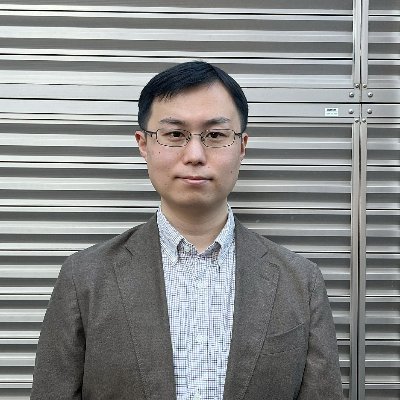 tokibito
tokibito あらかじめ用意しておいた、脆弱性(ぜいじゃくせい)のあるウェブアプリケーションを題材として、CSRF、XSS、セッションハイジャックといった攻撃を実際に試し、体験します。
Chromeのdevtoolを使ってCookieの内容を編集したり、テキストエディタで作成したHTMLから情報を送信したりします。
想定する参加者は次の通りです:
- HTMLを自分で記述したことがある
- 自分で記述したJavaScriptのコードを動かしたことがある
参加する場合は以下を準備してください。
- 無線LANにてインターネット接続が可能なWindowsまたはmacOSのPC
- Google Chromeをインストール
- テキストエディタをインストール(Visual Studio Codeを推奨します)
予想外のデータを正式なコンテンツとして処理するためのデータ構造を考えたい
作業メモからスライド資料を生成し、登壇中に話の順番や内容を考えられるプレゼンテーションツール「LTooL」を開発・運用しています。現在の課題はデザイン性で、独自のパーサーで作業メモからスライド形式に変換する仕組みが、スライドのデザイン性に私自身のデザイン力という依存を生んでいます。生成AIを利用すれば、自分の力では到底作れないデザイン性の高いスライド資料を一瞬で作ることができます。LTooLの良さはスライド資料の質ではありませんが、LTooLから自分の予想を超えたコンテンツが作られるという理想にとても魅力を感じて、現在は生成AIを活用した仕組みの開発を進めています。そこで「どのようなデータ構造で管理すれば予想外のコンテンツに対応可能なアプリケーションが作れるか」という壁にぶち当たり苦戦しています。TechRAMENまでにどこまで進められるかわかりませんが、苦戦の行く末を話せたらと思います。
自作PC!やろうぜ!
IoT機器は多様化し、「PCを購入する」というのが一般的な今、なぜ自作PC推しなのか。
自らの経験だけをたよりに、自作PCの本質に迫り、その魅力を伝えたい!
ブログを作りたいなら Astro
 みやもとなおゆき
みやもとなおゆき Astro.build というwebフレームワークの推しポイントを語ります。
学習コストが低い、デプロイ関係の公式ドキュメントの充実、軽量、そしてOSSである。
これほどに語りたくなるwebフレームワークはあるでしょうか?
聞き終わるころには 「npm create astro@latest」と入力せずにはいられなくなるでしょう。
ブログを書こう~アウトプットのススメ
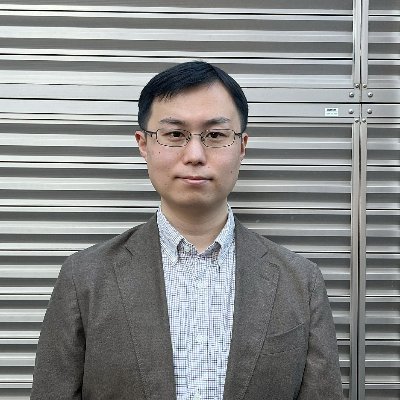 tokibito
tokibito みなさんはアウトプットをどのようにしていますか?
XのようなSNSだと書いたことが流れていってしまいますが、ブログならちゃんと残せて振り返りにも便利です。
自分のポートフォリオにもなるし、文章を書く練習にもなります。
誰かに質問されたときも、自分の言葉で書いた記事があればスムーズに共有できます。
アウトプットの手段としてブログに書くことの良さを紹介します。
AndroidとiOSのライフサイクル、図解でサクッと理解
 Haru
Haru 「あれ、これっていつ呼ばれてるんだっけ?」
最近のプロジェクトで、AndroidとiOSの両方を担当することになりました。
最初につまずいたのは、画面ライフサイクルの呼び方や流れの違いでした。
このLTでは、AndroidのActivity / Fragmentと、iOSのUIViewControllerのライフサイクルを図で整理し、それぞれの流れをサクッとつかむことを目指します。
「ライフサイクル、なんとなく全体像がつかめた!」と思ってもらえたら嬉しいです。
私と同じような初心者や、ネイティブアプリを触り始めたばかりの方にとって、少しでもヒントになればと思います。
想定視聴者
・AndroidまたはiOSのどちらかしか触ったことがない人
・これから両方触る予定の人
・ライフサイクルを「?」と思っていた人

