ChatGPTは小説を書けない
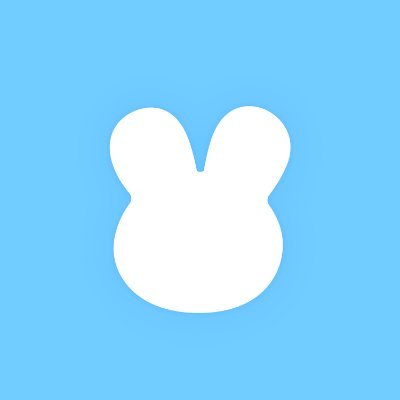 匿名希望Y
匿名希望Y 「ChatGPTに小説を書かせてみたけど、思ったより浅かった」──そんな経験はありませんか?
このLTでは、ChatGPTがどこまで物語を創作できるのかについて、実体験に基づいた分析を通して、生成AIの限界と可能性を探ります。
・なぜChatGPTはドラマ性やどんでん返しを自然に生成しないか
・ChatGPT、AIのべりすと、NovelAIの比較
・エラーの傾向(不自然な行動、キャラ崩壊、規約違反)とその対策
静的解析で始める高速ピンボール
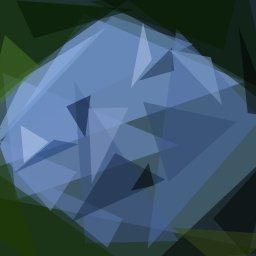 aereal
aereal 近年、静的解析ツールは単なる「チェックツール」を超え、開発体験そのものを変える存在になりました。ESLintやRubocopを使ったことがある方なら、その可能性の広がりを実感できるはず。
本トークでは、自作した静的解析ルールがワークフローをどう変えたかを実例で紹介します。
「typoや瑣末なコーディングスタイルの指摘ばかりのレビュー」から「設計議論中心のレビュー」への転換、リファクタリング作業の大幅な効率化、そしてガードレールを整備して高速にVibe Codingする様はさながらピンボールのようです。
静的解析のおもしろさを改めて知るきっかけになるはずです。
「広く浅く」はダメですか?生成AI時代のマルチポテンシャライトの可能性
 hkws
hkws 「まずは一つの専門性を」。そんな正論を聞くたびに、少し悲しくなりませんか?興味の対象が広く、専門を一つに定められない。そんな私は輝かしいキャリアは歩めないだろうと考えていました。
しかし2025年の今は、そんな広い興味を持つ「マルチポテンシャライト」が輝けるのかもしれません。その理由となった実体験を紹介します。
- 興味の追求:仏教学から着想を得た「大量殺人計画者の説得」という思考実験―o3が私の思考の限界を引き上げてくれた話。
- 空想の実現:突然の起業、知見がほぼない技術スタック、使えるのは本業のスキマ時間という制約下でも、AIの助けで知識を増幅し、プロダクトを作れた話。
「一点に集中しないと」と焦るあなたが持つ広範な興味が、AIにより深化、具現化されることで、強力な武器になります。
正論から外れたキャリアだけど、それでもいいのかもしれない。そう思っていただける15分にします。
AR グラス + ミニ PC で実現する新しいモバイル環境
 gara
gara 昨年の大吉祥寺.pmで愛用の Linux ラップトップ PC について LT しましたが、ついにその PC も壊れてしまいました。
買い替えのタイミングで、私は大胆な挑戦をしてみることにしたのです。
2025 年の今だからこそ現実的になった AR グラス + ミニ PC という組み合わせで、従来のラップトップに代わるモバイル環境を構築しました。
本 LT では、物理ディスプレイを手放して AR グラスに移行する際に考えたことと、新しいモバイル環境の体験について共有します。
Outline
- ラップトップに感じていたつらさ
- 使用している AR グラスとミニ PC
- 現時点での感想
Learning Outcome
- AR グラスを使いたくなる。
- AR グラス + ミニ PC という構成の可能性を感じてもらう。
不確実性を力に変える:スタートアップで本質を掴み自走成長する仮説行動
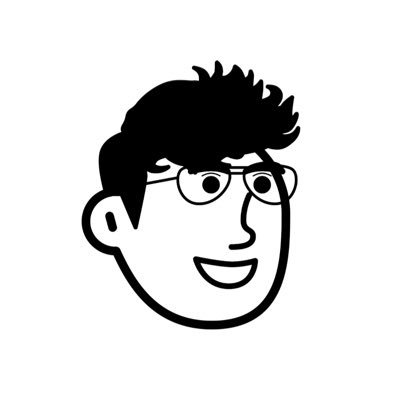 ohageeq | チバシゲル
ohageeq | チバシゲル 資金も人手も限られ、正解のないスタートアップでは、課題抽出と高速な学習ループが生命線です。
本トークでは、会社立ち上げから組織拡大フェーズまで様々なスタートアップフェーズの経験で、実践してきた仮説行動のサイクルを軸に
- “やらないこと”を削ぎ落として真の顧客価値を見抜く方法
- 役割を越えて課題に飛び込む越境行動を実践する方法
- 他者を巻き込み学習ループを定着させる仕組み化の方法
について、過去の自分の経験談をもとに発表します。
カオスを恐れず自走し、成長エンジンに変換する方法を共有します。
生成AI時代に、あえて「本を書くこと」の価値
 佐藤智樹
佐藤智樹 生成AIによって、膨大な情報の中から必要な情報にアクセスすることは非常に簡単になりました。
私自身も、OSSのコードリーディングには Deep Wiki/Search を、ドキュメントの理解には NotebookLM を多用しています。
そんな時代に、「本を書くこと」にはどんな価値があるのでしょうか?
私自身、技術書典という技術同人誌の販売イベントに参加し、疑問を抱きながら執筆を進めました。そして販売を終えた今、「本を書くこと」には、自分の内面に生まれる価値、情報を整理して伝える価値、読者との間に生まれる価値などが存在すると感じています。
本セッションでは、そんな「本を書くことの価値」について、筆者としての視点からお話しします。
セッションを通じて、「自分の体験も形にしてみようかな」と思ってもらえたら嬉しいです!
新規プロダクト開発における開発手法の変遷を、良し悪しとともに振り返る
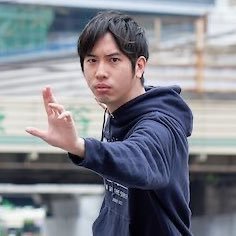 りばすと
りばすと 私はEM2年生。 2024年4月に新規プロダクトをリリースし、現在はそのプロダクトをなんとか成長させていくべく邁進しています。
新規プロダクトのリリース、そしてその後の成長にあたってはさまざまな進行上の課題がチームに襲い掛かりました。
・ スクラムを解釈した開発イベントがなぜかうまくいかない
・ 社内や社外からのプロダクトへのフィードバックが集まらない
・ プロダクトマネージャーとタスクの温度感がすり合わない
・ プロダクトの課題が無限に積まれ、さばいてもさばいてもなくならない
......
これらの課題が発生した背景には、新規プロダクト開発においてはフェーズごとに求められる立ち回りが大きく変化するというものがありました。
本セッションでは、そのような状況に対応するため繰り返し見直し、変更・改善してきた開発手法の変遷について、良かった点と反省点の両軸から振り返ります。
習慣は第二の天性なり 〜エブリディ ブログを書いて 1000日超え〜
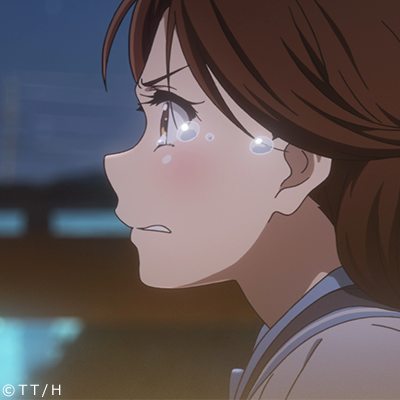 nikkie
nikkie 私は毎日1記事ブログ執筆という"奇行"を続けているのですが、2025年は連続1000日を踏破する年です!(6/21時点で948日)
技術ネタもアニメネタも、体調がすぐれない日も、ストックなしで業務後に勉強会参加という日も、もはや"狂気"といえるくらい、もがいて繋げてきました。
ここまで継続して得たものはいくつもあるのですが、今回は「習慣化」についての学びを共有します。
この発表を聞いても毎日ブログを書けるようにはなりませんが、聞いた方に毎週・毎月何かを継続するヒントがあったら嬉しいです。
モチベーション
- 過去の自分のため
- Today I learned
- 将来のLLMをかしこくするため
- 流入やホッテントリは狙わない
テクニック
- 1日の写真に撮るように
- 小さいは正義(移り気な私対策)
- 生成AIの利用(Copilotによるサジェスト、ネタの提供、検索代行)
プレイングマネージャー挑戦のススメ
 Yohei Kajiro
Yohei Kajiro マネジメントに興味はあるけど、「完璧にできるか分からない」と二の足を踏んでいませんか?
「開発以外の部分でも組織に貢献したい」
そんな思いからプレイングマネージャーを始めて1年が経ちました。2025年の今、振り返ってみると想像以上に大変でした。
最初の頃は時間の使い方が下手で、マネジメントでは無力感を感じ、プレイヤーとしても中途半端。「何をやっているんだろう」と思った日々もありました。
でも、試行錯誤を重ねるうちに、自分なりの貢献方法が見えてきました。この試行錯誤の1年間で得た経験は、確実に無駄ではなかったと感じています。
「マネジメントに興味はあるけど、一歩踏み出せない」という方に向けて、「私もまだ迷っていますが、挑戦してみて良かったです」という体験談をお届けします。
IaC x VibeCoding AIファーストな開発スタイルの可能性
 かいもの
かいもの 本セッションでは、Terraformを中心としたIaC環境でAIを最大限活用するための実践的な戦略と、IaCxAIで実現できる新しい可能性について解説します。
話すこと
- AIドリブンなIaCの開発について
- AIファーストなTerraform開発環境/運用方法の提案
- AI x IaCが非エンジニアとSREの架け橋になる可能性
IaCとAIは非常に相性がよく、運用の難しいインフラIaC基盤の生産性を高められると感じており
うまく使うことで安全に、リポジトリの治安を守りつつ、AIが暴れられる環境をつくり、スケールさせる方法を提案します。
コード・サンガ 機械共生記
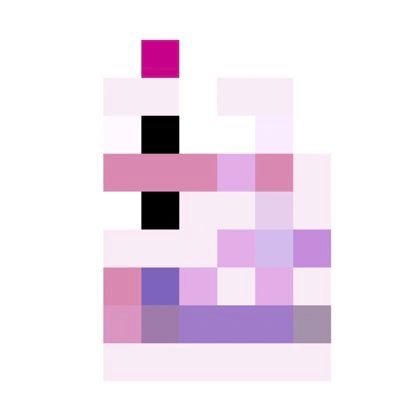 nwiizo
nwiizo かつてソフトウェアは決定論的な機械だった。しかし今、LLMを基盤とする存在が「行為者性(agency)」を獲得し、確率的で予測不可能な振る舞いを見せ始めている。これは単なる技術革新ではない。デジタル世界における新たな「種」の誕生である。
環境を認識し、意思決定し、行動する。失敗から学び、経験を蓄積し、自らを改善する。私たちは今、AIエージェントという未知なる存在と出会い、共に進化する岐路に立っている。
本セッションでは、エージェントシステム設計の実践知を共有する。MVA(最小実行可能エージェント)から始め、モジュラリティによる複雑性の管理、マルチエージェントが織りなす創発、人間との協調がもたらす新たな可能性を探求する。
透明性と自律性、効率と倫理、管理と創造性。これらの二項対立を超えて、人間とAIが共生する未来への設計思想を提示する。エージェントは道具を超えた存在へと進化しつつある。
夏だ!祭りだ!浴衣で歩こう!!~浴衣の歩き方のコツ~
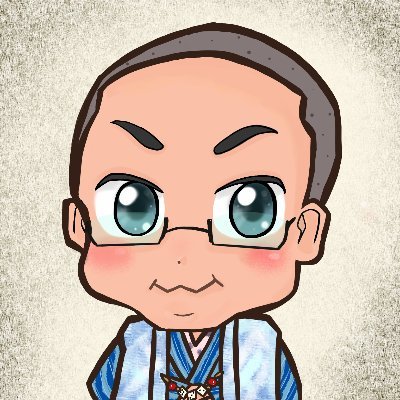 白栁隆司
白栁隆司 大吉祥寺.pmの開催は9月6日です。言うまでもなく、まだ夏ですよね。
今年も夏祭りや花火大会に浴衣で出かけた方も多いことでしょう。
ですが、浴衣で歩く歩きにくかったり、気崩れしたりしませんか?
実は、洋服のときと浴衣のときでは、適した歩き方が違うんです。
サンダル、靴、下駄(草履)の3種類、男女に分けて浴衣での歩き方のコツを、普段着が着物な白栁が紹介します。
キレイに見えて楽に歩ける、そんな歩き方を身に着けて、残りの夏を浴衣で祭りを楽しみませんか?
そして、次の夏への準備もぜひ……。
モザイク型ロールモデルによるキャリアデザイン~【ロールモデル】は必要か?~
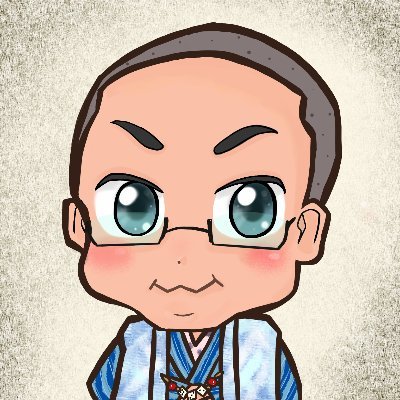 白栁隆司
白栁隆司 「ロールモデル」とは、自分のキャリアを考えるときに参考にする他者の生き方や働き方のことです。
かつては身近な上司や家族をモデルとするのが当然でしたが、昨今は働き方が多様化し、単一の人物を目指すことが難しくなってきています。
特に、IT業界ではここ10年でこれまでの10年になかった新しい職種も増えました。
このトークでは、複数の人物の良い要素を組み合わせ、自分だけの理想像をつくる「モザイク型ロールモデル」という考え方を紹介します。
エンジニアカウンセラーとして先例のない道を歩んでいる白栁が、自身のキャリアを例に、ロールモデルの活かし方と新しい設計法をお話しします。
──「あなたは誰かではない」
──「単一継承は、多くのオブジェクト指向言語では禁止されていますが、キャリアであれば大いにしていい!!」
怠惰で持続可能な、自由なタスク管理 - TaskMD Shelfの実践
 Songmu
Songmu TaskMD Shelfは「積極的棚上げ」によって、怠惰なハッカーでも持続可能なタスク管理を実現する、とてもシンプルな手法です。
今やらないことを明示的に棚上げし、集中すべきことに専念します。その際、「見直し日」を必ず設定することで、後からの見落としを防ぎます。
これらをタスクを全て意味付けられたMarkdownで管理するため自由に柔軟に管理できます。例えば、「見直し日」が来たタスクや、今やるべきタスクを簡単に一覧できるのです。
本トークでは、何故新たにタスク管理を考えたのか、既存のタスク管理手法の思想を振り返り、それらの手法で困ることをTaskMD Shelfでどのように解決したのかを紹介します。
また、テキストデータを使う「自由な」タスク管理の哲学や利点についても触れます。AIに秘書的なサポートを受けるやりかたや、具体的なタスク管理の手法や自動化についてもお話します。
RDRAを使ったドメイン駆動設計における集約の取り扱い方とコンウェイ
 工藤ユミ
工藤ユミ ドメイン駆動設計文脈における集約の考え方は、私自身アーキテクトとして案件に入っている中でも長いこと上手く言語化できないものでした。
そんな中、RDRAという要件定義フレームワークを実際に使って運用してみる中で、
「こう考えたら、集約の範囲の決定やユースケースとの関係を把握しやすくなる!」と根拠をもって確信したものを発表したいと思います。
この考え方を基本にすることによって、たとえ分散アーキテクチャになったとしても、だいぶ運用しやすくなります。
さらに上記の集約の考え方は、チームの責任範囲の設計とも密接に関わりを持ちます。
コチラの内容のメインターゲットは、アーキテクトだけではなく、
チームの分割などを考えるPM・PdMさん、そしてビジネスアーキテクト向けです。
アーキテクト思考
 yonekubo
yonekubo ITアーキテクトとしてシステムアーキテクチャ設計や技術選定、その他諸々の業務を遂行する際、じつに様々な思考方法を駆使しています。
「思考力」を鍛錬してきたからこそ、ここまで生き残ることができたと感じています。
思考力は、アーキテクトに限らず、どんな職種においてもたいへん重要です。
技術力の大部分がAIで代替可能となったとしても、思考力はそう簡単に代替されることはありません。
ITエンジニアとして成長し、活躍するためには、思考力こそが最大のレバレッジポイントだと言えます。
アーキテクトがビッグピクチャーを描き、その実現の過程で利用する思考方法ーー抽象化、メタ思考、アナロジー、推論(演繹・帰納・アブダクション)、etc。
激動の時代を、この先生きのこる武器を手に入れましょう。
わりとなんでもできちゃう Fargate SPOT bastion (with ecsta とか)
 sogaoh
sogaoh 本トークでは、Terragruntとecspressoを利用してIaCで構築したFargate bastion('踏み台')を、
多少の手を加えることでプロダクト運用に役立てようとしている事例を紹介します。
Fargate SPOT採用によるコスト最小化や、ecsta等のツール連携による柔軟なタスク実行、CI/CDとの統合など、
「なんでもできる」bastionを実現するための工夫と、実際に直面した課題を具体的に共有します。
会社と現場の狭間で何が起きているか
 くろきり
くろきり 現在私は受託開発の会社で執行役員として仕事をしています。
会社からは売上や粗利など数字を求められ、数字のための施策に加えて
メンバーが働きやすい環境を作るため日々体制や制度を整えつつ
現場ではプロジェクトマネジメントをしながらも自身もコードをバリバリ書いている日々を過ごしています。
会社としての数字と現場の温度感。
それは必ずしも同じ施策でどちらも解決できるものではありません。
しかしその両方を満たしていかねば会社が回らないのもまた事実。
このトークではどちらにも深く関わるポジションとして
お互いの認識齟齬がなぜ起こるのか、それを解決するためにどうすべきかというものを自身の体験から話していきます。
多動な自分が、人にプログラミングを教えることでエンジニア人生を立て直した話
 taketora
taketora 気づけば、本業ではテックリードを務め、副業では海外の開発メンバーと一緒に開発案件を回すようになっていました。
他にも、不動産会社の立ち上げ、テックカンファレンス(関数型まつり)の主催、そしてランニング(趣味で月200km以上)など、色々な活動やっています。
新卒の頃は、誤字脱字、ケアレスミスが多く、プログラミング言語仕様の意味よくわからないままなんとなく動くコードを書いておりました。
そんな自分を少しずつ変えるきっかけになったのが、2018年に始めた「人にプログラミングを教える」という講師の副業です。
教えることで自分の理解の浅さに気づき、言語化を繰り返すうちにようやく地に足のついた知識が身についていきました。
このトークでは、多動ぎみな自分がどう失敗と向き合いながらキャリアを築いてきたか、率直にお話しします。
同じような失敗をしている方へ、何か伝わると嬉しいです。


 シキム
シキム