2025年のWebフロントエンドのふりかえりと2026年
 sakito
sakito BuriKaigi 2025では「2024年のWebフロントエンドのふりかえりと2025年」について話しました。
https://www.docswell.com/s/sakito/Z82RGP-burikaigi2025
話の中では、2025年のフロントエンドはどうなっていきそうかの推測もしていました。
今回は2024年の推測が当たっていたのか、2025年を振り返りつつ話をします。
そして、2026年のフロントエンドがどうなっていくのかも考察していきます。
複数のローコード、ノーコードサービスを使いこなすためのノウハウ
 りなたむ
りなたむ ローコードやノーコードサービスが台頭して久しい昨今、組織によっては、様々なローコードやノーコードのサービスが統制なく使われているといった現状も存在します。
そんな折、
「どちらがいいのか?」「どちらかに寄せるべきなのか?」
と、聞かれることがよくあります。
ここでは、Microsoft 365 を主軸に活用しつつも、Power Platform と kintone が混在する組織の中で、どういう構成であれば最適な組み合わせとなりうるのか、ロールプレイング的なセッションとして、デモを交えながら解説していきます。
デモの内容
Power Apps with AI Builder x kintone で
極力オペレーションを減らした 在庫管理システム
https://x.com/Rinatamu_ITDR/status/1982679540712505828
など
※本内容は Cybozu Day 2025 で軽くお見せする内容をもっと深堀した内容となっています。
※本内容は業務担当者や開発者、DX推進者など幅広い層に見ていただける内容です。
歴史から学ぶ、Goのメモリ管理基礎
 Takuto Nagami
Takuto Nagami 「本当にメモリ管理は難しすぎてわからなぁぁぁい‼︎」と思っているみなさん!
メモリ管理への理解を深めるために、その発展の歴史を学んでみませんか?
たった一つのメモリ確保処理を見直しただけでCPU使用率を57%、メモリ使用量を99%も削減できた例があるほど、メモリ管理の知識はアプリケーションのパフォーマンス向上に直結します。
しかしメモリ管理に関する教材の多くは、ガベージコレクションの具体的なアルゴリズムやコンパイラ内部のメモリ構造といった複雑な機能が「どのように(How)」動作するのかに焦点を当てており、初学者向けとは言えません。
本来「How」を理解するためには、「なぜ(Why)」その機能が必要とされ、「何を(What)」実現するかの理解が不可欠です。
そうした土台がないまま「How」の議論を追うのは困難でしょう。
ヒープ、スタック、ガベージコレクションのような仕組みは、プログラミング言語におけるデータ管理をわかりやすくするために進化してきたものです。
動機を知ることでこれらの仕組みをより深く理解し、メモリ管理を語れるエンジニアになりましょう!
本セッションでは、特にGo言語のメモリ管理機能を取り上げてその進化の軌跡を紐解きつつ、発展的なメモリ管理の知識を修得するにあたって強固な土台となる知識を提供します。
[対象者]
- メモリ管理という言葉すら知らない方
- メモリ管理について学びたいが、理解に苦しんでいる方
[話すこと]
以下のメモリ管理機能がなぜ必要とされ、何を実現するかについて、それぞれの相関関係を強調しながら話します。
- ヒープ・スタックのメモリ構造
- GC (ガベージコレクション)
- ヒープエスケープ・エスケープ解析 (Go特有)
- スタックコピーによる可変サイズスタック (Go特有)
- メモリ管理の知識がプロダクション環境のパフォーマンスに大きな影響を与えた例とその解説
[話さないこと]
メモリ管理機能の詳細な処理ロジックや実装
[アウトライン]
- はじめに (5分)
- 自己紹介
- メモリ管理はパフォーマンス向上のため非常に重要
- たった1か所のメモリ確保処理の見直しで、CPU使用率が57%、メモリ使用量が99%も削減された事例が存在
- メモリ管理に関するセッションは難しい
- 実装の詳細やロジック (How) に関する技術的な内容が多い
- 処理の抽象的な解釈や、必要性に対する理解 (What, Why) が不足している
- Goの高度なメモリ管理を学ぶには、幅広い機能の基礎知識が必要
- 各機能が「何を」して「なぜ」あるのかを理解することで初めて習得できる
- 「How」の前に「What」と「Why」に焦点を当てるのが、修得の最短ルート
- メモリとは何か / 古のメモリ管理 (2分)
- メモリ=プロセスの一時的なデータ保存領域
- メモリへの直接的なデータ挿入 (アセンブリのデータ管理)
- 変数の誕生 / スタックとヒープ (5分)
- 【課題】人間が全てのメモリアドレスを把握する必要がある
- 高級プログラミング言語の登場
- 変数=データの抽象化
- 人間はアドレスを気にしなくてよくなるが、言語側が代わりにアドレスを管理する必要がある
- スタックの発明
- 関数呼び出しのネスト構造や変数スコープをメモリ空間上でうまく表現できる
- スタックの図解説明
- 【例】Goでの変数定義や関数呼び出し
- 直接的な挿入も可能にする、ヒープとポインタ
- 大きいデータ・サイズ不定のデータ
- 関数をまたいで利用されるデータ
- 【例】C言語のmalloc / free
- ヒープの自動管理 / ガベージコレクション (2分)
- 【課題】ヒープ上の使い終わったデータは人間が削除する必要がある
- メモリリークやOOM Killのリスクが高まる
- ガベージコレクション (GC)
- ヒープ上の未使用データを検出
- 未使用データを自動的に削除
- 【課題】ヒープ上の使い終わったデータは人間が削除する必要がある
- Goのヒープエスケープ (6分)
- 【課題】ヒープに大量のデータを置くとGCの負荷が高くなる
- 【例】構造体や配列をすべてヒープに置く→半分以上の変数がGC対象に
- ヒープエスケープの導入
- できるだけスタックにデータを置く
- 型で判断するのではなく、必要なものだけヒープへ「逃がす」
- エスケープ解析
- ヒープへ逃すか決まるのは、実行時ではなくビルドの段階
- どの変数がエスケープするか見るためのビルドオプションがある
- ゼロアロケーションライブラリ
- 関数内でヒープに置かれるデータを一切出さないパッケージ
- 非常に効率的で、基本的にパフォーマンスが向上する
- 実装はやや複雑で、コードリーディングが難しい
- 【課題】ヒープに大量のデータを置くとGCの負荷が高くなる
- スタックコピーによる、可変サイズスタック (4分)
- 【課題】通常の言語ではスタックには上限が設けられ、スタックオーバーフローが起きる
- あらかじめ大きなスタックを確保しておくか…?
- 【課題】常に大きなスタックを持つと、ヒープが小さくなって不便
- 可変サイズのスタックにより、効率的なメモリ利用を実現
- セグメント化スタック (旧実装)
- スタックコピー (現行の実装)
- はじめに紹介した事例の解説 (4分)
- 参考: https://developers.cyberagent.co.jp/blog/archives/54653/
- フィルタリング関数が呼び出されるたびにヒープ上にスライスを1つ作成
- このヒープに置かれた変数がボトルネックになっていた
- 既存のスライスを利用することで割り当てを無くし、メモリ使用量99%削減
- たった1つのアロケーションがパフォーマンスに大きく影響することを示している
- CPU使用率57%削減
- アロケーションとGCコストの削減の合計
- まとめ (2分)
- 今回のセッションはあくまで出発点
- 他のセッションや資料で、各機能を深堀りしてみよう!
- 次に見るべきおすすめの過去セッション紹介 (時間が余ったら)
- このセッションで得た基礎知識を土台に、次のステップに進もう!
- ヒープエスケープとエスケープ解析: "Escape Analysis in Go: Understanding and Optimizing Memory Allocation" - Go Conference 2023 Online
- GCの条件: "Go1.19から始めるGCのチューニング方法" - Go Conference 2023 Online
- pprofを使ったパフォーマンスチューニング: "Memory Management in Go: The good, the bad and the ugly" - GopherCon UK 2023
- 【発展】ヒープ・スタックの、OSレベルでの割り当て: "Goのメモリ管理" - Go Conference 2023 Online
- 並行処理に対するメモリ設計 (memory model): "よくわかるThe Go Memory Model - 行間を図解で埋め尽くす" - Go Conference 2023 Online
ユーザーが作成したコードをブラウザ上で安全に実行できるPluginシステムへのアプローチ
テーマ
webフロントエンドにおいて、実用的なプラグインシステム(ユーザーの書いたコードを安全に実行する環境)をどのように実現するか
想定する参加者層(前提知識)
- JavaScriptの実行環境自体に興味があるようなフロントエンドの中上級者の方
- CORSやCSPなどのブラウザのセキュリティ機構について最低限の知識がある方
- 「プラグインシステム」や「ユーザーカスタマイズ」といったユーザーの書いたコードを実行する機能を提供するサービスを開発してる・したい方
トーク概要
SaaSなどのWebサービスには画面や挙動をユーザでカスタマイズできる機能を提供するものがあり、Webフロントエンドにおいてはユーザの作成したJavaScriptを実行することでこれらの機能を実現することが多いです。
一方で、ユーザーの作成したコードを無責任に実行することは重大なセキュリティリスクに繋がります。また仮に悪意がないコードだとしても、以下のような問題を容易に発生させます。
- 過大な権限による不可逆な操作を行えてしまう / 逆に権限を制限しすぎるとプラグインで実行したいことができない
- 追加したコードによって製品本体の挙動が不安定になる
- 製品の挙動や構造に強く依存するコードが原因で製品自体のアップデートがしづらくなる
これらの問題を避けるためには、ユーザーの作成したコードを安全に隔離しつつ、細かく権限を設定できる仕組みが必要です。
このセッションでは、「ユーザーが追加したスクリプトを実行する機能」や「プラグイン/カスタマイズ機能」の開発における課題と、その解決策となる関連技術について解説します。より具体的には、実際にtoBのSaaSサービスで「ユーザーの作成したコードを実行する新しいプラグイン機能」を設計・開発した経験をもとに、以下のような内容について話します。
- ユーザーの作成するコードを実行する難しさについて
- セキュリティ上の問題だけでなく、製品の可用性などにも関わる
- 現状考えられる隔離の方式とメリット・デメリット
- iframe / web worker / JSEngine on WASM / Realm Shims
- iframeを選択した理由と注意すべきこと
- オリジンによるリソースアクセス制限やCookieについて
- 機能やアクセス先を制限するための仕組み
- CSPの設定・Channel Messaging APIによる疎通と注意点
- これから期待される関連仕様
- ShadowRealm について
これらの「プラグイン/カスタマイズ機能」開発に携わる方々をサポートするとともに、「JavaScriptを安全に実行する」という観点から、ブラウザのセキュリティ機構やJavaScriptエンジンの仕組みへの理解を深めるきっかけを提供することを目指します。
なぜRustのエラーメッセージはわかりやすいのか?
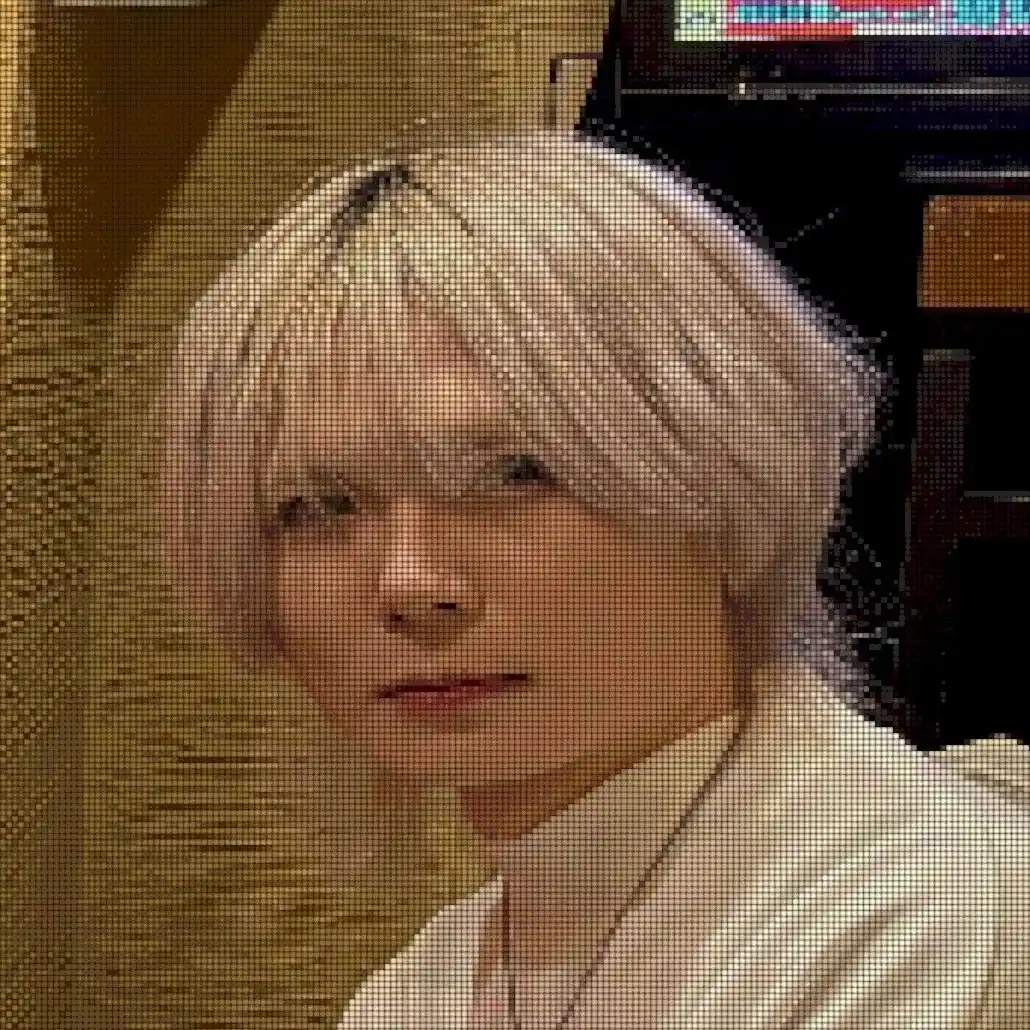 Yuki Okushi
Yuki Okushi 私たちは常日頃からありとあらゆるエラーメッセージと向き合っています。ソフトウェアエンジニアに限った話で言えば、コンパイラや言語処理系のエラーメッセージは最も頻繁に向き合うインターフェースの一つであり、毎日眺め、頭を悩ませていることでしょう。
そういった中で、Rustコンパイラ(rustc)はわかりやすいエラーメッセージ(diagnostics)を出すことに注力しています。そして、そのエラーメッセージは一つひとつが丁寧に設計され、コードレビューで磨かれ、ユーザーフィードバックにより改善されています。
わかりやすいエラーメッセージとはどういったものなのか。どのように実装、改善されているのか。どのように開発者体験、あるいはユーザー体験を向上させているのか。
このセッションではRustコンパイラへのコントリビューションで得た経験をもとにして、Rustコンパイラで行われているエラーメッセージの実装・改善活動を例に、わかりやすいエラーメッセージのあり方などについてご紹介します。
ここではRustやコンパイラを題材としますが、これらへの深い造詣は必要ありません。
Rustコンパイラの開発がどのように行われているのかといったOSS開発に関する知見だけでなく、日頃の開発においてエラーメッセージを通して開発者・ユーザー体験を向上させるテクニックや考え方をご紹介できる内容を目指します。
サイバー攻撃の分析とデバッグが捗るWindowsの動的解析機能
近年のWindows OSに実装されているデバッグ機能について解説します。デバッグは、ソフトウェア開発者がプログラムの複愛を特定したり、動作を確認したりするための一般的な動的解析技術であり、その特性から近年ではサイバーセキュリティでの問題分析や攻撃検知にも活用されています。Windows OSでの動的デバッグに用いられるソフトウェアとしてはWinDbgが広く知られていますが、Windows OS自体にもプログラムの動的解析を支える複数の機能が実装されています。本講演では、Windows OS自体に実装されている動的解析を支援する機能の中から、いくつかの機能に焦点を当てて、デモンストレーションを交えて解説します。
2025年のWebDriver BiDiの動向まとめ、そしてこれから
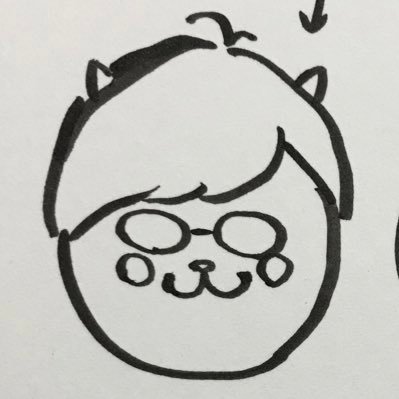 nus3
nus3 去年の Burikaigi では WebDriver BiDi とは何なのか話しました
https://speakerdeck.com/yotahada3/webdriver-bidi-burikaigi2025
今回は 2025 年の WebDriver BiDi の動向として
- 仕様についてどう言った議論があったか
- 各ブラウザベンダーの実装状況
- ブラウザツールの対応状況
をふりかえり、2026 年の WebDriver BiDi がどうなっていくのかを予想します。
副作用をどこに置くか問題:オブジェクト指向で整理する設計判断ツリー
 Koya Masuda
Koya Masuda 【テーマ】
アプリケーション設計において、「この処理はどこに置くべきか?」という問いは常につきまといます。
特にオブジェクト指向言語では、クラスやオブジェクトが自由に設計できる反面、責務と状態の境界が曖昧になりやすく、気づけば副作用があちこちに散らばります。
一度拡散した副作用は、バグやテストの不安定さを呼び、まるで割れ窓理論のように保守性の低下を加速させます。
本テーマでは、オブジェクト指向設計の原則(単一責務・不変条件・副作用の分離)に立ち返り、
「コールバック・イベント・非同期処理といった選択肢の中で、どのように責務と状態の境界を見極めるか」を体系的に整理します。
具体的な設計判断の基準と、現場で使える“判断ツリー”を共有することで、日々の開発における「処理をどこに置くか問題」に自信を持って向き合えるようになることを目指します。
【想定する参加者層】
- オブジェクト指向プログラミングの基礎(クラス・責務・状態)を理解している方
- 何らかのオブジェクト指向言語(Ruby / Java / PHP / Python / TypeScriptなど)で業務アプリケーションを開発している方
- ミドル〜シニア層のエンジニア(コード設計やレビューを担う人)
※発表者はRailsエンジニアであり、サンプルコードはRubyで示しますが、設計原則は言語・フレームワークを問わず応用可能です。
【トーク概要】
「コールバックに書くべき?」「イベントに切るべき?」「非同期に逃がすべき?」
日々の開発で誰もが悩む“副作用をどこに置くか問題”に悩むかと思います。この判断をセンスや慣習に頼らず、オブジェクト指向設計の原則に基づいて整理するのが本トークの目的です。
副作用を
- エンティティ内部の不変条件を守る処理(DB内で完結)
- 状態確定後の通知(他の関心へ伝える)
- 外部I/Oや重い処理(非同期・再試行を前提とする)
という3層に分類し、それぞれをコールバック/ドメインイベント/非同期ジョブに対応づけた「設計判断ツリー」を提示します。
また、現場で陥りがちなアンチパターンとして
- コールバックが連鎖して依存が見えなくなる
- 順序依存で動作が壊れる
- ロールバック後に外部I/Oが発火してしまう
といった問題を、責務と状態の境界設計の観点から分解します。実際のコード例(Rubyで示します)を通じて、「副作用をどこに置くべきか」を説明できるようになることを目指します。
AWS で試して学ぶ IPv6
 hmatsu47(まつ)
hmatsu47(まつ) 「IPv4 のアドレスがもうすぐ枯渇する!」と言われ続けてはや◯年。
これは決してオオカミ少年的な話ではなくて IPv4 アドレスの節約・やりくりを頑張っている人たちのおかげでもあると思うのですが、そんな「努力の限界」がいつ来るかについてはわれわれ素人には正確にはわかりません。
そこで、X デー(?)がいつ来ても良いように、今のうちに「完全に理解した」とは言わないまでも「雰囲気は掴んだ」というレベルになっておこう!というのが当セッションの目的です。
■話す内容(一部)
- IPv4 との違い
- アドレスの構成と表記
- アドレスの種類
- アドレスの割り当て方
- ホスト(ノード)間通信
- IPv4・IPv6 共存技術
- デュアルスタック
- NAT64 + DNS64
- AWS のリソースを IPv6 で組んでみる
- IPv6 の仕組みのうち AWS で隠蔽されている(意識しなくても良い)部分について軽く説明
- IPv6 専用 VPC で組んでみる
- デュアルスタックで組んでみる
- 結局 IPv4 パブリックアドレスは減らせるの?(安くなるの?)
- アプリケーション側での考慮点
- IPv6 を使うときの注意点
- GitHub、もしかして使えない?
- マネージドサービスを使わずにメールをまとめて送ろうとすると…?
などなど
■想定する参加者層(前提知識)
- IPv4 のことは概ね理解しているが IPv6 については何もわからない方
- 主に AWS を使われている方
State of Web UI 2025
 saku
saku よりパワフルで柔軟な UI を実現する、エキサイティングな Web の機能が、今年も多く登場しました。
CSS Containment、Value Processing、UA による DOM のクローン、Top Layer、そしてレンダリングエンジンにおける最適化。
針の穴に糸を通すような仕様と実装の工夫が積み重ねられ、不可能だったことを可能にする基盤が今、整ってきました。
その結果、ずっと絵に描いたモチだと思っていた機能が、気づけばポンっと実体化した。
それが、 2025 年の Web UI です。
参考:https://blog.sakupi01.com/dev/articles/2025-css-advent-25
そんな今年の Web UI を取り巻く HTML&CSS&JS 機能のアップデートと、今後登場が期待される機能、そして"Primitive 性" に焦点を当てた Web UI 進化の方向性をご紹介します。
俺が選んだITエンジニアキャリア戦略 〜Microsoft MVPからDirectorまでの道のり〜
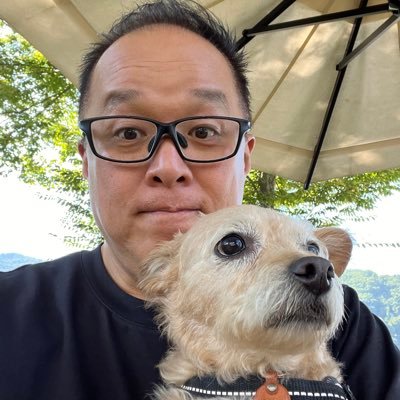 もり ひろゆき
もり ひろゆき ITエンジニアとしてのキャリアは、技術スキルだけでなく「どんな選択をするか」によって大きく形が変わっていきます。
どの技術を学ぶか、どんなコミュニティに飛び込むか、そしてチャンスが目の前に来たときに一歩踏み出すかどうか。
その一つひとつの選択が、自分のキャリアを作り上げていきます。
私は、Microsoft技術との出会いをきっかけにキャリアが大きく動き出しました。
コミュニティでの学びや仲間との交流が新たな視野を開き、Microsoft MVPを受賞することで次の扉が開きました。
そこからさらに挑戦を続け、現在はアバナード株式会社でDirectorという立場に至っています。
このセッションでは、私がどのように選択を重ね、どのような失敗や葛藤を経てチャンスを掴んできたのかを、リアルな体験談としてお伝えします。
いつもは.NETやMS技術系のテーマでしたが、今年は自身のふりかえりをかねてソフトスキル系のお話をさせていただこうかと思います。
エンジニアとして成長の道を模索している方、次のキャリアステップを考えている方に、キャリアを切り拓くための「勇気」と「ヒント」を持ち帰っていただければと思います。
対話型UI時代のWebブラウザを考察する
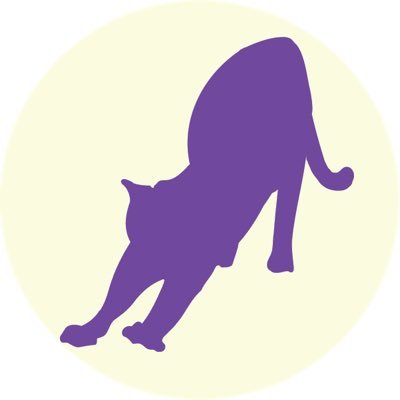 araya
araya Webブラウザはこれまで、数々の機能を実装し、セキュリティを強化し、相互運用性を高めながら発展してきました。
現在では情報アクセスの一部がAIを介した対話的UIへと移り始め、ブラウザでUIを提供する時代は終わるという声も聞かれるようになりました。
現代、もしくは近い未来私達が情報の消費者としてもコンテンツを作り出す開発者としても、Webブラウザに何を求めるのかを問い直します。
また、モダンブラウザと呼ばれる主要なブラウザエンジンに加えて、新興ブラウザエンジンの開発も進んでいます。
実際に1つのブラウザエンジンプロジェクトにコントリビュートしている発表者の視点から、ブラウザ開発に関わるモチベーションを紹介し、日本人開発者が参加する意義についても考察します。
人命を救う技術としてのEnd-to-End暗号化とMessaging Layer Security
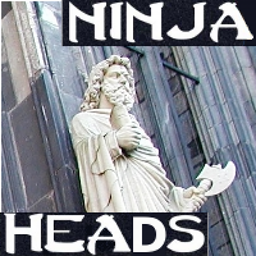 sylph01
sylph01 "Why do you need End-to-end Encryption in Ruby? Because..."
国際情勢の緊張が高まる現在、メッセージングのエンドツーエンド暗号化技術はかつてなく重要性が高まっています。
Eメールはその仕組み上エンドツーエンドでの暗号化を持たず、どうしても暗号化を実現しようと思うとS/MIMEなどの高価な仕組みやPGPなどの「オタクしか使っていない」仕組みに頼るしかありません。一方で我々が日常的に利用しているメッセージングアプリにはエンドツーエンド暗号化の仕組みが搭載されていますがベンダーごとに個別の方式で実装されており相互運用性を持ちません。
これらを解決すべくIETFで標準化が行われているMessaging Layer Securityという相互運用可能な鍵交換の技術があります。
現在私はMessaging Layer Security Protocol (RFC 9420)のRuby実装を進めています。この実装を通してMessaging Layer Securityの仕組みを解説することで、皆さんが日常使っているメッセージングアプリのセキュリティについて安心感を持つことができるようになるでしょう。
技術的には以下の内容をカバーする予定です:
- 求めるセキュリティ性質: Forward SecrecyとPost-Compromise Security
- 2人でこれを実現するのは容易だが3人以上の場合は難しい
- MLSの構成要素: Key Schedule, Secret Tree, TreeKEM
- 進行中のRuby実装について
ハッシュ化、共通鍵暗号、公開鍵暗号の概念程度の暗号技術の知識をある程度前提としますが、トークの内容自体はセキュリティに興味のある全技術者向けの内容です。
AIで開発はどれくらい加速したのか?AIエージェントによるコード生成を、現場の評価と研究開発の評価の両面からdeep diveしてみる
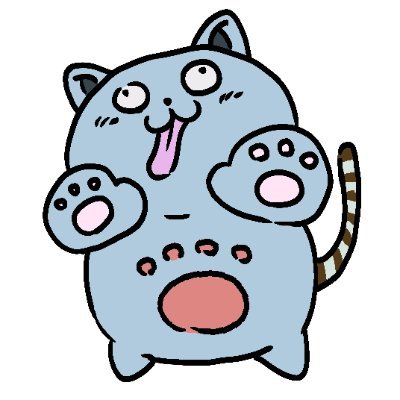 どすこい
どすこい テーマ
AIエージェントの導入によって、開発の現場は実際にどのくらい生産性が向上したかをテーマに、導入した現場での定量的な実測値とAIエージェントのベンチマークを深掘って考察した結果を発表します。
いくつかのAIエージェントの導入(2023年のCopilot、2024年のCursor、2025年のClaude Code)による社内でのマージ頻度やリードタイムの変化と考察、AIエージェントの研究開発の分野で参照されるHumanEval / SWE-Bench等のベンチマークの深掘り、そのベンチマークによる定量評価がどれくらい現場での定性的な評価と合っているのかを考察した内容を発表します。
想定する参加者層(前提知識)
機械学習やLLMに関する研究の知識などを必要とせず、コード生成をするAIエージェントを見聞きしただけの人にもわかりやすいような基礎からの発表にします。特に、ベンチマークについては、具体的にどのような課題があってどのように判定されているのかを噛み砕いて説明します。
トーク概要
本セッションでは、AI コードエージェント導入による開発加速の実態を、現場データとベンチマークの両面から整理してご報告します。
当社では 2023 年以降、その時点で有効と判断したコード生成 AI エージェントを導入してきました。マージ頻度やリードタイムの集計の結果、ある事業部では Cursor 導入後にマージ頻度がおよそ 3 倍、Claude Code 併用後にリードタイムがおよそ 1/2 となる変化を観測しました。この事実をもとに、「AI でどれくらい加速したのか」「どう評価すべきか」を定義し直します。
AI 導入初期はコード生成の品質が安定せず、人手による修正が前提となる場面が多いと感じていました。その後、モデル世代の変化に伴いコード生成の「精度」が向上し、コードエージェントの導入により開発体験が実際に変化した手応えがありました。ただし、この「精度」が具体的に何を指すのかに疑問を持ちました。変化量を外部基準でも確認するため、研究開発分野で一般的なベンチマークが何を測り、どのスコアを KPI としているかを整理する必要があると判断しました。
そこで、HumanEval と SWE-Bench を取り上げ、研究・開発分野で何を指標としてスコアを伸ばそうとしているかを解説します。これらのベンチマークでは、HumanEval は明確な入出力をもつ小粒度タスクに対する関数レベルの正確性を測定し、SWE-Bench は既存リポジトリ上での Issue 修正達成(文脈統合・依存解決・テスト通過)を測定します。現場では前者をユーティリティ/純粋関数の自動実装の置換可能性、後者を既知バグ修正や小〜中規模改修の到達率として読み替えます。本発表では、実際のテストデータを参照しながら両者の評価対象と前提条件を具体的に説明します。
あわせて評価指標にも短く触れます。pass@k は同一課題に対して k 本のコード生成を行い、少なくとも 1 本がテストを通過する確率を示します(例:pass@1 は単発生成の正答率、pass@5 は多様サンプルからの到達率)。SOTA(state of the art) は特定ベンチマーク・評価手順・バージョンにおける当時点の最高到達成績を指します。いずれも評価プロトコルと前提条件への依存性が高いため、比較は同一条件で行う必要があります。
そのうえで、ベンチマークの数値は次の三点で位置づけて読み解きます。第一に、何を前提に何を測っているか(課題の明確さ、必要コンテキスト、依存・ビルド環境、採点方法)を明示します。第二に、どの作業単位に対応するか(例:小粒度の実装、既知 Issue の修正、結合起点の不具合対応)を対応付けます。第三に、影響しやすい成分/しにくい成分を仮説化します。なお、研究分野の「コード精度」は pass@k やテスト合否が中心であり、仕様の曖昧さの解消、非機能要件、ステークホルダー調整、セキュリティやロールバック設計、コードデザイン(責務分割・凝集/結合・API 境界)といった現場要素は評価外になりやすい点を前提にします。本セッションでは、この読み替えを対応表と最小手順として提示し、新しいモデル・ツール・論文に出会った際に、作業単位や手元の指標へトレースする実務的なガイドとして持ち帰っていただきます。
聴講者が得られること
• AI 導入による効果が定量的にどのくらいあるかと、その評価方法
• 研究開発分野での AI エージェントの扱われ方と、どのスコアを KPI として伸ばしているかの整理
• 研究ベンチマークが開発現場でどの程度・どの領域に起用できるかを考え、議論するための視点
React 19でつくる「気持ちいいUI」 — 楽観的更新のすすめ
 もりしげ
もりしげ テーマ
React 19の楽観的更新で、日常のUIをもっと気持ちよく、操作体験を磨くヒントを届けます。
React 19の正式リリースから1年。
主要なライブラリやフレームワークでも対応が進み、今では実際のプロダクト開発でも十分に使える段階に入りました。
本セッションでは、React 19で追加された「新しいレンダリングの考え方」と「フック(useTransition / useOptimistic)」を活用し、「待たせない」「引っかからない」「自然に感じる」UI体験をどう実現できるのかを、実例を交えて紹介します。
非同期処理やサーバー通信が当たり前になった今、「読み込み中」「遅延」「再描画のちらつき」は避けられません。
しかし、React 19のuseTransitionやuseOptimisticを使えば、ユーザーに「遅れ」を感じさせないアプローチを実装できます。
フォーム送信、フィルタリングUI、ボタン操作など日常的なインタラクションを題材に、「技術でUXをなめらかにする」ための発想と実装パターンを一緒に探ります。
想定する参加者層
- Reactでの開発経験があるフロントエンドエンジニア
- React 19や新しいレンダリングの仕組みに興味がある方
- 「UXを良くしたいけど、どこから手をつけていいかわからない」方
- 理論よりも、現場で“手を動かして試したい”タイプの方
(主に初中級者〜中級者の現場エンジニアを想定)
トーク概要
React 19では、useTransitionやuseDeferredValueを使って「急ぎの更新」と「ゆっくりしてもいい更新」を分けることで、UIの引っかかりを減らす仕組みが整いました。
さらにuseOptimisticを組み合わせることで、サーバー応答を待たずにUIを「先に動かす」ことができます。
この「先回りするUI」は、ユーザーに「軽快でスムーズな操作感」を与える鍵になります。
正式リリースから1年が経過した今、これらの機能は既に安定しており、Next.jsやReactRouter(Remix)などの主要フレームワークでも標準的に採用されています。
つまり、「もう試す段階ではなく、使いこなす段階」です。
本トークでは以下の3つのテーマを中心に進めます
- 「待たせないUI」を実現する考え方とコードパターン
useTransitionとuseDeferredValueの具体的な活用例- Concurrent Renderingの理解を深める
- 「楽観的UI」のつくり方
useOptimistic+ Actionで即時応答を実装- 失敗時のロールバック処理のベストプラクティス
- これからのUX設計の方向性
<ViewTransition>で実現するシームレスな画面遷移- Reactの進化が示す「体験設計のこれから」
難しい理論を詰め込むよりも、「これなら自分のプロダクトで使えそう」と思える具体例を中心に構成します。
セッション後には、参加者が「自分のUIをもっと気持ちよくできそう!」と感じられることを目指します。
疑似コードによるプロンプト記述、どのくらい正確に実行される?
 黒曜
黒曜 ClaudeやChat GPTなどの生成AIでは、プロンプトを記述することで出力をコントロールします。
この際、自然言語ではなく疑似コードを用いてプロンプトを記述することで、手順や論理構造を端的に指示するテクニックが知られています。
疑似言語にはJavaScriptの文法を用いる例が多いですが、SudoLangなど専用の文法も考案されています。
この手法は一見便利そうですが、実際にどれだけ正確に意図が伝わるのでしょうか?
if文のネストは正しく解釈されるのか? for文やwhile文によるループは正確な回数繰り返されるのか? Prologのバックトラック・Go言語のGoroutineなど、言語ごとの特殊な機能は正しくエミュレートされるのか?
わたし、気になります!
というわけで試した結果を共有します。
想定する参加者層
生成AIに関心を持っているエンジニア。
特にプロンプトエンジニアリングの経験は問いません。
テーマ
生成AIの疑似言語によるプロンプティングの正確性・限界を確認する
攻撃にも障害にも強いクラウド設計 ─ 可視化と検証で築くサイバー&システムレジリエンス
 Shun Yoshie
Shun Yoshie 2025年後半は、ランサムウェア感染、データ損害、クラウド障害という話題がIT業界を震撼させました。
クラウドはスケーラブルな一方で、障害・攻撃・設定ミスなどのリスクを正しく評価できていないことは問題です。いま求められているのは、単なる高可用性ではなく「レジリエンス=回復力」を備えた設計です。本セッションでは、マルチクラウド(AWS/Azure/GCP/OCI)におけるレジリエンス可視化について考え、システム障害・サイバー攻撃の両面から耐性を強化するアプローチを解説します。四大クラウドにおけるベストプラクティス比較も行い、設計・評価・運用を一体化した継続的レジリエンス向上の手法を紹介します。
想定対象は、クラウドアーキテクト、セキュリティ担当者、システム企画担当。中級者以上を主な対象とします。
Rustで広がる組込みの世界 ― Raspberry Pi Pico 2Wからはじめる安全で楽しいIoT開発
 大野 駿太郎
大野 駿太郎 Raspberry Pi Pico 2Wという小さなマイコンをRustで動かしながら、組込み開発の面白さを“ちょっと深く”味わっていく話をします。対象は、普段はWebやアプリを触っているけれど、マイコンにも興味がある学生さんやエンジニアの方、あるいはC言語での組込みに少し触れたことがあるけれどRustでの開発は初めて、という方です。
Raspberry Pi Pico 2Wは、1,000円ちょっとで買えるボードですが、デュアルコアCPU、Wi-Fi / Bluetooth、USB通信など、かなり本格的な機能を持っています。このトークでは、そんなPico 2WをRustで動かしてみる中で見えてきた“Rustらしい組込みの考え方”を紹介します。
トークの中では、
・Lチカ(LED点滅)のプログラムを動かす
・USB経由で、PCのGUIアプリからLEDの点滅速度を変える
・Blutooth通信を使ってスマートフォンのアプリ(Flutterで自作)からLEDの点滅速度を変える
という使い方を実物で示しながら、その中身で活躍するコードのテクニックを紹介します。単なるハードウェア制御ではなく、「PC・スマホ・マイコンをRustでつなぐ」体験を通して、Rustの良さを感じてもらえることを目標とします。
Rustで組込み開発をすると、最初は「何がそんなに違うの?」と思うかもしれません。でも、実際に書いてみると、変数の所有権や型システムが“動かないバグ”を事前に防いでくれたり、スレッドや割り込みの扱いがとても安心できる設計になっていたりします。C言語では見落としがちな部分を、Rustは“コンパイルエラー”として教えてくれるのです。これは、組込みのようなハードウェアに近い開発では特にありがたい特徴です。
このトークでは、そんなRustの「安全さ」と「気軽さ」を両立させる実践方法を、Raspberry Pi Pico 2Wという分かりやすい題材を通して紹介します。コードの細かい部分よりも、「なぜこう書くと安全なのか」「どんな考え方で設計するとRustが生きるのか」というポイントを中心にお話しします。また、途中でPico 2W特有の“ちょっと変わった構造”(PIOによる柔軟なI/O制御や、無線モジュールCYW43の動作など)にも軽く触れ、マイコンの内部構造を理解する面白さも感じてもらえるようにします。
このトークを通して、Rustを使った組込み開発が「難しそう」から「やってみたい!」に変わるきっかけを届けたいと思っています。マイコンを初めて触る方にも、CからRustへ一歩踏み出してみたい方にも、ぜひ聞いてほしい内容です。
AWSと生成AIで学ぶ!実行計画の読み解き方とSQLチューニングの実践
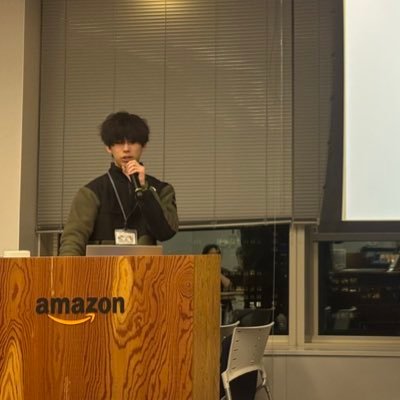 やくも
やくも 本セッションでは、Amazon Aurora を題材に、SQLの実行計画分析とパフォーマンスチューニングを
AWSサービスと生成AIの力で効率化するアプローチを紹介します。
従来の手作業による実行計画の読み解きでは、時間がかかり、知識の属人化も起きがちです。
しかし、Aurora Performance InsightsやCloudWatch LogsなどのAWSサービスを活用し、
さらに Amazon Bedrock や Claude 3 などの生成AIモデルに実行計画を要約・分析させることで、
より直感的かつスピーディーにチューニングを進めることが可能になります。
◼️テーマ
データベース最適化/SQLチューニング/生成AI活用/Aurora/パフォーマンス可視化
◼️想定する参加者層(前提知識)
中級者以上のエンジニア向け
• SQLを日常的に書いている方
• クエリのパフォーマンスチューニングに苦手がある方
• チューニングの「調査・分析」を効率化したい」方
• 生成AIを業務活用してみたいクラウドエンジニア
初心者も歓迎
• 実行計画を読んだことがない方でも理解できるよう、最初に基礎概念を解説します。
◼️トーク概要
「SQLが動くけれど遅い。何をどう直せばいいか分からない。」
──そんな経験をしたことはありませんか?
SQLのチューニングには“実行計画”という最強の手がかりがあります。
しかし、EXPLAINを見ても「Index Scan」「Nested Loop」などの言葉の意味が分からず、
“結局どこが遅いのか”が掴めないという声を多く聞きます。
この発表で以下のようなことを持ち帰っていただきたく思います。
• 実行計画から何が分かるのか?
• SQLチューニングの属人化からの脱却
• Amazon CloudWatch Database Insightsについて
たかがボタン、されどボタン ~button要素から深ぼるボタンUIの定義について~
 やまのく
やまのく テーマ
HTMLのbutton要素とa要素の正しい使い分け、マークアップ、アクセシビリティについてを主題とします。安易な実装が引き起こすバグやアクセシビリティ低下という課題に対し、Web標準に基づいた「ボタンの定義」についてを改めて見直す内容を提供します。
想定する参加者層
- とりあえず<div>や<a>にonClickを書きがちな方
- コンポーネント設計の際に、<button>と<a>の使い分けで議論した経験のある方
- UIのセマンティクスやアクセシビリティに関心のある方
トーク概要
今やWebサイトやアプリケーションに必ず存在するようになった「ボタン」というUI。私たちは毎日当たり前のように実装していますが、「ボタンとは何か?」と聞かれたら、明確に定義できるでしょうか?
<a>タグをボタン風に装飾したUI、type属性を忘れて意図せず画面をリロードさせる<button>、そして歴史の彼方に消えつつある<input type="button">...。なぜこんなにも多様な『ボタンのようなもの』が生まれ、そしてバグの温床となるのでしょうか。
私はこれまで、マークアップのセマンティクスを重視する立場として、こうした「残念な」実装が溢れる現状を常にもどかしく感じてきました。「動けば良い」という流れの中で、なぜ「本来あるべき姿」が失われてしまうのでしょうか。
このセッションでは、「type属性の指定漏れ」でバグを踏んだ経験や、デザイナーと「ここはリンクか?ボタンか?」で実装方針が割れた際の苦い議論を基に、このボタンUIを深掘りします。
HTML仕様やアクセシビリティの観点から「ボタンとは何か」を再定義すると同時に、私が実務のコードレビューや設計議論で直面してきた葛藤と、それを乗り越えるための知見を共有します。
この発表を経て「たかが」と思っていたボタンUIについての考えを変えるきっかけになるかもしれません。
期待する聴者に持ち帰ってほしい内容
- 「ボタンとは何か?」という問いに対し、セマンティクス・振る舞い・アクセシビリティの観点から自信を持って説明できるようになる
- type属性の指定漏れによる意図せぬフォーム送信バグを、未来永劫なくすことができる
- リンクをボタンのように見せるUI(リンクボタン)を実装するときに配慮すべきことに気づける

