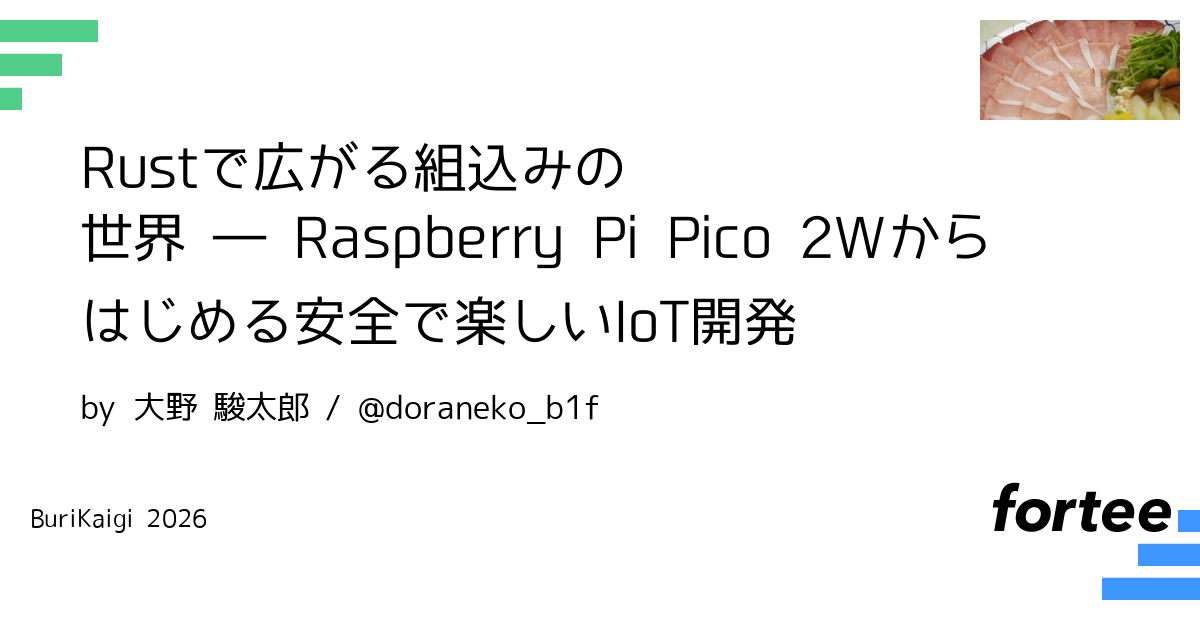
BuriKaigi 2026
Rustで広がる組込みの世界 ― Raspberry Pi Pico 2Wからはじめる安全で楽しいIoT開発
 大野 駿太郎
doraneko_b1f
大野 駿太郎
doraneko_b1f
Raspberry Pi Pico 2Wという小さなマイコンをRustで動かしながら、組込み開発の面白さを“ちょっと深く”味わっていく話をします。対象は、普段はWebやアプリを触っているけれど、マイコンにも興味がある学生さんやエンジニアの方、あるいはC言語での組込みに少し触れたことがあるけれどRustでの開発は初めて、という方です。
Raspberry Pi Pico 2Wは、1,000円ちょっとで買えるボードですが、デュアルコアCPU、Wi-Fi / Bluetooth、USB通信など、かなり本格的な機能を持っています。このトークでは、そんなPico 2WをRustで動かしてみる中で見えてきた“Rustらしい組込みの考え方”を紹介します。
トークの中では、
・Lチカ(LED点滅)のプログラムを動かす
・USB経由で、PCのGUIアプリからLEDの点滅速度を変える
・Blutooth通信を使ってスマートフォンのアプリ(Flutterで自作)からLEDの点滅速度を変える
という使い方を実物で示しながら、その中身で活躍するコードのテクニックを紹介します。単なるハードウェア制御ではなく、「PC・スマホ・マイコンをRustでつなぐ」体験を通して、Rustの良さを感じてもらえることを目標とします。
Rustで組込み開発をすると、最初は「何がそんなに違うの?」と思うかもしれません。でも、実際に書いてみると、変数の所有権や型システムが“動かないバグ”を事前に防いでくれたり、スレッドや割り込みの扱いがとても安心できる設計になっていたりします。C言語では見落としがちな部分を、Rustは“コンパイルエラー”として教えてくれるのです。これは、組込みのようなハードウェアに近い開発では特にありがたい特徴です。
このトークでは、そんなRustの「安全さ」と「気軽さ」を両立させる実践方法を、Raspberry Pi Pico 2Wという分かりやすい題材を通して紹介します。コードの細かい部分よりも、「なぜこう書くと安全なのか」「どんな考え方で設計するとRustが生きるのか」というポイントを中心にお話しします。また、途中でPico 2W特有の“ちょっと変わった構造”(PIOによる柔軟なI/O制御や、無線モジュールCYW43の動作など)にも軽く触れ、マイコンの内部構造を理解する面白さも感じてもらえるようにします。
このトークを通して、Rustを使った組込み開発が「難しそう」から「やってみたい!」に変わるきっかけを届けたいと思っています。マイコンを初めて触る方にも、CからRustへ一歩踏み出してみたい方にも、ぜひ聞いてほしい内容です。

