ジョッキでミルクを飲む最強のLT会 #JMLT
 umiwatarin
umiwatarin 皆さん、6月(7月)です!!!
6月1日は「牛乳の日」、6月は「牛乳月間」です!!!
これは最強のイベント、JMLTのご紹介をするしかない!!!
「牛乳を飲む」だけでハレのイベントとなったLT会「JMLT」より、地域の特性に合わせた柔軟なイベントの作り方をご紹介します。
これを聞いたあなたも、地域コミュニティをビルド&ジョイン!!!!
Cheeeers!!!!!!!!!!!!!!!!
道民学生ボランティアスタッフ体験記 in 東京
 須藤真由
須藤真由 今年、私は北海道から東京へ、JJUG CCC 2025という1000人規模のJavaイベントに初参加・初ボランティアスタッフとして関わりました。スタッフミーティングから当日のお仕事、そして終了後の“私なりの楽しみ方”まで、すべてが初めてで学びの連続!「道民の学生」という立場で、なぜ東京の大規模コミュニティに飛び込み、どんな意義や気づきを得たのかを、現地でのリアルな体験と共にお話しします。
遠距離家族の2か月を支えた、自作のステータス通知デバイスとその結果
 鈴木孝宏
鈴木孝宏 10年ぶりに北海道へUターンした私。しかし、Uターン直後に待っていたのは、2か月にわたる家族との別居生活でした。
この発表では、そんな状況の中、家族と私をつなぎ続けた自作のステータス通知デバイスについて紹介し、2か月間の運用結果を報告します。
具体的には、
・ESP-WROOM-02は現役? 2か月連続稼働で問題は?
・あらかじめ用意していたOTAアップデート、実際に活用できたのか?
・想定とは異なる、思いがけない使い方になった機能
といったトピックを中心にお話しします。
小さな自作デバイスでも、遠く離れた家族の安心や日常を支えることができる。
そんな可能性を感じた体験を、共有できればと思っています。
tcで遊ぶ!WebRTC配信をわざと崩してみた話
 Akiba
Akiba 通信が悪くなると、WebRTCの映像はどこまで崩れるのか?そんな疑問から始まり、実際に検証してみました!
本LTでは、WebRTC配信を"わざと崩して”検証する技術を紹介します。
WebRTC は JavaScript API を呼ぶだけで、ブラウザ間でカメラ映像・音声を暗号化し P2P でリアルタイム送受信できる技術です。
通信劣化時の映像崩れを検証するため、tcコマンドを使って帯域制限や遅延、パケットロスなどを意図的に発生させ、通信劣化時のWebRTC配信を再現しています。
解像度やビットレート、コーデックを変更しながら、どのように映像品質が変化するのかを観察します。
「リアルタイム性最優先」「ラグがなければ画質は犠牲にしてもOK」といった極端な設定にも挑戦した知見をお話しします!
オンデバイスAI技術"GoogleAIEdge"ひとくち解説
 Atria
Atria 昨今AI技術が生活に浸透し、Webやスマートフォンなどのアプリに組み込まれているケースが散見されます。
現状クラウド上のAIが強力でよく利用されますが、リソース管理問題やセキュリティ上の課題があります。オンデバイスで動作するAIであれば、これらの課題は回避できます。
このセッションでは、Android、iOS、ウェブ、組み込みデバイスなど、クロスプラットフォームに対応したオンデバイスAI技術であるGoogleAIEdgeをざっくり解説します。
セッション内では、今年5月にGoogleが発表した小規模モデルGemma 3nの動作デモをAndroidデバイス上で行います。
こんな方におすすめ
- Googleが進めているオンデバイスAI周辺の取り組みをざっくり知りたい方
- オンデバイスでAIを動かしたい方
- クラウド上のAIモデルを使いまくった結果、従量課金で痛い目を見たことがある方
部活で使えるツールが増えてきた? のでSSO(シングルサインオン)を実装してみた話
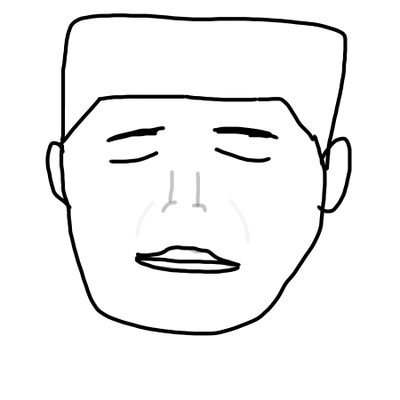 しのひろ
しのひろ 部室の鍵が空いているか確認できる「syorikey」システムを更新するにあたり、これまでの“basic認証”というレトロ感あふれる方法に別れを告げ、ちゃんとした認証を導入しようと決意。
そもそもVPN、クラウドサーバ、Wi-Fiなど部内には認証が必要なサービスが多く、「これもうSSO(シングルサインオン)しかないじゃん?」という声がずっとありました。
そこでついに、学祭準備しながら、バイトしながら、研究もしつつ、部活で後輩にネットワークとサーバ構築を教えつつ、なぜか睡眠不足になりながら、意地で実装してみたという話を、サクッと軽めにお届けします。
プログラムを1行、いや1文字も書けない僕がITコミュニティーを運営したらどうなるか?
 Hazime
Hazime 北海道のへその街 富良野で活動するFuraIT(ふらいと)。
2014年に設立されてから10年が経過。
途中からこのコミュ二ティーを引き継いだのはいいけど、どうしたものか。
ただ継続することを自身の目標に掲げていたら今は何が起きているのか。
そんな話をします。
今日はラッキーなのか、どうなのか?!毎日違う旭川〜美瑛〜富良野の風景
 Hazime
Hazime TechRAMEN 2025 Conference の写真撮影担当が趣味で撮影した風景写真をただただ流す時間。
ちょっとした息抜きに。
写真を見るとまた違う時期に来てみたくなるはず!
四季を通して美しいこのエリアのファンになって欲しい!
そんなLTもアリですか?
予想外のデータを正式なコンテンツとして処理するためのデータ構造を考えたい
作業メモからスライド資料を生成し、登壇中に話の順番や内容を考えられるプレゼンテーションツール「LTooL」を開発・運用しています。現在の課題はデザイン性で、独自のパーサーで作業メモからスライド形式に変換する仕組みが、スライドのデザイン性に私自身のデザイン力という依存を生んでいます。生成AIを利用すれば、自分の力では到底作れないデザイン性の高いスライド資料を一瞬で作ることができます。LTooLの良さはスライド資料の質ではありませんが、LTooLから自分の予想を超えたコンテンツが作られるという理想にとても魅力を感じて、現在は生成AIを活用した仕組みの開発を進めています。そこで「どのようなデータ構造で管理すれば予想外のコンテンツに対応可能なアプリケーションが作れるか」という壁にぶち当たり苦戦しています。TechRAMENまでにどこまで進められるかわかりませんが、苦戦の行く末を話せたらと思います。
自作PC!やろうぜ!
IoT機器は多様化し、「PCを購入する」というのが一般的な今、なぜ自作PC推しなのか。
自らの経験だけをたよりに、自作PCの本質に迫り、その魅力を伝えたい!
ブログを作りたいなら Astro
 みやもとなおゆき
みやもとなおゆき Astro.build というwebフレームワークの推しポイントを語ります。
学習コストが低い、デプロイ関係の公式ドキュメントの充実、軽量、そしてOSSである。
これほどに語りたくなるwebフレームワークはあるでしょうか?
聞き終わるころには 「npm create astro@latest」と入力せずにはいられなくなるでしょう。
ブログを書こう~アウトプットのススメ
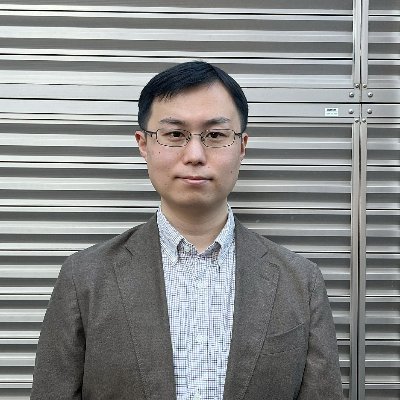 tokibito
tokibito みなさんはアウトプットをどのようにしていますか?
XのようなSNSだと書いたことが流れていってしまいますが、ブログならちゃんと残せて振り返りにも便利です。
自分のポートフォリオにもなるし、文章を書く練習にもなります。
誰かに質問されたときも、自分の言葉で書いた記事があればスムーズに共有できます。
アウトプットの手段としてブログに書くことの良さを紹介します。
AndroidとiOSのライフサイクル、図解でサクッと理解
 Haru
Haru 「あれ、これっていつ呼ばれてるんだっけ?」
最近のプロジェクトで、AndroidとiOSの両方を担当することになりました。
最初につまずいたのは、画面ライフサイクルの呼び方や流れの違いでした。
このLTでは、AndroidのActivity / Fragmentと、iOSのUIViewControllerのライフサイクルを図で整理し、それぞれの流れをサクッとつかむことを目指します。
「ライフサイクル、なんとなく全体像がつかめた!」と思ってもらえたら嬉しいです。
私と同じような初心者や、ネイティブアプリを触り始めたばかりの方にとって、少しでもヒントになればと思います。
想定視聴者
・AndroidまたはiOSのどちらかしか触ったことがない人
・これから両方触る予定の人
・ライフサイクルを「?」と思っていた人
要求分析で探る、LLMへの入力における知識の価値
 川瀬弘嗣
川瀬弘嗣 ChatGPTやGeminiに何かをお願いする時、どれだけ詳しく指示を書いていますか? 最近のLLMは非常に賢く、自動でWeb検索までしてくれます。少し曖昧な指示でも、よしなに情報を集めて回答してくれるため、「もう自分が詳しく知っている必要はないのでは?」と感じる瞬間もあるかもしれません。
このトークでは、ソフトウェア開発の「要求分析」をテーマとして、この疑問を検討します。 LLMに対し、要求分析の知識のない曖昧なプロンプトで要求抽出をさせた場合と、要求分析手法という専門知識を含んだプロンプトを与えた場合、そのアウトプットにはどのような差が生まれるのか、具体的な比較結果をお見せします。
LLMがそれっぽい答えを出してくれる今、私たちがこれからも専門性を高めていく意味はあるのでしょうか。このトークを通じてその答えを探っていきましょう。
新卒エンジニアがAzure Fundamentals取ってみた ~合格記~
 Haru
Haru クラウドといえばAWSのイメージが強いですが、私が関わっているプロジェクトではAzureを使っていました。そこでまずは基礎から学ぼうと考え、Azure Fundamentals(AZ-900)を受験し、無事に合格しました。
2024年卒エンジニアとして、業務ではまだ本格的にAzureに触れた経験がない中で、どのように資格の勉強を進め、何に苦労し、どう乗り越えたのか。
初心者目線での学習方法や活用した教材、モチベーションの保ち方など、これからクラウド資格を目指す方にも役立つ情報をお話しします。
現在は次のステップとして、AZ-204(Azure開発者向け中級資格)の取得を目指して勉強中です。その“その後”の話にも少し触れたいと思っています。
想定する聴講者
・クラウドに興味はあるけど、未経験の人
・AWS経験者で、Azureに興味がある人
・AZ-900の受験を検討している人
「箱庭」をハックするGoogle Apps Script: Slack Bot開発で得た知見(可能性と挑戦)
 katzumi
katzumi Google Apps Script (GAS) は、Googleサービスを自動化・拡張する無料のサーバーレスなスクリプト環境です。
ちょっと特殊な環境で制約が多いと感じるかもしれません。しかし、その制約こそが技術的挑戦を刺激して箱庭的な楽しみ方があります。
なによりサーバーレスでgoogleアカウントさえあれば基本的に無料で使え、趣味プログラミングの環境として魅力的です。
本LTでは、登壇者がGASでSlack Botの開発を通じて得た知見をお話します。
- ライブラリの利用
- TypeScriptベースの開発環境
- データ永続化(KVS)
- 非同期処理の実現(ライブラリ作成)
- ロギング
- 外部サービス利用
- 失敗談
技術的な課題解決を楽しみ、GASの可能性を最大限に引き出したいと考えているエンジニアの方々に、GASの奥深さと可能性を味わって頂く内容です
メロンはどのように作られるか
 くろさん
くろさん 旭川の皆さん。
富良野の皆さん。
周辺地域の皆さん。
そして私を含むその辺地域に無関係の皆さん。
メロン食べてますか?
旭川のお隣富良野の特産品であるメロンの栽培について、
2024年と2025年(予定)の数週間、実際に富良野のメロン農家でメロン栽培をちょっとだけ手伝ってわかった
素人なりの「メロン栽培を支える技術」をお話しします。
[話すこと]
- 農家のみなさんからきいたこと、それに基づいて調べたこと
- ソフトウェアエンジニアの視点から手伝えそうな農業と自動化
[話さ(せ)ないこと]
- メロンの生育に関する農業方面のガチ目な話(素人なので)
咲けない場所にさよならを ~自分を知って、咲かせる未来~
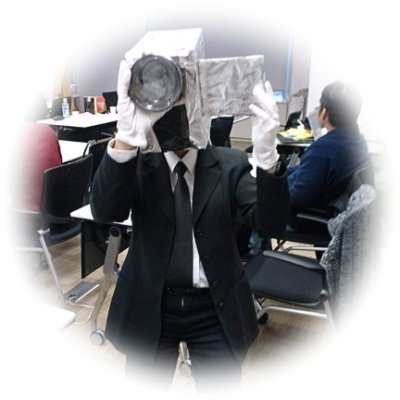 jnkykn
jnkykn 「置かれた場所で咲きなさい」というベストセラーがありますね。
私も、「美しい考え方だ」と共感して、いつか花が咲かせられるかも!と頑張った時期がありました。
なかなか成果が出せないまま「苦しい」と感じていたある日、
「自分の力が発揮できている」と感じられる場と、「しっくりこない」「うまく動けない」と感じる場があることに気が付きました。
自分がどんなときに活き活きできるか?を知ることで、自分に適した土壌を見つけて、花を咲かせられるかもしれません。
自分に合った土壌を見極めるためのヒントや、職場、家庭以外の「+αの場所づくり」のお話をします。
仕事に関係ないこと、どんどん試そう!~世界を広げる好奇心を最強の武器に~
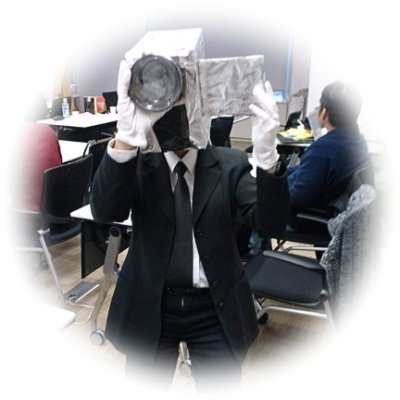 jnkykn
jnkykn 「仕事には関係ないけど、この技術面白そう」と思ったことはありませんか?
私は、あります。
「面白そう」っていう軽い気持ちで試したことが、実は仕事やいろんなところで生きてくる。そんな経験はありませんか?
私は、あります。(2回目)
そんな、「仕事に関係ない技術探求の魅力」を、5分でサッとお話します。
果たして、5分で伝えきれるのか!?
LTで語り切れなかった続きはブログで!
技術に自信がなくても、好きな気持ちだけでコミュニティ活動はできる
 かげろん
かげろん 「技術」に自信を持てていますか?
自分は学生の頃から自信がなく、それでも技術は好きなのでエンジニアとして就職して今に至ります。
勉強や個人開発は苦手だったり他にやりたいことがあって手が伸びず、それでも技術自体は好きな気持ちがありました。
そんな自分にとって、特定の技術に縛られない「田舎の技術コミュニティ」はとても居心地がよく参加できており、たまには発表してみたりすることがあります。
そうして関わり続けるうちに、他の勉強会やカンファレンスへ参加してみたり、スタッフとして運営に関わるようになっていました。
このトークでは、「技術に自信がなくてもコミュニティに参加し続けたことで得られたもの」についてお話します。

