全日本PHPersコミュニティーサミット
 PHPカンファレンス関西
PHPカンファレンス関西 全国各地で開催されているPHP勉強会の主催者が集まって話し合う史上初?のパネルディスカッションです。
東京、関西、福岡、名古屋、新潟をはじめ、PHP Lovers Meetup、PHPer Tea Night、PHPxTKYからもパネリストが参戦。
これからコミュニティに参加してみたい方、新しく地域コミュニティを立ち上げてみたい方にもオススメです。
■モデレーター
PHP勉強会@東京 koyhogeさん
■パネリスト
PHP勉強会@東京 chihiroさん
関西PHP勉強会 あかつかさん
Fukuoka.php seike460さん
Nagoya.php たつきちさん
niigata.php 沼(nicozetsche)さん
PHPer Tea Night おかしょいさん
PHP Lovers Meetup chatiiさん
PHPxTKY スーさん
and more.
ソフトウェア・デザインに向かおう ~ 世界を(ちょっとだけ)変えるソフトウェアを目指して ~
 杉本啓
杉本啓 ソフトウェアを作る仕事は労苦以外の何物でもありません。
労苦は、複雑な世界に向けて使いやすい道具を作るという仕事の本質的な難しさに起因していて、技術や手法を洗練すれば除去できるものではありません。
アジャイルにすれば楽になると思いきや、開発にまつわる周辺的な複雑さが緩和されることによって、役に立つモノを作ること自体に内在する難しさが却って際立ってきます。
我々は、何のために、労苦を甘受してソフトウェアを作るのでしょうか。
労苦を軽減することも大事ですが、労苦の意味を知ることはそれ以上に重要です。
自分たちが作るソフトウェアの存在意義が腑に落ちなければ、私たちはけっして労苦を乗り越えられず、真っ当なソフトウェアを創り得ないでしょう。
この基調講演では、その糸口として、ソフトウェア作りとは何か、どうして私たちはソフトウェアを作るのか、それを踏まえてソフトウェアをデザインするとはどういうことか、といったことがらについて、一緒に考えてみましょう。
我々の仕事には意味があります。
`#[DataProvider]`だけじゃなく`#[TestWith]`も使ってみませんか?
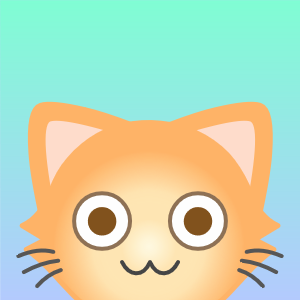 荒巻拓哉
荒巻拓哉 PHPUnitにおける「データプロバイダー」とは、1つのテストメソッドを引数を変えて実行する「パラメタライズドテスト」を実現する仕組みです。
#[DataProvider]アトリビュートを使うと実現できるのですが、類似のアトリビュートに#[TestWith]があるのはご存知ですか?
以前はちょっと使いにくかったのですが、最近では#[TestWith]もとても便利になってきていて、私自身#[DataProvider]よりも#[TestWith]を使う機会が増えてきています。
このLTでは、パラメタライズドテストを実現するアトリビュートの種類と、私なりの使い分け方をお話しします。
想定する観客
- PHPUnitを使っているがデータプロバイダーを知らない人
#[DataProvider]は使ったことがあるが#[TestWith]は知らない人
バイブスあるコーディングで PHP便利ツールをつくるプラクティス
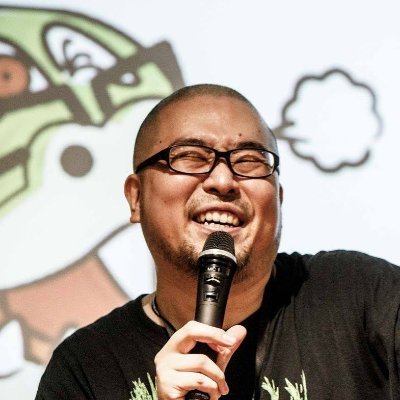 uzulla
uzulla 考えるより感じろ!
「今やってるこれ、何度もやってるな…これ、便利ツールにしたら二度と書かなくて済むのでは?」って思う瞬間、ありませんか?
そんなときにバイブスあるコーディングです!!!
このLTでは、そうした“ノリ”で作る小さなPHPツールの実装Tips、サクッと役立つテクなどを紹介します。
難しい理論や設計の話はナシ!Vibeのままコードを書いて、便利にして、また次のコードへ。
今日のバイブスが明日の時短になるかも。
OSI参照モデルから、設計やチームの“壊れない構造”のヒントを得る
 まさき。
まさき。 過去のカンファレンスでOSI参照モデルのプロトコル実装に関する発表を聞いたとき、「自分でも実装してみたい」と思うと同時に、このような“階層による責任の分離”は、コード設計や組織構造にも通じるのでは?と感じました。
OSIが解決している課題や、層が混ざったときに起こる問題を紐解くことで、私たちの設計やチーム運営にも活かせる視点が見えてきます。
本LTでは、異分野から学んだ“構造を守る”ための考え方とその応用についてお話しします。
カンファレンスに参加したあなたが明日からできること
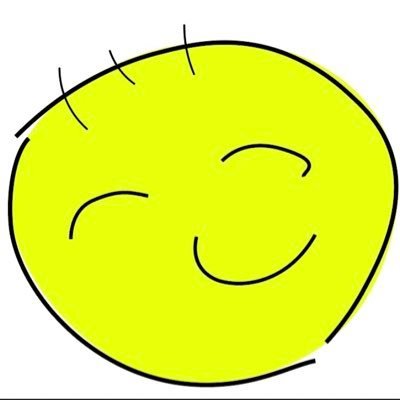 あかつか
あかつか PHPカンファレンス関西2025ではカンファレンスに初めて来るという方も多くいることと思います。
私が、カンファレンスに参加したときは知らない世界をたくさん見ることができ、大いに刺激を受けた一方で、レッドピルを飲んで真実を知ってしまったような感覚も味わいました。
業務で扱うコードは制約もあり、せっかくカンファレンスで学んだことを活かせないことも少なくありません。
そんな中でも、今日カンファレンスに参加したあなただからこそできることがあります。
このトークでは、カンファレンスに参加したあなたが明日から、自分の周りから少しずつ、改善を始める方法をお話しします。
統合された開発環境に何を求めるか
 うさみけんた
うさみけんた 歴史的にコーディングツールは、高機能なIDE(統合開発環境)とシンプルなテキストエディタに大別されます。
コンパイルが必要な複雑な言語と対比して、PHPのようなスクリプト言語はシンプルなテキストエディタでも開発できる単純な言語と考えられていましたが、昨今ではPhpStormのような複雑なIDEの機能も求められています。
本トークではPhpStormなどがどのような機能を備えているか、EmacsやVS Codeといったツールでどこまで肉薄できるかを追求します。
PHPでgit addとgit commitやってみる
 ひがき
ひがき Gitの仕組みについて解説しつつ、git addとgit commitするまでをPHPのコードでどう実現するかを話します。
話す予定
・Gitでファイルを保持する仕組み(Blobオブジェクト・Treeオブジェクト・Commitオブジェクト)
・git addをPHPで実現するには
・git commitをPHPで実現するには
「オブジェクト設計スタイルガイド」からはじめるドメイン駆動設計入門
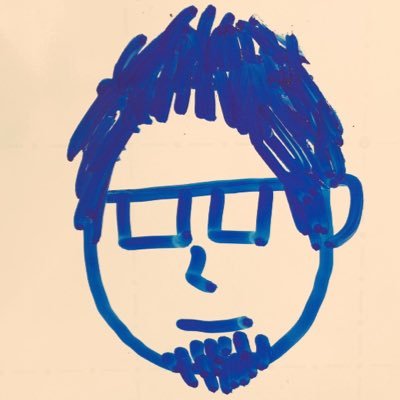 Endo Futoshi
Endo Futoshi 本セッションではMatthias Noback 氏が著者の「オブジェクト設計スタイルガイド」を通じて、ドメイン駆動設計での手法について入門する発表になります。
まずは、「オブジェクト設計スタイルガイド」を通して学べる「意味あるオブジェクトの作り方」や「ふるまいを持つクラス設計」の考え方を振り返り、そこからドメイン駆動設計で登場するエンティティや値オブジェクト、ユビキタス言語といった基本概念とのつながりを解説していきます。
具体的には以下の内容を通じて、現場での活用方法について紹介します。
- 小さな設計改善が、どうやってドメインモデリングにつながるのか
- PHPでの具体的なコード例(ValueObject、Entityなど)
- 「まずどこから始めればいいの?」という現場向けアドバイス
サーバにsshした時も安心!! 素Vim入門
 たけてぃ
たけてぃ phperの皆さんはサーバにsshで入って作業することはありますよね?
その際、shell scriptを流したり、vimで編集したり、色々な作業をすると思います。
本ワークショップでは安全に作業するTipsやVimの基本操作、VimでPHPを書く時の便利な方法などを一緒に学んでいきます。
ASTの力でPHPをminifyする
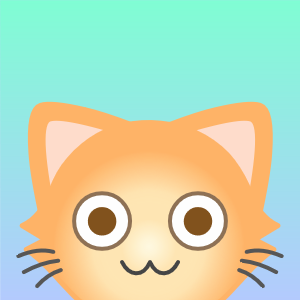 荒巻拓哉
荒巻拓哉 PHP-Parserを利用すると、PHPのコードを抽象構文木 (AST) に変換したり、逆にASTをソースコードとして出力したりすることができます。
ASTの一部を書き換えることもでき、たとえばRectorはこれを利用してソースコードの書き換えを行います。
この技術を利用すると、PHPコードをminifyすることも可能です。
minifyはソースコードの空白の除去や変数名の短縮などにより、ソースコード全体のサイズを圧縮することです。JavaScriptやHTML、CSSでは、ブラウザ↔サーバー間の転送量削減のためによく行われます。
WASMを使いブラウザ上でPHPを動かす事例も増えている昨今、PHPコードをminifyしながらASTの力を感じてみませんか?
想定観客
- 抽象構文木を知らない人
- ASTが何の役に立つか分からない人
- PHPをブラウザで動かしている人
; を書かずにPHPを書く業
 うさみけんた
うさみけんた 現代の多くのスクリプト言語は行末に ; を必要としないシンタックスを提供している一方、PHPは基本的に式文の終端に ; を要求しているため、他言語からPHPへの参入障壁となっています。このトークではPHPの言語機能を駆使して、コード上に ; を書かずに任意の処理を記述するテクニックを紹介します。
チームで「具体と抽象」を読んだなら
 加納悠史
加納悠史 具体と抽象の関係は、プログラムだけでなく実際の仕事でも非常に重要な概念です。
しかしながら、具体と抽象の関係性は、知らなければなかなか気づくことができません。
いろいろなタスクに具体と抽象の関係性を見つけ出し、チームで布教活動を行っていたところ、チームメンバの発案で「具体と抽象 ―世界が変わって見える知性のしくみ」(細谷 功 著)の読書会を行いました。
すると、日々の会話やタスクの進め方にもみるみる変化が...
この発表では、「具体と抽象」に入門し、日常的に使うようになったチームの日常を紹介します。
Factoryパターンで“壊れにくさ”を注入して、安全に仕様変更する
 まさき。
まさき。 共通クラスへの仕様追加、みなさんどうしてますか?
私は一度、抽象クラスに処理を書こうとして「これ全テスト壊れるやつだ」と震えました。
Factoryパターンを導入して処理を切り出したことで、影響範囲の限定、レビューの見通し改善、テストのしやすさまで一気に良くなりました。
このLTではその設計改善の実体験を共有します。
「個人情報を返さない」はずが…APIの落とし穴と未然防止策
 スー
スー 「このAPIエンドポイントは絶対に個人情報を返さない」…
そのはずが、ある日、意図せず個人情報を含むレスポンスを返してしまっていた。
考えただけでも恐ろしいこの事態は、残念ながら実際に起こりえます。
本セッションでは、私たちが経験した「個人情報を返してはいけないAPI」から、予期せずそれが返却されてしまったインシデントの事例を共有します。
気づくことができなければサービスが潰れかねませんでした。なぜそのような設計・実装上の欠陥が見過ごされたのか? どのようにして問題を発見し、インシデントとして対応を行ったのか?
そして最も重要な、具体的な再発防止策として何を導入したのか(テスト戦略の見直し、静的解析、コードレビュープロセスの強化、監視アラート設定など)を、原因分析から得られた教訓と共にお話しします。
対岸の火事ではない情報漏洩リスクに対し、明日から実践できる防御策のヒントを提供します。
私たちはなぜ PHP をアップデートしないといけないのか? 〜攻めと守り、両面から見たバージョンアップの本当の意味〜
 まさき。
まさき。 PHPのアップデートといえば、新しい文法や関数が使えるようになって開発者体験が向上した!みたいなどちらかというと攻めの意味合いに目が行きがちだと思います。
しかし実際に CVE 対応を検討する中で、OS のバージョンによりパッチの適用に課題が生じた経験から、“守り”の視点の重要性を実感しました。
このLTでは、アップデートにおける“語られない守り”に光を当て、今を守りながら未来を選び取るための向き合い方を共有します。
PHPUnitの限界をPlaywrightで補完するテストアプローチ
 ゆずねり
ゆずねり PHPアプリケーション開発では主にPHPUnitを使い、ユニットテストを書いていると思います。
PHPUnitは個々のクラスやメソッドをテストするのが得意なツールですが、実際のユーザがブラウザを通して体験するJSやCSSまで含めたレンダリング結果や、複数のページ遷移を伴う複雑なフローへのテストは苦手です。
こんな時にPlaywrightを使うとフロントエンドのテストが効率的にできます。実際にブラウザを動かしてテストを行うツールであり、ユニットテストが苦手としている領域をカバーすることができます。
一方でPHPUnitと比べ実行速度は遅く、メンテナンスのコストも高くなる傾向があります。
本トークではPlaywrightでできることを紹介しつつ、PHPUnitとPlaywrightの特性に沿ってテストをかき分けることでテスト時間を短縮し、より安心してリリースできる環境作りを紹介します。
PHPStan 型付け体験教室
 うさみけんた
うさみけんた PHPStanは簡単に使い始められる便利なツールですが、レベルを上げようとするとPHPStanの型付けの特性について学ばなければ効果的に型をつけることはできません。本ワークショップではブラウザから動かせるPHPStan Playground上で問題を解くことでPHPStanの型についての理解を進めます。
このワークショップではブラウザ上で動作するPlaygroundとPHPが動作するローカルマシンのどちらでも取り組むことができます。
(ローカル環境でのPHP開発環境について本編時間内ではサポートできません)
PHPの文法について基本的に理解していると望ましいですが、可能な限りサポートします。
var_dumpを読んでから、カンファレンスの景色が変わった
 まさき。
まさき。 以前、別のカンファレンスで「var_dumpとvar_exportの理解から始めるPHPのソースコードリーディング」というタイトルで、
php-src の中身を読んで調べた内容を発表しました。
発表の準備として、改めてvar.cやzend系の関数を読み直す中で、不安だったところを丁寧に確認し、自分なりの理解を深めていきました。
その過程を経て、今ではphp-srcを読むことが自然な選択肢になり、調査や設計判断の場面でも「読んで確認する」ことが当たり前になったと感じています。
このLTでは、発表がきっかけで“読む”という技術の向き合い方が変わった、自分自身の小さな変化を共有します。

