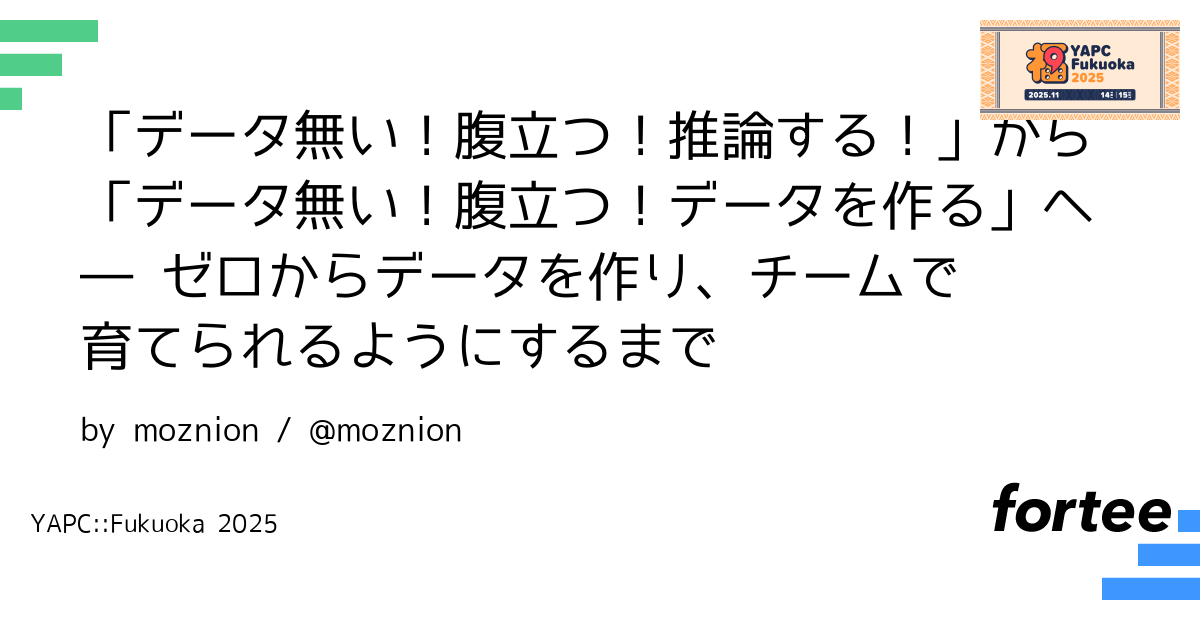
YAPC::Fukuoka 2025
採択
2025/11/14 12:55〜
Track A
トーク(40分)
「データ無い!腹立つ!推測する!」から「データ無い!腹立つ!データを作る」へ ― ゼロからデータを作り、チームで育てられるようにするまで
 moznion
moznion
moznion
moznion
話者が所属する組織ではプリペイドカードを用いた決済機能とそれに付随した家計簿アプリを開発しているのですが、そこでは日々膨大な量の「名前」と格闘しています。カードの決済店舗名、家計簿の支出名、レシートからの店舗名や費目名などなど……これら名前が各々何であるのかを機械が理解できるようにするにはどうすれば良いでしょうか。
例えば「セブンイレブン」という名前を見た時、人間はそれが「コンビニ」の名前であることを一目で理解できますが、未学習の計算機にこれをやらせるのは困難です。ではどうするかというとパッと思いつくのは計算機に推論させるという方法があります。昨今の大規模言語モデルであれば例に挙げたようなタスクはこなせる可能性がある一方、現状ではコストが高くなりがちという問題もあります。そもそも人間に判断が付かないものは機械にとっても難しいものです。仮に「たんぽぽ」という店舗名を見た時、これがどんな種類の店であるかを自信を持って回答できるでしょうか? 人が見ても判然としないものを機械に推論させても有意義なものが出てくるかというと難しいものがあります。
我々はこうした課題を解決するためにマスターデータ(辞書)を地道に作っています。本トークでは自然言語処理の理論・手法を要するものを、プロダクト作りの現場においてどうシステムや良い体験に適用していくかという実践的な話題を取り上げます。主に取り上げる予定の話題を紙幅の都合上以下に箇条書きにします:
- LLM時代ではその知識の源泉となるデータは益々重要
- 推論せずに結果が得られるならば推論する必要は無い
- 何の解決を目的としてデータを作るか
- データが無いところからどう作りはじめると良いのか(一定の根性の話)
- どのように作ったデータを育てるか
- 作ったデータを有効に使う方法
- データを作り、育て、有効活用できるチームをどう構築するか

