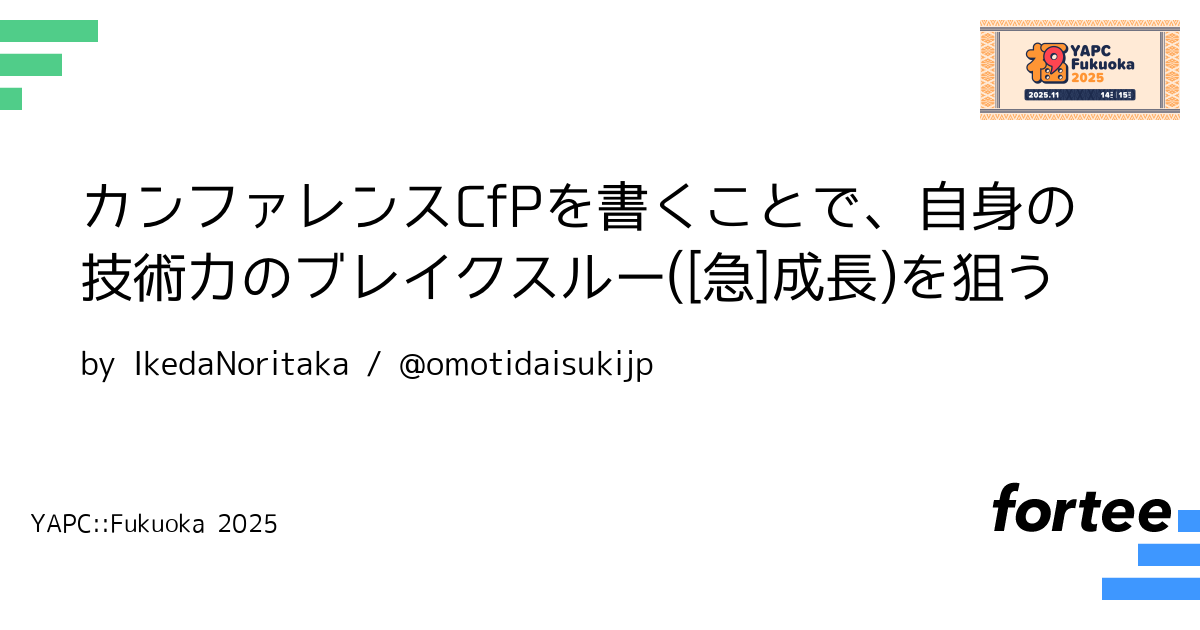
YAPC::Fukuoka 2025
カンファレンスCfPを書くことで、自身の技術力のブレイクスルー([急]成長)を狙う
 IkedaNoritaka
omotidaisukijp
IkedaNoritaka
omotidaisukijp
福岡に在住していた学生時代のイベント参加で感銘を受け、以降は参加者としても運営としてもカンファレンスに関わってきた。
TSKaigiなど複数回カンファレンスで登壇し、自身の日々の具体的な技術の考察が、抽象化された学びとなった。また、本業の技術的な成果の可視化と社内外での認知向上に寄与したと実感している。
私はアウトプットの形式として登壇を好んでいる。その場で得られる反応を踏まえ説明を調整できる点や、懇親会でテーマの議論が継続する点に価値を感じている。AIが開発プロセスに組み込まれる時代でも、「整理して伝え、議論する」営みは技術理解を深め、仕事の成果にも繋がり得ると考えている。
本発表では、登壇の魅力と、プロポーザル作成に備えた技術の棚卸しの手法、そしてそれを聴衆へ効果的に持って帰ってもらうための登壇に特化したアウトプットの作り方について、過去登壇した具体例を元に紹介する。
登壇はブログなどのテキスト媒体とはまた別の魅力に溢れている。ブログなどの作成時に考慮が必要な、ワントピックへ絞る制約や、ストーリーテリングしながら詳細な実装説明まで行う難しさを回避することができる。
登壇の魅力は、15〜30分の枠であれば、聴衆に最後まで聞いてもらえる中で、課題発見から成果が出るところまでを、具体的なコードを見せながらでも伝えられる点にある。
日々の個別具体の技術的な議論や取り組みを抽象化し、学びに変えやすい。
最近だと、AIによるDevOpsの構築といったテーマは登壇形式と相性が良く、今こそ積極的に登壇する意義を示す。
登壇は、本業での成果の証明にも大きく寄与する。日々の成果を抽象的なパターンや技術的示唆へと棚下ろしをし、評価面談用のテキストに留めずプロポーザルとして提出・登壇・発表することで、現地のエンジニアからの反響を得て成果を明確化し、技術力の発露を証明しやすくする。

