デザインシステムドキュメントの技術選定2025
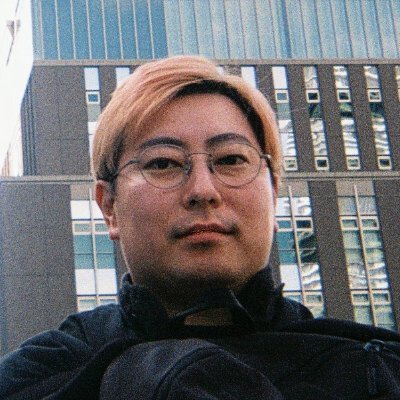 takanorip
takanorip デザインシステムは、思想や原則といった「ルール」、再利用可能なUIコンポーネントである「実装」、それらの利用方法を示す「ドキュメント」の3要素で構成されます。
特に「ドキュメント」は、デザイナーとエンジニアとをつなぐ共通言語として極めて重要な役割を担います。
ドキュメントが参照しやすく、運用しやすいかたちになっていないデザインシステムは、その機能を発揮できないまま腐っていくことでしょう。
このトークではそんなデザインシステムの根幹をなすドキュメントサイトの技術選定について話します。
ドキュメントサイトに必要な要件を整理し、それらを満たすための最適な技術は何なのかについて考えます。
加えてドキュメントサイトのユーザビリティや生成AI活用のために注意したいポイントなどについても解説します。
俺流レスポンシブコーディング 2025
 TAK
TAK 私が2021年に公開して、現在もシェアが続いている「俺流レスポンシブコーディング」は、当時現役だったIEのためにほぼメディアクエリに依存した実装の紹介となっていました。
しかし、IEがサポート終了した現在では、grid, min(), max(), clamp(), コンテナクエリといったレスポンシブコーディングにおける「ゲームチェンジャー」的な機能が広く利用でき、メディアクエリへの依存度を大きく下げることが可能となりました。
このトークでは、これらのモダンなCSS機能を駆使し、「メディアクエリは適した場面でのみ使用する」ことを目指す、Intrinsicなレスポンシブコーディングの手法を紹介します。
また、progress(), スタイルクエリ, if(), Anchor Positioningなど、将来のレスポンシブコーディングをさらに進化させる機能についても予習として解説します。
なぜ僕たちのNext.js導入はうまくいかなかったのか
モノリス化が進んだプロダクトの中で、「ユーザー影響の少ない画面から段階的にフロントエンドを切り出していこう」
そんな構想から始まった、バックエンド・フロントエンドの分離プロジェクト。
Next.js を使い、OpenAPIで型生成を行い、アーキテクチャパターンを学び…将来的にプロダクト全体への展開も視野に入れていましたが、
結果的に今は「撤退」を選ぶことになりました。
本セッションでは、どんな構想を立て、なぜ実行に移し、そしてどこで限界を感じたのかをリアルに共有します。
同じようにフロントの切り出しを検討しているチームにとって、立ち止まって考えるきっかけになれば幸いです。
ハイパーメディア駆動アプリケーションとIslandアーキテクチャ: htmxによるWebアプリケーション開発と動的UIの局所的適用
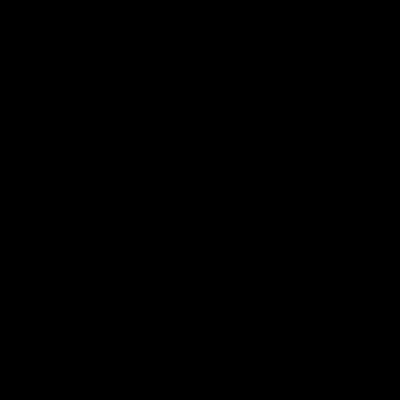 中村遼大
中村遼大 ハイパーメディア駆動アプリケーション(HDA)アーキテクチャは、従来のマルチページアプリケーション(MPA)の単純さと柔軟性に、シングルページアプリケーション(SPA)の操作体験を取り入れる設計アプローチです。本セッションの前半では、HDAの設計思想に基づく実践例として、htmxを用いたWebアプリケーションの画面遷移や状態更新の設計手法を具体的に紹介します。後半では、局所的な動的振る舞いが求められる場面において、Islandアーキテクチャを取り入れて補完する方法とその設計上の工夫について考察します。
「え?!それ今ではHTMLだけでできるの!?」驚きの進化を遂げたモダンHTML
 西 悠太
西 悠太 「HTMLって単なるマークアップ言語?JavaScriptがないと動的なUIは作れない?」そんな固定観念は、もう捨ててください!
実はHTMLはここ数年で革命的な進化を遂げ、かつてないほど表現力豊かで強力な言語になっています!これまでJavaScriptの実装が必須だったポップアップやモーダル、複雑なインタラクション、パフォーマンス最適化など、多くのことがHTMLだけで、宣言的かつシンプルに実現できるようになりました。
本トークでは、そんなモダンHTMLの持つ真の力を凝縮してお届けします。
このプロパティいつ使うん?~mdnのCSSリファレンス、全部読んでみた~
 yata
yata 普段の開発を行っていると、mdnのCSSリファレンスを端から読むことってそんなに多くはないと思います。
ですが改めて読んでみると、「知らなかったけどこれは便利だな!」というものから「このプロパティいつ使うん?」とつい思ってしまう様なマイナーなものまで、様々なプロパティと出会うことができます。
今回の発表では、mdnのCSSリファレンスを全て読んで見つけたマイナーなプロパティを紹介しながら、何とか業務内でも用いることが出来そうな用途を可能な限り捻り出して紹介します。
「自分でmdnを通読するのはめんどくさいけど、何か面白いものがあるなら知りたい!」という贅沢な方々に向けて、すぐに業務に役立つ訳ではないけれど知っておくといつかどこかで使えるかもしれない知識をお届けします。
知れること
- 一般的に広く使われていないが、特定の用途で便利なプロパティ
- 通常では使わない特異なプロパティ
堅牢なフロントエンドテスト基盤を構築するために行った取り組み
 Shogo Fukami
Shogo Fukami 皆さんはフロントエンドテストを書いていますか?
バックエンドテストがあるのに、フロントエンドは手つかず。そんな現場は珍しくありません。
私たちのプロダクトも、テストがあったものの重要な部分はカバーされていない状態からスタートしました。
「何を、どこまでテストすべきか」 が曖昧なままでは、導入は前進しません。
そこで私たちはクリティカルユーザージャーニーに絞った「必要十分」なテスト戦略を策定し、
限られた工数で最小の投資から最大の品質向上を実現し、壊れにくいテスト基盤を構築しました。
本セッションでは、
- クリティカルパスをどう特定し、優先順位を付けたか
- Playwright/Vitest などを用いた実装手順
- CIへの組み込みとメンテナンスコストの抑え方
これらを具体的なコード例とともに紹介し、堅牢なフロントエンドテスト基盤を構築する方法を共有します。
細粒度リアクティブステートのスコープ設計 - React と Jotai/Bunshi に見るスコープ管理の課題と解決策
 恩田 崇
恩田 崇 フロントエンドステート管理の大きな潮流に細粒度リアクティブステート管理 (fine-grained reactivitiy) が挙げられます。Solid.js や Svelte, Angular, Vue, Preact など様々なフレームワークで採用されている考え方で、Signals として TC39 で標準化の議論もはじまっています。
本セッションでは、React を題材にフロントエンドステート管理の歴史を紐解きながら、各時代が解決した課題と限界を振り返りつつ、なぜ細粒度リアクティブという考え方が必要になったのか、また、新しく見えてきたスコープ管理という設計課題を考えていきたいと思います。
その上で、Jotai / Bunshi を導入した実プロダクトでの事例をもとに、細粒度リアクティブステート管理における実践的なスコープ設計の解決策を紹介します。
心地よいアニメーションのつくりかた
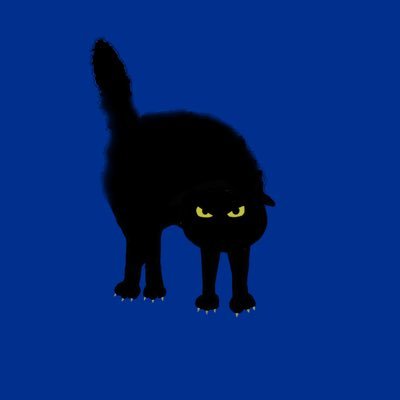 wattanx
wattanx 「あ、このアニメーション気持ちいい!」 - そんな体験には再現性があります。
本セッションでは
- なぜ心地よさがユーザー体験を向上させるのか
- 心地よいアニメーションの設計
- Motion での実装テクニック
をデモ中心で解説します。
フロントエンド初級者でも「セッション後すぐに試せる」具体的 Tips を持ち帰れる内容です。
Wasm×C++で実現するフロントエンドAI画像処理
私が所属しているカミナシでは、AIによるラベル検査機能をリリースしました.
これは端末のカメラで撮影したラベル画像から異常を判断するもので、従来はフロントエンドで撮影した画像をGPU搭載サーバへ送り推論結果を返していました。しかし通信待ち時間や運用コストの問題があります。
そこで今回は、フロントエンドならではの問題を克服し、C++で実装した推論処理を呼び出すWasmを採用。Wasmのバイナリを約9MBまで圧縮し、SIMD最適化やLazy Loadingを駆使しブラウザ上で約200msの高速推論を実現しました。また、Wasm開発時・リリース時に陥りがちな問題や、押さえておきたいメモリ管理やキャッシュ制御、エラーハンドリングのポイントも交えてご紹介します。
実際にこれらに関する一部のことは記事で紹介しています。
https://tinyurl.com/3rwtwa3m

