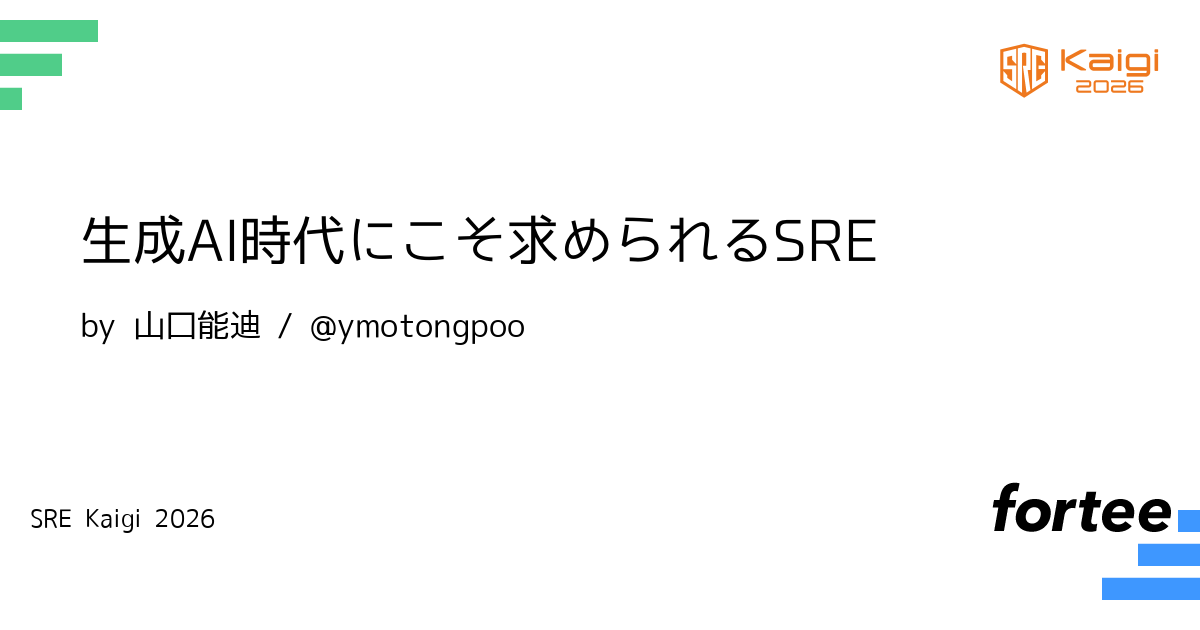
SRE Kaigi 2026
生成AI時代にこそ求められるSRE
 山口能迪
ymotongpoo
山口能迪
ymotongpoo
■ 発表カテゴリ
・Architecture: SREの視点からのシステム設計
・Culture: SRE文化の醸成と組織変革
・Future: SREの未来と新しいトレンド
■ 発表概要(400字程度)
生成AIを用いたシステム開発・運用が急速に普及してきましたが、一方で生成AIとの共存が課題となっています。本セッションでは、生成AIを用いたシステム開発・運用において、なぜこれまで以上にSREのプラクティスが重要になってくるのか、その理由を述べ、その対策として求められるSREのプラクティスを振り返ります。また同時に、生成AIがあるからこそ、よりその価値が高まるプラクティスについても解説します。本セッションを聞くことで、今後のシステム開発・運用において、生成AIとSREが両輪となって、開発者、運用担当者、さらには他の多くの部署の人々にとって大きな価値をもたらす枠組みを理解できます。
■ 発表の詳細(1000字程度)
2025年10月現在の生成AIツールは大規模言語モデル(LLM)ベースのものです。LLMベースの生成AIは、指示に対してもっともらしい出力を生成する一方で、注意深く利用しないと人間が期待しない結果を混入させるなど、まだまだその利用において課題が多い状況です。現在の生成AIツールの利用に関しての議論は、特に個人〜小規模チームでの開発(機能の実装)の話を中心としたものがほとんどで、その成果物をどのように安全に本番環境に導入し、そして安定して運用していくかについては多く語られていません。
本セッションでは、SREで挙げられている継続的インテグレーション(CI)、Infrastructure as Code、カナリアリリース、オブザーバビリティ、インシデントレスポンス、ポストモーテムといった各種プラクティスが、なぜ生成AIを前提とした開発・運用プロセスにおいて重要なのかを「生成」「分析・調査」「要約」の3つの点から解説します。
まず「生成」に関して。生成されたコードの安全性に大きく寄与するのはテストです。CIによって機能要件だけでなく、非機能要件(特に性能品質)にまで及んでテストを行うことが今後ますます重要となります。またIaCの設定も生成AIで行う事例が増えていますが、これも必ずテストが必要です。危険な設定項目が変更されていないかなど、SREにおいて推奨されている事前チェックが活きてきます。テスト後のリリースでも障害範囲を最小限に抑えるためにカナリアリリースといったSREが推奨するリリース戦略が効果を発揮します。
次に「分析・調査」です。先にも述べたように生成AIは、多くを出力することに目が向きがちですが、その結果の精度を上げるためには適切なコンテキストが必要です。その観点では、実は運用こそ有効に活用できます。IaCはまさにシステムの設計・仕様と実際をつなぐ重要なコンテキストです。IaCが静的なコンテキストとすれば、オブザーバビリティは動的なコンテキストです。何が起きているかを理解する上で、オブザーバビリティは障害の原因究明のための大きなヒントとなります。
最後に「要約」です。生成AIによりインシデントレスポンスやポストモーテムにおいて、雑多にメモされ、かつ様々な場所に置かれた情報を整理して要約することで、SREに必要な文書生成の効率が大きく向上します。
このようなさまざまなSREプラクティスが生成AIを前提とした開発・運用で、効果を発揮し、また効率を上げられるということを一つ一つ解説していきます。
■ 対象聴衆とその人たちが得られるもの
実際にSREをいま実践している人々も、SREを実践していない人も、また生成AIの活用を積極的に行っている人も、これから導入を検討している人も、すべての人々が生成AIが普及した新しい時代のシステム開発や運用において、SREの価値がより高まることを理解できるようになります。
■ なぜこのトピックについて話したいのか(モチベーション)
私は日本においてSREが普及しはじめるころから、その啓蒙を積極的に行い、そのために日本のSREコミュニティにとって普及する価値があると考える多くの英語版の関連技術書籍を翻訳してきました。そんな中、技術者は生成AIという新たな道具を手に入れ、その普及が広まる中で、開発者・運用者不要論を唱えるような人まで出てきました。しかし、実際にはそのためには生成AIを正しく振る舞わせるためのコンテキストが重要で、そのための活動は実はSREで言われているようなプラクティスそのものが意味をなすということはあまり知られていないように感じます。
このような背景から、SREを知っている人には改めて新たな価値を認識してもらい、SREを知らなかった人にも新たに関心を持ってもらいたいと考えて本セッションを応募しました。

