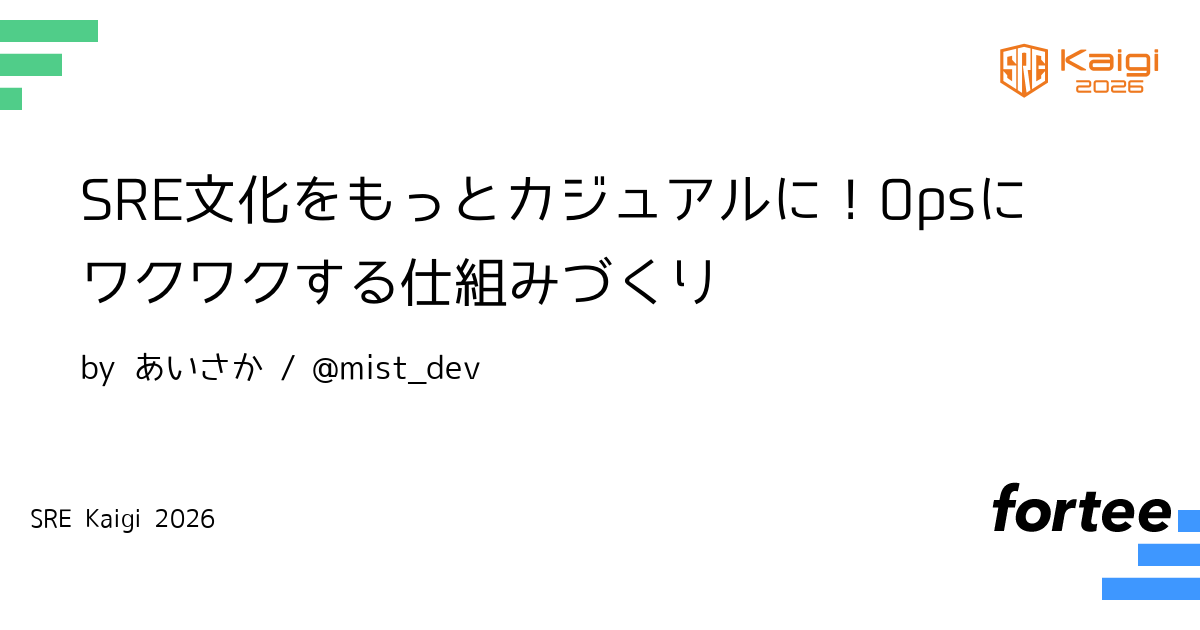
SRE Kaigi 2026
SRE文化をもっとカジュアルに!Opsにワクワクする仕組みづくり
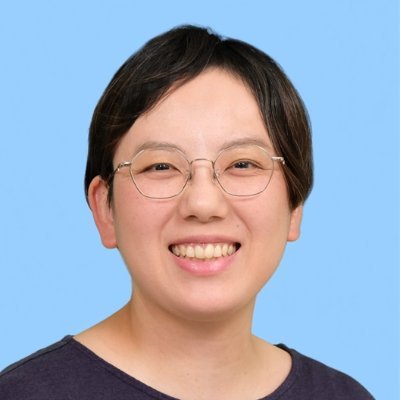 あいさか
mist_dev
あいさか
mist_dev
■ 発表カテゴリ
募集要項(https://srekaigi.notion.site/SRE-Kaigi-2026-CfP-25a6f7392c108187a9e6e47c346396b2) にある6つの発表カテゴリからお選びください
・Culture: SRE文化の醸成と組織変革
・Case Studies: 実際の導入事例や失敗談
■ 発表概要(400字程度)
SRE文化を広めたい!と思っても、アプリケーションエンジニアにとってOps的な要素は「プロダクト開発を進めることを阻害する」ちょっと邪魔な存在として扱われることがあります。では、どうすればエンジニアがOpsに前向きに関わり、モチベーション高く取り組めるのでしょうか。本発表では、ポストモーテムを続ける中で見えてきた課題や、Sentryアラートのチューニング、DependabotのPRをマージしやすくする工夫など、実際の試行錯誤を交えながら紹介します。
■ 発表の詳細(1000字程度)
- ポストモーテムとインシデントマネジメント委員会の変遷
私たちは1年間ポストモーテムを継続的に実施してきましたが、次第に“ポストモーテム疲れ”が目立つようになりました。アプリケーションエンジニアにとっては義務的で負担の大きい活動に映り、Opsへの関心が下がったようでした。そこで、ポストモーテムのフォーマットを見直し、インシデントマネジメント委員会でのポストモーテムの管理方法を見直しを行いました。
- Sentryアラートの改善
従来のSentry通知は件数が多すぎて“オオカミ少年アラート”状態になっていました。アプリケーションエンジニアが本当に対応すべきアラートが埋もれてしまい、結果的に信頼性向上にはつながらない状況でした。そこで、アラートを分類・整理し、重大度の高いものだけをSlackで共有するように調整しました。エンジニアが自発的にアラート対応を行えるよう、日々の見直しを行っています。
- DependabotとAIエージェントの導入
Dependabot が作成するPRは、「PRを能動的に見に行かないといけない」「何をしていいかわからない」問題を抱えていました。そこで、AIエージェントを活用してPRの要約や修正を自動生成し、開発者が安心してレビュー・マージできる環境を整えました。単なる「ノイズ」だったPRを「品質を守る小さなOps活動」として受け止められるようにしてもらえるよう、働きかけを行っています。
■ 対象聴衆とその人たちが得られるもの
自組織でSRE文化を広げたいSREやテックリード
SREとアプリケーションエンジニアの協働に課題を感じている方
アプリケーションエンジニアにモチベーション高くSRE文化を浸透させるための具体的なプラクティスを持ち帰っていただくことができます。
■ なぜこのトピックについて話したいのか(モチベーション)
各社のSREの取り組みについて会話するときに、「アプリケーションエンジニアにOpsの文脈に興味を持ってほしい」という話を聞く機会が多いと感じました。所属組織でも直面している課題であります。そこで、私たちが試行錯誤してきたプラクティスを共有し、同じ悩みを持つ方々にヒントを持ち帰っていただきたいと思っています。

