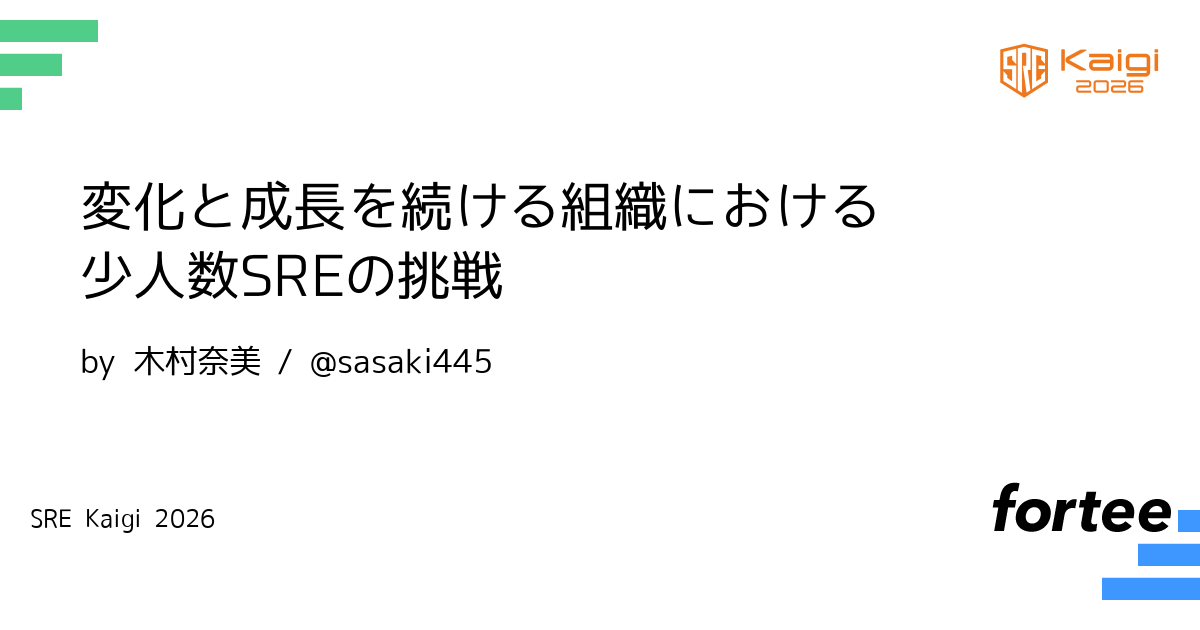
SRE Kaigi 2026
変化と成長を続ける組織における少人数SREの挑戦
 木村奈美
sasaki445
木村奈美
sasaki445
■ 発表カテゴリ
・Culture: SRE文化の醸成と組織変革
■ 発表概要(400字程度)
GENDAは「M&Aによる連続的な非連続な成長」を続けており、グループインする企業や、それに付随するプロダクトは予測不可能なペースで増えていきます。そのペースに合わせて比例的にSREメンバーを増やすことは現実的ではなく、いかに少人数でスケールできるかが鍵となります。
グループ内の全プロダクトで各種設定がベストプラクティスに沿っており、信頼性が高く保たれている状態が理想的ですが、SREチームが細部まで確認・対応していてはスケールできません。また、グループ企業やプロダクトによっては、技術スタックや文化も異なります。その差異を無視して一律にルールを強いては、かえって開発効率を損なう可能性も高いです。そのため、横断的にガードレールを敷きつつも、ある程度は各プロダクトチームの自主性に任せるというバランス感が大切です。
拡大し続ける組織の中で、SREチームは各プロダクトチームとの距離感を模索し、より事業に貢献できるチームとなれるよう取り組んできました。その挑戦を経て得た学びをお話します。
■ 発表の詳細(1000字程度)
私はもともと一つのプロダクトの専任インフラエンジニアとして入社しましたが、組織の規模が急成長したことにより、そのプロダクトに留まらない横断的な働き方を期待されるようになりました。各プロダクトを深く理解し、品質を高めるような改善をしたい、という思いはあったものの、専任だったときと同様のやり方は通用せず、思うように成果を上げられない時期もありました。2025年にはSREメンバーが2名入社したこともあり、改めてSREチームの在り方を議論し、大きくバージョンアップさせました。その結果、社内でのSREチームの存在感が拡大していきました。
本セッションでは、これまでのSREチームの歩みと、拡大し続ける組織におけるSREチームの在り方をお伝えします。
- 専任インフラエンジニアから横断SREへ
- 一つのプロダクトの安定性向上に成功
- その間にプロダクトが急増し、横断的な働き方のニーズが高まる
- 他プロダクトも同様に最適化しようと、巡回を計画する
- 思うように進まなかった停滞期
- ヒアリングしても、特に困っていることが挙がらない
- SREだけでできることは限られており、プロダクトチームのエンジニアの力を借りる必要があるが、開発の妨げになっては本末転倒
- 自分自身もそのプロダクトだけにフルコミットはできない葛藤
- SREチームのメンバーが増えたものの、プロダクトとの適度な距離感がつかめずにいた
- SREチームの在り方を見直し
- 現在のメンバーで改めてSREチームのあるべき姿を議論し、ゴールから逆算して道筋を立てる
- 各プロダクトとの接点を増やしてみる
- 社内での存在感を高める取り組み
- 取り組みの一例を紹介
- 無理にプロダクトでの作業を作らず、現時点で「絶対にやらないといけない作業」の効率化から始める
- 各プロダクトチームで共通して認識してほしいことをガイドラインに落とし込み、その伝達も仕組み化する
- 新しいことは一つのプロダクトで小さく試してみて、他プロダクトに展開を試みる
- 今ないものに対する意見は出ないため、まずは実際にものを用意してから意見を募る
- 成果
- プロダクトチームのエンジニアから相談を受ける機会が増えた
- 一部プロダクトチームで観測の習慣が定着しつつある
■ 対象聴衆とその人たちが得られるもの
- 大規模な組織で活動する小規模なSREチーム・プロダクトが増加し続ける環境におけるSREチーム
- 複数プロダクトを効率的に運用するための知見
- 他のチームとの連携を改善するための知見
■ なぜこのトピックについて話したいのか(モチベーション)
SRE領域のカンファレンスに参加した際に、他社のSREチームも自分たちと同じように、少人数で多くのプロダクトを運用していたり、プロダクト開発チームとの連携に悩んでいることがわかりました。そのため、自分たちの取り組みを話すことが、同じ悩みを抱える人たちの役に立つと考えたのがきっかけです。

