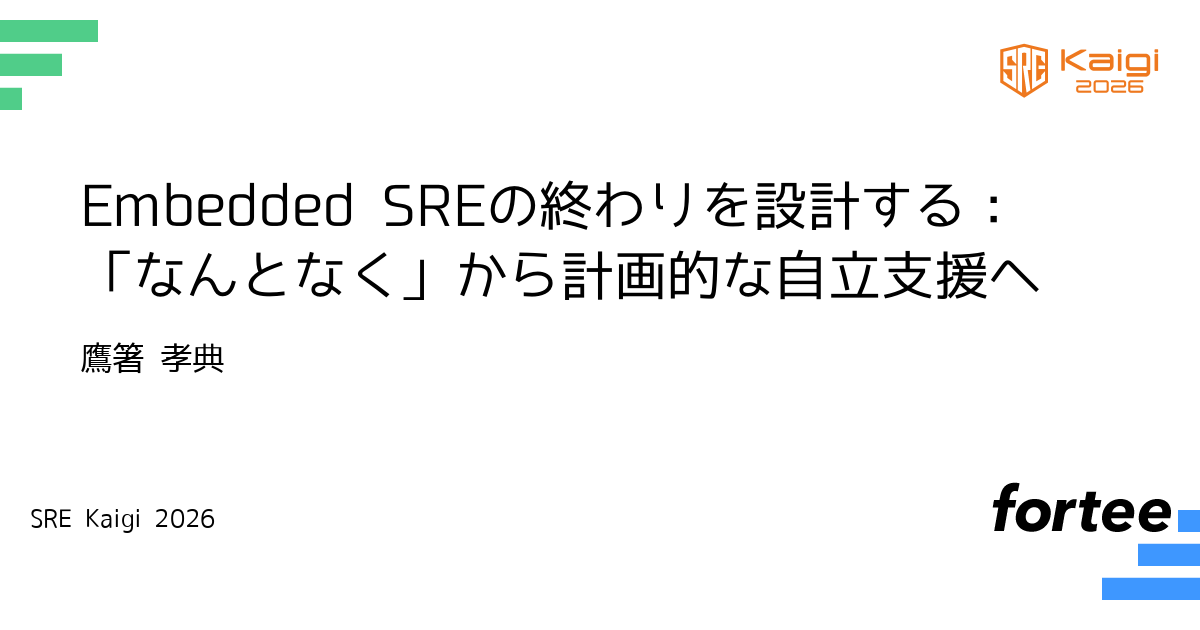
SRE Kaigi 2026
Embedded SREの終わりを設計する:「なんとなく」から計画的な自立支援へ
■ 発表カテゴリ
・Culture: SRE文化の醸成と組織変革
■ 発表概要(400字程度)
「いつまで私たちはここに関わり続けるのか?」Embedded SREとして開発チームに伴走する中で生まれた問いが、計画的なExit戦略の策定につながりました。本発表では、従来の「なんとなく関わり、なんとなく分業する」SREサポートから脱却し、明確な目標と期限を持った知識移転プログラムへと転換した経緯と実践を共有します。Knowledge Transfer MatrixとConfidence Scoreという定量的な手法を用いて、OpenTelemetry、Terraform、Kubernetesなどの技術スタックにおける知識移転の進捗を可視化。単なる技術移転ではなく、開発者がSREマインドセットを内在化し、自らオーナーシップを持って運用できる文化醸成までの道のりを共有します。Embedded SREという役割の「成功」が自らの役割の終焉を意味するパラドックスと、その先にあるSREの在り方について、実体験に基づいた考察と提言を行います。
■ 発表の詳細(1000字程度)
問題の本質:「なんとなく」の関係性
Embedded SREとして日々プロダクトの課題に向き合う中で、ふと疑問が湧きました。「いつまで私たちはこのチームに関わり続けるのだろうか?」振り返ってみれば、これまでのSREサポートは「なんとなく関わり、なんとなく分業する」状態でした。明確なゴールもなく、終わりも見えない。これでは開発チームはいつまでもSREに依存し、SREは限られたリソースを特定チームに固定し続けることになります。
社内を見渡せば、同様のサポートを必要としている開発組織が複数存在します。この状況を打破するには、Embedded SREという役割に明確な「終わり」を設計する必要がありました。
Exit戦略への転換点
転換点は、開発者との直接対話でした。「Exitに向かって協業していきましょう」という提案に対し、開発者から前向きな合意を得られたことで、両者の意識が大きく変わったように感じます。これまでの「サポートする側/される側」という関係から、「共通の目標に向かって並走するパートナー」へ。目標を共有し、期限を設定することで、両者の行動に明確な意図と責任が生まれることを期待しています。
Knowledge Transfer Matrixによる可視化
知識移転を「なんとなく」ではなく、計画的に進めるため、Knowledge Transfer Matrixという仕組みを利用しました。
このマトリックスは、縦軸に技術領域(OpenTelemetry Collector設定、Terraform管理、Kubernetes運用、GCPサービス活用など)を配置し、横軸に開発メンバーを並べ、各交点に1から10のConfidence Scoreを自己評価で記入する形式です。
自己評価方式を採用することで、開発者自身が「何を知らないか」を自覚し、主体的な学習意欲を引き出す効果も狙っています。さらに、スコアの推移を可視化することで、個人とチーム全体の成長を実感できる仕組みとしました。この定量化により、感覚的だった「知識移転」が、測定可能で改善可能なプロセスへと変わりました。
ロードマップの設計思想
Exit戦略は大きく基盤構築期と自立移行期の2つのフェーズで設計しています。
基盤構築期では、まず現状の可視化と課題の洗い出しから始め、自動化可能な領域を特定して実装を進めます。この期間はペアワークを通じた基礎的な知識移転に重点を置き、開発者がSREの視点や考え方を理解する土台を作ります。
続く自立移行期では、開発者主導での運用タスク実行へと段階的に移行し、SREの役割はメンタリングとレビューへと徐々にシフトしていきます。最終的にはオフィスアワーでの相談役として、必要な時にサポートする形を目指します。
両フェーズを通じて協働とペアリングを重視し、一度にすべてを引き渡すのではなく、小さな成功体験を積み重ねながら徐々に責任と権限を移譲していくことが、このロードマップの核となる思想です。
パラドックスが示すEmbedded SREの価値
Embedded SREの「成功」とは、自らが不要になることです。この一見矛盾した目標設定こそが、Embedded SREの本質的価値を体現しています。特定チームに固定されることなく、より多くの開発組織に価値を提供し、組織全体のレジリエンスを向上させる。
この実践で得られた知識移転の方法論やツールは、他の開発チームにも適用可能な形で標準化し、全社的なSREプラクティスとして展開することを視野に入れています。一つのチームでの「終わり」が、より大きなスケールでの「始まり」となる。それがEmbedded SREのExit戦略が目指す姿です。
期待される効果と課題
このアプローチでは次のような効果を期待しています。開発者の主体性向上として、自己評価を通じた学習意欲の醸成。SREリソースの最適化により、より多くのチームへの支援が可能に。そして知識の民主化として、特定個人への依存から組織的な能力への転換です。
一方で、開発者の負荷増加への配慮、適切なペースの見極め、モチベーション維持など、実践を通じて解決すべき課題も想定されます。発表時点での実際の成果と課題を、包み隠さず共有する予定です。
■ 対象聴衆とその人たちが得られるもの
対象聴衆:
- 複数の開発チームを限られたリソースでサポートしているSREチーム
- 開発チームへの知識移転に課題を感じているSRE/DevOpsエンジニア
- SREプラクティスの標準化・展開を推進する立場の方
- 開発チームとSREチームの協業方法を模索している方
得られるもの:
- 「なんとなく」の関係から脱却し、明確な目標を持った協業への転換方法
- Knowledge Transfer MatrixとConfidence Scoreによる知識移転の定量化手法
- 開発者との合意形成と段階的な責任移譲のアプローチ
- 計画的なExit戦略の設計思想と実践的なヒント
■ なぜこのトピックについて話したいのか(モチベーション)
「いつまで関わり続けるのか」という個人的な疑問から始まったこの取り組みは、SREという役割の在り方そのものを再考する機会となりました。
限られたSREリソースで増え続けるサービスの信頼性を担保するには、従来のサポートモデルでは限界があります。開発チーム自身がSREとしてのスキルと考え方を獲得し、自律的に高い信頼性を維持できる組織を作ることが、持続可能な解決策だと考えています。
Embedded SREは、永続的な役割ではなく、開発チームが自立するまでの期間限定のミッションであるべきです。そしてその「終わり」を意図的に設計することこそが、プロフェッショナルとしての責任だと考えています。
この発表を通じて、同じように「なんとなく」のサポートを続けている方々に、計画的なExit戦略という選択肢があることを伝えたいと思います。それは決して無責任な撤退ではなく、チームの成長を信じ、より多くの価値を組織全体に提供するための、戦略的で前向きな決断なのです。
まだ実践の途中ですが、だからこそ生々しい課題や発見を共有できると考えています。SREの在り方について考える機会になれば幸いです。

