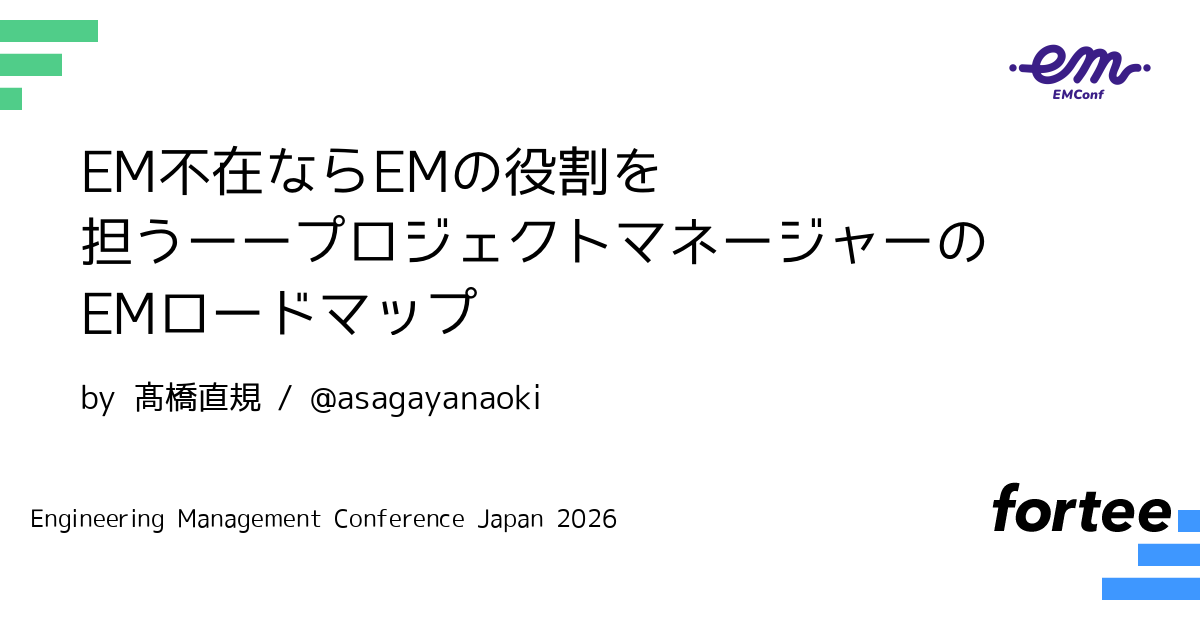
Engineering Management Conference Japan 2026
EM不在ならEMの役割を担うーープロジェクトマネージャーのEMロードマップ
 髙橋直規
asagayanaoki
髙橋直規
asagayanaoki
私は2007年よりエンジニアとして様々なプロジェクトに関わってきました。
私が経験してきた受託・準委任のソフトウェア開発の現場には、EMという役割が存在しませんでした。
はじめてプロジェクトマネージャーの役割を担ったのは、2018年頃で基幹システムの刷新案件でした。
それ以来、プロジェクトにまつわる様々な要因(スケジュール、リソース、リスクなど)を管理し、
望まれたゴールに対してプロジェクトを推進していくことを、プロジェクトマネージャーの役割として意識してきました。
ただ、契約やリリースが終わるとリセットされるようなプロジェクトのあり方に、
エンジニアが短期的な目的のために消費されていくようなイメージを拭うことができずにいました。
より長期的な視点でエンジニアが成長し価値を発揮していくためには何ができるかを悩んでいました。
そうしたエンジニアの価値のあり方として、
継続的なチーム成長やプロダクトの価値実現が重要と考えていた私にとって、
エンジニアリングマネージャーの存在は大きな発見でした。
私はプロジェクトマネージャーとして、
人とプロダクトが共に育つ環境をプロジェクトの内側から生み出すことを目的に、
意識的にEMの役割を取り入れました
具体的には以下のような試行錯誤を実践しました。
・メンバーの活躍に対して説明責任を負う:個人の成長意欲をプロダクトやチームの成長機会に結びつけ評価が行える状態を実現
・プロダクト思考への推進:各開発作業においてプロダクトの目的に紐づけて考えるようにチームを推進
・継続的なプロジェクトの実現:リリースや契約終了を終点としないために、チーム開発を強化し自己組織化と成長を実現
・組織運営のプラットフォーム化:契約にあたる調整は個人でハンドリングし情報はチーム全体に共有
これらの取り組みにより、契約・プロジェクトの継続とメンバーの継続的な評価向上を実現し、
何よりプロダクト開発に挑戦する文化をチーム内に根付かせることができました。
当セッションでは、EM不在の現場でもプロダクトの価値実現とチームの成長へ動いていくためのマネジメントの実践を共有します。
Learning Outcome
対象の聴衆:プロジェクトマネージャー、テックリード、エンジニア
得られるもの:EM不在でも、人×プロダクト×プロジェクトを成長させていく意欲

