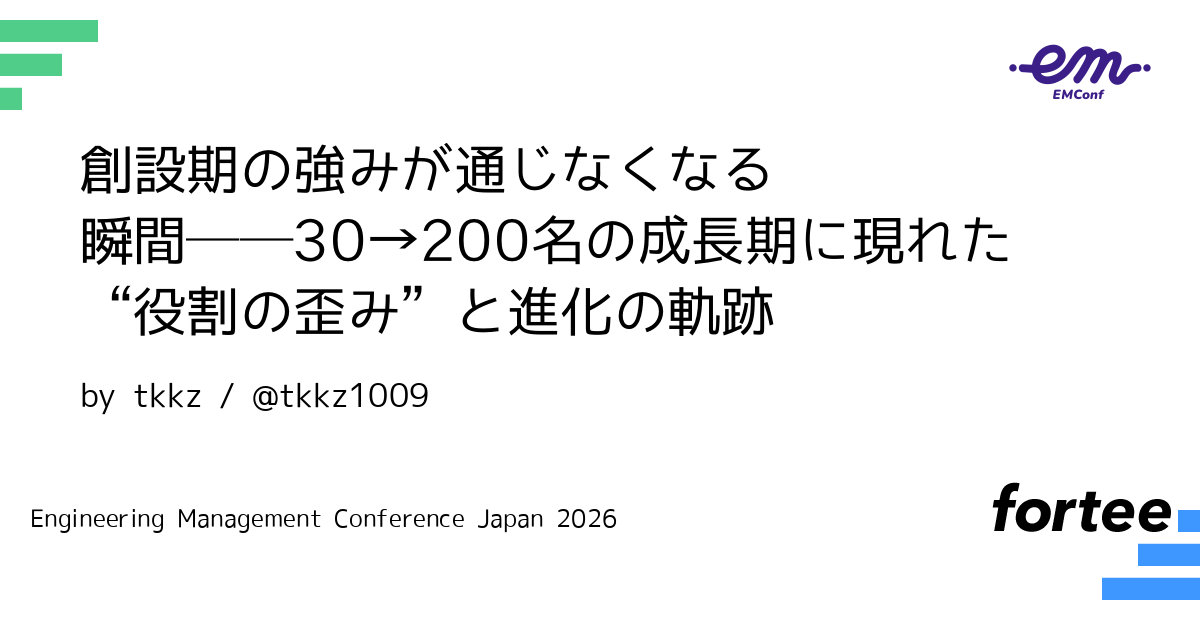
Engineering Management Conference Japan 2026
創設期の強みが通じなくなる瞬間──30→200名の成長期に現れた“役割の歪み”と進化の軌跡
 tkkz
tkkz1009
tkkz
tkkz1009
創設期には「何でも支える」強みを発揮してきたEngineering Office(EO)は、開発組織が30→200名へ急拡大するなかで、組織のスケールと期待の増大に応えきれなくなっていきました。
特に成長期では、EOが自然と“依頼の受け皿”になりやすく、発信文化醸成・社内イベント運営・企画制度企画/運用・稟議・SaaS管理・発注対応など多様な業務が累積します。一方で役割境界や判断領域は曖昧なまま広がり、業務集中や組織戦略との接続の弱さといったボトルネックが顕在化しました。
同時にEO自身も「開発組織からの期待値の変化」を十分に言語化できないまま業務に向き合っており、EOが次フェーズへ進化する上でのハードルとなっていました。創設期の“何でもやるEO”の強さは、スケール期には“境界の曖昧さ”として能力発揮が難しく——ここをどう乗り越えるかが論点でした。
本セッションでは、EOが「何でも屋」から組織全体やEMなどのMgrにとって開発組織を成長(Enable)させる「組織運営とEnableを担うパートナー」へ進化する軌跡、これまで・現在地・これからを整理します。
具体的には、
(1)EOが担う責務・役割・期待の変化の再定義
(2)Mgr支援を“作業代行”ではなく、意思決定・判断の型・振る舞いに再解釈する
(3)属人化や責務偏りを防ぎ、EOだけに閉じず多様なステークホルダーと共創し成果最大化を図るステップ
の3点を中心にEOに限らず、スケール期の組織なら再現可能なアプローチとして提示します。
Learning Outcome(対象の聴衆と、その人たちが得られるもの)
▼対象となる聴衆
- Engineering Manager / 開発組織のMgr
- プロダクト開発組織のMgr・リーダー
- EO / Developer Enablement / DevHR、開発組織のバックオフィス
-
数十→100名以上の組織スケールに向き合う方
▼得られるもの
-成長期に起きる「境界の曖昧さ」「依頼累積」が生む構造的課題の理解
-EOが“戦略理解・Enable伴走者”へ進化するための実例と現在地
-フェーズ変化に応じた組織/Mgr支援の再定義視点

