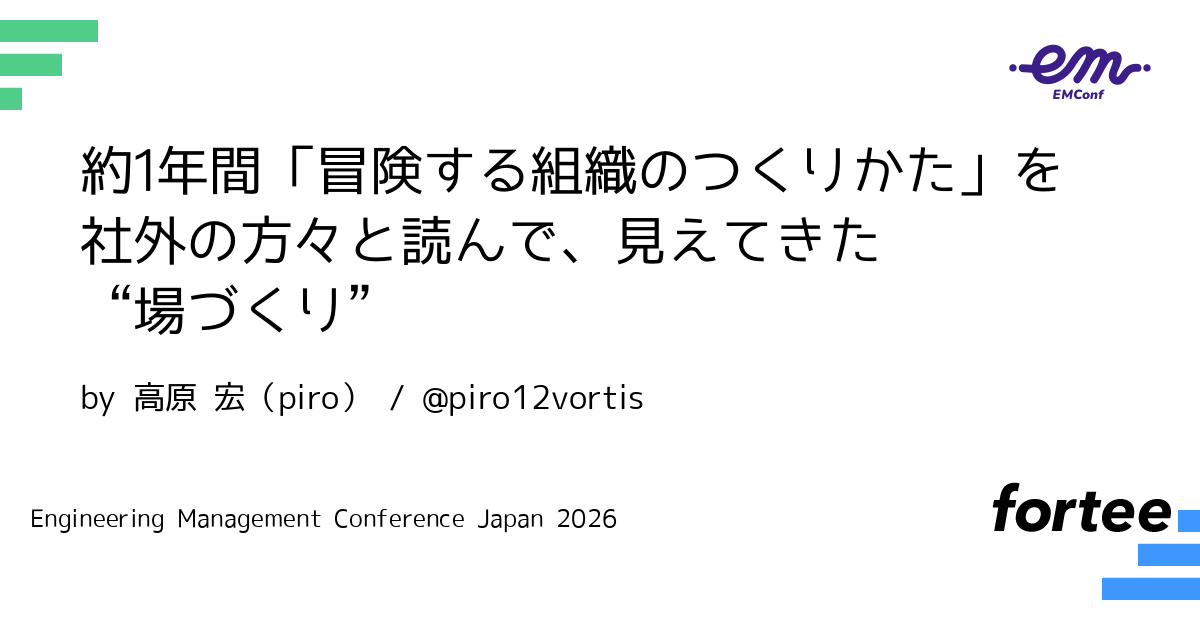
Engineering Management Conference Japan 2026
約1年間「冒険する組織のつくりかた」を社外の方々と読んで、見えてきた“場づくり”
 高原 宏(piro)
piro12vortis
高原 宏(piro)
piro12vortis
EMConf JP 2025 で『マネージャー全員でマネジメントポリシーを作った』話をさせていただいた約ひと月前、組織マネジメント界に新しいパタンランゲージ的な共通言語を生み出しそうな本が出版されました。奇しくも今回基調講演をされる安斎勇樹さんが記した『冒険する組織のつくりかた』です。
当時は「人にやさしい組織マネージメント勉強会」の本読み会で『マネージング・フォー・ハピネス』を読み終えた直後、次に読む本を選ぶタイミングでした。
そこで、届いたばかりの『冒険する組織のつくりかた』を候補に出したところ、他にも同じ本を挙げた方がいるなどして支持が集まり、2月からみなさんと読み始めることができました。そして、このプロポーザルを書いている11月前半もまだ途中です。この調子だと読了は12月に至りそうです。
この1回に読む量の平均は30ページ未満というゆっくりペースの読書会で何が起こってきたのか?どうして1年近くも続いているのか?参加し続ける魅力や価値はどこにあるのか?などをふりかえって探究します。
どうやら、この場で起こっている現象は「増幅」、書籍だけでなく参加者も「触媒」と言えそうです。
Target Audience
・組織変革や行動変容といったチェンジ・マネジメントを担っている方
・社内|外で読書会などの勉強会を行いたい人|行っている方
・『冒険する組織のつくりかた』を触媒に生まれた学びに興味がある方
Learning Outcome
・対話や気付きを増幅する場づくりのヒントを得られる
・AI時代の(人間ならではの)本の読み方について考える材料を得られる
・参加者のコンテキスト共有レベルに合わせたコンテンツ選定の事例を知ることができる
・『冒険する組織のつくりかた』から出てきた気付きや学びの一端を知ることができる
※読書会(勉強会)の場づくりにフォーカスした内容を予定しており、書籍『冒険する組織のつくりかた』の内容を紹介するセッションではありません(具体的な気付きや学びの紹介とコンテンツ選定の観点で一部は触れると思います)
※参加者仲間か運営の方との共同登壇を画策しています

