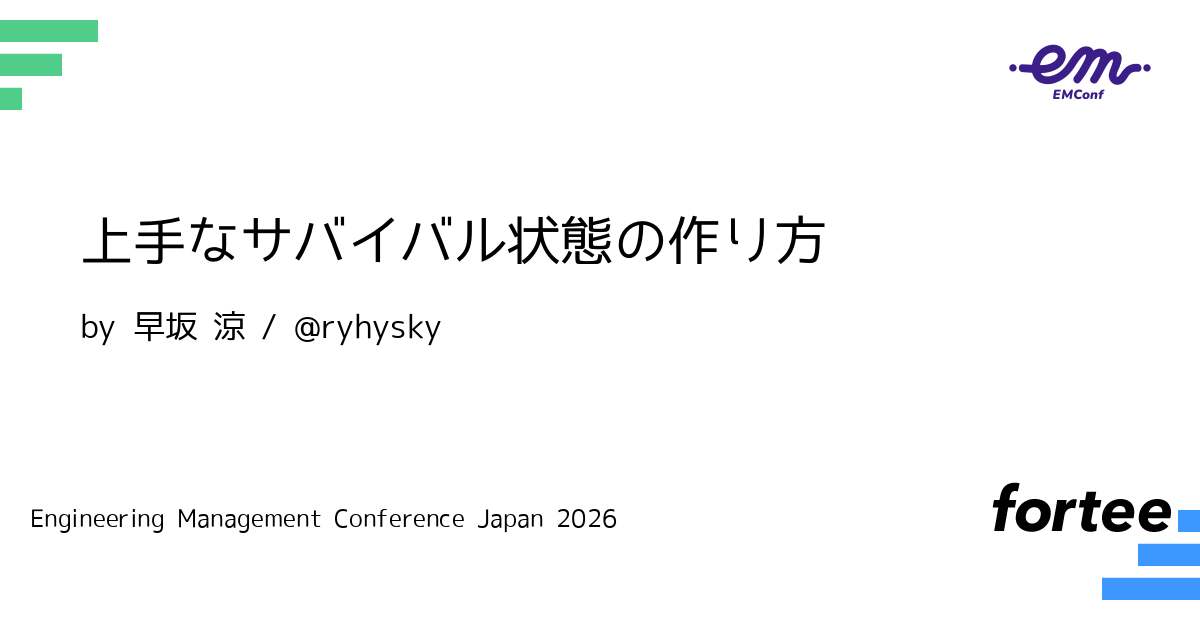
Engineering Management Conference Japan 2026
上手なサバイバル状態の作り方
 早坂 涼
ryhysky
早坂 涼
ryhysky
概要
私は焦っていた。
UPSIDERの事業部CTOとして大きな組織を任された以上、組織やプロダクトを成長させるために、早く次世代のキーパーソンを育てなければと。
早く組織を大きくするために適度なサバイバル状態を作り、人や組織の成長を促したい。
しかし多くのマネージャーも直面するように「どの程度が適度なのか?」は難題です。
負荷が足りなければチームは停滞し、やりすぎればメンバーを疲弊させ、バーンアウトを引き起こします。
本セッションでは、チームの成長を最大化する「適度なサバイバル状態」をいかに設計・維持するかを、実践例と失敗談を交えて共有します。
ぬるま湯状態では当事者意識が生まれず、スキルも停滞する。一方で、障害対応の連続やリソース不足が続けば、離職やメンタル不調に直結します。
重要なのは「成長への挑戦」と「持続可能な働き方」を両立させる繊細なバランスです。
セッションでは、3つの類型に分けてサバイバル状態をデザインする手法を紹介します。
①健全な緊張感型:目標設定やプロダクトデータの見せ方で適度なプレッシャーを生み出す。危機感を煽らずに当事者意識を醸成する工夫。
②クライシス対応型:障害や炎上時のコミュニケーション設計。混乱を成長機会に変えるポストモーテムの実践と、リカバリー後のチームケア。
③リソース制約型:人手不足や技術的負債下での優先順位づけ。「できないこと」を明確にし、小さな勝利を積み重ねることでモチベーションを維持する方法。
さらに、メンバーごとの負荷耐性の違いへの対応など、実務で即活用できる具体策や失敗事例も率直に共有します。
EMの仕事は、チームを「鍛える」ことであって「追い込む」ことではありません。
本セッションが、参加者の皆さんがチームの成長を加速させる「触媒」となるヒントを提供できれば幸いです。
Learning Outcome
対象聴衆
• チームの成長速度に課題を感じているEM
• メンバーのモチベ管理に悩むEM
• 高い目標と持続可能な働き方の両立を模索しているEM
得られるもの
• 適度なサバイバル状態をデザインする実践手法
• チームの負荷状態を測定・調整する具体的指標とアクション
• 失敗から学んだリカバリー戦略と長期的信頼構築のコツ

