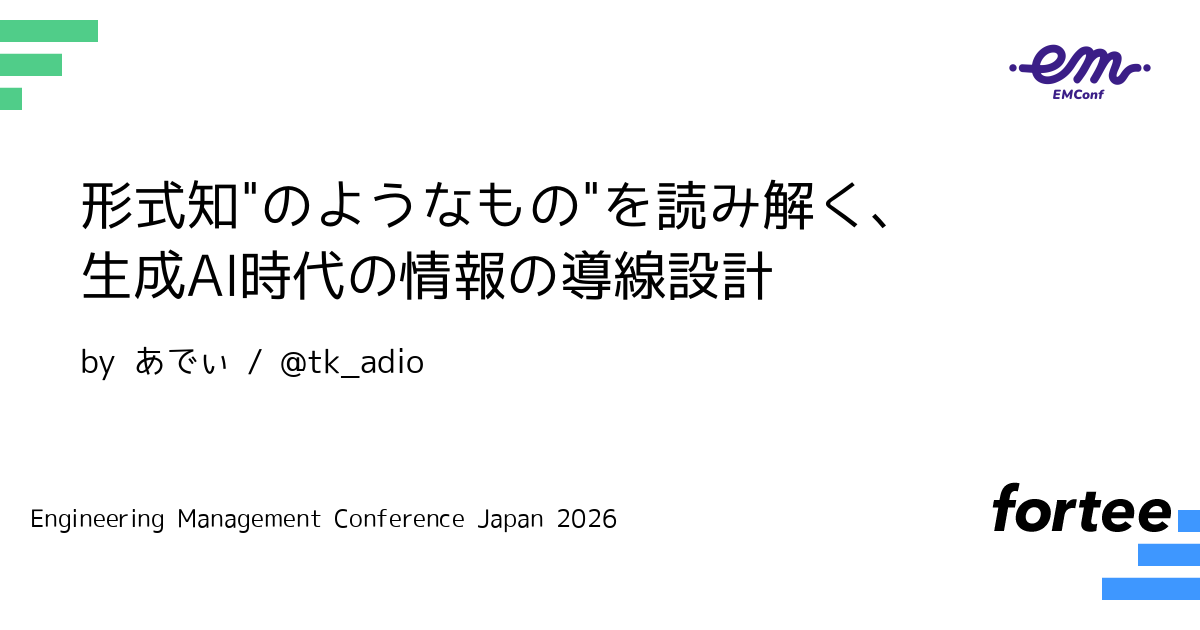
Engineering Management Conference Japan 2026
形式知"のようなもの"を読み解く、生成AI時代の情報の導線設計
 あでぃ
tk_adio
あでぃ
tk_adio
私が今年EMとしてGENDAのテック組織にジョインしたとき、生成AI時代特有の情報の壁に直面する経験をしました。
情報はたくさんあるのに、最新かどうか分からない。探すと似た資料が複数あり、結局どこから手をつければいいのか迷ってしまう。この感覚はオンボーディングの良し悪しではなく、生成AI時代の特有の壁だと感じ、情報設計について考え始めました。
生成AIの普及により、ビデオ会議の議事録やSlack要約など、組織内の情報は自動で増えるようになりました。
「とりあえず録画しよう。誰かがあとで見るかも」
「要約は自動だし、入れよう。あったら便利かも」
そんなかもしれないを理由に意図を持たない情報が積み上がり、まるで形式知のように蓄積していきます。
プログラミングの文脈で言えば、「使うかもわからないコード」はシンプルに保つべきもの。
なのに情報になると、途端にルーズになり、その原則を忘れてしまいます。
その結果、未来の誰かに技術的負債ならぬ「整理の負債」を預けてしまっているのかもしれません。
しかし情報では、積み上がったものをただ捨てればいいわけではありません。過去の経緯や判断の軌跡にも価値があるからです。課題の本質は、増え続ける情報を負債にしない設計にあります。
生成AIによって情報が自動的に"増幅"される時代。
その中で、チームの理解を促す“触媒”としての設計や導線づくりが求められていると考えます。
このセッションでは、生成AIが生み出した情報を、生成AIとともに読み解く。そんな少し皮肉で、けれど避けられない時代の体験を出発点に、新しいメンバーが迷わずキャッチアップできるようなチームの情報の導線設計を考えていきます。
Learning Outcome
対象となる聴衆
新しいチームにジョインするEM・マネージャー
新メンバーのオンボーディングや、チームのナレッジ共有設計を担当・関心のある方
効率的な情報キャッチアップに課題を感じている方
このトークから得られる学び
AIが自動生成したカオスな情報を価値ある情報へ導くためのヒント
「情報が多すぎて分からない」というキャッチアップ体験を、チームの「ナレッジ設計」に活かすための視点

