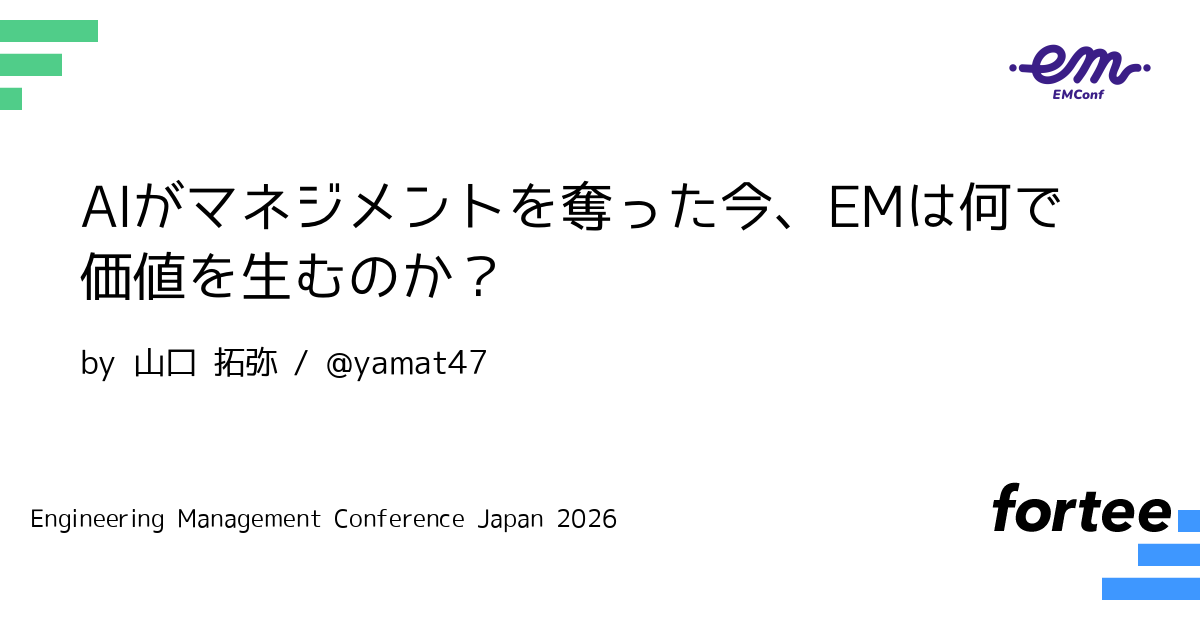
Engineering Management Conference Japan 2026
AIがマネジメントを奪った今、EMは何で価値を生むのか?
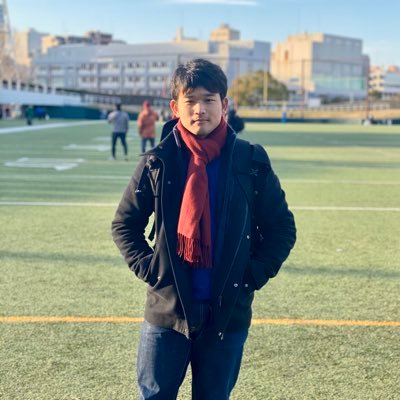 山口 拓弥
yamat47
山口 拓弥
yamat47
概要
生成 AI やコーディングエージェントによって個々のエンジニアの自律性が飛躍的に向上し、要件整理や設計、実装の補助など EM がこれまで担ってきた多くの「管理的な役割」は縮小しつつある。LLM が組織のボトムアップを行う一方で、EM の存在意義はいわゆるチーム管理から事業貢献へと急速にシフトしつつあると考えている。すなわち AI 時代における EM に対する本質的な問いは「事業貢献にどれだけの責任を負えているのか」である。
本セッションではワンキャリア社における実践を題材に、EM の役割を事業中心に再定義して行った取り組みを紹介する。当社の EM は、すべての投資・施策・プロジェクトに対して投資対効果を説明する責務を負っている。開発プロジェクトや AI ツールの導入、O'Reilly Learning の導入といった人事施策や業務委託の採用に至るまで、提案は必ず事業的な観点で精査される。抽象的な「これが良さそう」といった基準では評価されず、売り上げや利益に関するリターンや成長率・ROIC との整合性に基づいて判断される。価値構造を数値で語ることができなければ承認されない。
このため、EM は財務三表やユニットエコノミクス、他社の IR 分析などをテーマにした継続的な勉強会を開いており、事業成果を前提にした意思決定や提案を日常的に行っている。またユーザー価値とビジネス価値とが衝突する場合には、曖昧な妥協はせず「中長期目線も含めて事業にとって何が最適か」という点を明確に判断するような構造を整備している。
AI が自律性を増幅しつつある昨今、EM は組織の単なる管理者ではなく事業を動かす触媒としての責務を負う必要がる。本セッションでは、その変化に適応しつつある EM の行動様式を提示する。
Learning Outcome
本セッションを通じて聴衆は、AI によってエンジニアの自律性が高まる現代において、エンジニアリングマネージャーの役割が「管理」から「事業貢献」へと再定義されつつある構造を正しく理解できる。従来型のマネジメント活動だけでは組織に対する付加価値を維持できない一方で、事業成果を基準とした意思決定を担う EM の重要性がむしろ高まっていることを、具体的な実践事例を通じて学べる。

