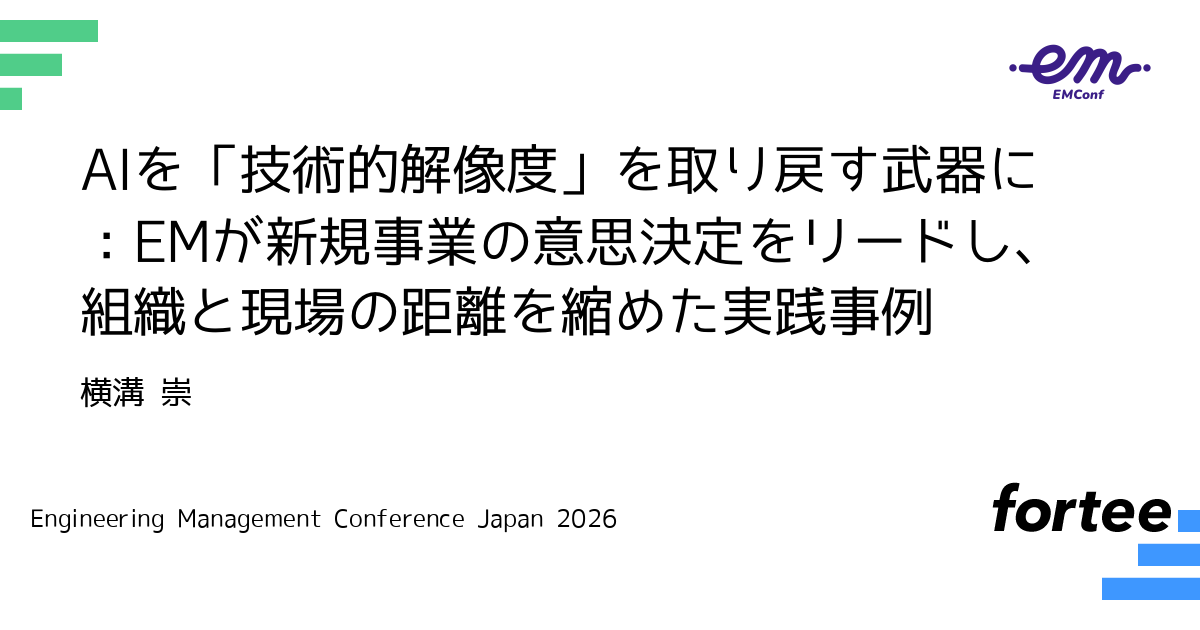
Engineering Management Conference Japan 2026
セッション(20分)
AIを「技術的解像度」を取り戻す武器に:EMが新規事業の意思決定をリードし、組織と現場の距離を縮めた実践事例
横溝 崇
概要
多くのエンジニアリングマネージャー(EM)は、キャリアを重ねるにつれて「人・組織・プロセス」に注力する時間が増え、現場の「技術的解像度」が低下するという構造的な課題に直面するかと思います。この距離は、技術的な意思決定の遅延や、戦略レベルでの議論の曖昧さにつながりかねません。
本セッションでは、登壇者自身が経験した、未経験のコードベースで新規事業の立ち上げを担う中で、技術的な前提を持たないEMが直面した意思決定の遅延とリスク特定の問題を共有します。
そして、AI診断ツール(Cursor/Devinなど)をどのように活用し、既存コードベースの「全体構造」を短期間で理解したのか、そして、その構造診断を通じて技術的リスクを可視化し、PdM/PMMを含む事業部門との具体的な意思決定をスムーズにした実践プロセスを具体的に解説します。
AIを「現場の距離を縮める診断ツール」として活用することで、EMが技術的な弱みを補い、本来持つべき技術的意思決定力を拡張し、いかにプロダクト・テクノロジーマネジメントに再参入できたかを紹介します。
Learning Outcome(対象の聴衆と、その人たちが得られるもの)
対象とする聴衆
- 技術的な現場との距離を感じ始めた、あるいはその予感を持つエンジニアリングマネージャー(EM)。
- 新たな組織や未経験の技術ドメインにアサインされ、技術判断に焦りを感じているEM。
- AI活用を検討しているが、具体的なマネジメントレイヤーでの活用事例を知りたいリーダー層。
聴衆が本セッションから得られるもの
- EMが技術的解像度を維持・回復するために、AIを「コード診断ツール」として活用する具体的なステップとプロンプト設計のヒント。
- 技術的な制約やリスクを、短期間で事業戦略・戦術の議論に結びつけるための、構造的理解とリスク特定のアプローチ。
- 技術的な前提を持たない環境でも、AIを駆使することでプロダクトとテクノロジーのマネジメントに主体的に関与し、意思決定の質を高めることができるという実践知。

