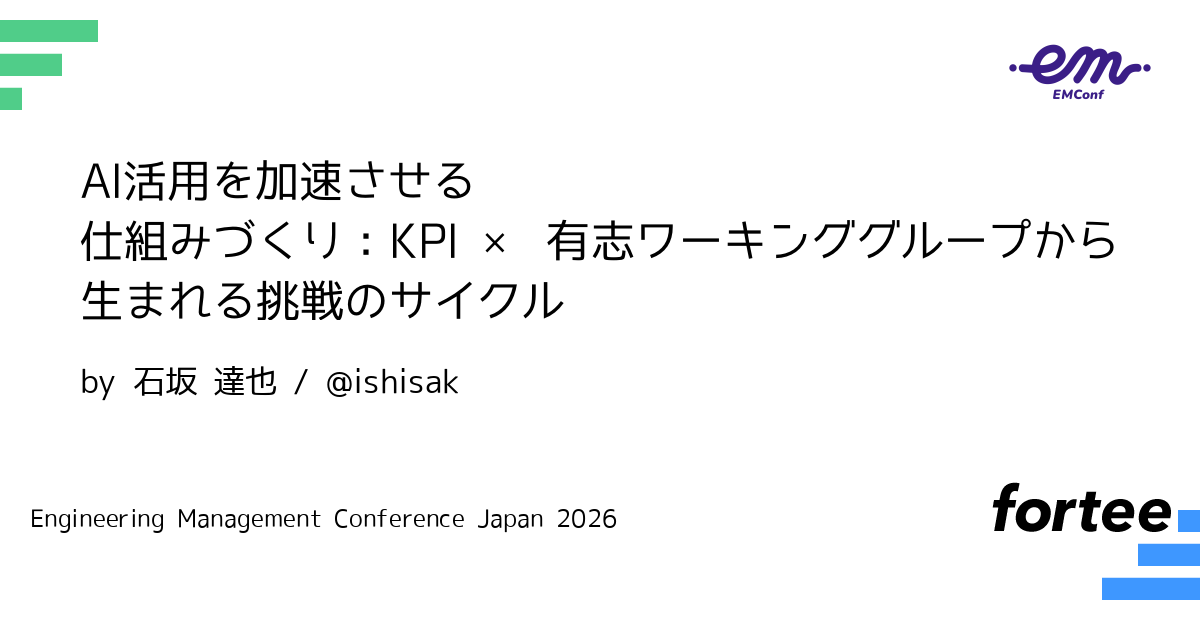
Engineering Management Conference Japan 2026
セッション(20分)
AI活用を加速させる仕組みづくり:KPI × 有志ワーキンググループから生まれる挑戦のサイクル
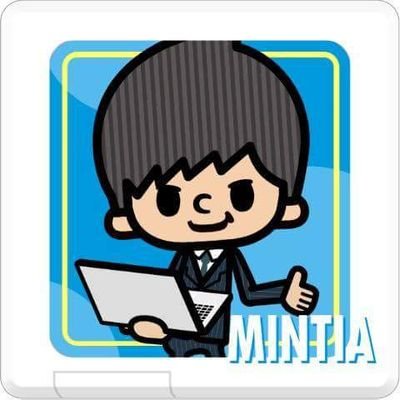 石坂 達也
ishisak
石坂 達也
ishisak
概要
「AIを導入しよう」と声を掛けるだけでは、すべてのメンバーの行動変容にはつながりません。
日々のタスクに追われてAIを試す余裕がない人もいれば、興味を持って積極的に活用する人もいます。
本セッションでは、この課題に対し KPI設定による“仕組みとしての後押し” と
有志による 「AI駆動開発ワーキンググループ」活動による“自発的に試せる場づくり” を組み合わせ、
AI活用が組織全体に広がっていったプロセスを紹介します。
取り上げる内容は次のとおりです。
- KPIとして「AI活用によるアウトプット量向上」を明示し、挑戦を後押しする仕組みづくり
- アウトプット量を設定した際のメンバーへの伝え方・心理的ハードルの下げ方
- 日常的にトラッキングし続ける仕組み
- 有志メンバーで始めた「AI活用の実験→ツール/ナレッジ共有」を行うワーキンググループ
- 成功例・失敗例を共有し続けることで生まれる“挑戦の連鎖”
- メンバーが“試す”ようになる文化づくりの工夫
「仕組みとしての後押し × 現場の自発性 」を掛け合わせたことで、 AI活用が自然と広がっていった実践プロセスをお話しします。
Learning Outcome
対象の聴衆
- EM / VPoE / CTO / テックリード
- チームにAI活用を浸透させたいが進め方が分からない方
- AI導入が一部の個人技で終わってしまっていると感じている方
- 強制ではなく“文化としてAIが根付く”状態を作りたい方
その人たちが得られるもの
- AI活用を“行動レベル”で定着させるための仕組み設計の考え方
- KPIにアウトプット量を設定する際の説明方法・心理的ハードルの下げ方
- 強制になりすぎず、挑戦を後押しする仕掛け方
- ワーキンググループを起点に、継続的に学びが循環する仕組みの作り方
- 成功例・失敗例を共有し合うための場づくり
- アウトプット量を“評価”ではなく“挑戦の共通言語”にするためのマネジメント視点
- KPIを押し付けではなく、「挑戦の回数を増やす装置」に変える方法

