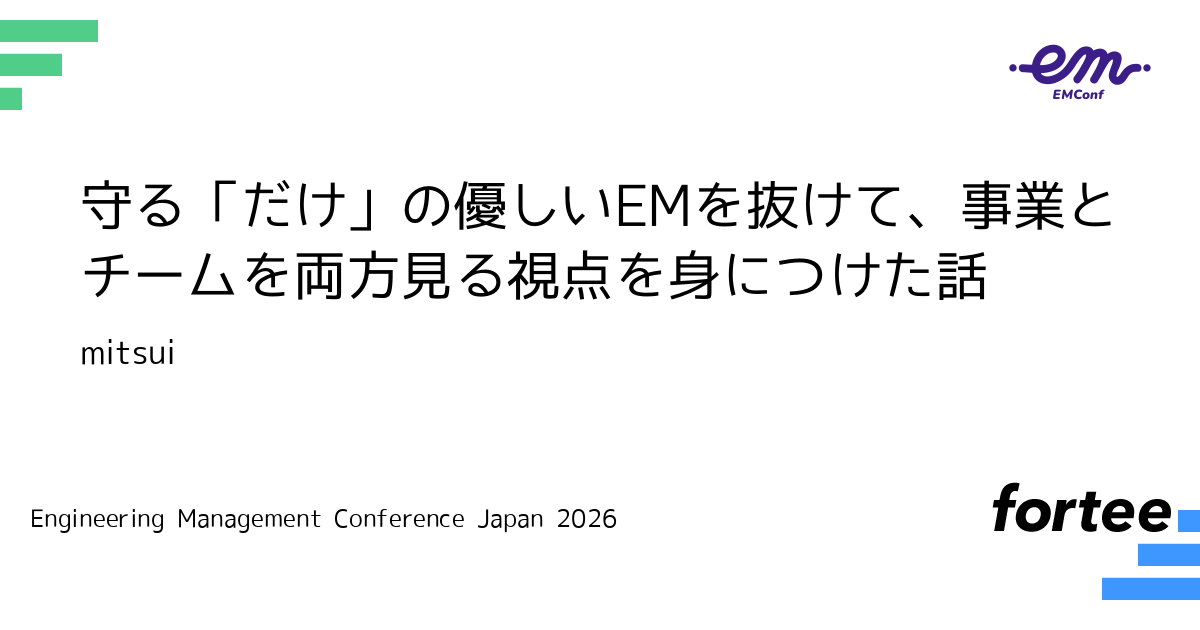
Engineering Management Conference Japan 2026
守る「だけ」の優しいEMを抜けて、事業とチームを両方見る視点を身につけた話
 mitsui
mitsui
入社後しばらくして、所属していたチームにてPdMと主力エンジニアが短期間で離れる出来事が続き、経験の浅いメンバー中心の体制になっていました。扱っているドメインもコードも難易度が高く、「チームを安定させること」が最初の課題でした。私は外圧を整理し、やることを絞り、問い合わせ対応も含めて一緒に状況を確認しながら進めるなど、「守る」ことに振り切りました。その結果少しずつ不安は減り、チームは安定し、連携も強くなっていきました。
その後、短期での成果が必須となる新規プロダクトを担当することになりました。期限は動かず、不確実性も高い。このタイミングで初めて、「このまま守り中心のままでは事業の期待に間に合わない」と自覚しました。判断が遅れるほどリスクが増える状況だったため、技術判断や優先度判断を自分が一時的に引き受け、プロセスも短いサイクルのカンバン運用へ切り替えました。これはプレイングに戻るというより、プロジェクト全体の不確実性を下げ、チームが動きやすい環境をつくるための“介入”でした。
結果としてプロジェクトは期限に間に合い、チームも状況を理解したうえで前に進むことができました。この経験から、「守る/推進」はどちらが正しいかを選ぶ話ではなく、状況に応じて切り替えるモードだと捉えるようになりました。事業とチームの両方を見て意思決定する視点が、自分にとって大きな転換点になりました。本セッションでは、このモード切替の背景と判断基準、実際に行った介入のプロセスを共有します。
■Structure of the Talk
守りに振り切らざるを得なかった背景と当時のチーム状況
守りフェーズで実際に行ったこと(外圧整理、モブプロ、対話など)
異動した先は「短期成果が必須な新規プロジェクト」
EMが一時的に介入すると判断した理由と、判断のオーナーシップを持つ動き方
スクラムの形式にこだわらず、短サイクルのカンバンに切り替えたプロセス設計
結果として何が起きたかと、「守る/推進」はモード切替だと捉え直した学び
■Learning Outcomes
「守るだけ」のマネジメントがどこで限界にぶつかるかを理解できる
守り/推進を切り替えるべき局面を見極めるための判断基準を学べる
事業とチームの両方を見ながら、EMがどう介入すべきかの具体的なイメージを持ち帰れる

