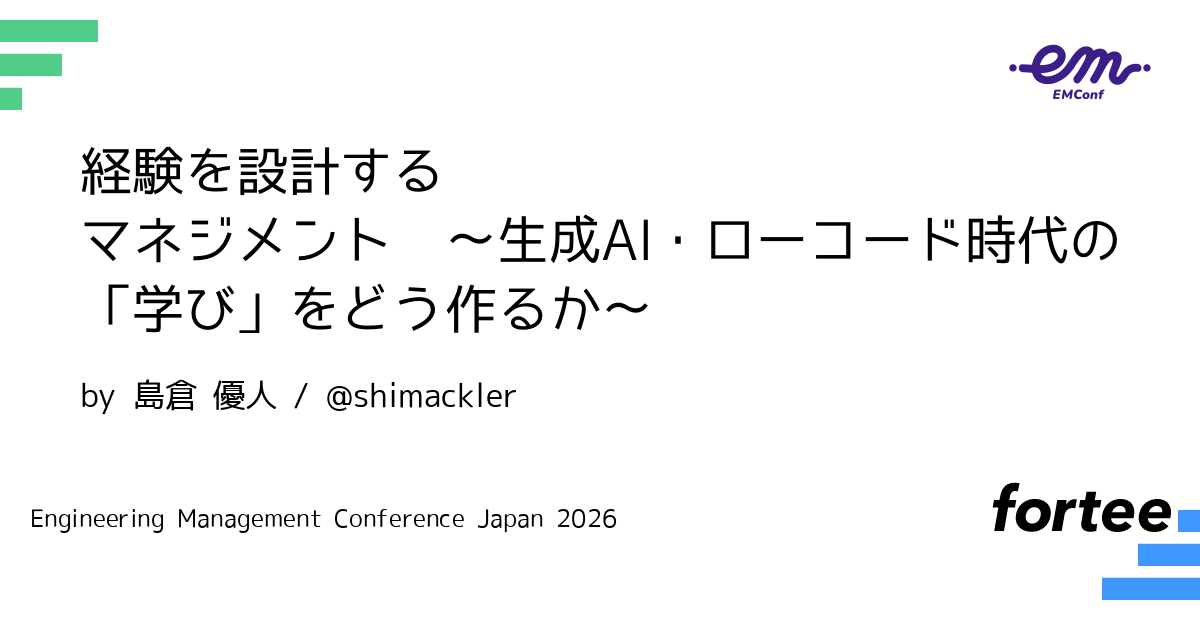
Engineering Management Conference Japan 2026
経験を設計するマネジメント 〜生成AI・ローコード時代の「学び」をどう作るか〜
 島倉 優人
shimackler
島倉 優人
shimackler
「概要」
生成AIやローコードの普及により、エンジニアリングの現場は大きく変化しました。経験の浅い人でも、AIに聞きながらコーディングし、ローコードでアーキテクチャのテンプレートを使って開発を行うことが当たり前になりつつあります。
便利になった反面、「経験を通じて学ぶ機会」が減っているとも感じます。
私は社会人になってから本格的にアプリケーション開発を学びました。オンプレミス・フルスクラッチ開発の現場で、開発の基礎を徹底的に経験しました。その経験をもとに、社内Javaフレームワークや開発自動化ツール、ローコード(OutSystems)や生成AI活用など、さまざまな技術領域に仕事の幅を広げてきました。
気づけばベテラン・中堅社員と呼ばれる年次になり、チームリーダーとして育成に携わる立場になりました。そのとき改めて、「私は泥臭い経験があったからこそ今がある」と実感しました。しかし、生成AIやローコードなど便利な技術が当たり前になった今、“経験ありき”の自分の育成観では通用しないのではないかという葛藤もありました。
とはいえ、生成AIが主流の時代に「経験しないと人は育たない」と言い続けるだけでは前に進めません。そこで私は、便利な技術が知識を“代替”する一方で、マネージャーが設計すべきは「経験による失敗」や「経験を通じた深い理解」だと考えるようになりました。経験を意図的に設計し、体験を通じて理解を深めさせることが、チームの技術力を高める鍵になると感じています。
本セッションでは、生成AI時代における「経験させるマネジメント」について、実際の取り組みや失敗からの学びを共有します。
「Learning Outcome - 対象の聴衆」
・ エンジニアリングマネージャー、テックリード、育成担当者
・ 生成AI/ローコード時代におけるチーム育成やナレッジ共有に課題を感じている方
・ 経験の浅いメンバーを抱えるチームのリーダー
「Learning Outcome - その人たちが得られるもの)」
・ 「経験が積みにくい時代」にチームを成長させるためのマネジメントの視点
・ AIや自動化ツールがやってくれる部分を、いかに経験させるか
・ 経験を組織的に再利用するアプローチ
・ 技術だけでなく“学び方”をデザインするためのヒント

