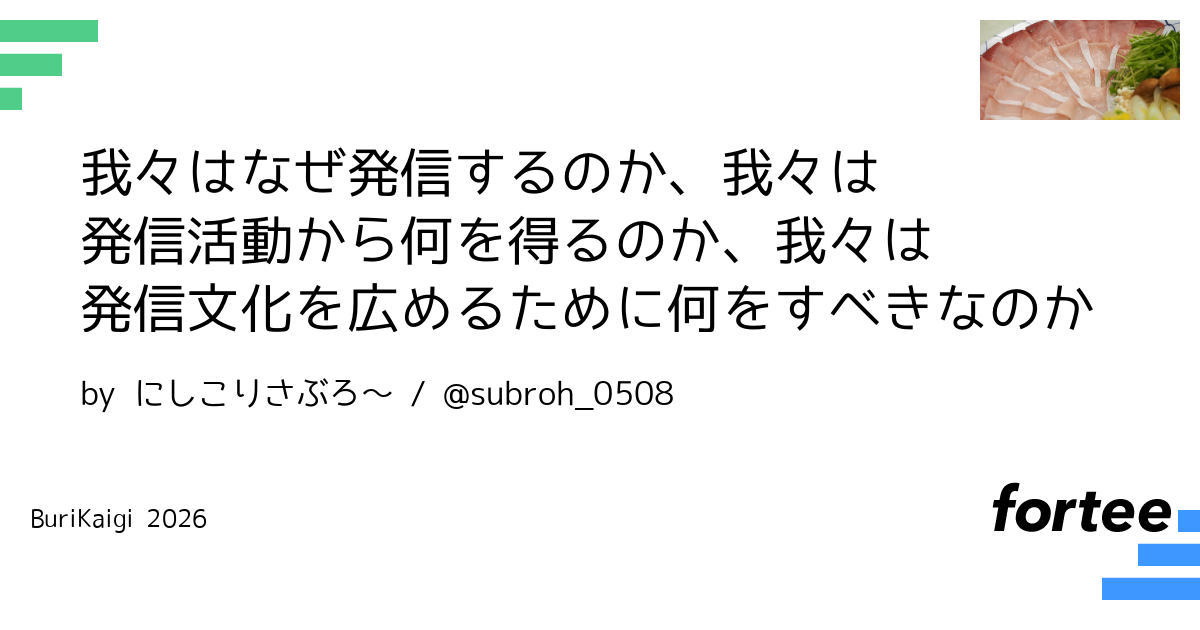
BuriKaigi 2026
レギュラー
我々はなぜ発信するのか、我々は発信活動から何を得るのか、我々は発信文化を広めるために何をすべきなのか
 にしこりさぶろ〜
subroh_0508
にしこりさぶろ〜
subroh_0508
登壇や記事執筆といった発信活動は、エンジニアのキャリアアップに良い影響をもたらします。
発信活動を通して、自身の知見・経験が言語化され、誰かの課題を解決し、キャリアの可能性が広がる。発信活動を継続することで、新たな仲間との出会いも生まれ、活動そのものが「楽しい!」と感じるようになる。
多くの人々が「何かを得られる」「何か楽しいことがある」と信じ、実際にリターンがあるからこそ、富山の地でのイベントが10年も続くのだと思います。
そんな発信への熱い想いを持つであろうみなさんの組織に、発信文化は根付いているでしょうか?
発信が組織の文化として根付くには、自分以外のメンバーも継続的に発信へと取り組んでいる必要があります。一方で見落としがちですが、発信活動(特に外部への発信)は、しばし多くの労力を伴います。自身の思考整理にはじまり、情報の裏取り、執筆作業、発表練習などなど。発信をしたことのない誰かに、発信活動を通して「何かを得られる」「何か楽しいことがある」と感じてもらい、能動的な行動へとつなげるには、様々な壁を超えなければなりません。
本セッションでは、長らく個人で発信活動を続けつつ、業務ではDevHRとして試行錯誤を積み重ね、組織全体の発信数が年間10件にも満たなかった状態から、直近半年で50件を超えるまで引き上げた実績も交えつつ、「組織全体で壁を超え、発信を文化として根付かせる」ために必要なことについて、シェアできたらと思います。
Learning Outcome
- 発信活動のモチベーションは、大きく3つに分類できる
- 「発信そのものが楽しいから」
- 「個人の成長・ブランディングのため」
- 「組織の成長・ブランディングのため」
- 人を発信活動へと向かわせるには、「腹落ちする理由」と「機会」が必要である
- 発信活動の継続に必要なのは、外部露出を増やすことではなく、言語化習慣を身につけ、発信に対するFBが得られる環境を用意すること
想定する聴講者
- 身近に発信活動の仲間が欲しいと感じる方
- 三日坊主になりがちな発信活動を長く継続させたいと感じる方
- 組織に発信文化が根付かず困っている、または根付かせたいが何から着手すればいいか分からないマネージャーの方
セッションの流れ
1. 我々はなぜ発信するのか?
- 発信活動のモチベーションの3分類について
- もし誰かを発信へと向かわせるのなら、発信以外の活動を上回る楽しさ、あるいは意義を提示しなければならない
2. 我々は発信活動から何を得るのか?
- 発信活動の継続に最も重要なのは、言語化の習慣を身につけることである
- そして、発信活動によって得られる最大のメリットは、自身の言語化に対するレスポンス・FBを通して、言語化の精度が発信を繰り返すたびに上がっていくことである
3. 我々は発信文化を広めるために何をすべきなのか?
- そもそも、1や2の考えに至ったのは、7年以上続けている自身の登壇活動から得た成功体験と、自身が所属する組織に発信文化を持ち込もうとして頓挫し続けた失敗経験が背景にある
成功体験
- 外部への発信を継続することで、エンジニアとしての成長の天井を自ら引き上げることに成功した
- いつしか「組織の顔」として社内で認識されるようになり、人事職という新しいキャリアのルートを切り拓いた
失敗体験
- 「発信そのものが楽しい」という自身のモチベーションを自分以外の人にも当てはめてしまい、最初の一歩すら踏ませることができない
- 「個人の成長・ブランディング」につながるメリットを示すも、組織が「他者や組織に対する貢献・ホスピタリティを重視する」カルチャーであるために、高い心理的ハードルを超えるほどの価値を感じてもらえない
転機
- 難航するエンジニア採用へのテコ入れのため、これまで殆ど注力してこなかった採用広報・技術広報の領域に大きな投資をすることが決まる
- そして、その予算編成と年間の活動計画の立案を突然任される
- 上位スポンサーを決めたカンファレンスのうち、3件はスポンサーセッションをもらえることに
- ここで初めて「登壇を業務として、自分以外の誰かに依頼する」経験をする
- 登壇のネタは、依頼先のメンバーとすり合わせしつつ、こちらから提案
- 結果、「組織の成長・ブランディングのため」にお願いした登壇は、自分では絶対に生み出すことのできない素晴らしい内容のものとなった
※以降、直近の発信文化醸成の試行錯誤を交えつつ、Learning Outcomeへとつなげていきます。

