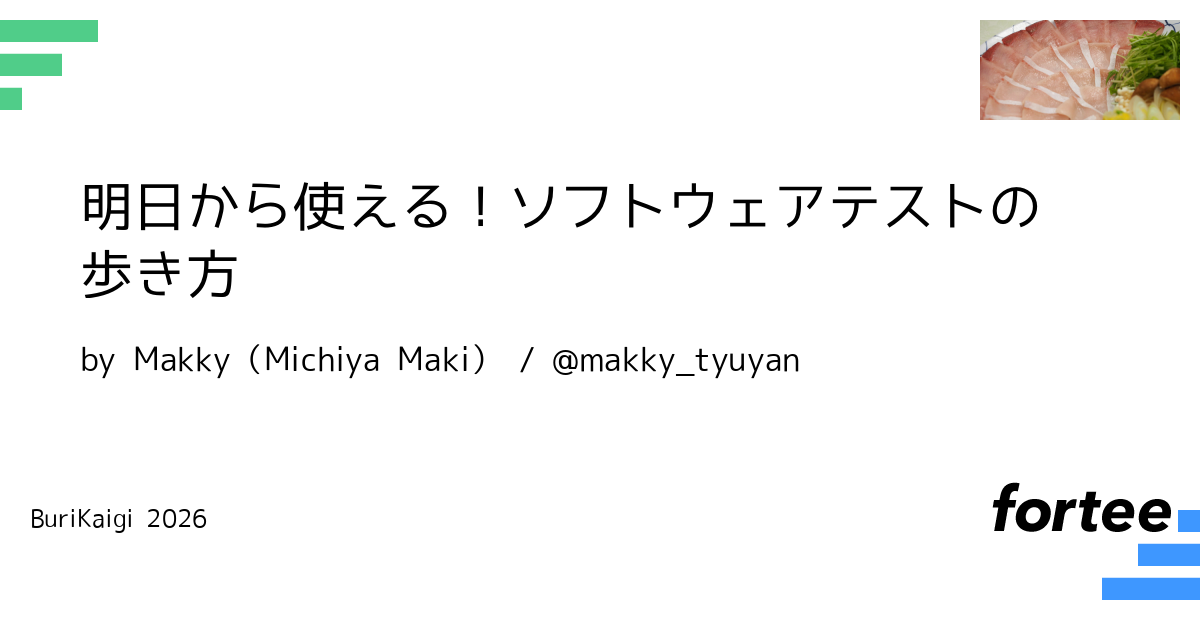
BuriKaigi 2026
明日から使える!ソフトウェアテストの歩き方
 Makky(Michiya Maki)
makky_tyuyan
Makky(Michiya Maki)
makky_tyuyan
テーマ
明日から使える!ソフトウェアテストの歩き方
想定する参加者層(前提知識)
主にソフトウェア開発に携わる一般エンジニアを対象としています。
テストを我流で行っている方、または単体テストや結合テストの品質をもう一歩上げたいと考えている初学者〜中堅エンジニアを想定しています。
JSTQBなどの体系的なテスト知識がなくても理解できる内容ですが、仕様を読みコードを書いた経験があると理解が深まります。
テストエンジニアだけでなく、開発者・PM・デザイナーなど「自分の成果物の品質に責任を持ちたい」と考えている方にもおすすめです。
トーク概要
テストって、どこまでやればいいんだろう?
機能は動いているけど、なんとなく不安。レビューでは「テストケースが浅い」と言われる。
そんな経験をしたことがある方は多いのではないでしょうか。
このセッションでは、現場で本当に役立つ「ソフトウェアテストの考え方」を、明日から実践できる形でお伝えします。
テーマは「同値分割を基本としたテスト技法」「経験ベーステスト」「生成AIを活用したレビュー技法」の3つ。
教科書でおなじみのテスト技法に加え、現場で実践している生成AIの活用方法を紹介します。
テストは、実際のプロジェクトでどう活かすかとなると、途端に難しく感じる人が多い分野でもあります。
私自身、スタートアップでQAエンジニアとして日々開発と向き合っています。
IT業界20年。開発者やマネージャーとしての経験を経て、「理論通りにやってもうまくいかない現場」と、「時間がない中でも品質を守る工夫」を何度も経験してきました。
そこで気づいたのは、テストは“やり方そのもの”ではなく“テストの考え方”を学ぶことが大事だということ。
同値分割の前に「どんな違いが意味を持つのか」を見抜く目。境界値分析の前に「どこが境界なのか」を見つける力。
そして、マニュアルに載っていない「勘」や「経験」は、実は“多くは理屈で説明できる”ものだということです。
本セッションでは、JSTQBの定義をベースにしつつ、
・仕様の読み方をどう変えるとテストがしやすくなるか
・チームで納得できるテストを作るために必要な考え方
・不具合を探索する道標の作り方
など、「ものづくりのラストワンマイル」を埋めるヒントをお話しします。
単に「テストをやる人」ではなく、
「品質をつくる人」として一歩踏み出すためのきっかけになればと思っています。
テストを専門にしていなくても大丈夫。
むしろ、今までは“なんとなく動作確認していた”という方にこそ聞いてほしい内容です。
セッション後には、自分のプロダクトや関わっているプロジェクトを少し違う視点で見られるようになり、
「ここは確認しておこう」「ここが危なそう」と、自然にテストの意図が浮かぶことを期待して準備します。
テストは退屈な作業ではなく、プロダクトを深く理解するための一番身近な探求です。
このセッションを通じて、あなたのテストが「やらされるもの」から「やりたくなるもの」に変わる。
そんな体験をお届けしたいと思っています。
「自分のテストがなんとなく不安」「レビューで指摘されがちでしんどい」そんな方に、
明日から試せる“ソフトウェアテストの歩き方・付き合い方”を持ち帰ってもらえるセッションです。

