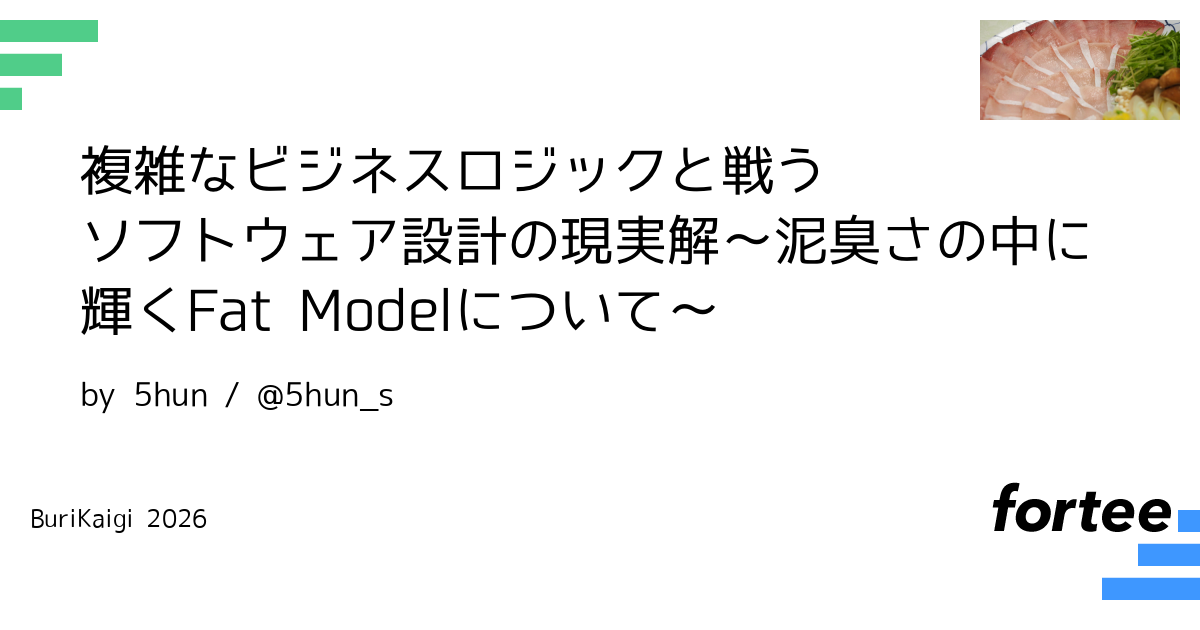
BuriKaigi 2026
複雑なビジネスロジックと戦うソフトウェア設計の現実解〜泥臭さの中に輝くFat Modelについて〜
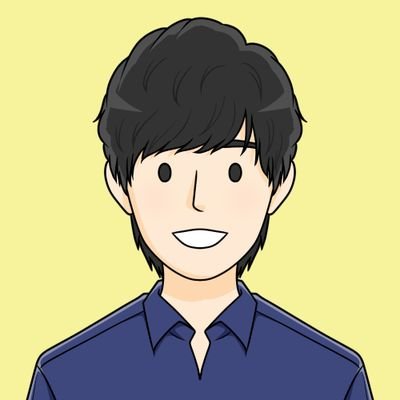 5hun
5hun_s
5hun
5hun_s
【テーマ】
複雑なビジネスロジックを持つ機能の設計についての、現実的なアプローチ
【想定する参加者層(前提知識)】
要件定義や設計から開発まで担当しているソフトウェアエンジニアを主な対象とします。
特に、複雑なビジネスロジックの実装で悩んだ経験のある方はきっと共感できる内容となっています。
他には、今後そのような業務を行う予定、または興味を持っている方も歓迎します。
MVCやオブジェクト指向、アジャイルな開発手法についての知識があると、より深くトークを楽しめると思いますが、それらを特別に意識しない、普遍的な「設計思想と現実的な判断基準」に焦点を当てたトークをする予定です。
※特定の業界知識は不要です。
※スピーカーは、Ruby on Railsで開発を行っていますが、設計思想と現実的な判断基準が中心となるため、他言語・他フレームワークのエンジニアにも十分応用可能な知見を提供します。
【トーク概要】
私の所属する会社では、クライアントと保証契約を締結するために必須の与信審査をRuby on Railsでプログラムのソースコードに落とし込んで自動化し、現在に至るまで約2年間運用してきています。
月間1万件を超えるこの審査業務は、与信に関する高度な専門知識や経験、柔軟な判断を要し、「プログラミングによる自動化に向かない」領域とされてきました。
しかし、私たちは、アジャイルなアプローチで開発を進め、「将来が読めない」という現実と向き合いながら、必要に応じて進化できるシステムを、泥臭くも丁寧に築き上げてきました。
本セッションでは、教科書的な設計原則と現実が衝突した際に、どのように設計判断をすればよいのか、具体例を交えながら、私自身の経験を踏まえて知見を共有します。
具体的には、以下のような内容について話します。
・拡張性を生む骨格設計:すべての土台となる基本ルールを、一番初めに明確化することの必要性
・Fat Modelを恐れない:ロジックをModelに集約させることで得られる凝集度と保守性
・判断基準を「設定」として切り出すコツ:個別パターンのビジネスロジックをカテゴリ化し、設定として切り出すことのススメ
・それでも吸収できない例外パターンへの対処法:可能な限りのグループ化と、最終手段としての影響を最低限に留めるハードコーディング/割り切りの判断基準
これは単なる「実装事例」ではなく、複雑なドメインロジックに日々格闘する全てのエンジニアに贈る、泥臭くも強いコードを生み出すための設計哲学と実践録です。
理想と現実のギャップに悩むあなたの現場に、即戦力となる「泥臭くも強いコード」を生み出すためのヒントを持ち帰ってください。

