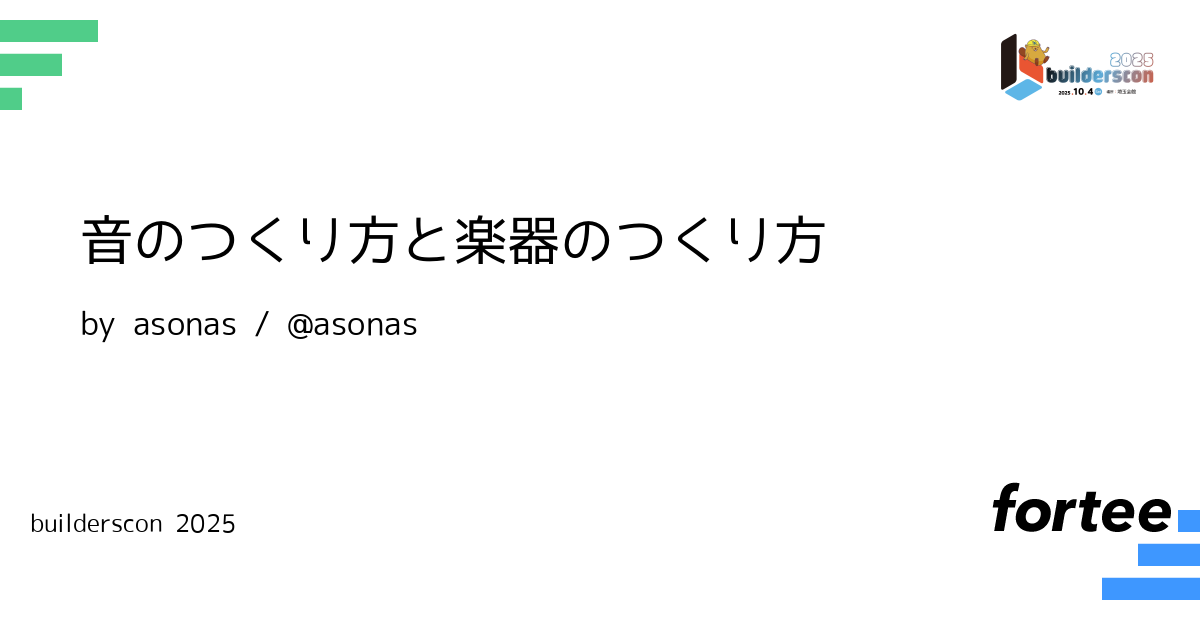
[CANCELED] builderscon 2025
採択
2025/10/04 14:00〜
main
40分
音のつくり方と楽器のつくり方
 asonas
asonas
asonas
asonas
直近1年ぐらいで私が実装した楽器などを製作した成果の発表をします
- groovebox-ruby
RubyKaigi 2025 で「How to make the Groovebox」というタイトルで登壇したときに発表しました。
RubyKaigi
VCOやVCF といった基本回路を Ruby でモデル化し、dRuby で分散シーケンサを構築した過程を振り返ります。
ここでは「波形を出すだけなら数行で始められる」という敷居の低さを示しつつ、簡単なMIDIの仕組みなどをふまえてデモをやります
- Generative Sequencer
groovebox-rubyで得られた知見を元にランダムな音楽を奏でられるGenerativeなシーケンサーの実装をしました。これはRubyKaigi 2025の事後勉強会で発表しました。
connpass
とある本に紹介されていた「占い的作曲法」を読んだ衝撃から rand で音楽を作曲してもよいという発想から200行程度のシーケンサーのを実装をしました。
こちらは事後勉強会の登壇当時はRubyで実装しましたが、PicoRubyでの再実装をして小さなマイコンがGenerative Sequencerとして機能します。
こちらもデモをする予定です
- 自作ミニモジュラーシンセ
これも趣味で制作しているものですが、ブレッドボードに載せたマイコン(Raspberry Pi pico)から出ているPWMのジャンパ線を差し替えることで波形の合成やフィルターをかけられるような小さなモジュラーシンセを実装中です。
Lチカの先に何ができるのか?を考えた時にひとつのアイデアとして音が鳴らせると面白いかなと思って実装中です。
今回のトークで聴衆の方々には、2025年は僕にとって楽器をつくる年で普段仕事で使っている領域とはまた違った学びがあったのでそれをbuildersconに参加される方々にも持ち帰っていただければと考えています。

